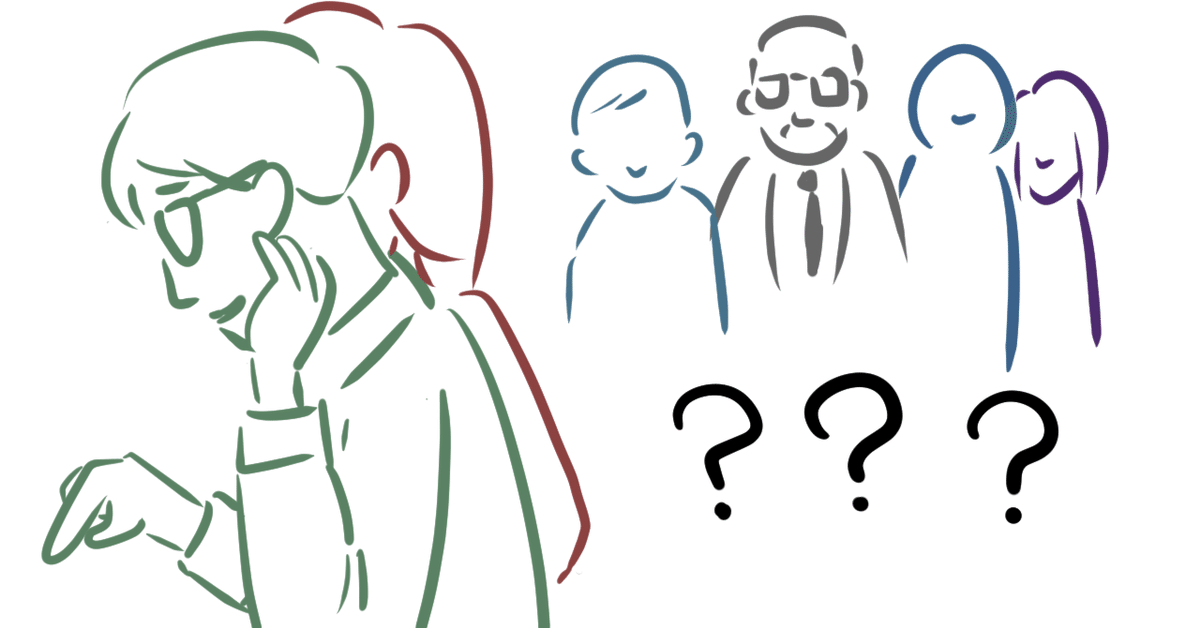
東田直樹氏が文字盤で話す理由 その4
前回は彼の言葉は介助者が作っているものであるという話をしました。がっつり疑似科学と認知されているファシリテイテッド・コミュニケーション(FC)なんです。
そして米国にFCを持ち込んだダグラス・ビクレン氏とのつながりが深い事も書きました。グーグルで「ダグラス・ビクレン」で検索してみてください。すぐにこれが出てきます。
東田直樹さんの著書「自閉症の僕が跳びはねる理由」を最初に出版したエスコアール社のサイトです。
ダグラス・ビクレン&東田直樹 ジョイント講演会/フォーラム
主催:ダグラス・ビクレン&東田直樹講演会 企画運営委員会
協賛:日本アムウェイ合同会社、株式会社エスコアール
日時: 2008年11月16日(日)
こんな講演を日本でしていたんですね。協賛している会社がまた興味深いです。
企画運営委員長:(独)国立特別支援教育総合研究所 教育支援部上席総括研究員 笹本 健
「動作法」「表出援助法」関連の方のようです。
やっぱりこの辺に繋がっていく…。
ビデオレターをお寄せになっている大越桂さんも、どうやら指の動きを使った筆談でコミュニケーション取られる方のようです。
ここで凄い情報は、東田直樹さんが高校生の時に書かれた
講演補足資料、
「パソコンを打っている時に僕の頭の中で起こっていること - 話せない僕が見つけたコミュニケーション方法 -」
この日のために書いた詩 「ずっと夢みてたこと」
です。こちらが直接のpdfです。
https://escor.co.jp/gr/dn-forum/dl_files/naoki_supplemental_data_20081116.pdf
まあ実際は母親の声なわけですが、結構なヒントがありますね。ここでは、「パソコンのキーボードを見ながら、言葉を見つけて思い出す作業 を、頭の中で繰り返し行っている」「僕が話せているのは、画面上に出てきたものを読んでいるだけ」と書かれていますが、私は実際はこの反対をやっていると考えています。
NHKのシリーズをよく見ていると、思い出せずに同じフレーズを繰り返したり、タイプせずにセンテンスを先に発したり、言葉が抜けているのに勝手にディレクターが埋めてしまう部分も見られます。つまり最初からフレーズがあるんじゃないかと。
自閉症者を知っている人は解ると思いますが、セリフ覚えが得意な人も多いんですよ。CMとか映画を丸々覚えたりとか。テレビ用のは仕込んだセリフを、文字へのこだわりが強い東田さんの才能を使って書かせる作業に見えます。
つまり、音として覚えたものを文字盤やパソコンに変換する作業。だから映像では母親の介入はそれほど無いように見えるのですが、実際は何度もやって編集しまくりの可能性があります。
広島大学学術情報リポジトリにこんな文献があります。
Facilitated Communication (FC)と表出援助法の比較研究
―― 肢体不自由,重複障害のある児童生徒への効果を求めて ――
大和大学教育学部
落合 俊郎 *・小畑 耕作 *・井上 和久 *
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/4/42877/20170427112306739206/CSNERP_15_11.pdf
興味深いのは6ページ目のこの記述。
4)東田・東田(2005)この地球(ほし)にすんで
いる僕の仲間たちへ 12歳の僕が知っている自閉の世
界,エスコアール出版部
介助付きコミュニケーションとの接点は抱っこ法
(阿部,1988)の中の筆談援助法とよぶ方法であり,
既に報告されていた事例があった(高橋,1993,田中・
田中,2001)。東田・東田(2005)では,介助付きコミュ
ニケーションの手続きは FC や表出援助法と同じで,
この本に付属している DVD では,母親が彼の脚に触
れた状態で自分でキーボードを打ち,原稿を書いてい
る様子が映し出されている。
大和大学教育学部 落合 俊郎 *・小畑 耕作 *・井上 和久 *
「動作法」「表出援助法」「抱っこ法」「筆談援助法」…
なんか色んなの出てきちゃいましたね。
あら。良く見たら、上の文献を書いた落合俊郎(広島大学大学院教育学研究科教授)氏も、ダグラス・ビクレン&東田直樹講演会 企画運営委員会の一員のようです。
そしてこの方、鈴木敏子(教育実践家・筆談援助の会代表)氏がどうやら東田親子に筆談と抱っこ法を教えたエスコアールの経営者だった方のようです。
次はこの辺りを調べてみます。
あ、それから。
この日のために書いた詩 「ずっと夢みてたこと」
を読んでみてください。
私は泣きそうになりました。
あなたが未来のためにできること。
障害者のためにできること。
ぜひNHKや政府に教えてあげてください。
