
【長編小説】『月は、ずっと見守っていた』第11章「聞こえない声」
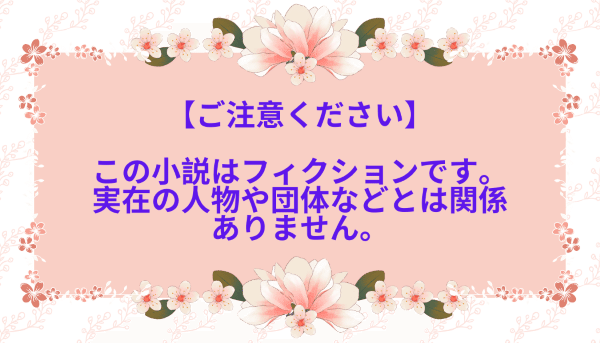
前回のあらすじ
誕生日当日、七海は高橋との関係に対する戸惑いを抱えつつ、彼との食事に向かう。ずっと斜に構えていたが、彼の純粋な気持ちに気づき、また、条件付きの愛情しか受けていない彼女は、それがトラウマとなり、人の好意を素直に受け取れなくなっていることに気づき、高橋に対して、申し訳なさが募る。その後、酒に酔い思わぬ、大胆な行動に出た七海は、翌朝目覚めると高橋が隣にいることに驚く。昨夜の行動が理解できず戸惑いながらも、何かの始まりを予感する。
第11章「聞こえない声」
付き合い始めてから、高橋は見た目と違って心配性らしく、マメに連絡をしてくるタイプだった。
七海は、自宅で仕事をしているのでスケジュールがわかりにくいのもあるだろう。
朝と夕方には必ず「今、どこ?」と定時連絡が入るようになった。その様子を彼女は『まるで小学生の男の子が、お母さんを探しているみたいね』と微笑ましく思っていた。
しかし、自宅で仕事をしているとはいえ、電話やドアのチャイムに出るのが、もどかしい時がある。しばらくして、彼に合鍵を渡した。
この『合鍵を渡す』という行為は、特別な意味があると思われがちだが、一人暮らしの七海にとっては「救出メンバー」という意味もあった。
もちろん渡す相手はちゃんと選んでいる。それに、これまで合鍵を渡した人たちは、皆「万が一」の時と心得ていてくれた。
しかし、高橋の場合、どうも『鍵=恋人=フリーパス』と過去の経験からそう思い込んでいるようだった。
これまでに何度も、訪問前に、LINEか電話のどちらかで、在宅確認と、玄関のチャイムを鳴らすようにお願いしていたが、高橋は、わざとなのか忘れっぽいのか、いつもリビングに来てから「あっ!忘れた~エヘッ」と悪戯っ子のように笑う。
彼女は、彼が持っている“無邪気さ”に、どうしても甘くなってしまう自分を感じていた。
彼の言動は、時々子供っぽくて、どこか頼りないようにも見えるが、何気ない一言や、ふとした笑顔に七海の胸が軽くなる瞬間がある。
たとえば、何か失敗しても「大丈夫だよ、どうせみんなそんなもんだよね?」と笑う姿を見て、七海は少しだけ肩の力を抜くことができる。
高橋の存在は、七海にとって、唯一心地よい場所のような気がしていた。
そのうち、高橋は休日になると、七海の家で過ごすことが、多くなっていた。
一方、七海は締切の関係で、土日が休みではないことが多い。できれば一人で籠りたいと思っているが、彼が静かに過ごしているので、最近は彼の存在にも慣れ、いつしか彼のことを「高橋さん」から「洵くん」と呼ぶようになっていた。
洵は、リビングから見える広い空が好きだった。
今日も何気なく椅子に座って眺めている。
今の時期、雲一つない真っ青な空が、夏が近いことを思わせる。
「今年も暑くなるのかな?」と昨年と比べながら周囲を見渡し、何かを確認して首をかしげる。
毎回、七海の家に来るたびに、彼は不思議に思っていることがある。
それは、引っ越してきたばかりだと聞いていたのに、写真立てやアルバムが一切ないことだ。
「七海さん、写真とか全然ないね。ツインズの写真も。」
キッチンで料理をしていた七海は、振り返って笑いながら答える。「ああ、我が家のデータはパソコンで管理してるの。パソコンの壁紙もツインズの写真だし。」
高橋は肩をすくめて言う。
「デジタル派なんだね。俺、パソコン音痴だから、よくわからないや。」
七海はにっこりと笑って、
「そんなことないから!こういうものは慣れよ。やってみる?」と誘う。
高橋は照れくさそうに、「いや、いいよ。テレビ見てる方が楽しいし。」と答えた。
彼は、七海がフリーランスのエンジニアだと知ったとき、少し驚いた。
何度か、彼女が仕事をしている画面を背後から覗いたこともあったが、そこに広がる世界はまるで異次元のようで、彼には全く理解できなかった。
彼らが就職した時代は「情報化」の波が始まった頃で、コンピューターエンジニアの男性は、羨望の眼差しを向けられていた。
その男性たちの中に彼女はいたのかと思うと、ますます彼は、苦手なことを彼女に知られたくないので、彼女が仕事をしているときは、興味のない振りをして静かにテレビを見ていることにしている。
ふと、昨日の七海が、普段とは違う行動をとり、少し違和感を覚えていたことを思い出した。
いつもの店で、同世代のしずちゃんや麻衣ちゃんたちと、楽しそうに飲んでいても、彼女がLINEを交換する素振りを全く見せなかったのだ。
むしろ、あえて距離を置いているような気がして、少し気になった。
ちょうどそのとき、キッチンでの用事を終えた七海が、ビールとつまみを持って戻ってきた。
「昼から飲むんですか?」と彼がいたずらっぽく尋ねると、
「だって休みの日ぐらいじゃないと、昼から飲めないじゃない。」とカラカラと笑いながらお酌をする。
「昨夜、しずちゃんたちと楽しそうだったのに、LINE交換しなかったのはどうして?」
七海は一瞬考え込んでから、「あー、それは…特に深い理由はないかな。」と答える。
「そうか、七海さんなら誰とでも、すぐ友達になれるのに、珍しいね。」
高橋が言うと、
「不思議なところで引っかかるのね。」と七海は笑いながら、グラスに残ったビールをグイっと飲み干した。
その後、次のビールを取りにキッチンに行きながら、彼女は、「そういえば、どうして女友達がいないんだろう?」とふと思う。
その時、突然七海に例の頭痛が襲った。
激しい痛みに、彼女は顔をしかめ、頭を抱えながら、「ううっ…」と呻くように声を漏らした。
七海は立っていられず、膝から崩れ落ちるようにその場に座り込む。目の前がぼんやりと歪み、耳鳴りが激しく響き始める。
頭の中はまるで音が消えたかのように静かになり、視界もかすんでいく。空気が重く感じられ、体全体が、何かに押しつぶされるような感覚に襲われた。
遠くに洵の声が聞こえるが、それもだんだん遠くなり、七海はそのまま気を失った。
洵は、驚いて駆け寄り、「おい、大丈夫か?」と声をかけながら、目の前の状況にどう対応すべきか分からず、彼女を腕に抱きオロオロするだけだった。
暫くして、彼女は、目の前にぼんやりとした輪郭が浮かんでいるのが分かったが、その顔ははっきりとは見えない。
「七海さん、大丈夫?ここはわかる?」と心配そうに覗き込むその顔が、少しずつ明瞭になり、焦点が合うと、洵だった。彼の腕の中に倒れこんでいた。
「私、どうしてたの?」七海は不安そうに尋ねる。
洵は一瞬戸惑ったが、深く息を吸ってから言う。「大丈夫だよ。痛みとかはない?」
「大丈夫、少し頭が痛いだけ。」と七海が答え、起き上がろうとするが、よろめいてしまう。
洵はがっしりと腕で彼女を支え、しばらくそのまま膝に抱き寄せて落ち着くのを待った。
七海が気を失っていたのは5分程度だったと洵が言った。
その間、彼女は不思議な体験をしていた。
目の前には大きなスクリーンが広がり、映画のフィルムが巻き戻されるように、彼女の記憶が次々と映し出される。
シーンは、ツインズの誕生の瞬間から一気に流れ、早送りのように過ぎていく。
そこに現れるのは、喜びに満ちた彼女の顔、次第にスローモーションになり、葬儀場の情景が現れた。
棺の前に立つ憔悴した七海が、沈痛な面持ちで、花を手にしている。
そこに横たわるのは、23歳で医療過誤で亡くなった親友の綾香だった。
その後、シーンが変わり、綾香とよく行った海の見えるカフェが映し出され、彼女が何か言っているが、その声は聞こえない。
「綾香ちゃん、もう一度言って。」とスクリーンに向かって言うが、綾香は微笑んで手を振り、静かに消えていった。
スクリーンが暗転し、辺りが闇に包まれると、七海は穴に吸い込まれるような感覚になり、次に意識が戻り気が付くと、洵の腕の中だった。
それから彼女は、時折込み上げる悲しみに声を震わせながら、綾香と出会って知った『親友』の頼もしさと、安心感。
いつまでも続くと思っていた関係が、突然『死』で寸断され、あの悲しみを繰り返すくらいなら、どんなに孤独でもかまわない。
もう誰とも別れたくないから、それからは、女友達を作らなくなったと語った。
洵は「それは、さすがに辛いよね…」とだけしか言えず、憔悴しきった彼女を見守り続けた。
よほど、記憶が戻る時は、体力消耗が激しいのだろう。
彼女がグッタリとしているので、早めに休ませて、彼は帰途に就いた。
歩きながら、七海の記憶が戻る様子を思い返して、突然の異変に『救急車を呼んだほうがいいのか?』とか、『このまま死んでしまうのではないか』と心配だったことを思い出す。
また、気がついてからも、その様子が苦しそうで、できることなら、無理に記憶を戻すことをせず穏やかに過ごして欲しいと願わずにはいられなかった。
To be continued

次回配信予定日は、2025年1月12日(日)
次回予告:第12章「そばにいる風」
七海は記憶を取り戻す過程で、親友・綾香との思い出を再確認。彼女との別れとその後の後悔に心を痛める。仕事に向かう合間に、過去の記憶をパソコンに整理し、綾香の死後の自分の心の変化を受け入れようとする。涙が流れる中、綾香が生前にくれた歌『Wind Beneath My Wings』を聴き、彼女の優しさを再認識。最後に、七海は風を感じながら、綾香が今も「そばにいる」と感じて前向きな気持ちを抱く。
[前回までをお読みでない方は、こちらから]
