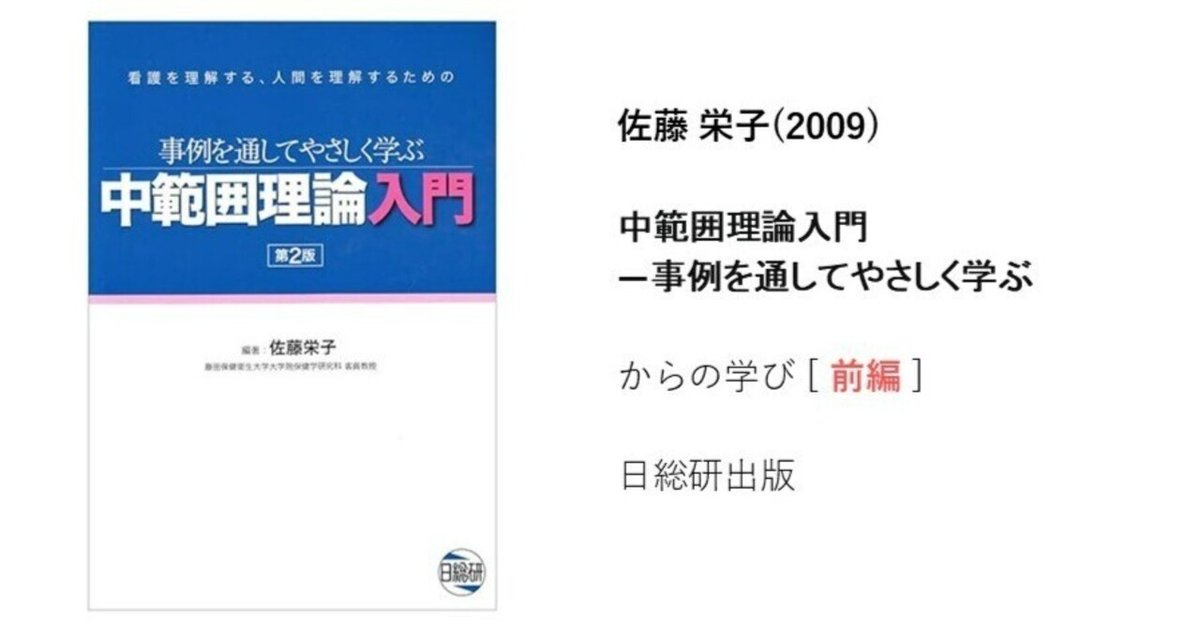
【#107_研究メモ】今更ながら、理論って何ですか??~佐藤栄子(2009)佐藤(2009)『中範囲理論入門 [第2版]』 「序章 中範囲理論の概説」 からの学び[前編]
研究を進めていると、理論とは何か? ということが、わかるようでよくわからなくなってきたので、改めて、こちらの書籍を。
佐藤栄子(2005)『中範囲理論入門』。
タイトルになっている、中範囲理論とは、「日常的な研究仮説を生み出すような理論と、包括的かつ体系的な努力によってつくり出される大理論との間にあるものである」 (本書, p. 20)と定義づけされています。 いったんこれぐらいの理解で。後はおいおい(笑)
▽▽▽
本書の冒頭で、「重要用語の定義」がなされており、この時点からすでに理解が進みます。

いかに、これらの用語を、なんとなくの感覚で使っていたことか・・・
一つひとつの定義をしっかりと把握することで、研究についての議論をする際の解像度がもう一段高まる気がします・・・(高まって欲しい!!)
と、同時に、まだ自分の理解が及ばない記述も・・・涙 もう少し読み込んでみます。
▽▽▽
「理論」については、著者の数だけ定義があると論じられています。ただ・・・・

というように、「理論の生成と発展過程のどこに焦点や重点を置いて定義」するかによって、表現は変わってくるとのことです。
▽▽▽
パラダイム・メタパラダイム・概念モデルについても、補足の説明があったので、重要だと感じた部分を抜粋してみます。

少しずつ概念的な違いがあるということは、理解してきましたが、自分の研究領域でみたときに、どの様に表現できるのか、再度考えてみたいなと思います。
余談ですが、看護領域のパラダイムの、総体性・同時性の信念は面白いですね。成人発達理論や組織開発とも繋がってくる感じがします。メモしておきます(笑)
研究を進める上で、研究テーマに関連した先行研究を読んだり、データを集めたりが研究かと思いましたが、そもそも“研究”とは何を意味するのか? どのような”研究法(具体的な方法論への理解)”に則って進めるのが妥当なのか? について理解を深めることも、非常に重要だなと改めて感じています。
時間はかかりますが、一歩一歩ですね!
※本論文は、中原先生に教えていただきました。資料名を思い出すのに、番匠さんにもお世話になりました。ありがとうございました!
