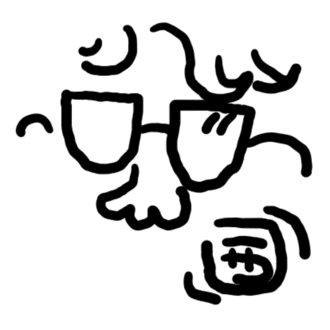『技術書の読書術』を読んでみた感想
『技術書の読書術』を読んでみた感想
はじめに
年始から技術書をたくさん読もうと計画していましたが、正直、技術書ってなかなか最後まで読み切るのが難しいですよね。分厚いし、途中で挫折してしまったり、「自分の読み方が悪いのかも」と悩んでしまったり……。
そんなときに目に留まったのが、今回読んだ『技術書の読書術』。タイトルからして「これなら効率よく読みこなすヒントがあるかもしれない」と思い、手に取ってみることにしました。
どうしてこの本を選んだのか
私自身、エンジニアとしてのスキルアップを目指すうえで、体系的な知識を身につけたいという思いが常にありました。今までは「ノリと経験」だけでこなしてきた部分が多かったのですが、改めて基本を学び、顧客により高い価値を提供したい。そのためには、技術書を避けて通るわけにはいかない。
とはいえ、どの本も分量が多くて読み進めるのが大変。そこで、「技術書を効率よく読むための本」というのは、ちょうど欲しかったコンテンツでした。
本書の中で印象に残った点
1. 90分読書法
最も印象的だったのが「90分読書法」です。自分で締め切りを設定し、短い時間で要点を一気に読む。目次や前書き・後書き、太字や図解、そして「つまり」「要するに」といった箇所を中心に拾うことで、大づかみに内容を把握してしまう方法です。
「全部を最初から最後まで真面目に読もうとしなくていい」というのは、シンプルだけど大きな気づきでした。実際にやってみると、“限られた時間”という意識が集中力を高めてくれます。
2. 複数入門書を並行して読む
本書では「同じテーマの入門書を数冊読み比べる」アプローチが紹介されていました。どの本にも書かれていることは基礎知識として重要度が高く、逆に特定の本だけにある内容は著者独自の視点やノウハウ。
今までは一冊を最後まで読まないと次に進んではいけない、という気持ちがありましたが、そういう縛りを外すのもありなんだなと、ちょっと気が楽になりました。
3. アウトプットの仕方
読んだことを自分の言葉でまとめ、ノートやブログに書いておくと定着が早い——これはいろんなところで言われていることですが、本書をきっかけに「もう少しアウトプットを習慣にしてみよう」と改めて思いました。完璧な文章じゃなくてもいいから、ざっくりメモして残しておく。必要になったとき、すぐに振り返れるのは大きいです。
実際に読んでみて感じたこと
読書法を一から学ぶ、というのはちょっと面倒そうに聞こえるかもしれません。でも、本書では「とにかく構えずに試せる」具体的な手順が多く紹介されていて、私のように本を途中で投げがちだった人でも取り組みやすいと感じました。
特に、時間を区切ってざっくり読むというスタイルは、自分には合っているなと思っています。すべての項目を丁寧に読む必要はない、という許可をもらったことで、読書そのものへの気持ちが楽になりました。結果として、集中力も高まり、「本を読む」ことそのものを以前より楽しめるようになった気がします。
まとめ
『技術書の読書術』を読んでみて、あらためて「技術書は読み方ひとつでハードルが下がる」という実感を得ました。エンジニアとしてスキルアップを目指すうえでも、読書法を工夫するのは大事なことだと思います。
90分読書法で短時間集中して読む
入門書を複数比べて、共通点・相違点を押さえる
アウトプットしやすい形でメモを残す
こういったテクニックを試してみるだけでも、技術書との向き合い方はガラッと変わるかもしれません。
私自身もまだ試行錯誤中で、実践できていない部分も多いですが、「いきなり全部を完璧に読む必要はない」というのは、気持ちを前向きにしてくれるキーワードだと思います。もし同じように「技術書が読めない…」と悩んでいる方がいたら、こういう読み方もあるんだな、くらいにゆるっと捉えてもらえればうれしいです。
最後に
エンジニアとしてもっと成長したい、そのために技術書を活用したい。そんな方には、『技術書の読書術』が一つのヒントになると思います。私もこれから、さらに多くの技術書に挑戦しながら、自分なりに読書スタイルをアップデートしていく予定です。
もし興味があれば、ぜひ一度手に取ってみてください。あなたの「読めない」を変えるきっかけになれば幸いです。
いいなと思ったら応援しよう!