
【読書録】大好きなほんを探して④(2021.4)
阿佐ヶ谷のいいところは南口に出てすぐのところに「書楽」があるところで、見かけよりも奥行があって大きいし雑誌はほしいのが大体置いてあって文芸書もけっこうある。海外文芸もちゃんとある。文庫コーナーも。
高円寺にいたときはAYUMI BOOKSしか行ってなかった。そっちはそっちでなんかすごい洒落てて好きだった。お店を入ると奥に細長く続いてて、まず雑誌コーナーに突き当たる。そこに江口寿史のイラスト集が置いてあったり(ずっとあった)、「Neutral Colors」みたいなかっこいい雑誌ドーンと構えてたりして、とにかくかっこいい店構えだった。雑誌コーナーの左手に文庫コーナーとか哲学・芸術関連のコーナーとか漫画コーナーがある。お店自体はこじんまりとしてるからそんなにたくさんは置いてなくて、置く本は趣味よく、わりときっちり選ばれてるのかなっていう棚の雰囲気。映画とか音楽の本がドドドーンと平積みになってたり(村上春樹のスタン・ゲッツの本とかだけじゃなくて、ほんとにいろいろ)、かっこよかったな。
書楽は高円寺のそことは全然違くて、広い店にできるだけスタンダードにとにかくズラズラズラッといろんな本並べてくっていうスタイルな雰囲気で、まあわりにスタンダードな本屋さんなのかなっていう気がする、白い蛍光灯で内装とかもお洒落目に寄せてたりしてないし。だから行くときに心構えとして(?)イベント感を持たなくていいというか、何一つ用事がなくてもふらっと行っちゃうので、週5は入店してるな。でなんか買ってるな……
①『草の上の朝食』保坂和志(中公文庫)

でも保坂作品は書楽にない。どうしても中古じゃないと手に入らないようなモノじゃないかぎり、本はなるべく新刊書店で手に取って買いたいっていう思いがあるので、保坂作品は吉祥寺のジュンク堂とかまで行って買う。書楽は中公文庫の「ほ」のあたりを見ると誉田哲也しかねーんだよ。
そしてジュンク堂で買った保坂①。
先月読んだ「プレーンソング」の続きで、登場人物はおなじ。主人公の回りでアキラがふざけたり、島田がうだうだしたり、よう子がしゃべったりゴンタが部屋に来たりする。それだけ。90年代初頭の東京の、なにげない一風景にすうっと入っていくような作品。
大きく異なるのは工藤さんという、なんだか得体の知れないような、だけどなんか可愛げがあるな~……という女性が新たに登場して、主人公と仲良くなること。
主人公が三谷さんという競馬狂いとよくいっしょに行く喫茶店で働いていたひとが工藤さん。ケバくて派手な女の子で、主人公はまずそういう見た目がタイプでめっちゃ興味を持つ。店に行くたびに工藤さんを探すようになって、とうとうご飯に誘ったりする。でも主人公は全然手際よくことを進められない。工藤さんも見た目の割に全然主人公をたぶらかそうとかはしない。いつのまにか、雰囲気がなんか独特なええ感じに向かって動いていく。
工藤さんは笑わずに一度視線をテーブルに落とし、それからぼくの肩ごしに漠然と視線を向けて数秒間そのまま視線を動かさなかった。はじめて話す相手に急にそんな反応をされても意味がわからなくて、ぼくは変なことを言ってしまったのかと不安になったが、とりあえず場所でも変えてごまかすことにして、/「じゃあ、ご飯食べに行こうよ」/と言って、インド料理屋に入った。(p.126~p.127)
意味不明。なんでいきなりインドなんだよ。それでこのあと手をべたべたにしてチキンを食うのはなんなんだよ。しかも工藤さんがそれに全然げんなりとかしないっていう。
とか思うけど、読んでて不自然ということはなくて、おかしみの中にいろんなことを抱き寄せて、「草の上の朝食」は優雅なペースでとんとん時間が進んで行く。主人公とまわりの男女が、ただただたのんべんだらりと生きる。それがなんだか、まぶしく感じられてくる。
当時読んだ人は全然そんなことないと思うけど、僕はこれ、VHSを再生するときと同じような気持ちで読み進めた。物語の芯が、強烈なモチーフに支えられたりしてなくて、「日常の写生」みたいな話であるぶん、よけいに時代の調子を色濃く反映しているように見えてくる。よう子は眉毛が太くて(今見るとダセェ)服を着てそうだな、とか、アキラは当時の江口洋介的ロン毛な髪型なのかな、とか。そういう、自分とは異なる時代――90年代――に20代を送った人のことを考えるとき、脳内の画面にはジリジリと線が入る。VHSになる。そんなことないか?
「ヤダよ。プリンスなんかキンキン声でチビで見栄はって踵の高い靴はいて、あんなやつ業界ではアメリカの野口五郎って呼ばれてんだぞ」(p.84)
クソひどい。クソひどいけど今の若者には言えないプリンス評すぎる。
②『残響』保坂和志(中公文庫)

「草の上の朝食」といっしょにジュンク堂で買ったやつ。
「コーリング」「残響」の2編を収録。
書かれた時期は「草の上の朝食」とか「この人の閾」とかとあまり大きく変わらないけど、こっちでは三人称での語りが頑張って進められているのがまずちがう点。
何人かの登場人物の視点をコロコロ移動しながら、それぞれの思いが交錯するさまが見られる。あ~すれちがってる~とかってなる。こう書くとなんだかありきたりっぽいけど、例のうねうね続く保坂文体は健在で、だから読書してる感覚としてはけっこう独得。むしろ、共感しやすい話を持ってきてくれているから、文章自体の味を楽しむにはいいのかも。
それぞれの登場人物は、もう終わった恋とか、そういうことをふとぼんやり思い出したりしている。みんな、今、そばには誰かがいるのに、それでもふとした時の過去の引力ってすごいらしく、けっこう堅牢な孤独の城のなかに閉じこもっている感じがあって、「草の上の朝食」とかと比べると、意外と暗さがある。だからちょっと胸に沁みちゃう。
口述の『未明の闘争』は、これよりも15年くらい後の作品で、その間には「カンバセイション・ピース」とか他の作品が挟まる訳だけど、「暗さ」という点では、この2作は通底するものがある気がする。
個人的には、保坂和志はこれを読んで! みたいな話をするときに、一番はじめに来るヤツではないけど、2,3冊読んでくれた人には「こんなんあるよ」と言いやすいと思う。味の違いを説明しやすいので。
③『アメリカの夜』阿部和重(講談社文庫)

初阿部和重。
もともと興味があった作家だけど、この文庫はまず装幀がいい! とamazonで本をあさってるときに思って、デビュー作から入ってみることに。
初期の阿部和重は蓮實重彦の影響を受けていて云々、というのは知っていたので、小説然じゃない作品なんだろうなとは思っていたけど、書き出し。
ブルース・リーが武道家として示した態度は、「武道」への批判であった。リーは、自ら創出した「武道」である截拳道(ジークンドー)の理論家=体系化をもくろみ、それについての膨大な数におよぶメモやイラストを遺している。(p.7)
思った以上に小説じゃないやつだった……と思ってちょっとシビれた。
まじか、このテンションでずっと続いてくのか、と思ったら、ほんとうにそう。作品やテキストの引用をもとに論考めいたことが書かれたり、主人公の思考や内面が連綿とつづられたり。で、その上、けっこうリーダブル。で、「」でくくられる会話文がほとんどない。――(ダッシュ)につづくかたちでところどころ発話が記されるのみ。
映画という芸術に情熱を捧ぐ、「特別な存在」になろうと願う、阿部和重本人っぽい中山唯生くんがバイトに行ったり人間関係に悩んだりして、物語はすすんでいく。(この唯生(ただお)くんっていう名前もね~)
(中略)彼らは「特別な存在」であろうとしていた自分自身をわすれてしまったようだ、演ずることのなんたるかがまるでわかっていない、ここでは「自然さ」など必要ではないのだ、必要なのは物語の模倣に徹することのみである、おれが見本をみせてやろう……(p.154)
人間関係の些細な機微についてはけっこう共感できる箇所も多くて、文体の特異さのわりに「うん、うん」と思いながら読み進められる。物語自体もちゃんと筋があって、きちんと進んでいく。なのに読書の感じとしては重厚というか、ずっしりしていて、小説を読んだー! っていう感覚にならない。気品のある批評を読んだときの雰囲気にちかい。
すごいよね! 保坂和志より「アメリカの夜」のほうがプロットで説明しやすい内容のはずなのに、読後感は小説らしくないんです。小説とは、物語とは、という話になってくる。
200ページないっていうサイズも、これ流文章を味わうほどよい分量。おもしろかった。
④『ジョン・レノン対火星人』高橋源一郎(講談社文芸文庫)

だめだよ。わたしはベッドに裸で寝転がり、手淫しながらでないとまるでだめなのだ。/「大変だよ! 『すばらしい日本の戦争』が湯ぶねの中で暴れてる! 早く来て!!」/くそ・くそ・くそ・くそ・くそったれ!!!(p.158)
……という調子で終始進む、高橋源一郎の最初期の作品。
ポルノ小説家である「わたし」に、頭の中から「死躰」を取り除けずにいる「すばらしい日本の戦争」から葉書がとどくところから話が始まる。
話の筋は見えなくないし、ちゃんと進んでいるっぽいな~とは思うけど、でも「きちんとした小説」では全然なくて、もうあちこちぶっ壊しながら気怠く気怠く「わたし」の回りでいろんなことが起きる。まず文体がもうルール全無視。ついていけるけど、ついていけてない、みたいな感じになる。
そもそも、わたしの話ですが、最近読む量を増やしていて、なんだかまともな文章ばっかり読んでるとそっちのほうが頭おかしくなりそうな気がしていて、型破りなものを読みたいと思ってこれを選んだというのが、『ジョン・レノン対火星人』を読み始めた理由だったのだけど、その、「文章が当たり前に流れ過ぎて言っちゃう違和感」とか「不安」を打ち砕くには、すごく適材適所な働きをしてくれた。ほんっとうに型破りで、個人的にはとても好きです。「突発性小林秀雄地獄」とかも好きすぎる。
章の立て方、章内をさらに①②③……と分けて短文でつないでいくスタイル、ゴシック体と明朝体のつかいわけ、などなど工夫が凝らしてあるのもおもしろい。小説ってそうだよな~自由でいいんだよな~と改めておもえる。
というふうに、ついついスタイルに魅せられてしまったけど、中身については、巻末の内田樹の解説を読むことで、「アッ~そういう背景の物語なのか」と思う、&「じゃあ村上春樹はこういうの嫌いだったりすんのかな……」と思ったりもした。いろんな全共闘。
⑤『一号線を北上せよ ヴェトナム街道編』沢木耕太郎(講談社文庫)

これね、古本屋で100円だったからずっと前に買ってたんだけど、なんか読まずに置いていて、で、『ジョン・レノン対火星人』読んだら、今度はまとも~なやつが、事実を書いただけのやつが読みたくなっちゃって、沢木さんの旅行記に手を出した。
2000年ころ、アマゾンで飛行機落っこちてギリ助かったとかいう伝説をお持ちの沢木先生、体をぶっ壊しながらも、「これ、旅行行った方が治るくね?」というマジで深夜特急全開な思考回路でベトナムに来ちゃう。
寝てろし。
でも沢木先生は寝ません。ホーチミンからハノイを目指すバス旅がスタート。
ワケわからんパッケージツアーで観光楽しんだり、「異国におるこの雰囲気、最高だぜ、ふ……」みたいな感じになったり、道間違えて詰んだり、林芙美子を読んだりする。ほんとに、『深夜特急』のヴェトナム編だな~っていうようなもので、『深夜特急』ファンからすればとてつもない安定感にのっかって読める。
ただなんかね、すんごくリーダブルなんだけど、大事なとこを触れてないような気もして、なんか「もっと激しい部分がほんとはあるのではないかな~」みたいな気がしてくるところがあって、読書体験として物足りないかなあというのもちらついたけど、『深夜特急』の未読の章をいま読んでる、みたいなふうに思えるというのは、よかった。あれはマジで夜中まで読んだからな。大2の時。
沢木さんあるある(?)として、映画とか小説の紹介→引用→本編、みたいな書き方がよくあるけど、今回もホテルのバーで「ミス・サイゴン」というカクテルを飲むとこで、ミュージカル『ミス・サイゴン』の話をしたりする。そんでミス・サイゴンを飲む。
出てきたミス・サイゴンは、スピリッツにライムを絞り込み、甘みを加えるために何らかのリキュールを数滴たらしたものだった。しかし、そのリキュールが何なのかは、私の粗雑な舌では識別できなかった。(p.43)
……いや、わかんねーのかよ!!
しかも粗雑な舌て……そこまで言わんでも……
というように、ルポを書いている人でありながら、旅行記では緻密さをほとんど意識しない書き方をつらぬく沢木先生節を堪能できるのでした。
⑥『季節の記憶』保坂和志(中公文庫)

谷崎賞のHOSAKA作。どこかのインタビューかなんかで、著者にとっても重要な作品だと語られていた気がする(最近お昼食べながらよく保坂のインタビューをスマホで読んでる)。
「プレーンソング」「草の上の朝食」はたまた「カンバセイション・ピース」ともつながる、似た作風の一作。主人公の「僕」は、雑誌の編集の下請けを仕事にしていて、鎌倉・稲村ケ崎の古いアパートに、小さい子どもと二人で暮らす。近所の美紗ちゃん・松井さんという年の離れた兄弟と仲良くなり、お互いの家をほとんど我が物のように行き来して飯を共にする。蝦乃木さんというオッサンから電話がかかってきたり、二階堂くんが突然家にやってきたりする。思い思いに日々を過ごし、時が流れていく、という、これもまたそれだけの話。
キャラの立ち位置は、それぞれけっこう「プレーンソング」「草の上の朝食」にそれぞれ当てはめられる人がいた気がするけど、「季節の記憶」では、何と言っても息子のクイちゃんの視点があることがちがう。
「うん。つぼみちゃんが字、書くけどクイちゃんが字、読まないからお姉ちゃんと弟ってクイちゃん、とつぼみちゃんが思ったの。お姉ちゃんは学校から帰ってきたら勉強、しなくちゃいけないんだけど弟は学校、行ってないからお姉ちゃんは勉強、して弟は遊ぶの――」(p.340)
保坂作品は、特異なように見えて実はマジでやばいリアリズムだよ、みたいなことを「プレーンソング」の解説で石川忠司が書いていたけど、これもそれに通ずるものをもった箇所で、(明確にそのことに触れている箇所が作中にあるけど)子どもが話すとき特有の息継ぎの不自然さを、文に忠実に反映している。「あ~わかる、こういう話し方するわ」ってなって、子どもが話している様子が脳内にはっきり流れる。
細かいように見えて、ここをサボるとたぶん、実際よりも子どもがずっと優秀な存在になってしまったり、物語の中で必要以上に意味を持ってしまったりするかもしれない。そういうのを防いで、マジで「ただの子ども」として描くためにはこういう工夫がいるのだ、ということか。
クイちゃん、鼻水たらしたりするシーンは別にないけど、すんげえ鼻水たらしたわんぱく小僧なんだろうなと個人的には思うし、なんていうかね、あのちいさい男の子特有のにおいが、文からむんむんしてくる。
どの方向から見ようが山は山で同じ一つの山であることに変わりないし、人に見られなくても山も海も存在していて、それはなんというか、じゅうぶんに自足している。(p.134)
保坂っぽいフレーズもユーモアもしっかり多数ある。
それからもうひとつ紹介するなら、両親が離婚している話なのに、別れた奥さんの影が暗く差すようなシーンがまっっったくないということ、同性愛者の二階堂くんに対する主人公の態度がすっごいあっけらかんとしていること(クイちゃんは二階堂くんとなかよし)、などなど、なんかほんとうに、「小説ならついつい意味を持ってしまいそう(だと読者の多くが考えがち)なこと」が、全然意味を持たないで、ただただ当たり前のこととして流れていく、というのは着目してもよい点。96年初出の小説なので、もろもろ、令和とはだいぶ価値観がちがかったと思うんだけど……だからか、そのへんもすごく心地いい。圧迫感がまったくない。すべてがユーモアに帰している。
文庫で360ページ弱と、まあまあの読みごたえがあるけど、「プレーンソング」などが好きならぜったいこっちも楽しめる。
「デカい物語だァ……」みたいな感動ではない。そもそも、これほど展開らしい展開のない物語を、どれくらい「ものがたり」と呼べるのかわからない。
でも、とても逆説的なことに、保坂作品は、そのページをめくるたび、本棚に一冊ずつ置いていくたび、自分の心のなかに「ものがたり」がつもっていく確かな感覚をくれる。あたたかい、きらきらした、やさしくて無垢な時間。それはきっと、小説という虚構のもつ、すばらしい力のひとつだ。
⑦⑧『未明の闘争』保坂和志(講談社文庫)

野間文芸賞とったHOSAKA作。
単行本の発売が2013年なので、かなり最近の作品と言っていいと思う。
文筆家っぽい主人公が、アキちゃんとご近所さんといっしょに、妻の不在の夜に家の中でだらだら話してる、っていう、これまでの保坂作品とも近しい設定の場面がキホン……のはずなんだけど、回想とかがぐるんぐるん混じってくる、しかもそれがいっこいっこめちゃくちゃ長い、というのが設計図か。読んでて、いまどこだよってなる。
冒頭、
(略)私は一週間前に死んだ篠島が歩いていた。(上p.7)
っていう、「……どれがなに?」文からスタートする。(これについて触れてるサイト、いくつかあるよね)
こういう、あえて主述をぐにゃっとさせる文章自体については、著者から色々と発言もされているので、考えや意図があってあえて崩している訳で、そこはまあ純粋にそのスタイルの文から感じられることを楽しめばいいと思う。「ただしい文」ばっかりだと、フィクションを書く上では行き止まりになるってのは想像もできるし。
でも、それはさておき、やっぱり中身こそおもしろくて、キーになりそうだなと僕が思ったのは、『未明の闘争』では、「喪失」「死」がひとつ重要なモチーフになっていること。
まず、篠島が死んでいるでしょ。それだけじゃなくて、作中、けっこう大事な立ち位置の女の子もぷいっと消えちゃう(「春樹!?」と思った)。あと、これはそんなにそこに影響してないかもだけど、奥さんがいるのに、ずうううっと家を不在にしてる。帰ってくる気配も全然ない。
そういう「失ったもの・失われたもの」が、重厚な雰囲気を醸し出していて、「カンバセイション・ピース」あたりまでにあったひょうきんな軽快さが、ちょっと影を潜めてる。文章自体はユーモアっぽい雰囲気もあるんだけど、その奥で語られてることはけっこう重くなってきている。
「隣のおばあちゃんにもこんな娘時代があったんだ。」ということを発見し、その途端に、/「この子にも老いが内包されている。」/と思ったのだった。/ 人は四十九日かけてあの世に到着する。……(後略)(上p.54~p.55)
保坂自身も2013年だともう還暦目前だからなのか、主人公はこれまでの作品に比べて年をとったという思いを抱かせる。若さの喪失についての思いが、上の一節には出ている。
だいたい見るというのは一人でするのではなく、心にかかっている誰かといつも一緒にする。(上p.110)
出てくる風俗もボブ・マーリーや楳図かずおなど、絶好調。楳図かずおの引用クソしつこいけどなんかぐいぐい読んじゃった。
そう、なんかね、いっこいっこの描写は「クドい!」って言いたくなるとこは、確かにあんだけどね。でも、読み終わった後は「よかった……」ってなる。「未明の闘争」っていうタイトルが、すごく大きく、暗いムードで全体をかっこよくまとめてくれるんよね。
文庫だと上下巻で読みごたえはこれもまあまああるけど、おもしろいです。チャーちゃんの話とかめちゃくちゃ出てくるし、ごめんだけどクドい、ってところどころなるかもだけど、全体のテーマがテーマなだけにむしろ若い人のほうがこれウケそうだな。分量的にもGW読破にちょうどいいかもね。
⑨『先端で、さすわ さされるわ そらええわ』川上未映子(ちくま文庫)

川上未映子の詩(これ詩であってます?笑)。高橋源一郎がめっちゃ評価してたはず。
女子の内面をひっぱりだした、というわけでもないのか、なんかうまく言えないけど、明らかに書き手は女性だ、ということは意識できる感じで、めっちゃリキッドな文体で自由~に川上流世界のとらえかたが描かれてる。
川上未映子って「たけくらべ」の現代語訳とかもやってて、そもそも伝統的な日本の文体ってリキッド(句点でどんどんつないでくとか、切れ目があいまいでだらだら流れるような文章)だよね、みたいな話があるっぽいんですけど、まさに「たけくらべ」ってそういう文章で、川上訳はそのリキッド感がかなり上手く残されてるんだよね。文の流れとか、息遣い、音感に相当敏感な人なんだろうなということを感じてます。「たけくらべ」気になる人はチェックをば。
で、それかっこいいよな~、と思う次第。意味にがんじがらめにならないで、音先行で文章つくれるって、マジセンスだよな~。
真夜中、ほんまの真夜中に、視線が背中に食い込むん感じて振り返ると幼児のわかたしが泣いているではありませんか。話しかけても無言話しかけても無言でだんだん悲しくなってくる、はれまこんなに小さかったけか幼児対応のわたしは襟のだるだるにゆるんだ青いタンクトップを着ています、……(後略)(p.16)
終始こういう世界。流れがすごい。ズラーーーーっと読めて、意味もイメージも入って来る。
(略)馬鹿馬鹿しいと思うかもしれないけど、僕は、ききみに、僕の顔をみてほしいよ、こうなったときに、僕の体をみてほしいよ、こんなふうに僕と離れて電話をかけたりしないでほしいよ、……(後略)(p.135)
ここはけっこう思いがこもってる感じで、意味先行かもだけど、それでもそういうのはこの本のなかでは珍しいくらいだと思った。
でね、文庫版なのに解説が、まさかの無し! すごいよね。オメェが読め、なにかを感じやがれ、さもないとちょっきん、なー。ということか。
⑩『空港時光』温又柔(河出書房新社)

温又柔さん好きなのに、これちゃんと通して読んでなかったとかバカなのかなと思って読みました。
台湾出身の温さんは、台湾出身だけど日本語が母語(と外から言い切っていいのかどうか)のような感じで、日本に生きる台湾ルーツの女性や、台湾語・中国語(北京語)にまつわる物語を数多く執筆されているひと。もう、絶対代わりのいないひとだし、(単純な動機なんだけど)やっぱり外国につながる物語ってそれだけでわくわくするので、好きな著者です。
「空港時光」は、空港をめぐる10の掌編~短編サイズの物語。それぞれの人物が交錯したりはしないけど、「空港」っていう共通の場所を通すことで、行き先・帰り先になっている日本と台湾のイメージに、厚みが出る。
空港っていうロマンチックな場所が設定されているし、男女の話も当然盛り込まれているけど、ただただロマンスが繰り広げられるだけではなくて、日本と台湾の歴史が、それぞれの登場人物の視点から、それぞれの思いをもとにして、つまびらかになっていく、という面もある。
まずは、日本語じゃない言語を混ぜるっていう書き方をつらぬいているのに、文章が読みやすいっていうことと、オムニバスでさくさく進むのが心地いいっていうこと。ただし、個人的には、ほかのしっかり分量ある温又柔作品にけっこう感銘を受けているので、ひとつひとつが短すぎて物足りないな、と思ったっていうのは正直な感想としてもったところ。
これから温又柔さんを読む~っていう人には、個人的にはデビュー作の「好去好来歌」(白水uブックス『来福の家』収録)か、オダサク賞とった「魯肉飯のさえずり」をオススメしたいかな。こっちはその後に読むと、もっと楽しめる気がする。
⑪『もうひとつの季節』保坂和志(中公文庫)
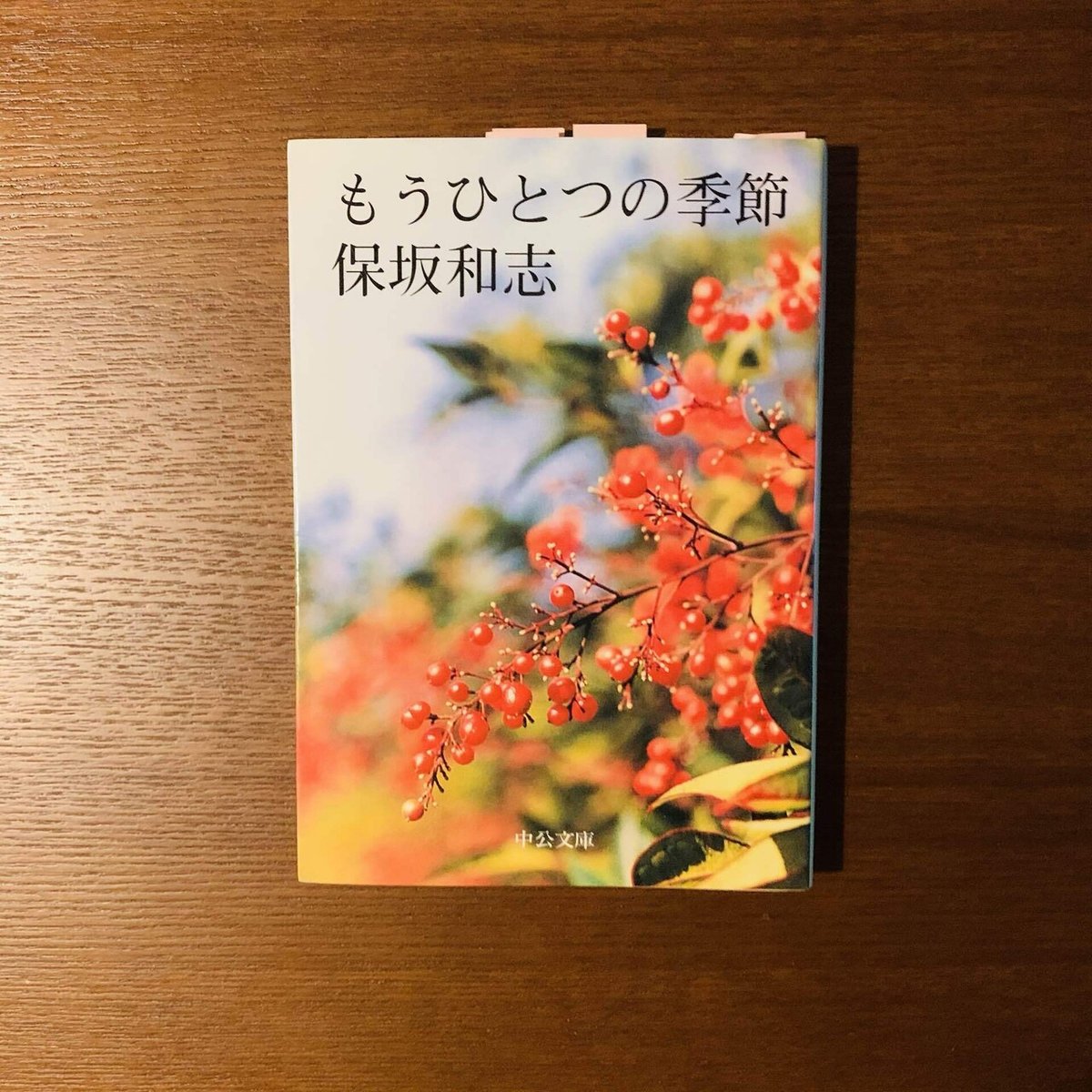
先述の「季節の記憶」の続編。
クイちゃんが相変わらず大活躍する話だけど、変わっているのは、かわいい挿絵が大量に入っていて、読んでいてなんかとっても朗らかな気持ちになるということと、猫の茶々丸をめぐってひと騒動あって、わりに「オッ」っていう展開があるということ。
分量は「季節の記憶」と比べるとかなり短い、半分以下。だから「プレーンソング」→「草の上の朝食」のときと同じような感じにはならないかな(工藤さんも出てこないし)。
「季節の記憶」自体がけっこう完成されていた感があったけど、でもたしかに保坂作品って決定的な大展開がないぶん、こういう続編が出てきても全然違和感がない。むしろ、「そうだよな、この作品に出てきた人たちも、この人たちなりにいまもどこかで年を取って、暮らしてるんだよな」みたいな気持ちになる。あたりまえに暮らしてるんだよな、と思う。
ほんとうに、もう本のつくりの時点(挿絵多すぎ)で「もうひとつの季節」なので、「季節の記憶」から読むのがいいんじゃないかな、と思う。養老孟子さんは「もうひとつの季節」から読んじゃったみたいだけど。
⑫『すべての、白いものたちの』ハン・ガン/斎藤真理子訳(河出書房新社)

ハン・ガンは「菜食主義者」でハマった作家。
昨今、韓国文学ブームはまだまだ続いてると思いますけど(新刊出るペース頭おかしい)、「菜食主義者」はアジア出身者初のマン・ブッカー国際賞とったやつで、クオンの「新しい韓国の文学」シリーズの1作目で、都甲幸治さんの『引き裂かれた世界の文学案内』でも取り上げられている小説で、もうとにかくいろいろとスゴイ作品で、ちょっと格が高め。以前のnoteで触れるので参照されたし。
それで、ああ翻訳読みたいなーと思って、ハン・ガンもう1作、と思って書楽で探してたらこれと目が合った。まず装幀がいいよねー。中身そんなに知らなくても、装幀次第で「買う!」ってなるもんね。やっぱり装幀って大事だよな。
中身は、「白」いものに関するごくごく短い、もう掌編以下みたいな長さの文章が連綿と続いていく。詩集なのかなと思ったけど、とおして読んでいくと、小説のもつ推進力みたいなものを感じてしまって、詩ではないのかなあと思いなおしたり。
著者が長編を執筆後、ワルシャワに滞在する機会があって、そのさいに書かれたものだということ(だから風景にはポーランドっぽい「寒さ」が影響してくる)。
二か月ほどが過ぎ、寒さがやってきて、私にとっては長いつきあいの重い片頭痛のために、夜、コップ一杯の水で薬を飲み下したあとで、(淡々と)私は悟った。どこかに隠れるなどとはしょせん、できることではなかったと。(pp.9-10)
冷気が肺腑の闇の中に吸い込まれ、体温でぬくめられ、白い息となって吐きだされる。私たちの生命が確かな形をとって、ほの白く虚空に広がっていくという奇跡。(p.91)
まず思うのは、すっっごく詩的な言葉を操る人だな~、ということ。(月並みだけど)暗くて、さみしくて、そのなかに一筋スーッと光が差し込むような、とんでもない美しさをたたえた言葉がズラズラ並んでいる。
「梨泰院クラス」で、チョ・イソが済州島で詩を読んで、マ・ヒョニにその言葉を贈る(で「ガンバレ」ってエールにする)シーンがあったけど、韓国では日本なんかよりもはるかに詩が身近、というのはたしかに聞いたことがある。
だからなのか、日常からするすると抜け出した、そういう感覚の言葉をもって表現することが、あっちでは「つくる」側にも、「よむ」側にも、もしかするとけっこう体に根付いたことなのか? と、かっこいい考えに至る。んですけど、飛躍してますかね?
いや、そこまで飛躍してないんじゃないかな、と思わせてくれる、自然なハン・ガンの言葉のはこび。
ハン・ガン個人の詩的センスが脱帽ものであることは当たり前だと思うけど、そもそも韓国にそういう人をはぐくめる土壌が(日本なんかと比べると)より強くあるんじゃないかな~と考える。少なくとも、そう考えたくなる。
内容は、(相変わらず)「死」の雰囲気が漂うもの。生まれて間もなく死んだ、「私」の姉。どこか「菜食主義者」に共通してくる。でも、重厚な死のムードじゃない。ふんわりとした、だからこそ危険な、連れていかれちゃいそうな「死」の雰囲気。
じわりじわりとこちらを蝕む、あやしい「死」の雰囲気。
なんかさ、『菜食主義者』もそうだけど、『中央駅』(彩流社)とか、けっこう(「死」じゃないまでも)ギリの世界線で生きてる人、みたいなの出てきますよね。この辺の作品、ほの暗いムードが通底してるな~と思う。『砂漠が街に入り込んだ日』(リトルモア)とかも。言葉は詩的で、で、書かれているものの「朽ちていくさま」を眺めているさまが描かれる。みたいな。
うん、なんか共通点がある気がする。気になりすぎる。。
ということで韓国文学もうちょっとディグりたくなった。まずはハン・ガンをも少し読もうかな。
ちなみに、この本、ネットでは訳者の斎藤真理子さんによる解説もあって、基本的な章立てとかの解説のほか、出版にあたっての裏話がいろいろ読める。「全部読んでからこっちを見てね」との但し書きがついているので、従ってくださいまし。
⑬『アメリカン・スクール』小島信夫(新潮文庫)

保坂和志といえば小島信夫、みたいなところがあるから読んでみた。
「第三の新人」、だからこないだ読んだ庄野潤三とかとひとくくりにされがちで、たしかに新潮文庫の短編ベストみたいなつくりは似てる。大正~昭和初期の「大長編つくるゾッッ」っていう流れに逆行して短編書いてたひとたちみたいな捉え方もあるらしい。何をもって「第三の新人」なのかはよく知らんけど、なんか飄々としてますよね。みなさん。
『アメリカン・スクール』は8篇収録しているもの。
おもしろかったものをあげると、「汽車の中」は、終戦直後の混み過ぎてる汽車のなかでのドタバタ活劇に、めちゃめちゃ暗いオッサンの内面が入り込んできてる、ブラックなユーモア劇。
カーブが来たら列車から放り出されそうでもうヤバい、とか、ギュウギュウすぎてトイレにいくために掻き分けなきゃいけない人波の詰まりすぎな状態を見て絶望する(しかもトイレにすら乗客がふつうに座ってる)とか、荷台に楽勝で人が寝てるとか、寝台特急でもないし大型連休でもないのに、まさに「すし詰め」の車内。
ウソだろこんなの、と今見ると思うのだけど、うちのおばあちゃんがね、日立の海辺の生まれなんだけど、終戦後、汽車に乗って東京に塩を売りに行ってた話をむかしよくしてくれて、そのときの情景にソックリだったの。びっくりした。ほんとに混み過ぎてて頭おかしかったって言ってたから。しかも汽車が遅すぎて全然進まないもんだったらしい。「あーこれか!」と思った。
祖母の話してた情景に不意に出会って、しかもけっこう嫌な話なのにユーモアが効いてるから不思議と活き活きしていて、なんていうか、モノクロ写真みたいな世界でしか思い描けてなかった「終戦後」の世界に、どんどん色が付いていくような、ほんとの人が実際に生きていた世界として具体的にイメージできるようになっていくような、そういう心地だった。
但し、かの女は、握り飯の腹にあてた指を、それまでに、いまどきどこで入手したのか、アルコールを浸した綿で消毒を終っていたのだが――(p.39)
当時もアルコールで消毒してたんだ……と思うとおかしい。
あとはね、なんといっても「馬」!
これはすごい! キョーレツ!!!
ある日家に帰ると、いきなり我が家が増築されかかってて、「は? なにこれ?」ってなって、奥さん(トキ子)に聞いたら「え? わたしが建ててるよ?」みたいになって、「は? なにが?」っていう。
「え、おまえの家だよ。」
「……!!?」
「え、ダンナ(奥さんのこと)、これ馬小屋にすんでしょ?」
「あ、これ馬小屋にすんだっけ。じゃあそうしよ」
……!!?
家を建ててる間、「僕」は家のすぐそばの精神病院につっこまれる。「僕」は自分ちが気になってしょうがないから、窓から自分ちをずっと見てる。すると、夜。あれ、男でてきた? えッ、トキ子ォ……
GTOの教頭みたいになってくる「僕」。でもその「僕」というのは……っていう話になったり。
馬がやってきて、その家の二階が「僕」の部屋になるんだけど、馬スペースに本棚が大充実したり、トキ子の鏡台が入ってきたり、なんか明らかにおかしいことになってくる。
「動物をかわいがったことのない人には何にも分らないわ。そんな人はにんげんだってほんとの気持、わからないのよ」/「あいつは、おれたちとおなじ言葉をしゃべるじゃないか」/ するとトキ子はおかしくてたまらないといったふうに笑いだし笑い終ると急にツンとして、/「しゃべって悪いの」(p.333)
全方位を疑わざるをえなくなってくる「僕」に、トキ子は「でもあなた、私に告白してくれたもんね」みたいなことをところどころで差し出してくる。なんやかんや言うけどあなたとわたしってラブラブよね。で、あなたのほうがこの関係においては責任を負う立場よね。わたしがあなたの告白に応答した立場であるのだから、主導権はわたしにあるのよね。……田中みな実でもそんなんやらんぞ。
そんな風に話が進んでくんだけど、まあ話の筋は説明できなくはないけど、この作品のすごいことは、情景が先にあって、それを言葉でなぞっていくっていうスタイルじゃなくて、もう完璧にね、言葉が先行して、それに世界がつられていっちゃってること。
主人公が病院から見た人影は誰だったのか? 電車に乗っているといつのまにか隣に来てたトキ子はいつからそこにいたのか? そもそも「馬」はなんだったのか?
だから常識的なものさしで図ろうとすると、ぜんぜん意味わかんない。「えっ、これどうなってんの? 絵でかくとどうなってんの?」ってなるとこがいくらかある。でもこれ小説だから。言葉で引っ張れる媒体ですから。そのまんま読めばいいっていう話なんだと思う。
「りんごがテーブルの上にあります」っていう文があるとして、その奥に隠れている状況は、「トキ子がテーブルにりんごを置いた」なのかもしれないし、「テーブルの真ん中からりんごがボンッと突然でてきた」なのかもしれないし、「あっちのテーブルにはりんごがあるけどこっちのテーブルにはりんごはない」かもしれない訳で。「わたしの頭のなかのテーブルにはりんごがあるけど、現実のテーブルにはりんごなんか一個もない」かもしれないし。
絵だとさ、「これはトキ子んちのテーブルだから、トキ子の家のテーブルにりんごが置かれてるっていう絵だねー」「こっちのテーブルには完全にりんごあるけど、そっちのテーブルには完全にりんごないね」っていう話になるけどね。
小島信夫式文章は、そのへんの「あやふやさ」をガンガンついて来る。文章にしかできないおもしろいことを、たくさんやっている。
だから個人的にはカリカリしっかり言い当てようとしているみたいな江藤淳の解説にはなんとなく違和感があったし、保坂和志の解説もそれよりはいいんだけど、「だからってこの文章を真似しようとしても……」みたいな感じを受けてしまう。ある時以降の保坂文に違和感があるのは、だからだったのか……ってなった。
言葉はなんでもできる。どこでもあらわせる。読んでいくうちに言葉に魅せられる、すごい1篇だった!
(※「馬」、村上春樹が『若い読者のための短編小説案内』で取り上げてます)
⑭『「利他」とは何か』伊藤亜紗編、中島岳志、若松英輔、國分功一郎、磯崎憲一郎(講談社新書)

話題の(?)一冊。新書コーナーで幅きかせてますよね。
著者5人が、コロナ禍によせて「利他ってどういう生き方?」みたいな話を、それぞれの専門分野から話す。
新書だからさすがに紙幅がぜんぜんなくて、それぞれの言いたいことの5%くらいしか言えてなくね? 感があって、だいぶ物足りないと思ってしまった&そもそも利他どころか専門分野の話も十分にできてないので、これら5名の本を気になっている人むけの自己紹介本、っていうくらいかなと感じました。「利他」については正直、むりやりつなげてるだろこれ、っていう感じを受けないこともなくて、5名が所属してるセンターの研究もこれからなのかなあっていう。
個人的に伊藤亜紗が気になってて、読んでみたい本がいくつかあったから買ったっていう動機なので、伊藤さんの文章に触れられたのはよかったな。
あと、中島岳志が志賀直哉とチェーホフを引き合いに出してたのがいちばん「利他」の話としてはおもしろかった。
それからイソケンだけはぜんぜん「利他」っていう言葉につなげようとしてすらいなくて(笑)、先述の小島信夫「馬」の話とか、なんか引用ばっかりして小説のかたちの話で終わらせてて、「オイッッこれでいいのかよ!!!!」ってなった。あとがきの中島岳志フォローなかったら意味不明だったぞ。なんか……これでいいのか、本……
**********
今月はまんがもおもしろかった。下記。
・ブルーピリオド(山口つばさ)
→スポ根美大受験漫画。美大受験マンガな時点でおもしろいのに、余計おもしろいのは、主人公が金髪リア充ヤンキーなのに、めっちゃ繊細で、人付き合いに空虚さを感じてるっていう超令和設定なこと。創作に熱を注いでいるひとのための至言満載。
・水は海に向かって流れる(田島列島)
→読んだら死ぬラブコメ。以上。設定がやばい。これはやばい。全3巻なのがいい。
・子供はわかってあげない(田島列島)
→あ、おれこの人の絵がそもそも好きだなってなった。海!
・ハチミツとクローバー(羽海野チカ)
→ようやく読みました。真山ッッッッ。「ハチミツとクローバー」ってそういうことか……
それから4月は、書肆侃侃房のムック『ことばと』で、「ことばと新人賞」受賞した「ゾロアスターの子宮(大沼恵太)」が鬼すごかった~。小島信夫「馬」より先に読んだけど、似たような感じで、言葉が先行して世界作っちゃってる&家がイカレていくっていうのが共通してる。何が起きているのかつかめないまま、ついつい読んじゃって、文章自体にひきこまれる。ちょっとスリラーっぽい感じで、ビビリなわたしは背筋ゾーッってなりながら文を負いました。すごかった。すごい読書体験だった~。
小島信夫「馬」に引き込まれたのも、この作品に惹かれたからかもしれない。
あ~、この感覚!この感覚をもっとじょうずに説明したいな。文字が化ける、というかさ。デタラメ言ってるはずなのに文字がめっちゃ「語ってくる」っていうかさ……あ~~~、この言語化をさぼったらだめだな。
ゴールデンウィーク折り返してほしくないな。スマブラしよっかな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
