
とある民間伝承が残った土地•前編【創作】
あの日の出来事を、
子供達は「思い出」と呼び、
大人達は「怪談」と呼んだ。
◆創作絵本マーケット
2024年5月3日。
とある地方の町で催された創作絵本マーケットへ行ってきた時の話である。いわゆるコミックマーケットの絵本版のようなもので、プロアマ問わず様々な絵本作家の作品の売買が行われていた。加えて地方の町で催されていたイベントなので、都心で開かれるものに比べて人がごみごみとしていなくて丁度良かった。
どの絵本を買おうか。会場内を歩き回っていると、面白そうな作品を見つけた。絵本といえば大体は小さな子供向けの作品が多い。しかしその作品は自身が親なら絶対にお勧めを躊躇う、子供には重すぎるテーマだった。
「これって、人身御供がテーマですか?」
大人にも重すぎるテーマな気さえする。作者である、児童文学作家の男性は自信満々に「えぇ」と言って頷いた。立ち読みはしない主義なので、購入すべきか迷う所である。
「ちなみにこの人柱、おしろのお話はモデルなんかはあるんですか?」
「このお話はこの淵背町を流れる萩生川の安庄土手に佇む、おしろ明神と呼ばれる小さな石の祠にまつわる伝説をモデルにしています。現地には伝承の概要が書かれた看板もありますのでぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。」
「へぇ〜、ところでなぜこのようなお話を書こうと思われたのですか?」
「………実は、この人柱伝説を子供の頃に聞いて感銘を受けたんです。加えて私はおもに怖い話や不思議な話を絵本や児童書として出しているので、作家になった暁にはこの伝説を絵本に起こそうと決めていました。規制だ不適切だと煩く言われている世の中ですが、残酷さや物悲しさを通して子供達に何かを訴えれたらなと思って作った一冊です。ぜひ、気が向いたらで構いませんので買ってみてください。」
結局、私は男性の作品に対する情熱と購買欲に負けてその絵本を買った。
久しく絵本に触れる機会がなかったからというのもあるが、やはり「子供向けであるのに人柱をテーマにしている」点がどうしても気になって財布を出してしまっていたのだ。無論、立ち読みはしていない。会場の外のベンチに座り、絵本『ひとばしらのむすめ』を読んでみる。
………読了してみて思ったのが、確かに重いテーマではあるものの、不思議とどこか美しさがある物語だった。
●飼い猫の視線
東北地方某県の淵背町に住む米原雅恵さんの家では猫を飼っている。キジ白のオスで、名前は橅(ブナ)という。現在では人間で言うところのお爺ちゃんに匹敵する老猫である。非常に素っ気ない素振りを見せるが、時折甘えるてくる姿は愛苦しくいのだと、米原さんは橅の可愛さを自慢した。
そんな橅が、たまに誰もいない方向を見つめている時があると言う。その様子を動画にも収めていたそうなので、見せていただくことができた。動画内では2回程、橅が何もない所を見つめている姿が収められている。


顔を洗っている橅が【0:02】と【0:34】の辺りで、画面左側、向こう側を見つめているのが分かる。



2回目の【0:34】に至っては、視線の方向へ向かってノソノソと歩いていった。
「家の中にいる時も、外にいる時も、いつも同じ方向を見ているので何だか気味が悪くて。」
確かに猫は、人間には感知できない邪気を感じ取ることができる。と、されているがその行動に深い意味はない。猫は聴覚が敏感で単に耳を澄ませているだけでどこも見ていない。なので、人間から見ると何もない所をじっと見つめているように見えるのだ。人間の耳では聞こえない音を聞いているだけ、なのである。しかし米原さんは、その可能性をも疑っている。
「だとしたら、橅が見ている方角に何の意味があるのでしょうか?気になって調べてみたら、橅はどこへ行っても、一定の方角に視線を送っていることが分かったんです。」
そう言うと、米原さんは赤線が5本引かれた地図を見せた。丸状のマークのある場所は、橅が突然知らない方向を見つめ出した場所。そこから伸びた矢印付きの線は、橅が見つめていた方角を指している。
家の敷地内、ひいては外へ散歩に出かけた際に橅がひたすらに見つめていた方向を、スマホのコンパス機能を用いて記録したものだ。

「ここ、線が重なっている場所がありますよね?山の中なんですよ。何があるのか気になって行ってみたら、寂れた祠があったんです。生い茂った木々や草に囲まれて佇んでいて、ぱっと見ただけでは祠の存在を確認できなかったかもしれません。」
写真は撮りましたか?と尋ねてみると、米原さんは「なんか分からないんですけど、とても不気味な雰囲気だったので撮ってないですね」と答えた。加えて、帰宅後に橅の様子が変わったと付け足した。
「普段は塩対応な橅なんですけど、祠から帰った後になって異様に私に甘えてくるようになったんですよ。本当に何ででしょうかね。」
●行方不明事件の多い地区
「いい加減、勘弁してほしいもんです。」

愚痴をこぼした宇崎篤(53)さんは、現在から38年前に弟の宇崎一郎(50)さんが行方不明になったことを話す。
事件は昭和61年、西暦1986年の7月下旬に起こった。当時の一郎さんは友達と一緒に遊ぶよりも一人で遊ぶことが多く、それに見合った行動力も伴っていたそうだ。その影響か、幼い子供であるにも関わらず両親は半ば放任主義な所があった。6歳になった一郎さんは夏になると、虫籠と網をお供に蝉やカブトムシが大量に生息している長束山地区へ一人で出かけるようになった。その日も一人で出かけたのだが、夕飯の時間になっても一郎さんは戻らなかった。行方不明の状態は4日ほど続き、地域の方々が協力して捜索を行った。駐在さんや消防団も出動する事態となった。
行方不明のままではなく、行方不明になった、と篤さんが言っているように一郎さんは、一時は行方不明になったものの、四日後に長束山地区の茂みにて、蹲って眠っている状態で発見された。安堵したものの一郎さんは何だか様子がおかしく、山で何があったか尋ねてみても「話したくない、話しても信じないでしょ」といって頑なに自分の身に起きたことを話さなかった。
事件後、組合長さんに叱責されたこともあって、かくして両親の放任主義はなくなった。その後の一郎さんの様子も、山で起こった出来事について黙っている以外は特に変わったところはなかったそうだ。現在は栃木県に住んでおり、篤さんと関わることは必要な時以外はあまりなくなった。再会しても、長束山でのことを追及するつもりはないと言っていた。

「あん時は本当すごかったです。地域のみんなで探し回りました。地域のおじさんたちが、お寺からホラ貝やあたり鉦を借りてきて鳴らしながら一郎を探していたのは今でも覚えています。」
行方不明になった子ってのは他にもいるんです。
そう言って篤さんは自宅の近くに住んでいる小松重一さん(43)を呼び、自身を紹介していただいた。彼もまた、同級生で仲良くしていた女の子が長束山へ一緒に遊びに行って、一時の間行方不明になったことがあるのだという。

「小学校1、2年生の頃かな。あの日はその子も含めて学校の友達数人と缶蹴りをしたんだよ。場所は長束山の近くの原っぱで、全員あっけなく見つかったんだけどその子だけはいつまで経っても戻らなかったね。日も暮れてきちゃって、みんな探そうとは口々に言うものの怖くてさ、結局父兄を呼んできて大きな騒ぎになったよ。」
宇崎一郎さんの時と同じく、この時も当たり鉦とホラ貝を鳴らしながら捜索を行ったそうだ。そして5日程経って、長束山の麓で泥だらけの状態で気を失って倒れているところを発見された。
当時、長束山地区近辺や淵背町内では行方不明となったその女の子を探すための協力を仰ぐアナウンスが連日流れていた。重一さんのお父さんはその音声を録音しており、ご厚意によりその音声を聞かせていただくことができた。わざわざカセットテープを取りに一度ご自宅まで戻らせてしまって本当に申し訳ない限りである。篤さんは「あぁ、懐かしいねこれ。」と頷きながらテープ音声に耳を傾ける。

こちらは防災ふちのせ、防災ふちのせ
淵背北警察署から
行方不明者の発見について
お願い申し上げます。
本日、午後3時46分頃。
淵背町長束山地区から
7歳の女の子が
行方不明となっています。
特徴は、身長は125cmくらい。
中肉中背、黒髪のおかっぱ
くすんだ××××シャツに
ジーンズの短パンを履いて、
×××××のスニーカー
を履いています。
見かけた方は110番通報、または
淵背町北警察署までお知らせください。
※×××はノイズで判読不可だった箇所
「気になるのは、アナウンスの所々にノイズが入っているんだよ。その騒ぎからだいぶ経ってからの話だけど、このことを思い出してさ。大学時代に同じ学部の先輩でコンピューターに詳しい人がいて、そのノイズが入ってる箇所を解析してもらったらさ、何ていうか………猫の鳴き声のような、女性のか細い声みたいなのがまざっていたんだよ。何か、不気味でさ。何喋ってるか分かんないし。」
カセットテープの音声にノイズが入る原因として再生機器であるカセットデッキ内部(ヘッドやキャプスタン、ピンチローラー等)に汚れがついていることが殆どであるとされる。
持ち主である重一さんのお父さん、そして息子である重一さんは現在もカセットデッキの手入れを欠かさないようで、汚れることはありえないというが。1990年に録音されたこの音声には、確かにノイズは入っている。修理屋さんにも頼み込み、何度もノイズを消そうと試みたが、今も消えないそうだ。

「まったく関係ない話なのですが、このチラシは2枚ともデザインが似ていますね。同じ方が作ったのでしょうか?」
私のさりげない質問に篤さんと重一さんは苦笑いしながら「そうだよ」と答えた。


「この二人だけじゃないさ、この地域では何度も行方不明者が出てるんだよ。決まって年齢が5歳から8歳くらいのちっちゃい子が。あまりにも多いもんだから、チラシのデザインもテンプレートができてるんだよ。また、出た時にすぐ印刷ができるようにさ。」
「もっと細かいこと言うと、60〜70年代あたりの古い頃のチラシには行方不明になった年代のみ書かれています。そして80年代あたりから現在に至るまでは、失踪した時間の短さと発生する頻度の多さから、このように日付まで書くことにしたんです。」

後で調べてみて分かったが、昨年の2023年にもこの町では小学2年生の女子児童が一時行方不明となった。1960年代あたりから、現在に至るまで淵背町では子供の行方不明事件が多発している。こんな背景があってか、地元を離れる人が年々多くなったり、この町に移住してくる人は少ないのだという。
*取材テープの文字起こし
2024年4月29日のXの投稿。

そう、これこれ。この「かどぅ脇」さんって人がXに載せてるこの神社は、あたしが子供の頃にあるお姉さんと遊んだ場所だったんだ。確か今から23年前の2001年。あたしが小学校低学年くらいの頃かな。父親の実家がこの●●県の田舎町で、お盆の時期なんかに行くことがあったよ。
あたしは父親のことが嫌いなんだ。アラサーになった今もだけど。何が嫌いかっていうと、とにかく理屈っぽい性格なの。堅物とでも言うのかなぁ。ゲームや漫画は絶対禁止だったし、ひたすらに勉強ばかりを嫌々やらされていたのは嫌な思い出だよ。とにかく自分の考えが正しいと信じきっているみたいで、あたしの意見は「子供は黙って親の言うことを聞いていろ」って聞く耳を持たなかった。お母さんもあたしの味方はしなかった。父親が怖いのか、上司にヘイコラするように接していたよ。
淵背町のおじいちゃん家は周りが自然で何もなかったけど、子供だった自分には刺激的で楽しかったんだよね。お爺ちゃんはよくあたしに昔話を聞かせてくれてさ。家にあった日本全国の昔話をまとめた本を片手に音読してくれたのはよく覚えてるよ。
印象的だったのは、『きねがニタ』と呼ばれる昔話だった。何が印象的だったかっていうと、この昔話はおじいちゃんの家系だけが知ってるっていうものだったんだよね。そうそう、家に代々伝わる話とでもいうのかな。それだけでも何か特別感があるんだけど、この話はもう一つ変わっているところがあってね。それがどういう話だったかは………記憶が飛んじゃったんだよ、ごめん!ぱっと見じゃ想像つかないと思うけど、あたし記憶障害もちなんだよ。
確か………小学5年生の頃だったかな。父親と揉めてプチ家出したんだよ。町を歩いてたら、赤信号になった横断歩道をちっちゃい男の子がよちよち歩いてるのを見つけて。お母さんらしき人は一緒にいたママ友っぽい人と夢中になってお喋りをしてて気づいてなかったんだよ。
そこに猛スピードで大っきい車が突っ込んできてさ。デリカ並みの大きさの、子供に衝突したら間違いなく死んじゃうかもしれないって思って、その子のもとへ駆け出したんだよね。声を振り絞って、
「危ない!」
って叫んでさ。迫り来るフロントグリルに背を向けて、男の子を力一杯抱きしめたの。鈍感な人でも「これは死んじゃうよ」って感じるぐらい凄い痛みだった。さすがに子供の体じゃ衝撃に耐えきれなくてさ、少し飛ばされたよ。背中から感じた痛みはやがて、全身にジワジワと押し寄せてきてあたしは気を失ったんだ。意識が戻ると病院のベットの上にいて、脇には親がいて。開口一番、父親はあたしになんて言ったと思う?
「恥をかかせてくれたな。よくも子供に怪我をさせてくれたなと、向こうのお母様が怒っていたぞ。しかもよりによって、俺の上司の奥さんだとは………。」
空いた口が塞がらないってことわざあるじゃん?人間って酷くてどうしようもない状態を前にすると、本当にそうなるってことがわかったよ。お母は相変わらず申し訳なさそうに、下を向いて黙ったままだった。そしてあたしは決意したの。高校卒業したら、絶対に独り立ちしてやるって。
それまでの道のりは大変だったけど、充実していたよ。余計なこと考える暇がないからね。
両親から離れたかった?まぁ、そうだね。今は高卒で入った土木会社で働いてるよ。話とは全く関係ないけど結婚もしてないし。ただ、事故の影響で小学5年生以前の記憶のいくつかが飛んでしまったよ。ポッカリと穴ができたみたいに。おばあちゃんから教えてもらった『きねがニタ』と神社のことも、あの投稿を見るまでは記憶の彼方に消えていたよ。突発的に思い出したのも、何だか不思議な気がするよ。
ところで、絵本作りの為の取材ってことで君は話を始めてたけど、どうする?もう夜遅いけど。
………え?今度は地元の淵背町まで、来て欲しいって?分かったよ。あたしのガイドがなきゃ説明できないこともあるしね。まったく、君の熱量には負けたよ。
◆小学生の自由研究
2024年5月3日。
創作絵本マーケットの会場を後にした私は次に町立図書館を訪れていた。先程、人柱の話を聞いてからか、どうもこの町にそういった伝承が実在していないかが気になってしまったのだ。無駄な好奇心ゆえの行動である。
町立図書館は地方の図書館にしては規模が大きい。全体的に広々としていて、玄関から向かって右脇の廊下は展示スペースも兼ねていた。この時期は、どうやら近隣の小学校に通う児童らの自由研究を展示していたようだった。手書きのポップに書かれている内容によれば、図書館の近くに所在する淵背町立第一小学校の第3学年の児童らが作ったものである。
自分たちの暮らす町をテーマにした自由研究を行っている。目的は地元についての知見を深めるため。酷いものでなければ、町のことであればテーマは何でも良い。A3サイズの方眼紙にまとめられた手作りの資料は各クラス内で発表が行われた後に、町立図書館内の廊下の展示スペースに一定期間の間展示される。
どれも着眼するテーマが素晴らしく、難しい言葉と簡単な言葉を混ぜた拙い文章のものも多かったが、子供達の熱意や一生懸命さが伝わる。

出来栄えとして良いなと思ったのはこの神崎梨乃ちゃんの発表だ。先程、絵本作家の男性から人柱伝説が残る土手の話を聞いたばかりなので私は食いついた。川の名前も一緒なので間違いない。何か、手掛かりはないか。
私は顔を近づけて、梨乃ちゃんの自由研究を一通り読んでみる。

【わたしたちの町の守り神】
淵背町立第一小学校3年生・神崎梨乃

【しらべた理由】
わたしのおじいさんから萩生川の堤防の話を聞いて、興味をもったのでしらべました。

【堤防の歴史】
慶長12年(1606年)、●●藩では治水策として萩生川の流路変更を計画。この地域一帯の肝煎を勤めていた河原安左衛門は、藩主の命により、6.64kmもの大築堤を執り行い、豊天な長束山耕土の基礎を確立。しかし、その後も堤防が決壊して水害を蒙った。
安左衛門の代から次代の庄左衛門の代となってからも、決壊の禍を絶つために更に三年の歳月を費やして修復をし、民生を安んじた。2代に渡って工事を行なったことから、この土手を二人の名前を冠して安庄土手と呼ばれており、今日も淵背町を守っている。

【感想】
むかしは土を使って手作業で作っていた堤防も今ではコンクリートやセメントを材料にブルドーザーやクレーン車などを使って、よりがんじょうに作られています。
わたしたちの町の守り神である土でできた安庄土手も、いまのやり方でより強いものになってくれる日が来ればいいなと思いました。堤防作りで亡くなった人がむくわれるように。
読んでみると小学生が使うとは思えない単語がいくつか見える。難しい言葉を使っているにも関わらず、ふりがなもない。
築堤、流路変更、蒙った。
大人でも知らなそうな単語を用いた文章。これは現地に設置されていると思われる立て看板か、郷土資料などに載っている文章をそのまま引用していると思われる。
だとすれば、これが表向きの史実。人柱の話ではなかったものの、探す上ではこちらも参考にしておこう。

ふと右隣を見ると、8歳くらいの女の子がいた。
私に倣って梨乃ちゃんの自由研究を怪訝な表情でじっと見つめている。その女の子の更に右隣には若い大人の女性がいる。
「やっぱり、梨乃はこれじゃ嫌なの?」
この女の子が梨乃ちゃんだったのか。呼び捨てにしている女性は梨乃ちゃんのお母さんで間違いないだろう。私は梨乃ちゃんの自由研究を眺めながら、神崎母娘の会話に耳を傾ける。
「不貞腐れたってしょうがないでしょ?人柱なんて、テーマにできるわけないじゃない。」
「だってそうしないと、おしろちゃんがかわいそうだもん。おしろちゃんのことをみんなに知ってもらわなきゃ。じゃないとまた梨乃みたいにいなくなっちゃう子が出ちゃうかもしれないし。」
二人の会話の中に人柱伝説の少女の名前、「おしろ」が登場する。私は聞き耳を立てる。
どうやら、淵背町では子供が神隠しに遭う事件が起きていたらしい。それがオカルト的な事件なのか、人為的な犯罪事件のかは別として。梨乃ちゃんの理屈では人柱の少女、おしろが自分の存在を忘れ去られようとすると神隠しを引き起こすのではないかという。確かに悲惨な最期を遂げた自分の存在を忘れられてしまうのは実に不憫である。怪談的に考えれば、人柱伝説が事実ならおしろが神隠し事件を祟りとして起こすのは、理にかなっているだろう。
また、神崎母娘はしばらくおしろによって引き起こされる神隠しの話をしていたが、二人とも不思議と怖がっている印象はなかった。
「といってもねぇ、もしそれが本当だったら町のイメージが悪くなっちゃうから秘密にしておいた方がいいのかもね。」
「ママだって昔に、この町でいなくなったことあるんでしょ?梨乃、重一おじさんから聞いたもん。ママは会わなかったの?おしろちゃんにさ。」
「うーん、昔山の中で会った気がするけど……何だかよく覚えてないんだよねぇ。そんなことよりも、勉強ちゃんとしなさい。最近ずっと、おしろちゃんのこと調べてばかりじゃない?」
梨乃ちゃんはほっぺをぷくっと膨らまして不満ありげな顔をする。神崎母娘はしばらくして、その場から去った。やはり、この町には何か秘め事があるのだろうか。
それに梨乃ちゃんのお母さんがおしろと会ったことがあると言った際、「山で会った気がする」と言ったのがどうも腑に落ちない。人柱伝説は萩生川の安庄土手が舞台のはずが、どうして山の中で「おしろ」なるものと遭遇したのか。
梨乃ちゃん、そして彼女のお母さんは神隠しに遭った際に見た女性をおしろと信じ切っていたが、そもそもその女性は本当に「おしろ」なのか?
非常に興味深いが、私はただ観光にぶらっと来ただけにすぎない。それに業がとても深そうな話なので余計な詮索はしない方がいいだろう。図書館で何も収穫を得られなければ、ここら辺でおしまいにしておこう。
◆ご当地PRキャラ
図書館で長時間をかけて、人柱伝説について記載されている本はないか探してみた。しかし、史実とはかけ離れた、あくまで伝説や民話に近い話なので、そのような情報が載っている本などあるはずがなかったのである。おしろ明神を訪れようと思ったが、金銭的な面からそこまでできる余裕はなかった。タクシーを一回利用するだけで懐に氷河期が訪れる。
お腹が空いてきたので、近くの道の駅へ向かう。徒歩数分で行ける短い距離とはいえ、運動不足がたたったせいか到着した頃には、情けないことに疲れ果ててしまった。
「ねぇ、あのグッズ可愛くなかった?」
農産物直売所の入り口のアウトテナント内でハンバーガーにかじりつこうとしたその時、向こうの席に座っていた若い女性二人組の話し声が聞こえた。
「人柱の女の子がモデルのやつでしょ?淵背町のPRキャラにもなってるっていう。」
「そうそう、お金足りなくて買えなかったけど。次また来ようよ。」
「え、また行くの?次は自分で行きなよ。っていうかなんでそんなにあのオシロちゃんグッズに拘るの?可愛いのは認めるんだけどさ。」

人柱という単語に私は反応する。この淵背町のPRキャラクターが、私が追っている人柱伝説の少女をモデルにしているらしい。あろうことかキャラの名前も『オシロちゃん』で同じだ。
「だって、人柱伝説が本当でもそうじゃなくても築堤で人が亡くなったのは事実じゃん。もしかしたら築堤で亡くなった人のことを忘れないように作られたお話かもしれないし。なんだかロマンがあるような気がして。」
「オシロちゃんには哀悼の意みたいな、教訓の意味合いが込められてるってこと?」
「………だから、忘れちゃ可哀想なんだよ。語り継がないでいかないと、浮かばれないよね。猟銃で撃たれた悲劇は絶対にね………。」
突拍子もなく出てきた"猟銃"という言葉にぽかんとした。呆気に取られたのは、一緒にいた女性もだった。
「猟銃?いきなりどうしたの?」
「えっ………、ウチなんか変なこと喋ってた?築堤で亡くなったって話しかしてないけど。」
「そんな訳ないって、本当に言ってたから!待って待って、何か怖いんだけど。」
「もしかしたらオシロちゃんに取り憑かれでもしたのかなぁ。なんか面白いね、やっぱ今買っちゃおうかな。えーっと近くにATMは………。」
眼前で不可解な現象が起きたにも関わらず。自らの意思とは関係なく、突如として謎の言葉を発した女性はあまり怖がってはいなかった。しばらくして女性らは席を立って、アウトテナントを後にした。
我に帰った私はハンバーガーを完食し、小腹を満たした後に件の『オシロちゃん』グッズが売られている売り場へと向かった。
缶バッジやステッカー、Tシャツや立ち絵がプリントされた大学ノートまである。財布の中身を確認しながら数分迷った結果、値段が手頃で実用性も若干ある正方形のキーホルダーを買った。パッケージに丁寧に梱包されたそれを眺めてみる。

「………語り継がなきゃ、なぁ。」
ほんの刹那。意識がぼやけた咄嗟に何かを呟いていたようだ。隣にいたお婆さんが不思議そうな顔で私を見ていた。
📕絵本『ひとばしらのむすめ』
むかしむかし、川べりの
ちいさな、ちいさな村であったおはなし。
その村は川のそばにあったので、
雨がたくさんふると、たちまち村は
こう水にのまれてしまいました。

たくさんのひとがしんでしまいました。
そんなことから、村びととえらいひとが
はなしあって、川にそって
おっきな、おっきな、堤ぼうを
つくることにしました。
堤ぼうをつくっているときも、
雨はたくさんふって、
またこう水がおこって、たくさんの人が
しんでしまいました。
「これでは何回つくってもおんなじ。」
みんなが落ちこんでいたそのとき、
だれかがいいました。
生きたわかいむすめを
川の神さまにささげたらどうだ
人柱をささげたらどうだ
神さまの怒りをしずめて
へいわに、なにごともなく
工事がせいこうするように祈ろう、と。
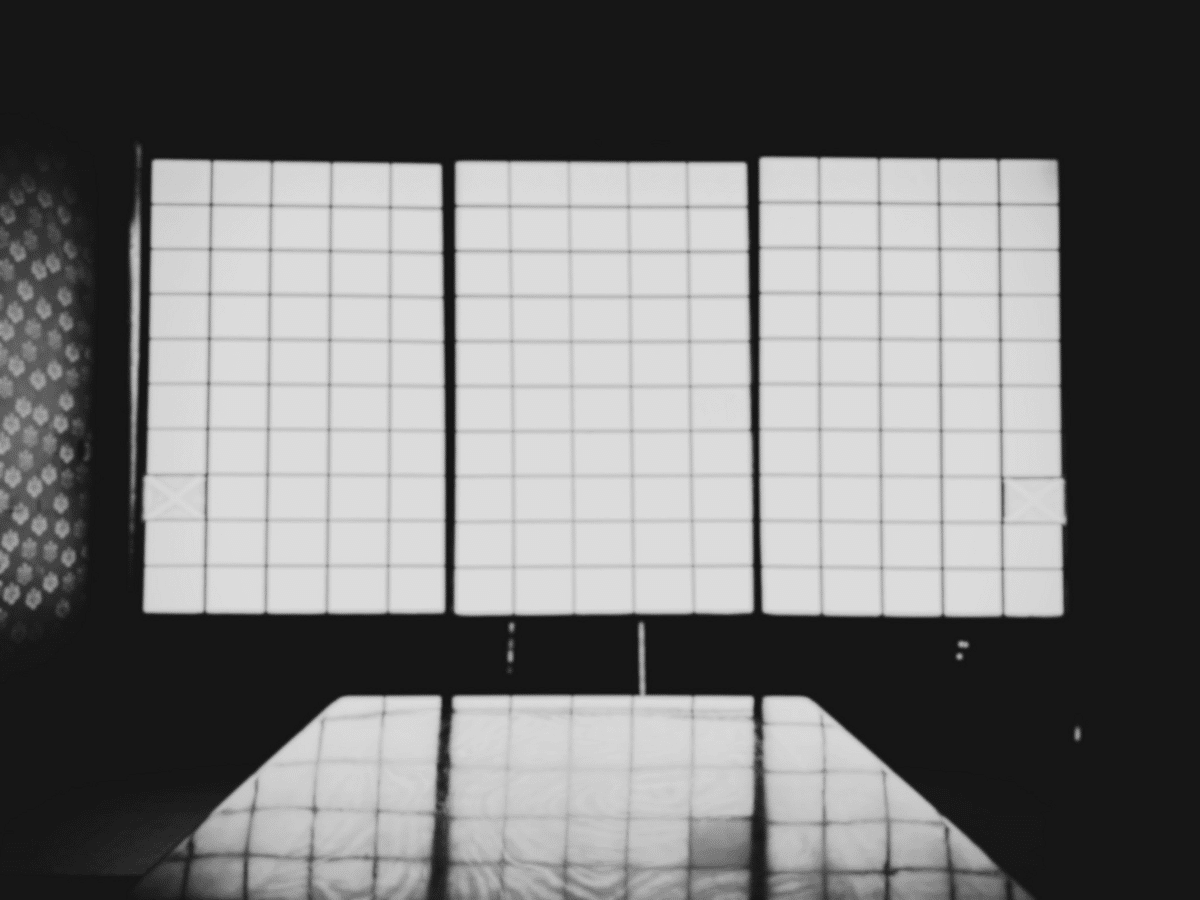
堤ぼうの完せいをいまか、いまかと
いそいでいた村びとは
ためらいもなく、そうきめました。
そして、人柱となるむすめとして
長者の家で使よう人としてはたらく
おしろという、うつくしいむすめを
人柱にしようときめました。
ある日のこと。
みんなが休んでいるところへ
おしろがにぎりめしを持ってきました。
おしろがそこをはなれようとすると、
ものかげからたくさんの男たちが
おそいかかったのです。
「おやめください、なにをするのです!」
「わるいが、神さまのいけにえになってくれ!」
おしろは、なにもできないまま
だれかにあたまを石でなぐられて
気をうしなってしまいました。
おしろが目をさますと
手と、足と、口と、目を
なわでしばられていました。
おしろは体をうごかせないまま、
生きたまま、
土のなかにうめられようと
しているのです。

「たすけて!たすけて!」
そうさけんでいるつもりでも、
くるしそうなこえがもれるだけでした。
やがて、そのこえも聞こえなくなって
おしろは土のなかにうめられてしまいました。
川の神さまへのおそなえものとなったのです。
「これでじょうぶな堤ぼうができた。」
あれから何年たったことでしょう。
むかしに作られた堤ぼうは
いまも、そしてみらいも川べりのこの町を
まもりつづているのでした。
お供えものとなったむすめのこと
をわすれたまま。
「ぼうや、ここにきたら手をあわせんしゃい。」
「わかったよ、おばあちゃん。」
「この堤ぼうをつくるのに、たくさんのひとがしんでしまったんじゃからのう。」
「あそこに、おんなのひとがいるよ!」
おばあちゃんは
ぼうやのゆびさした方を見ましたが、
だれもいません。
かぜにゆられる草や木があるだけでした。
「ありゃ、もしかして………」
おばあちゃんはこどものころに
だれかからきいた人柱のむすめのはなしを
おもいだしました。
どうせ、ただのむかしばなしだろう
とおもっていたはずが
ほんとうのことだとわかったのです。

おばあちゃんはおしろのことをしらべました
村のえらいひとにそうだんして、
おしろがいやなことがあると、
よくきていたという、山のなかの沼に
おしろをなぐさめる、
神さまとしてまつるためのほこらをたてて、
だいじに、だいじに、まつりましたとさ。
とっぴんぱらりん。
*駐在さんの昔語り
オートバイに乗って、祖父母の住む家まで向かおうとして道に迷ってしまった。方向音痴ってのは大人になっても治らないみたい。
スマホ片手に途方に暮れていると、一台のパトカーがやって来た。

「あたし、何かやっちゃいました?」
昔に来たことがあるとはいえ、地元の人から見れば私は不審者だ。通報されても文句は言えないと思う。それに今週仕事が忙しかったから疲れ気味だ。ぼけーっとしてて、知らないうちに事故を起こしていたかもしれない。加えて、あの絵本作家君のことがあったらねぇ。
「かどぅ脇」さんの神社の投稿に「子供の頃、行ったことがあります」とポストしたら、それを見たあの若い絵本作家くんが連絡を寄越した。どうやってあたしに行き着いたかは分からないけど、結果的に直に会って「あの子」についてほんの少しだけど、教えてあげた。上手く説明するには実際に現地まで行ってみる必要があると提案すると、絵本作家くんはぜひお願いしますと嬉しそうに言った。行くとは言ったものの、随分昔のことだ。それによく覚えていない、絵本作家君に欲しがっているものを与えてあげることができるかなぁ。
「もしかして………秋妻、一花ちゃんかい?」
何でお巡りさんがあたしのことを知っているんだ?とにかく、名前をちゃん付けで呼んだことからあたしのことを知っているのだろう。何か自分が犯罪行為をはたらいた訳ではなさそうだ。
「あの〜、私の名前をご存知なのですか?」
「まぁ覚えてはないさな。俺、昔この近くの長束山で一時行方不明になった一花ちゃんを見つけて保護したんだよ。一緒にオチャラカホイをして遊んだのも忘れちゃったか。」
「何だか、すみません。でもその節は本当にありがとうございました。」
「いいの、いいの」と言って警察官の幸田芳彦さんは朗らかな顔で笑って見せた。あたしは気分が和んできて、路肩にバイクを停めてパトカーの中で幸田さんと雑談に興じた。
話の流れで、やはり例の子供の行方不明事件の話題になる。あたしはあの事件では行方不明になった子供の一人である。事件が起こった時、警察内ではどのようなことが起こっていたのだろうか。気になったあたしは幸田さんに尋ねてみる。警察側から見たあの行方不明事件を。
「この町へ配属されて初めて教えられたのが、その子供の行方不明事件なんだよ。頻繁に起こるから、気ぃ引き締めておけってね。」
「頻繁に起こるんだったら、警察の方は何か対策などはされていたんですか?」
「いや、特にはね。そもそも行方不明事件の割には長い時で一週間。短い時で4、5日と発見されるのが早いんだよ。頻繁に起こるものの、比較的すぐ解決するから警察側もそこまで深い事件だとは考えてないんだよ。それに、明確な原因だって分からないしね。風の噂だけど、以前に報告書に"原因は神隠し"と書いた人がいたんだけど案の定、上の人から厳しいお叱りを受けてね。」
「明確な原因が不明で、頻繁に起こっているけどすぐ発見されるからこれといった対策なんてなかったんですね。加えてお偉いさんがオカルトの類を一切信じないタイプ警察署の方々にとって、扱いづらい面倒臭い事件だったんですね。」
「そう。出たら、探す。それだけなんだよ。」

行方不明事件の主たる被害者は子供の親御さんなのだが、淵背町北警察署の警察官もだと幸田さんは愚痴をこぼす。あたしがいなくなった時も、渋った顔で捜索をしていたに違いない。
では、今度はあたしの方から幸田さんにあの日のことを話そう。そこから話を展開させて、何か手掛かりはないか。心の底から会いたいあのお姉さんについてご存知ないか聞いてみる。
「では、今度はあたしの番ですね。ついこの間、あの日のことを思い出しました。」
「あの日のことって、行方不明になった日のことかな?」
「えぇ。あたしはあの日、祖父と一緒にお花を摘みに長束山へ行きました。ベニシジミっていうんですか?それを見つけて、追いかけたら茂みの奥へ奥へと入っていってしまって………」
◆タイムスリップ体験
「あれは、不思議な思い出だったよ。」
今年で53歳になるタクシー運転手の小倉稔さんは現在から47年前、当時6歳だった頃の話をした。

「あの出来事を子供は思い出と呼び、大人は怪談と呼ぶんだろうなぁ。」
昭和51年、西暦1976年の初夏の頃。
稔さんは家族で長束山地区を訪れていた。昼食を済ませて近くの山で遊んでみようという話になった。子供だった小倉さんはお父さんと一緒に、若干引いた目で眺めるお母さんを尻目にはしゃぎ回っていた。
やがてお母さんが近くの自販機で飲み物を買いにその場を離れる。お父さんは疲れたのか、芝生の上で大の字になって眠ってしまった。遊び相手がいなくなって退屈になった稔さんは何か物珍しいものはないか、辺りを見回していると何か聞こえる。

「………かい………い………にあそ………や。」
微かだけれど、誰かの声が聞こえる。その誰かさんは自分に対して言葉を発しているのか。耳を澄ませて、もう一度辺りを見回してみる。
「ぶな……かい?いっしょにあそ……うや。」
さっきよりも声がはっきりと聞こえた。声色が高い、やさしい抑揚の声。声の感じからして、自分に話しかけている誰かさんとは女の人らしい。
「ぶなきちかい?いっしょにあそぼうや。」
声が聞こえた方向を向くと、そこには人が立っていた。見た目からして、年齢は18歳くらいの若い女の人だった。
しかし、小倉さんは子供ながら違和感を覚えた。
服装が現代のそれとは違う、着物を着ていた。時代劇の農民が着ているような格好だったという。綺麗な長い黒髪、肌は透き通るほど白く美しかったそうだ。美しい反面、何だかお化けのようにも思えたと小倉さんは当時の出来事を振り返る。
女性は自分を「ぶなきち」という人と勘違いしていたのですぐさま、
「ぼく、みのる。ぶなきちじゃないよ。」
と答えた。着物の女の人は
「そうなんね。でも、おら、わらすだいすきやけ。いっしょにあそぶべ。」
と、小倉さんに遊ぼうと迫った。
とても別嬪さんで自身に優しく接してくれたので小倉さんは、悪い気はせず、その女の人についていってしまった。
手を引かれて辿り着いたのは、どこかの集落であった。時代劇なんかにでてきそうな家々が並び、行き交う人々は物珍しそうに子供の小倉さんを見つめる。着物の女の人は、小倉さんを子供たちの集まっている場所へ連れていった。人々といい、遊んでいた子供達といい、出立はどう考えても江戸時代のそれだった。
仲間に入れてあげてと頼むと、子供たちは嫌な顔一つせずに小倉さんに遊びを教えてくれた。
だるまさんがころんだ。けんけんぱ。竹製の水鉄砲。あやとり。泥メンコ。素っ裸になって、水遊びもした。どれもこれも新鮮で、本当に楽しい時間を過ごしたと懐かしんでいる。

ひとしきり遊んだ後に子供達と別れて、再び女の人の手に引かれて歩き出した。もう帰るのか、何だか寂しいな。歩き疲れると、女の人は小倉さんをおんぶしてくれた。やがて女の人は自らについて語り出した。
「おら、キネっちゅうんね。みんなからはおキネ、おキネってよばれとんよ。」
「………おキネ姉ちゃん、ぼく、かえりたくない。まだあそんでたい。」
「もう帰らぁないけん。そうじゃ、おらと指切りげんまんしてけねぇか?今日のこと、忘れんでくれぇ。おらのこと、ずっとおぼえててくれな。」
おんぶされて体がまた揺すられていくうちに、小倉さんはいつの間にか眠ってしまった。気がつくと、お父さんの運転する軽トラの助手席に座っていた。着ていた服は土や木の葉でひどく汚れており、数時間しか経っていないと思っていたが、4日も経っていたことも後で分かった。まるで、昔話の浦島太郎のような、不思議な体験を小倉さんは幼少期に経験したのだ。
「お父と、おっ母にそのことを話したんだけどなかなか信じてもらえなくてよ、ちと泣きそうになったで。でも、俺の話ば信じてくれた人がおってさ。それが秋妻さん家と忠琳寺の和尚さんだったんや。まるで、あの事件について新聞記者ばりに質問されたべ。懐かしいのぅ。」
「その後は、その女の人には会えたんですか?」
「残念だけどもうダメやったわ。何度もあの山に入ろうとしたもんだから、すっかりお父とおっ母に叱られちまって。そして気づけば、タクシー運転手になって、兄ちゃんにその話をしちょるっちゅうてな。」
やはり、この謎の女性が絵本のモデルとなった人柱少女なのか。だが名前が違う。人柱の少女の名前は確か「おしろ」だった、「キネ」ではない。
それに、小倉さんに事件について食い気味に質問してきた秋妻家と忠琳寺の住職さんも気になる。
彼らの元を訪ねれば、何かが分かるかもしれない。秋妻さん家は個人宅だから無理だとしても、忠琳寺はどうだろうか。私は運転手さんに、一つのお願いをした。
「すみません小倉さん。目的地を民宿から、忠琳寺に変更できますか?」
「いいってことよ。こっからは料金は取らねぇ、兄ちゃんだけ特別サービスな。」
小倉さんはニヤッと笑って、アクセルを踏み込む。タクシーは先程よりも軽快なスピードで山あいの道路を突き進む。
気がついて、後ろを見るとパトカーとオートバイもタクシーの跡をついてきていた。ライダーの体型からして乗っているのは女性だろうか?私達と目的地は同じなのだろうか?
●懐古話
子供の頃以来、久しぶりに訪れた。
長束山地区の『わすれなの森公園』。この公園のみならず、淵背町一帯ではノハラワスレナグサが咲くようになる。特に春から夏にかけての、一般的な開花時期には町外からも花を眺めに数多の人々が訪れる。

地元の方の話では、1960年代あたりからこの地ではノハラワスレナグサの異常すぎるほどの開花が見られるようになった。山林だけでなく、この町一帯に広範囲にわたって咲いているので、町を歩いていても草花に混じって小さく咲いているのをよく見かける。そのことから、大学の有識者らが何度か調査のため訪れたことがあるそうだが、現在もその原因は解明されていない。
「ワスレグサは確か、私を忘れないでって花言葉があったような。」
俺は、7歳までこの淵背町で育った。別に両親の実家がその町にあった訳ではない。田舎でのびのび暮らしたいという父親の単純な願望で、一時的に両親と俺の家族3人で移住した。
再び引っ越すきっかけとなったのはあの神隠し事件だ。後で分かったことだが、行方不明となった子供達は俺の他にもたくさんいた。俺はあの日の出来事を「思い出」と呼び、大人は「怪談」と呼んでいた。
近所の子供達と長束山地区へ出かけ、探検ごっこをしていた。浦沢直樹先生の漫画『20世紀少年』みたいに秘密基地を作ったのは懐かしい。俺はメンバーの中で一番年下だったけど、みんな親切にしてくれた。あの時は思っても見なかった。幽霊と思しき女の人に手を引かれて、昔の時代にタイムスリップするような体験を味わうとは。あの時は、女の人の名前を聞けなかった。
それから月日が過ぎた。関東の公立大学の文学部を卒業した俺は図書館司書の資格を取得し、図書館に就職した。一時作家の道は諦めたが、やはり本に囲まれた生活というのは捨てがたい。
特に好きなのは児童文学だ。『かいけつゾロリ』、『怪談レストラン』、外国の作品だと『エルマーのぼうけん』がお気に入りだ。
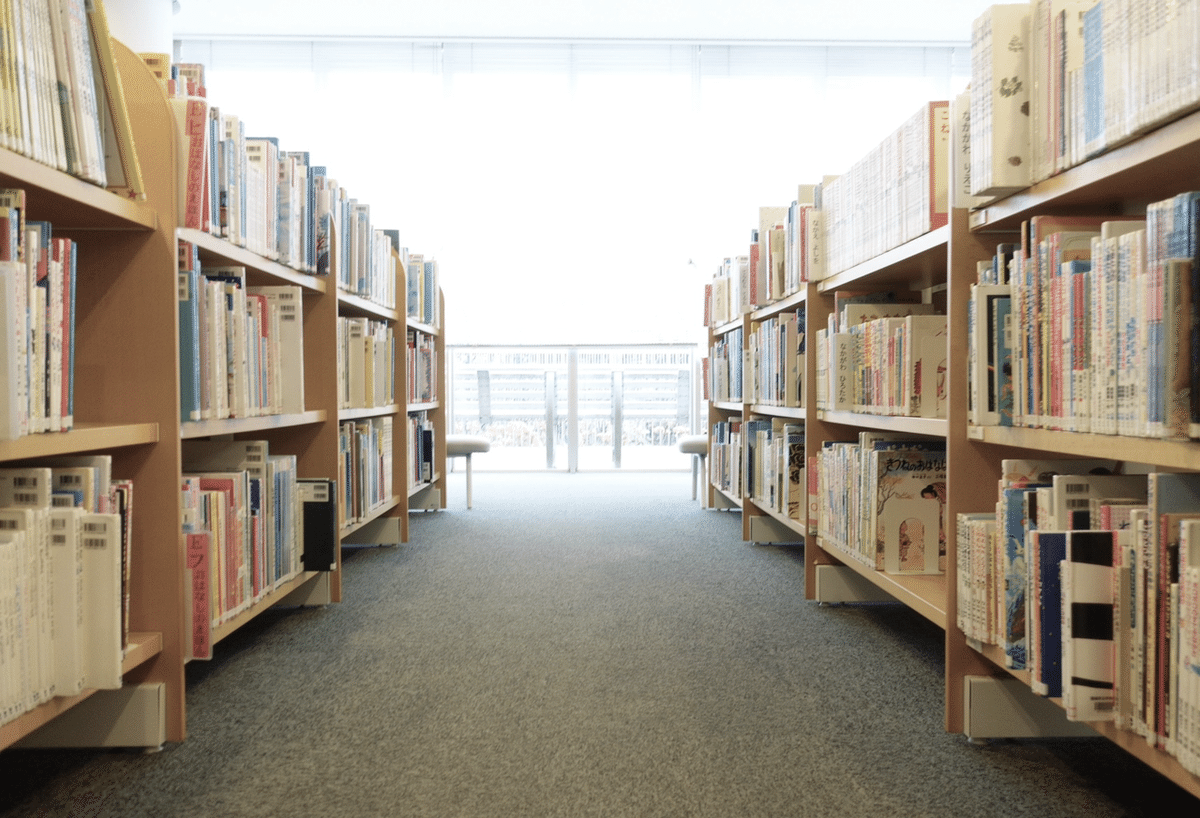
利用している人で知っている人がいるかは分からないが、意外にも図書館職員というのはとてもハードな仕事である。
俺が勤務していた図書館は定年退職した高齢の利用者が多かったこともあり、昼間はとても忙しかった。閉館後も、新しい蔵書や古い本の整理、延滞本の返却催促や傷んだ本の修復などで業務は山積みだった。そんなこともあり、一年も経たないうちに仕事が嫌いになった。
「今度の読み聞かせ会、頼んだよ。」
先輩にあたる女性の司書さんが俺に言った。
この図書館では月に一度、近くにある小学校の低学年の子供達に読み聞かせをするイベントがある。今まではアシスタントとして、先輩司書さんたちのお手伝いをしていただけだったが、まさか自分が任せられるとは思ってもいなかった。
第一、そういうのは物腰が柔らかな女性の声が適役だと思っている。少し野太めで低い声の自分が務まるものなのか。少し疑問は湧いたが、俺は「はい、よろこんで」と引き受けてしまった。先輩司書からアドバイスを貰いつつ、忙しい合間を縫って練習を重ねた。絵本のチョイスに関しては自信がなかったので、この時だけは先輩の司書さんに選んでもらった。
選ばられた絵本は長谷川摂子氏作、降矢なな氏が挿絵をつとめた『きょだいなきょだいな』と、せなけいこ氏作の『ねないこだれだ』である。


一つは明るくて面白い話、もう一つはちっちゃい子供にとっては少し怖い話。風の噂では『ねないこだれだ』を幼稚園児らに読み聞かせた結果、泣き出したり、夜トイレへ行けなくなってお漏らしが増えてしまった子もいるそうだ。そんな子供のトラウマになりかねないお話をどう読み聞かせるかが要であった。
結果的に自分はどうしたか。『きょだいなきょだいな』は声のトーンを高くした。裏声に近い声で音読したので、子供たちは笑い出したり、一緒に文章を音読しだす子も現れた。
場の空気が明るくなったので、次に『ねないこだれだ』を読み聞かせる。先程とは対照的に低いトーンで抑揚をつけずに音読する。読み上げるテンポも遅くして、寝つかせるようなイメージで。
そうした所、子供たちは多少のリアクションはしてくれたものの、食い入るように挿絵のお化けを眺め、俺の話を聞き入っていた。泣き出した子はいなかった。
「あれぇ、もう、おしまいなの?」
後ろの方に座っていたおさげの女の子が言った。最初はお話自体が短いのだからそう言ったのだと思ったが、実際は違っていた。
子供たちは怖い話の扉を開いたのだった。彼女の指摘を皮切りに、他の子供たちも「もっとこわいおはなしききたい!」と口々に言い始めた。こんなことがあるのだろうか。
「もしかしたら、子供達にとって適応な方法で怖い話を読み聞かせたんじゃないかな。すごいねぇ、良くやったよ。」
あの日以降、図書館の読み聞かせ会は主として俺が任せられるようになった。子供達だけでなく、親御さんや近隣の小学校の先生からも評判が良かったのか、図書館外でも読み聞かせを頼まれることも増えていった。
既存の絵本だけでなく、自作のオリジナルの物語を発表したのは最初の読み聞かせ会から3ヶ月経ってからのことだ。俺の処女作、恐らく一番初めに世の中に発表した作品。
小さな男の子が山で出会った不思議な女の子と遊ぶ話。女の子の正体は最後まで明かされず、謎を残したまま終わる。だが、物語の中に女の子の正体を匂わす描写がいくつもある。それは子供には分からないが、パパやママには分かる。残された謎は、パパとママが解明してあげることで解決される。発表した当初は自信がなかったが、子供達や親御さんの反応は予想だにしていないものだった。
「蒲田さん、コンテストに応募してみたらどうでしょうか?」
その作品を読み聞かせ会で発表した後、子供達と見ていた年配の男性の口から出た一言。そのお爺さんは俺が発表した物語を聞いて、遠い昔の出来事と重ね合わせてしまったという。
そのお爺さんが体験した出来事を簡単にまとめると、「山で着物を着た女の人に遭遇して、手を引かれて連れて行かれた場所で子供達と遊んだ」というものだった。もっといえば、「手を引かれて辿り着いた場所が昔の時代のような場所だった」いわゆるタイムスリップのような経験をしたとも語っている。記憶の片隅にいつまでも残り続けているものの、今日に至るまで女の人の正体は謎のままだ。
そしてお爺さんが当時住んだいたという町が、俺が7歳まで住んでいたあの淵背町と同じことといい、お爺さんの不思議な体験が、自身の過去の思い出と共通するものを感じた。このお爺さんは俺と同じ体験をしていた。
「それ、私も似たような体験をしたことがあります!」
あの出来事から数年経った現在、同志を見つけられた喜びから無意識に声のボリュームを上げてしまった。連絡先を交換し、互いに山で出会った女の人についての情報を仕入れては共有する。そんなことが日常に組み込まれていった。
俺はそのお爺さんと会うのが密かな楽しみになった。それはお互いの楽しみを二人で共有するだけじゃない。あの方はコンテストの作品を作っている際に感じていた心理的な不安を和らげてくれたのだ。この時は毎日の激務や読み聞かせ会の準備に加えて、殆ど寝ないで作品作りに没頭していたから疲労が溜まっていた。その中で、あのお爺さんは俺を労ってくれて、疲れを癒してくれた神様のような人だった。
「でもあの時はそんなこと予想できなかったよ。」
本当に唐突だった。俺の作品は幸運にもコンテストで最優秀賞を受賞した。加えて副賞として、大手出版社と契約を結んだことで晴れて絵本作家としての人生がスタートした。
授賞式後の懇親会で、俺はスマートフォンを確認した。あのお爺さんからの着信履歴が溜まっている。席を外して、電話をしてみると応対したのはお爺さんの奥さんだった。
「畑、彰さんですか?あの、実は、主人が。」
「まさか………」
「そのまさか、なんです。心筋梗塞で、主人は先ほど………」
言葉を失った。
ショックからか受賞作品の内容を、作者であるのに忘れてしまった。海馬から作品を作っている時の記憶がスポンと抜き出されたように。脳内が真っ白になっていた。
「前兆はあったんです。なんだか胸焼けがするとしきりに訴えていたので。でも主人は、結果発表を控えている畑さんに心配をかけたくないから内緒にしててくれと言っていて。」
「そんな………嘘ですよね?だって、つい先週にコンテストが控えてるってことで、前祝いにご飯を奢っていただいたばかりなんです。その時も、いつもみたいに、何の変哲もなく、私に親しく接してくれたんですよ。」

愚かな発言だとは分かっていた。それでも、信じがたいものだった。あのお爺さんの死は。結局、山で出会った女の人については何も解決しないまま、天へ旅立ってしまったのだ。葬儀に参列した経験は何度かあるものの、人の「死」というものがこんなにやるせなく、信じがたいものだったとは。社会人になってから遅すぎるタイミングで学習したのだった。
「待っててくださいね。長束山の女の人の謎、解明してくるんで。」
図書館を辞め、読み聞かせ会はしばらくの間休止することにした。絵本作家としての毎日を送る傍ら、俺はあの不思議な出来事についての調査を続けていた。お爺さんとの情報共有会は少しお遊びに近かったが、今度こそは本腰を入れる。
ある日、『かどぅ脇』さんという方が投稿したあの廃神社の写真を見つけた。山の場所からして恐らく、あの女の人に関わりがあるかもしれない。そして「子供の頃、行ったことがあります」というポストを見つけ、その方にXを介して連絡を取ってみた。最初は「あんまりしつこいと通報するよ?」と警戒されていたが、例の女の人の話をすると物腰が柔らかくなり後日、直接会って話をしてくださることができた。
秋妻一花さん。彼女も6歳の頃、俺と同じ不思議な体験をした。彼女は最近、仕事で派手なミスをして会社に損害を与えてしまったそうで、精神的に病んでいた。そんな折、『かどぅ脇』さんの雰囲気のある神社を見つけたという投稿を見て、幼少期に体験した不思議な出来事を思い出した。俺と同じ、淵背町の山で不思議な女の人に出会ったことだ。その影響からか、昔一緒に遊んだ件の女の人に会いたくなったという。小学五年生の頃に経験した交通事故の後遺症で、その時の記憶はスッポリと消えていたが、不思議なことに神社の写真を見た途端にフラッシュバックするように思い出したという。
しかし残念なことに、俺も、お爺さんも、秋妻さんもあの女の人の正体に辿り着けていない。最初は萩生川堤防の築堤で人柱にされたおしろという少女かと思った。だが、俺やお爺さんがあの女の人と会ったのは山の中。本来の伝承ではおしろを祀る祠が建てられたのは、彼女が嫌なことがあるとよく訪れていた長束山の沼の近くだという。もっと言えば、安庄土手に設置されている祠は戦後期に建てられたものである。しかし、どうもあの日見た光景から、人柱の少女おしろがあの女の人とは重ならない。第一、手を引かれて辿り着いた江戸時代の街道のような場所といい、村人に裏切られて悲劇を遂げた女性であると思えば、子供たちと仲良く遊んでいる。どうも『オシロ=山で会った女の人』説は違うような気がする。更なる調査が必要となった。何か情報を得られないか。その一環で、人柱オシロ伝説をテーマにした絵本を淵背町のフリーマーケットで発表したが、特に有益な情報は得られなかった。だが、通りすがりの若い男性が一冊買ってくれたので嬉しかった。
そして現在、秋妻さんをこの町に招いて、一緒に女の人の正体を突き止めようとしている。俺一人じゃ答えに辿り着けない。ノハラワスレナグサを眺めて物想いにふけっていると、電話が鳴った。
「もしもし、蒲田匠です。」
「あ、やっほー。秋妻です。ちょっと集合場所変更していいかな?」
「構いませんけど、場所は?」
「長束山地区の忠琳寺。分かる場所?」
「はい。分かりました、今行きます。」
俺は自家用車のエンジンを入れ、「わすれなの森公園」を後にした。この辺では歴史が古く、様々な伝承が残されているあの忠琳寺に一体、何があるというのか。
果たしてそこへ辿り着けば、お爺さんへ捧ぐための答えが見つかるのだろうか。
《後編》に続く
