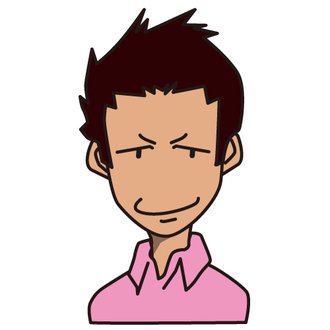スマート新書がやらないこと
しばらく「スマート新書のつくりかた」と題して連載をしていきます。今回は第2回で、前回の記事はこちらに。
スマート新書は、新書を現代に再発明・再定義するという企画です。ということで、これまで出版において当然と思われていた、いろんな要素を「省いて」いこうという発想が根本にあります。
以下に、省いたものを書いていきましょう。
書店配本
スマート新書は、書店で販売していません。
通常の本は、問屋(取次)を通じて、「新刊の書店配本」をしてみなさんに届けられます。取次経由で本を売る最大のメリットは、うまくいけば多くの書店で多くのひとに本が売れることと、お金の流れが簡単になることの2つです。しかし同時に、自分で流通をコントロールできないというデメリットもあります。
で、いろいろ考えた末、スマート新書では、新刊時の書店配本をやめました。当面は、noteでの直販とAmazonのみで販売します(今後、販売パートナーを見つけていっしょに売るのはあるかもしれません)。
カバー
カバーも省きました。ぼく自身、紙の本を読むときは、カバーを外して読むことが多いですし、小さい本だと特にじゃまになるので。とはいえ、持ち歩いて汚れるのは困りますから、スマート新書では、表紙に直接ビニール箔(PPといいます)がかけてあります。
通常の本にカバーがあるのは、美しいということもあるんですが、じつは流通のためというのも大きいのです。返品で戻ってきた本の、汚れたカバーを変えられるようにして、使いまわせるようにしているわけです。
オビ
オビもなくしました。キャッチコピーとイラストは、アメリカのペーパーバックのように、表紙に直接印刷しています。今後、必要なときはつけるかもしれませんが、基本、なくていいかなと思ってます。
見返し
見返しとは、表紙の裏についている色紙の部分で、これも省略してます。ぼくは通常の本をつくるときにはこういうところにけっこう凝るほうですが、このシリーズではなくていいかなと。
スリップ
よく本のなかにしおりみたいな短冊みたいな紙が入ってますよね。アレです。書店さんが注文に使うことがあるらしいのですが、今回は不要と判断して入れてません。
かつて取次はGoogleだった
ということで、流通まわりの話が多いですね。
取次を通じた書店流通というのは、じつは出版業界の最大の発明だったといっても過言ではないでしょう。出版社は、本を作って、取次に納入するだけでお金がもらえて、しかも全国の書店に本を配ってもらえます(もちろん、いい棚に置いてもらうために営業したり、宣伝したりは別途必要ですが)。
かつての取次の役割は、ネットでたとえると、Googleと似ています。Googleは、読者とコンテンツを(検索で)つないで、メディアには(広告を通じて)お金をもたらしています。取次もGoogleも、役割は「流通」と「ファイナンス」なのが共通しているのです。
一応言っておくと、取次はいまでも便利な存在です。ぼくらも通常の本を編集したらお世話になることもあります。あくまでも、今回のような規格外の本だから利用しなかったということです。いろんなやりかたが増えるのはいいことだと思います。
チーム紹介
前回紹介したデザイナー麦田さんと同じSCNRの白石さんです。カバーやストアのウェブサイト製作のディレクションと、そしてストアの写真の撮影もやってくれました。

先日の弊社忘年会での一コマ。宴もたけなわなのにイケメンです。
いいなと思ったら応援しよう!