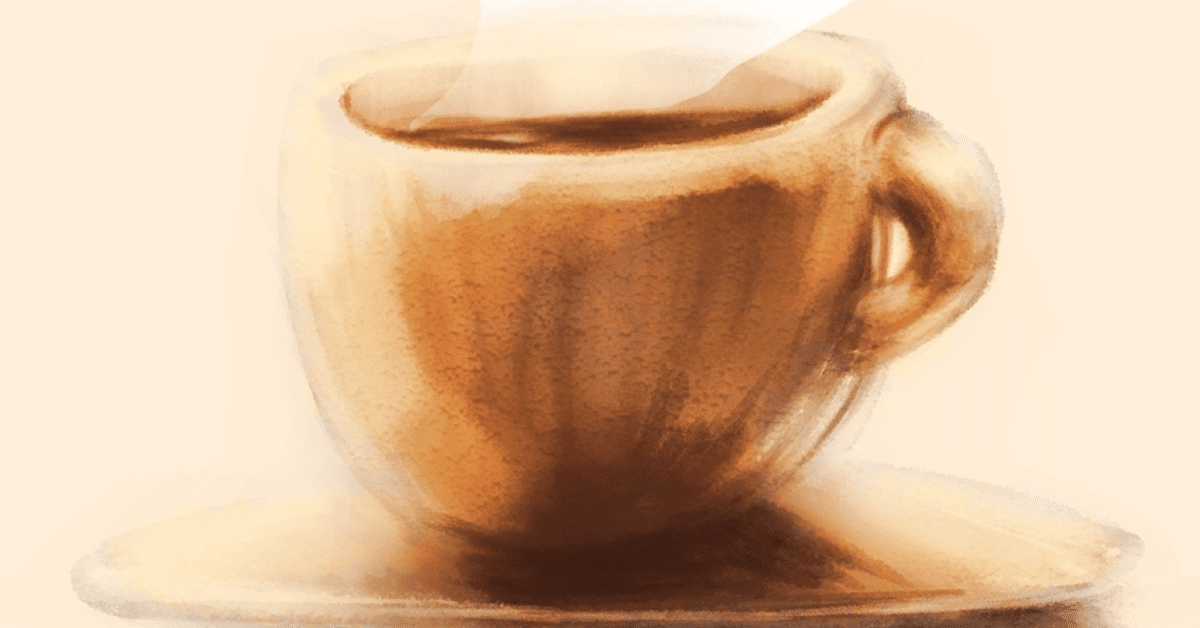
幽霊執事の家カフェ推理 第三話・友情のクロケット6
ドアベルが鳴り、何気なくそちらを見ると千枝子が入ってきた。今日は一人のようだ。
彼女はいつものテーブル席には行かず、カウンターに来た。
「先日は本当にありがとうございました」
丁寧に頭を下げられ、逆に塔子は恐縮した。
千枝子は、
「ここ、いいですか?」
と塔子の隣を示した。
「ええ、ぜひ。どうぞ」
千枝子は嬉しそうにカウンターに腰かけると、塔子と同じワインのセットを頼んだ。彼女がアルコールを、それも昼間に飲むイメージがまったくなかったので、塔子は少し驚いた。
「今日はお一人なんですね」
「ええ、夫が千晶を見てくれてるので。公園に行ってます。私も、今日は気分転換」
楽しげな千枝子の表情に、塔子も微笑んだ。やはり、時間さえ許せば夫とも協力しあえる関係なのだろう。
二人はスパークリングワインで乾杯し、ゆっくり飲みながらパターテ・アル・フォルノをつまんだ。
茹でたじゃがいもに香草やオリーヴオイルを絡めて焼き、削ったチーズをまぶした一品料理は、おつまみにぴったりだった。
眼鏡を上げて、得意げに運んできたところを見ると、これも倫巳が作ったらしい。
「・・・おいしい」
千枝子はため息をついた。スッとスパークリングワインを飲みほして、
「もう一杯お願いします」
と手をあげたので、塔子もおかわりを頼んだ。一緒に飲める人がいると、一人で寛ぐのとは、また違った楽しみがある。
しかし千枝子はおかわりのスパークリングワインも早々とあけると、今度は赤ワインをデキャンタで注文した。
「グラス二つで。・・・一緒に飲みましょう」
「ありがとうございます。でも・・・大丈夫ですか?」
塔子は少し心配になって訊いた。ペースが異様に速い。チラチラと動く彼女の瞳も、何か困りごとから逃げているようにも見えた。
千枝子は、勢いよくグラスにワインを注ぐと塔子に一つ渡した。それから、クイッと一口飲んで、大きく息をついた。
「・・・実は、あれからきょうすけくんのご自宅にお礼に行ったんですけど」
千晶から部屋番号や彼の好きなお菓子を聞いて、行ってみたという。
夜道で迷子になっていた娘を助けてくれたのだ。恐ろしい事態に発展したかもしれないと考えると、今でも肝が冷えると千枝子は言った。
だが現在、千枝子に杯数を重ねさせているのは別の理由だった。
少年の住むマンションを訪ねると、母親が千枝子を出迎えた。
彼女はかなり憔悴しているように見えた。この人も遅くまで息子を探し回っていたのだろうかと思うと、千枝子は罪悪感でいっぱいになった。
それでも勇気をふるって事情を話し、遅くまで「きょうすけくん」を外にいさせてしまったことを丁寧に詫びた。
「そうですか、あの子が・・・」
少年の母親は、どこか呆けたような顔で言った。あまり目を合わせてこないように千枝子は感じた。余計に緊張してしまう。
千枝子が千晶から聞いた彼の好物らしいクッキーの包みを出すと、
「どうぞ」
彼の母親は音もなく中へ進んだ。千枝子は恐縮しながら、靴を脱いで足を踏み入れた。
リビングには彼のものらしい、子ども向けの推理小説や漫画、おもちゃがたくさんあった。片づけても、子どものいる家はどこも似た感じで雑然としている。
この家族は最近引っ越してきたらしかった。まだ段ボール箱も残っているから、なおさら散らかって見えるのかもしれない。
チェストの上に、写真がたくさん飾られていた。
千枝子はその中の一つを覗き込んだ。昨夜の利発そうな少年が、ひまわり畑の中で微笑んでいる。
転校したときのものなのか、寄せ書きが後ろに立てかけてあった。
千枝子は何気なく文字を見て、慄然とした。
「恭介くん、ありがとう」
「天国で名たんていになってね」
塔子は、千枝子を見つめ返した。
そんなことがあるだろうか。あの夜、塔子自身も彼に会い、言葉も交わしていたのに。
「・・・恭介くん、夜道で車にはねられたそうなんです」
千枝子は見た目ほど動揺していないようだった。静かな口調で淡々と話していた。
それから残りのワインを大きな一口で飲み、
「だから自分と同じ目に遭わないように、千晶のこと、助けてくれたのかもしれません」
と、呟くように言った。
ぼんやりと帰り道を歩きながら、塔子は千枝子の話を反芻していた。
意外と驚きは少なかった。リュウが幽霊であることを(日々の暮らしの中で忘れそうになるが)知っている自分にとって、「きょうすけくん」と千晶の交流は、ごく自然に感じられたのかもしれない。
塔子はあの夜のことを思い出していた。彼を送っていこうとした塔子を、リュウは「追ってはなりません」と止めた。
理由は、これだったのか。
塔子は、あのとき「きょうすけくん」が入っていったマンションを見上げた。
リュウは帰った塔子を笑顔で迎えた。出迎えの言葉をつむぐ声が、いつもより静かな気がする。
彼は塔子が何か言う前に
「昼間のカフェに続いて恐縮ですが、冷蔵庫のじゃがいもを使いたく存じます。今夜はクロケットなどいかがでしょうか」
と言った。
なるべくいつも通りに感覚を戻そうと、努めてくれているような気がした。
夕食の前菜は、かわいいトマトカップだった。くり抜いたトマトに刻んだ中身や茄子、きのこ、アンチョビを和えて詰め、チーズを載せて蒸し焼きにしてある。
リュウが何気なく振る舞おうとする努力はありがたかったが、塔子はどうしてもあのときリュウが「きょうすけくん」を追ってはいけないと言ったことが、気になっていた。
訊いてみると、リュウはあっさりと肯定した。
「は。あの少年がこの世のものではないということは、承知しておりました」
あの局面ではお伝えするわけにもいかずに失礼いたしましたと言って、お辞儀をする。
もし追っていれば、何か恐ろしいことが起きたとでもいうのだろうか。
彼に続いて道路を渡ろうとしたところに、トラックが迫り来る・・・とか。
昼間の話を聞く限り、そうは思えなかったが、塔子は恐る恐る訊いてみた。
「いえ、恭介くんがそのような悪意をもった霊だとは、わたくしも考えておりません」
リュウはいくつかのボウルを器用に扱いながら、穏やかな声で答えた。
「ですが生きておいでの方と、わたくしのようなものたちの間には、決して越えてはいけない線がございます」
それから手を止めて、塔子を見た。
「塔子さまと、わたくしの間にもございます」
「・・・え?それって・・・」
リュウはそれ以上は答えなかった。
「お料理が冷めます。熱いうちにお召し上がりを」
と言って微笑んだ。
リュウが作ったクロケットはどれも見た目がバラバラだった。
長い円柱形のものや、外に衣がなく牛肉とトマトをマッシュポテトで包んだもの、それからよく見るオーソドックスなコロッケ。
「クロケットという料理は、国や地域によって食べ方や姿が変わります」
と、リュウはいくぶん明るい声で言った。
中の具材も魚であったり豆であったり鶏肉であったりと、異なるらしい。
塔子は円柱形のものを切って食べてみた。じゃがいもがベースになっているが香辛料が違うのか、いわゆるコロッケとは風味が違う。
「変わってる・・・でも、おいしいね」
リュウは嬉しそうに微笑んだ。
「クロケットはトーストに載せられることもあれば、シチューに入っていることもございます。例えば日本のクリームコロッケは、中にホワイトソースがありますな」
塔子は、リュウがいつになく口数が多い気がしていた。
が、料理がからむとこんなものかと思い直した。
「こんなコロッケがあるなんて知らなかった・・・そういえばコロッケってクロケットとも呼ぶんだね」
「は。わたくし、かつてそう呼んでおりましたから、くせでございまして」
リュウは照れたように言ってから、
「全く違う環境や意味合いで存在している料理たちが、何か一つ要素が共鳴することで、クロケットという共通の名で呼ばれました。今日も様々な国で、お互いに思いもよらない形で、食されているのでございます」
ボウルを静かに重ねて置くと、リュウは礼儀正しくテーブルに控えた。
「千晶さまの世界と恭介くんの住む世界は、本来なら決して出会うことのない線の上にありました。ですが、どこかに重なる地点があったのでございましょう」
そうかもしれない、と塔子はじんわり感じていた。
・・・リュウと塔子自身のように。
千晶と「きょうすけくん」の友情が、これからどうなるのかは塔子にはわからない。わかる日も来ない気がする。
だから、千晶の明日が楽しいものになればいいな、とだけ思う。
そして、もしあるのなら「きょうすけくん」の未来も。彼は天国で名探偵になっただろうか。
寄せ書きの話を思い出しながら、塔子は白ワインを飲んだ。
#小説
#連載小説
#執事
#家カフェ
#おうちごはん
#読書
#ミステリー
#推理小説
#執事
#幽霊
#グルメ小説
#ミステリー小説
#社会
#しごと
#社会の不条理
#独身女性
#生き方
