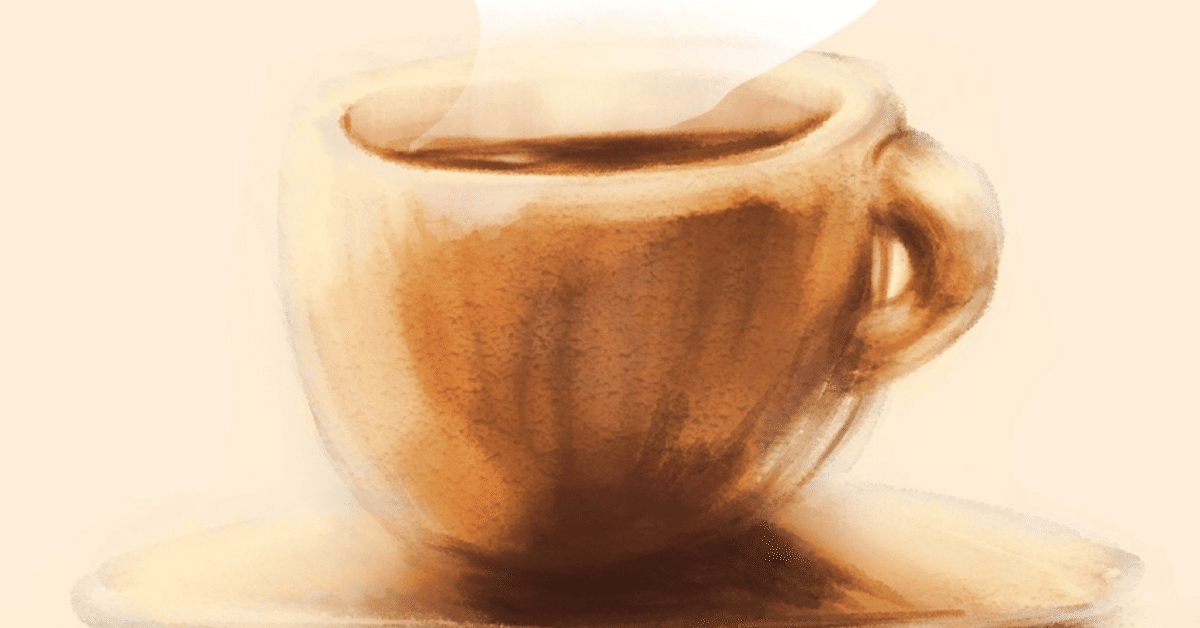
幽霊執事の家カフェ推理 第五話・逃亡のバーチ・ディ・ダーマ3
休日になると、多少は起きるのが遅くなる。塔子も例外ではなかった。
だが、時間がもったいない気がして、遅くても九時前には動き始める。
リュウは塔子の習慣を心得ていて、起きた時間に合わせて朝食を用意する。早めならパリッと焼き直したクロワッサンや、トーストとカフェオレ。
遅く起きた日なら、朝はフルーツヨーグルトとコーヒーだけにして、ブランチを豪華にしてくれる。今日は前者の日だった。
塔子は、大きなカップになみなみと注がれた熱いカフェオレで目覚めの体を温めた。
すっきりと晴れている分、外の気温は低そうだ。今日はゆっくり家で映画でも見ようかなと思った。
ソファでワイン片手に見ていると、だいたいリュウもそばで控えながら熱心に見入っている。存命中は、外出日に映画や劇場に出かけていたと聞いたことはあるが、まだ彼にとって映画は貴重で珍しい娯楽なのかもしれない。
だがその計画は、朝食の席で塔子が何気なく出してしまった話題に奪われた。
塔子は先週、残業帰りに江美里の店でビールを飲んだときのことをリュウに話した。リュウはそつなくコーヒーを淹れながらも興味を示した。
しきりに例のサイトを見たいと言うので、塔子は寝室からノートパソコンを持ってきた。
リュウはできあがった深煎りのコーヒーを塔子の席にそっと置いた。
アクセスして、塔子は思わずあっと声を出した。
「これって・・・」
「どうかされましたかな」
塔子は黙ってノートパソコンをリュウの方にずらした。そこには、最新の書き込みがあった。日付は今日、明け方だ。
ハンドルネームはbaci_di_dama。
「例の服の切りつけ事件、現場ってここの近くですよね。狙われそうな店員さんいたんですよね~。細くて、眼鏡かけたモテ系の。髪も茶色かったし、なんか心配になっちゃいました。帰りは裏の公園に気をつけて」
一目で倫巳のことだとわかる。塔子だけでなく、常連ならそう思うだろう。
「倫巳さんのことだよね、これ」
リュウも当然それは察していると思ったが、塔子は驚きを共有したい思いで言った。落ち着こうと、コーヒーカップを手に取る。マンデリンの深い香り が、不吉なイメージからいくぶん目を覚まさせてくれた。
それから塔子は、はたと気づいた。この、baci_di_damaというハンドルネーム。倫巳が作っているバーチ・ディ・ダーマのイタリア語表記だ。
そして、帰り道の記載。確かに店の裏側というか小道に面して、あのエリアを占める大きな公園がある。塔子もときどき散歩に行く。
この書き手はまるで倫巳の行動半径を把握しているかのように見える。
そして、そのことを暗に誇示しているようにも。
単にいたずらなのか。それとも。
これが犯行予告だということは、あり得ないだろうか。
塔子がそう思ったのは、文面からなんとも言えない悪意のようなものを感じ取ったからだった。
倫巳を暗示する、作為的なハンドルネーム。
あからさまに書かれた倫巳の外見。
まるで犯人が狙うことを誘発するかのような言い回し。
裏の公園。
いいだけ情報を露出しておいて、親切な警告文にはまったく見えない。
「考えすぎ?」
塔子はリュウに視線を投げた。が、リュウは黙って一連の書き込みを目で追っていた。
彼が塔子の問いに反応したのは、たっぷり数分経ってからだった。
「いいえ、そんなことはございません」
時間差があったので、はじめ塔子は何の返事なのか忘れかけていた。
「え、・・・ああ、そう」
少し気を削がれたが、気を取り直して訊いた。
「じゃあ、切りつけ事件の次の標的は倫巳さん・・・てことも、あり得ると思う?」
倫巳や江美里は、この書き込みをもう見ているだろうか。まだなら、教えてあげないと。
リュウはそっとノートパソコンを塔子の方に向けた。
「その前があれば、そういうことになりますな」
「どういうこと?」
たまにリュウはこうして、気を持たせる言い方をする。それも今のような大事な話のときに限ってそうするから、塔子はついじれったくなり声を大きくした。
「・・・わたくしも、これは確かに塔子さまのおっしゃるとおり犯人の言葉であると存じます」
塔子は黙って先を促した。
急かされていることに気づいたのか、リュウは今度は間をあまり置かなかった。そそくさとコーヒーのおかわりを注ぎながら、
「ただ、その犯人の狙いは初めから、倫巳さまだけだったと存じます」
「え?」
「このカフェの近くで立て続けに起こる、明るい髪色の華奢な男性を狙った事件。肌が露出するほど服を切られる・・・お嬢さまの前で申し訳ございません・・・が、けが人はいない。被害者たちは恥を恐れて通報しない。これらの事件は、何一つ存在しないのでございます」
「ん・・・?どういうこと?」
しばらくの間、塔子はリュウの言葉を咀嚼した。
「存在しないって・・・あ、フェイクニュースとか、そういうこと?」
「は。塔子さまは実に聡明でいらっしゃいますな」
リュウは微笑んでお辞儀をした。
「わたくしが生きていたころ、似た事件がございました」
それから背すじを伸ばして話し始めた。たとえ話で講釈をするときの仕草だ。
「ある高級ブティックの店員だけを狙って髪を切り、金品を奪うという事件が頻発したのでございます」
ブティックという表現に時代を感じる。が塔子はリュウをからかわず、先を聞くことを選んだ。
リュウはいつもの穏やかな声で続けた。
「犯人に関しましては、そのブティックに解雇された者の腹いせ、富裕層に対する反感などといった様々な噂が流れて憶測の新聞記事出回っておりました。ですが、一番大きく取り上げられたのは、恐怖の異常犯罪という説でございます」
塔子は思わず眉をひそめたが、リュウは表情を変えなかった。
「新聞社には様々な投書がなされました。親友の知人が犠牲になった、あの犯罪は外国の大きな組織が絡んでいる、犯行を見た者の行方がわからない・・・市民は次々にそういった情報を寄せ、新聞が連日大きく取り上げました。町ではどうやら危険な事件のようだ、表立って語ることはタブーである、といった雰囲気ができあがったのでございます」
塔子はなんとなくゾクッとして、冷めかけたコーヒーを急いで飲みきった。
「・・・それで?」
「ことが大きくなることを恐れたブティックの支配人が、店員たちに外出禁止令まで出す騒ぎとなりました。二週間ほどでしたが、そのブティックを閉めたのでございます」
リュウは、空になったカップを塔子の前から引っこめた。
「休業が明けてからは、二度と同様の犯行が起こることはございませんでした。もちろん犯人が姿を見せることも、逮捕されることもございませんでした」
それが本当なら、まさに怪人の犯行だ。塔子は、昔見た未解決事件の番組を思い出していた。
リュウはここで一息置くと、塔子を見つめて言った。
「ところが、後にスクープが出たのでございます。それらの事件はすべて事実ではない、創作だったというものでございます」
塔子は目をパチクリさせた。
「そうなの?」
「は。警察が犯人を野放しにしていると批判され、事件そのものが実在しないことを正式に発表したのでございます。あれはブティックの従業員による、ある種のストライキだったと警察は結論づけたそうでございます」
塔子は口を開けたまま頷いた。
「ブティックの支配人はすぐに否定しましたので真相はわかりかねますが、警察を訴えずうやむやになった点を考えますと・・・それに、確かにあの店は、従業員を酷使することで有名でございました」
リュウは生前その店を知っていたのだろうか。そんな口ぶりだ。
「この話の特徴は」
彼はあくまで礼儀正しく指を立てた。
「事件の倒錯的な恐ろしさや異常性が大きく広まる一方で、具体的な犯行場所や日時を示す情報がございません。実在しないからでございます」
そう言われて塔子は、カフェの書き込みを見直した。確かに現場は漠然と店の近くや道というだけで、日時に関してもまったく情報がない。
被害者の特徴や犯行手口は、これだけ具体的に書かれているにも拘らず。
「さっきの話みたいに、面白がる人がどんどん噂を広げた・・・ってこと?」
「は。いえ、わたくしの見解は異なりまして。失礼いたします」 と、リュウは器用に画面をスクロールしながら言った。
「わたくし、これらの言葉はすべてこの、baci_di_damaなる人物が、一人で書いたとにらんでおります。どれも別の名前にはなっておりますが」
「え?これ?」
「は。他はすべて別人になりすまして書いていると存じます」
「え、でもこれだって言い切れる?他にもこんなに書き込みいっぱいあるのに」
リュウは先ほどの話に戻りますがと前置きし、他の書き込みは見る人を煽るだけで現場に関する具体的な情報がないことを示した。
「そのわりにこの、裏の公園という言葉。こちらだけ場所が特定されておりますな」
確かに店のそばにある公園は、あそこだけだ。名前が書かれていなくても断定できる。
「そこに、この人物の意図を感じるのでございます。対象者・・・倫巳さまの目につくように鍵の言葉を使い、自分に気づいてほしいと、しきりにメッセージを送っているのでしょう」
リュウの声が少しずつ沈んでいくように、塔子には聞こえた。
「そして、そういった執着心の強い人物は多くの場合、単独犯でございます。このような犯人は、対象者を独占したいと思うのが自然であると存じます」
「ストーカー・・・ってわかる?そういうことだよね」
「は。例の板のような機械で、先ほどその言葉を見つけました」
タブレットのことだろう。リュウはレシピの研究によく使っていて、貸したら戻ってこなくなった。それ以来、やむなく塔子はノー トパソコンを使っている。
塔子はふと思いついて、ノートパソコンのキーボードを叩いた。そもそもこのページ以外に、事件のことが書かれているのか気になったのだ。
「切りつけ事件 カフェ」だとか「男性 服を切りつけられる」だとか、そのほか街の名前や事件の特徴を混ぜて何度か検索したが、無関係と思われる過去のニュース記事や映画などのページが出てく るだけだった。
リュウの推理、少なくともこれまでの書き込みが架空の事件であるという見解は当たっていると、塔子は確信した。そして、これがなりすましの単独犯であるということも。
口コミサイトに、これだけ無関係な事件の書き込みがされているなら、当然ブログやSNSでも事件の噂は投稿されているはずだ。それが一件も見つけられないのだから間違いない。
今まで一度も検索してみなかった自分に呆れる。
頭を振りながら、塔子はさっきの話に戻った。
「ストーカーだとしたら、もともと倫巳さんを知ってる人・・・ってことになるよね」
「は。あの方の素性を把握している者が犯人と存じます」
リュウは律儀に言い直した。塔子はため息をついて、ノートパソコンを指でつついた。
「こんな事件でっち上げてまで、何がしたいんだろ」
「塔子さまには、ご理解が難しいかと存じます」
「それ、どういう意味?」
「は。いえ、その・・・わたくし褒めております。その、健康なお心と申しますか」
塔子が発する疑惑のまなざしから目をそらし、リュウは咳払いした。
話題を強引に事件へ戻す。
「服を切って肌を・・・お嬢さまの前で申し訳ございませんが、そういった行為からわたくしには、相手の隠された姿を知りたい、内面や本質を把握したいといった願望・・・ある種の支配欲が見てとれるのでございます」
「支配欲・・・」
塔子はぽつりと呟いた。リュウは恭しく頷いた。
「は。いずれにいたしましても、あの方・・・倫巳さまは自衛なさった方がよろしいと存じます」
#小説
#連載小説
#執事
#家カフェ
#おうちごはん
#読書
#ミステリー
#推理小説
#執事
#幽霊
#グルメ小説
#ミステリー小説
#社会
#しごと
#社会の不条理
#独身女性
#生き方
