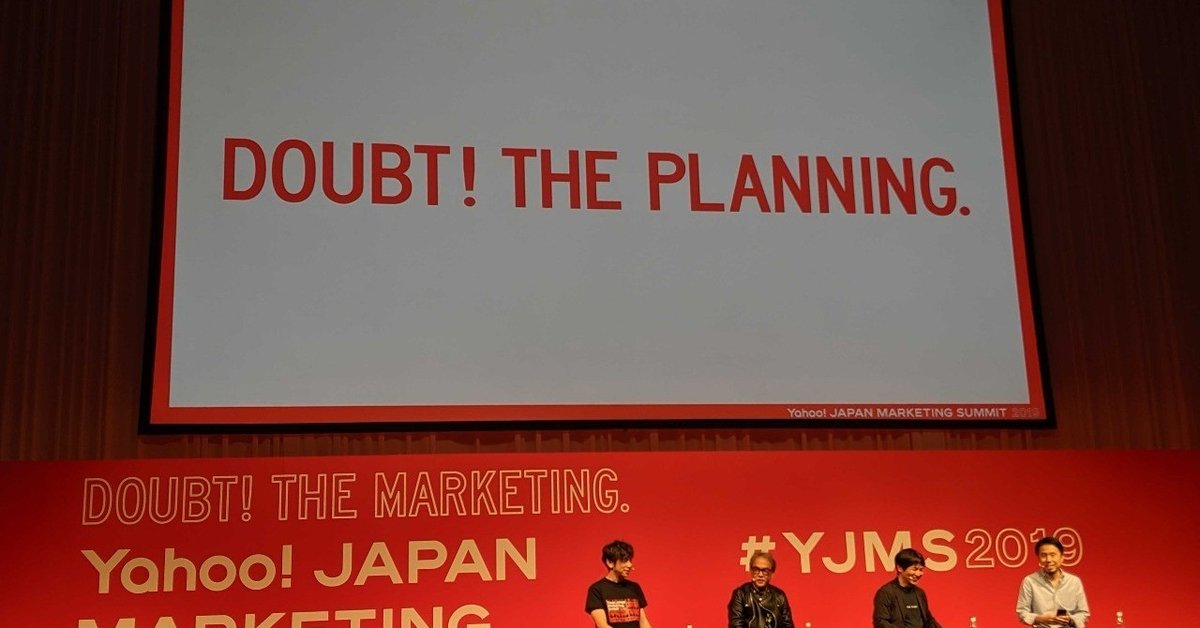
#YJMS2019 パネルディスカッション③ 「DOUBT! THE PLANNING.」
登壇者のみなさま
ナイアンティック アジアパシフィック プロダクトマーケティング シニアディレクター 足立 光 さん
株式会社ニューバランス ジャパン DTC&マーケティングディレクター 鈴木 健 さん
株式会社メルカリ 執行役員 CMO 村田 雅行 さん
モデレーター:ヤフー株式会社 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ 統括本部マーケティング本部長 井上 大輔 さん
自己紹介
足立さん「経営とマーケティングを両方やる人。再建が得意です。マーケティング歴は11年」
鈴木さん「広告代理店から事業者側へ。今はマーケとDTCという、直営店とEコマースもやっている」
村田さん「新卒で楽天で開発。そこからキラメックスを創業し、その後売却。メルカリにマーケ責任者としてジョイン」
井上さん「違和感という言葉よく使われますが、どういう意図で?」
村田さん「話題にしてもらうことが大事。違和感があると、言いたくなる。言いたくなってもらうために違和感が大事。メルカリが家電量販店っぽい折込チラシをだしたのも違和感」
足立さん「1日で3000くらいは広告を見るはず。そのなかで、『なんだこれ』と引っかからないとお金の無駄である」
鈴木さん「話題になる、は言葉では言いやすい。考えたこともなかったことだからこそ話題になるのに、広告代理店とかは既視感のあるものを出しがち」
井上さん「既視感がでない引っかかりの作り方は?」
足立さん「話題になっても売上があがらないこともある。話題化するのではなく、売るのが目的なので。落とし所をコンバージョンに結びつけるのが大事」
井上さん「どういうアプローチで考える?」
足立さん「基本的にはデータは見ない笑 超マクロな市場データは見るが、日々のデータは全然見ない。自分として何をやれば面白いか、というアイデアから考える。特定の人からイメージする」
鈴木さん「靴だと、機能性にフォーカスしがち。A社よりも良い、というような優位性を言いがち。しかし、ベネフィットは生活者・顧客が感じるところから生まれる。ので、お客さんが良いと思っていること、意味を感じてくれていることから、何に役立つかを考える」
井上さん「データの量というよりは、N=1のふかぼり?」
鈴木さん「ランニングは流行っていたりはするけど、なぜ走りたいか、という文脈や具体的なシーンを想起して考えることで違和感が生まれる」
足立さん「大事なのは競合を見ないこと。ただし、他の業界を見ておくのは大事。たとえば、ナイアンティックではポケGOの新聞広告をやったが、メルカリを参考にした」
井上さん「3Cというフレームワークに競合が入っているから、考えがち。では、フレームワークについて考えましょう」
STP
井上さん「STPについてどう考える?」
村田さん「メルカリはSTPという言葉を使ったことはない」
鈴木さん「考え方としてはもちろんしっているが、このフレームから始めちゃうと、そこの中でとどまっちゃうからそこから始めないほうがいい。自分たちの作りたい世界が何で、それをSTPに当てはめるなら、という順番で考えるべき。大学生に教えたときにSTPから始めちゃうとおもしろくなくなっちゃった」
足立さん「フレームワークを使うと誰でも同じアウトプットになっちゃう。戦略を考えるのは大事。ただ、同時にどんなことをどうつたえたら響くのかというアイデアも同じくらい大事。戦略があってもアイデアがなければ効かない」
井上さん「戦略というガードレールの中でアイデアを考えるのではなく、同じ土台で考えていくということですね」
村田さん「会社、サービスとしてお客さんに喜んでもらうために、どんなお金の使い方をしたらいいのかを考えるのがアイデア」
井上さん「どうアイデアを着想する?」
足立さん「他の業界を見る」
鈴木さん「フレームワークは考えを整理するのには使える。ランナー、などのお客さんと話すことでアイデアは生まれる。ターゲットの人たちが好きそうな場所に出向いて観察を行う」
足立さん「フォーカスグループなどは絶対やらない。お金をもらって、あんなに非日常なブースで素直な言葉は出てくるはずがない。ユーザーは世界にいっぱいいるので、普通にその辺で聞いたほうがいい。ターゲットがよっぽどレアでない場合は、普通に聞いちゃったほうがいい。コアなユーザーの声は一部でしかないので、商品開発で参考にするのは危ない。コアユーザーは割合としては少ないので」
井上さん「コアユーザーはほんの一部。だいたいの売上はライトユーザーから成り立っている」
村田さん「カスタマーの声はもちろん見ているが、マーケティングのアイデア自体は、自分の母親など周りの人の声を参考にすることが多い」
井上さん「人の話を聞くコツは?」
村田さん「会話を普通に楽しむ。楽しければストーリーなど自分から話してくれる」
足立さん「自然な感じで、に尽きる。品川、目黒、世田谷、などで流行っていることは日本中で流行っているわけではない。なので、日本の都心部ではないところでヒアリングするのが重要。東京の人たちは例外であることを忘れてはいけない」
CRM
井上さん「大事なお客さんへのアプローチをCRMだとするとどう考えている?」
村田さん「よく使ってくれている人にポイントやクーポンをあげたりはしているが、スターユーザーに特別何かをしている、ということはない」
鈴木さん「やってはいるが、ジレンマ。ロイヤリティパラドックスと呼びたいくらい。追求すればするほど、狭くなる。コアファンに通じることがそれ以外の人たちに通じるのかを考えなくなる。コアファンに対峙するのはメーカーとしては楽しい。ロイヤリティプログラムを全部否定するわけではないが、コンフォタブルゾーンに入ってしまうので、いつでも新しい顧客を意識するのは大切。ミクシィもモンストでコアユーザーを意識しすぎた結果売上が激減したという例もある
ブランドだけでなく、カテゴリーで一番ヘビーユースしている人は入れ替わる。自分のブランドだけ見ていると機を逃してしまうことになる。ニューバアンスであれば、スニーカーのハイブランドというカテゴリでお金を使う人の視点も忘れてはいない」
足立さん「僕がCRM語ると炎上しますけど笑 自分が言っていたCRMは、データをもとにメルマガやプッシュ通知を配信するようなこと。効かないとは言わないが、CRMによって勝った会社はほぼない。逆に、いち消費者として、CMR的なアプローチですっごい嬉しかったという体験ってないと思う。つまり、それで差別化しよう、勝とうというのは難しい。改善としてやるのはいいとは思うが」
井上さん「TESCOさんがスコアリングポイントというものを開発して、それはうまくいっていたが、TESCOもずっと調子が良かったわけではない。CRMは意外とコストがかかる。お金もかかるし、営業マンや他のメンバーへの教育コストなどもかかる」
鈴木さん「競合との同質化という点でやる意味はあるかも。amazonは日本だけでポイントプログラムをやっている」
ブランド哲学
井上さん「ブランド哲学という言葉について、考えていることはある?」
村田さん「まだ6年なので、今後はサービスブランドとしての哲学は作っていきたい。カルチャーには力を入れていて、コーポレートブランディングには成功していたとは思う」
鈴木さん「ニューバランスはプライベートカンパニー。Responsive Leadershipという言葉を大切にしている。会社が社会・コミュニティに還元する意識」
足立さん「1会社1ブランドのケースも1会社複数ブランドの場合もある。お客さんにとっても大事だが、社内的にも大事。ブランド哲学が大事なのは、リクルーティングにおいて。ブランド哲学に共感してくれたナイアンティックは『テクノロジーで家から一歩出して健康な人を増やそう』という哲学。生活者がそれを知らなくてもモノは売れていくが、それに共感したいい社員がいるからこそ、いいものが作れている」
井上さん「ブランド哲学がなくてもモノは買われる?」
鈴木さん「共鳴してくれる従業員が入ってくれる、というのももちろんある。Winning Aspirationという言葉が好き。勝つために気持ちが上がるものは何なの?何をやりたいんだ?というのがはっきりしているほうがしっくりくる」
足立さん「ブランド哲学だけでは売れない。一貫性を保つためのガイドラインという意味でブランド哲学があったほうが施策を回しやすいという点はある。ただし、それを人に知らせる必要がない場合もある」
井上「コミュニケーションを設計するための旗印を作っておく、というイメージですかね。Aspirationに込められた意味合いは?」
鈴木さん「野心、とか。この部屋も真っ赤ですが、赤には勝つための情熱、みたいな意味合いもある。そういった、勝つための情熱を燃やす部分から始めるのがいいと思う」
井上さん「外資系にいるとruthless,relentlessなど、容赦ない実行、のような軍隊っぽい言葉をよく使う。マーケティング用語自体、そういった軍隊用語から作られていることも多い。そういった、『気迫』的な部分も大切なのでは?」
CLOSING REMARKS「新体制の戦略」
ヤフー株式会社 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長 赤星 大偉さん
メディア・マーケティングソリューション・セールス、一環となる体制で挑戦していきます!

いいなと思ったら応援しよう!

