
No.1 『月世界旅行』 (1902)
『月世界旅行』

作品情報
監督・脚本:ジョルジュ・メリエス
製作年:1902年
製作国:フランス
上映時間:16分
サウンド:サイレント
カラー:カラー・リストアバージョン
出典:映画.com
あらすじ
天文学会のメンバーである6人の学者が、月世界旅行を企てる。巨大な砲弾に乗って彼らは月に着陸する。
そこは、見たこともない景色が広がる奇妙奇天烈な世界だった。探索の途中で、彼らは異星人の襲撃を受ける。奮闘むなしく生け捕りにされた彼らは、月の王に差し出される。
果たして彼らは無事に地球に戻れるのか-。
オフィシャルHP
感想
なにか映画が見たい気分で、フィルマークスをひらいてAmazonプライムにある映画を探す。
なにかをしたい、知りたいと思うときに検索すれば欲しい情報が手に入る。とてもありがたい時代で、そしてそれがもう自分のなかで、さも昔からあったかのように当たり前になっていることに気づく。
そういえば、むかしは駅前のTSUTAYAに20分かけて行って、映画を借りていたんだ。旧作5本で1000円のキャンペーンにまんまと乗せられて、たくさん借りては延滞金を発生させてしまっていた自分が懐かしい。
本屋に寄ったら気になった本を1冊多く買ってしまったり、スーパーへ行っては使う予定のなかった食材を買ってしまったり、特に必要としていないものも、実際にお店に行くとつい買ってしまう。
あの感覚はとても大切だった。
今はもう映画はサブスクをメインに、ないものは買ったりの生活だけど、また1000円レンタルをしたい気持ちが沸々と湧いてくる。
レンタルビデオ屋、復活しないかな。
そんなことを思い、フィルマークスで映画を検索していると、実にたくさんの見たかったはずの映画たちがラインナップされていて驚く。こんなにあったけ?となりつつ、あれもこれもとなってしまいながら、今回は映画史の本を読むと必ずと言っていいほどに出てくるメリエスの『月世界旅行』をチョイスして見ることにする。
大学の授業で見た気もするし、見なかった気もする。でも、あまりにも有名で16分と短いので授業でたぶん見たんだろうな、と思いながら、また見てみることにする。
今回、私の見た『月世界旅行』は2012年に日本で公開されたドキュメンタリー映画『メリエスの素晴らしき映画魔術』と一緒に上映されたカラー・リストアバージョンだった。
『月世界旅行』は当時モノクロで撮影、上映をされたのだけど、フィルムに直接彩色を施す方法でカラー版も上映されていた。そのオリジナルのカラー版はもうこの世には存在していない。
メリエスは『月世界旅行』を制作した後、映画の賃貸システムなどの発展についていけずに、自身の撮影したフィルムたちをすべて燃やしてしまう。
中平卓馬も撮影したフィルムを焼却してしまっていたり、小津安二郎の作品も現存していなかったりで、そこにどんな思いや仕方のない事象があれど、失ってしまうことはやはり言葉にできないくらい悲しい。
奇跡的に発見された、劣化のひどいプリントを現代の人々が手作業とデジタル技術をつかって修復して復刻、公開されたのが今回のカラー・リストアバージョン。映画に魅せられた多くの監督や関係者、そして映画ファンはこの公開をどんなに楽しみにしていたのだろう。と、同時に当時の人々はこの映画をどんな気持ちで見ていたのだろう、と思う。
この映画が作られた時代は、列車の到着や見世物小屋で行われるショー、海外の街の様子など、今でいう記録映像的なものがほとんどで、見世物性が強く、物語性のあるものは作られてこなかった。そんななかでメリエスは物語性のある作品をはじめて作る。
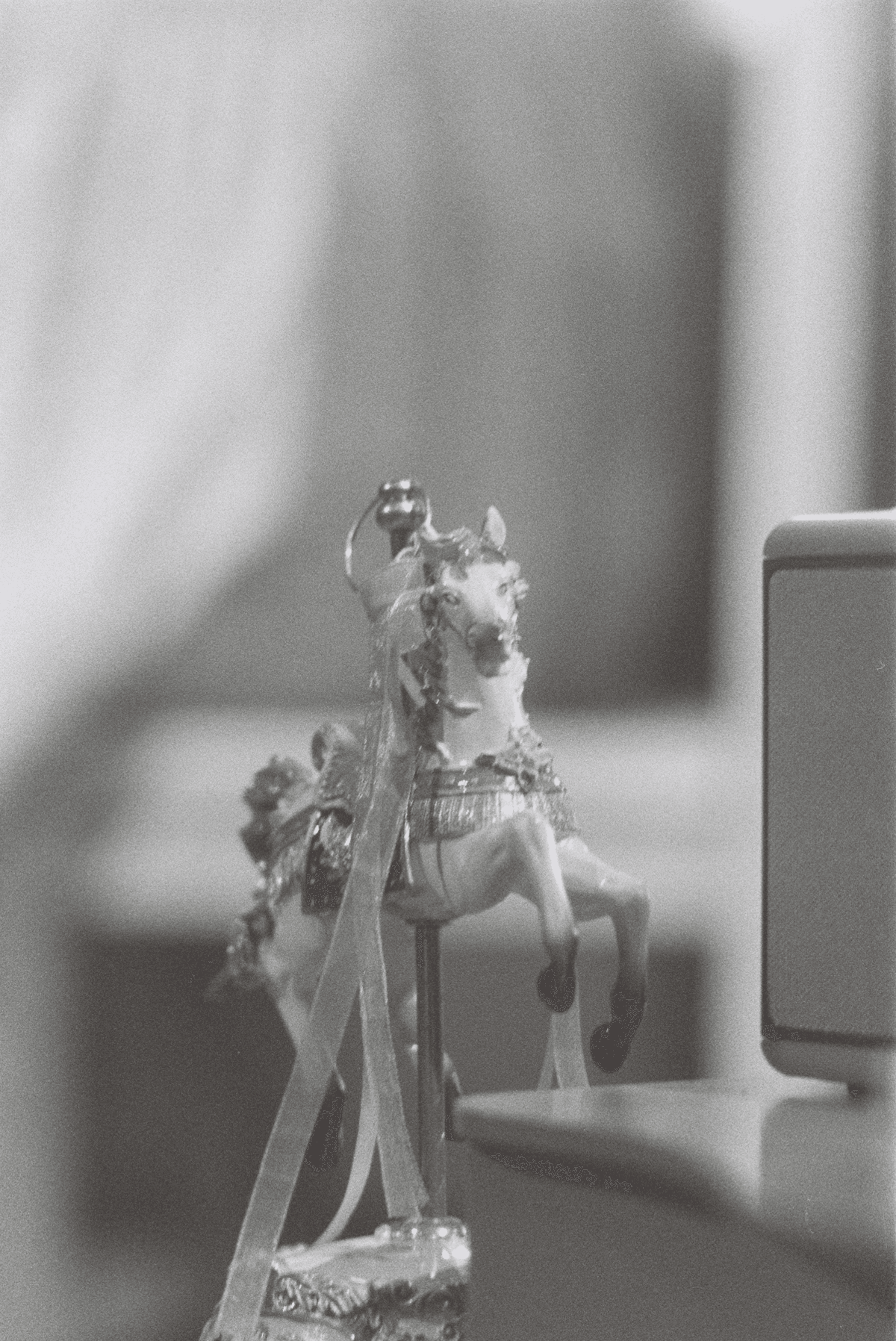
「映画」はここから始まったんだ。
ここから当時はまだなかったハリウッドに、たくさんの国に、輸出されて映画は発展していくのだ、そう思うと、つい心が躍ってしまう。
世界初のSFとして知られるこの作品は、フランスの作家ジュール・ヴェルヌが発表した『月世界旅行』を参考に映像化したもので、当時はサイレント映画の時代だったので、映画には同時演奏はあったものの、台詞などのサウンドトラックつかなかった。ストーリーを伝える上での「語り」の方法がとても少なかった。そのため、映画では展開や結末が広く知られている童話や小説などを誰もが知っている物語を題材に映画が作られていった。
はじめての物語のある映画。
それがこの映画をあまりにも有名にしている要素だと思う。当時は編集という概念がなかった時代、その時代に彼は編集というものを編み出し、物語映画を作った。
さすがマジシャンだと思わせられる。映画を魅せるということに、人の心理をつかむということに卓越している。
固定のカメラで、カメラは動かずに人が動くように撮っているのだけど、砲台から月へ行くとき、月へ近づいていくように撮られている。それまで映像には横の動きしかなかったのだけど、縦の動きを差し込むことによって表現している。
月に砲弾がめり込む。
誰もが知る月に顔があって砲弾が刺さっているこのシーンをメリエスは撮りたかったのだろうな、と思う。し、人々の印象に残るのもカメラワークの違いからなのだと思う。
人の動きも月へ行くまでは、右方向に流れるのに対して、月から帰ってるときにはきちんと左にされていて、違和感がないように作られている。
カメラワークなんて、映画の文法なんてなかった時代にこういうことを編み出してしまうなんて本当にすごいと思う。今では当たり前だけど、こういう人たちがいて、今日の映画は作られてきたのだろうと思うと、あまりにも凄すぎて言葉が出てこなくなってしまう。
宇宙人が消える演出とかもコミカルでとても可愛い。登場人物の動きも、サイレンだからなのだろうけど、大きく動いていてそれもコメディみたいで可愛く思える。
SFの最初の映画と言われているけど、侵略していく面では西部劇だったり、コミカルな動きはコメディっぽさやミュージカルっぽさを感じたりしてしまう。
いずれにせよ、ここから映画が始まったのだのだから、あらゆるジャンルの要素を持っていても不思議ではないのかな、と思う。
はじまりの映画を、映画ノートの最初にして良かった。
