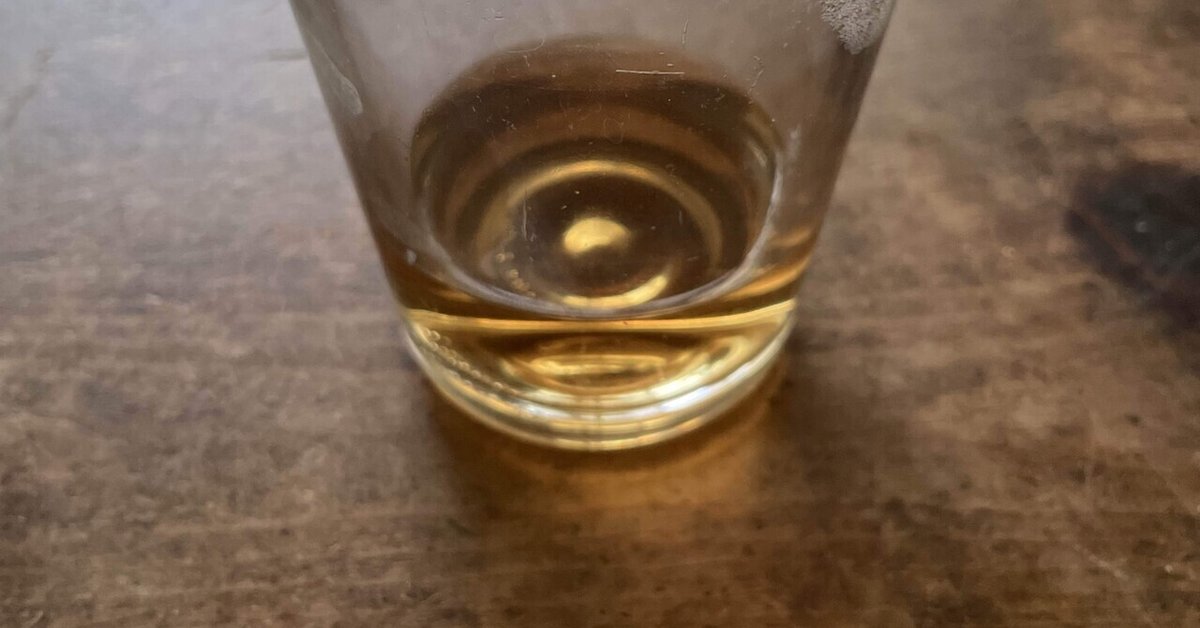
下北沢、お茶、サフラン、須賀敦子、ノマド
以前に茶摘みと製茶を体験させてくださった赤羽さんが「遊讀茶會」という「ひととき」をされるということで、参加させていただきました。
案内に「サフランにちなんだ須賀敦子さんの短篇を音読したく」とあったので、自分の中の「下北沢、お茶、須賀敦子、ノマド」の言葉が反応して、「島根のサフラン?」という好奇心が動いたのだと思います。
この頃、なんとなく、人と交わる時のスピード感がとても遅くなっていて、でもそんなに嫌ではなくて、気がついたのですが、どうも「小学校の低学年の頃の私」に戻っているようなんです。
ちょっとびっくりです。
赤羽さんのいろんなお茶をいただきながら、みなさんの会話を聞きながら、須賀敦子の短編を音読しながら、文章を読んでいる人の目が文字に沿って上から下へ視線が流れる様子を見て、「ああ、本を読む時の目が動くのをひさしぶりに見たかも」と思いました。
これってすごくいいなぁ。
「読んでる」というのが視覚的にわかる。それでさらに「声が聞こえる」。
声で内容が伝わってきて、「読んでいる文章」と「読んでいる人の表情」が一緒に入ってきて、その人の思考が動いているらしいことがわかりながら、自分の思考も動いている。
そんな風に、目が動く、顔の表情が動く、声が変化する、言葉の内容が流れていく、読んでいる人の思考の動きを感じる、私の思考の動きも感じられる。
こんなにたくさんのタスクが並走していることを、いっぺんに感じられていくなんて。
きっと、それがすごく好きなんだと思う。
だから、小さい子供は「本を読んでもらう」のが大好きなのかもしれない。
大人もきっと好きですよ。
須賀敦子の文章を初めて読みました(聴きました)。
たまたまなのか、他もそうなのかわかりませんが、『『サフランの歌』のころ』という16ページほどの短編には、彼女自身が子供の頃に「こんな場面で、こんな風に感じた」ということがずっと綴られていて、そのことを私自身「誰かの声」で知ることができたのも、とてもよかったです。(めったにできない体験かもしれません)
昨夜は、赤羽さんの紅茶と半発酵茶と山のお茶を分けてもらいました。
透明な茶器にお湯を注ぐと、最初に小さな茶葉が上と下とに二手にゆっくり別れて、次に上の葉がゆるゆると降りてくる。降りてくるよいうよりくるくる上下しながら舞う感じ。
しだいに、お湯に紅茶の色が移ってきて「ああ、今かも」と、タイミングが自然にわかったことに、びっくり。
3分とかではなくて、茶葉ごとにお湯の中での動きをみて「時を知れば」いいんですね。今は透明の茶器があるんですから、それができますし。
茶葉ごとに「違う」というのもわかって、その違いも愛おしくなりそうで。
お茶は、素肌のような味がして、だからこんな文章を書きたくなったのだと思う。
息子も無言で飲むことに入りながら飲み干していました。
赤羽さんをはじめ会をつくってくださったみなさま、ありがとうございました。
「きっと、この夜のことをいつまでも思いだすだろう」
『『サフランの歌』のころ』 須賀敦子
*
