
後ろ歩きで多くの介助を必要とする症例
以下に記す症例について、見方、知識の使い方、考え方の流れが参考になれば幸いです。
情報)
高齢の方である。
以前、パーキンソン病の診断を受けた。
トイレや椅子に腰かけるときの後方移動で足が出ず、多くの介助を必要とする。
今回、介助量軽減に向けて、アプローチ法を見出すため検討した。
後方移動)
体幹前傾・屈曲、股関節の屈曲が大きい。
後ろ歩きは小刻みで、後方への下肢の運びが少なく介助を必要とする。

途中で後方に進まなくなり、セラピストが椅子を差し出す。

歩 行)
矢状面では後方重心で小刻みである。

前額面は両足が接触し、股関節内転筋の緊張を伺わせる。
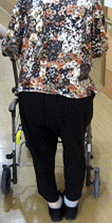
歩行を続けていると体幹・股関節・膝関節が屈曲して、より重心が後方に位置してきた。


椅子に腰かけるためにテーブルを持ち、横歩きをして椅子に向かう。

この時、体幹・股関節・膝関節の屈曲角度はテーブルをつかむために大きいが、横歩きの小刻みの程度は、歩行時と変わらなかった。

Q) どのように考えればよいか?
A) 後方に歩けないのは、股関節伸展による後方に支持基底面を作れないためである。
なので、股関節伸展を妨げる要因を考える。
Q) 要因は?
A) 股関節屈曲筋が優位に働いているためである。
Q) 何故?
A) 歩行の前額面で股関節内転筋の緊張から腹直筋・内転筋の筋連結を想像する。
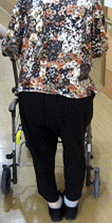
また、歩行の後半では、体幹、股関節、膝関節屈曲角度が大きくなる。

これは、大腿四頭筋の低下に対する筋連結を利用した大腿直筋活性と、膝関節屈曲角度から考えて大腿四頭筋を発揮しやすい肢位にさせたことが考えられるので、大腿四頭筋への対応と考えることができる。
Q) その可能性もあるが、横歩きで椅子に向かう場面では小刻みの程度に変化はなかった。
横歩きでは、側方への対応が必要なため腹斜筋が優位になり、腹直筋の作用が低下する。
すると、下肢の緊張を高めて膝関節伸展保持しようとする。
その緊張により、下肢のストラテジーは低下して立脚期の片脚での姿勢バランスが保てず、小刻みは多くなると考える。
なので、大腿四頭筋の低下の対応とした説明は難しいのでは?
A) 他の視点で考えたい。
Q) それは?
A) 下肢への筋収縮促通のための体幹筋作用ではなく、下肢の緊張を高めて体幹に作用させるとした考え方である。
Q) そのようなことはあり得るのか?
A) 寝たきりの方が上下肢を屈曲させるのは、脊椎の安定化のために行っている可能性があることから考えられる。
そこから、歩行の後半の屈曲肢位は、寝たきりの方と同様の対応と考えることができる。
Q) すると後ろ歩きは?
A) 歩くための対応とすると説明できない。
Q) では?
A) 後ろ歩きによる後方への転倒後を考えて、体幹の固定をするために下肢が作用していると捉えてみる。
その対応は前額面の股関節内転肢位から考えて腹直筋が優位である。
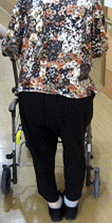
そして、歩行後半の下肢の屈曲肢位は、筋連結意外に、腹直筋収縮による骨盤後傾に対する立位保持のための下肢の対応と捉える。

Q) アプローチは?
A) 腹直筋以外の体幹筋の収縮を促し、股関節屈曲筋の優位性を減らす。
Q) 方法は?
A) 体幹側屈筋を収縮させて腹直筋以外の筋の収縮を促す。
実際、ご自身ではできないので、姿勢反射を利用した。
座位で他動的に体幹を左右に揺らす。
揺らす程度は、脇腹や腹直筋を触診し、脇腹の収縮が大きく、腹直筋の収縮が少ない肢位を探りながら行った。
これを本人の疲労を考慮しながら10分間行った。
Q) 結果は?
A) 小刻みの程度には変化はなかったが、屈曲肢位は減少し、本人が後方を確認しながら後ろ歩きができ、介助量が減った。
後ろ歩き~座位)



最後までお読み頂きましてありがとうございます。
