
<第12回>Step4-3.執筆(後編)〜③書くモチベーションが続くための気持ちの整え方とは?【文章の書き方入門講座】
こんにちは。
戦略マスター頼朝です。
今回も、第10回(前編)と第11回(中編)に続いて、Step4.「執筆」のやり方についてご説明していきます。
前編のテーマは、「題材メモをどうやって膨らませて書くの?」というものでした。
そして、中編のテーマは、「読みやすい文を書くための工夫とは?」でしたね。
前編と中編の各内容を理解しておけば、題材メモと構成メモをもとに文章を執筆していくことはできます。
しかし、書きたい気持ちはあるのに、ペンが進まなくなってしまう日もありますよね。
題材メモも構成メモも揃っているにもかかわらず、なぜだか1行も文章を書けない日があるものです。
私は子供の頃から読書と文章を書くことが好きでしたが、1行も文章を書けない日があったりしました。
そんな経験をされている方は、私の他にも多いのではないでしょうか。
書けないのは、知識や経験、技術の問題ではなく、実は気持ちの問題だったりします。
せっかく文章を書いてみたいという素敵な気持ちを持てたにもかかわらず、なかなか書けずにダラダラと日を過ごしてしまい、書きたい気持ちがだんだん萎んでいってしまうのはとてももったいないと思います。
ただ、私の場合は、気持ちの整え方を変えてみたら、ツイートの文章を毎日書き続けることができるようになりました。
そこで、「執筆」についての最終回である今回(後編)は、書くモチベーションが続くための気持ちの整え方についてご説明していきます。
10,000通以上の文章指導をしてきた私なりの経験を交えて、いくつかのポイントをお伝えして参りますので、参考になると感じてもらえるものが1つでもあれば嬉しいです。
それでは行ってみましょう!
戦略マスター頼朝@文章術でブランディング/リーダーシップ論(@6VQGPJH3FHYoZn6)さん / X (twitter.com)

3.書くモチベーションが続くための気持ちの整え方とは?
3-1.まずは自分が好きなように書いてみる
書き続けるためのコツの第一は、文章の細かいルールを気にせずに、とりあえず気楽に書き始めてみることです。
題材メモも構成メモも揃っているにもかかわらず、ペンが止まってしまう原因の1つは、文章のルールを意識しすぎて萎縮してしまっていることにあります。
そもそも文章のルールは、書き手が読み手に伝えたいことを理解してもらいやすくするためのものです。
つまり、文章によるコミュニケーションをより良くしていくための読み手と書き手共通の約束事なのです。
ところが、より良いコミュニケーション作りをするためにあるはずの文章のルールが、逆に書き手の手足を縛ってしまうのでは本末転倒ですよね。
また、会話とは違い、文章は発表前であれば、後からいくらでも書き直すことができます。
もし文章のルール的に間違った書き方をしているところがあれば、それは「執筆」の次の「推敲」の段階で書き直していけば良いのです。
したがって、まずは気楽に楽しみながら、自分が好きなように文章を書き始めてみましょう。
ところで、書き始められないもう一つの原因としては、「人に読んでもらう以上は、きちんとした質のものを提供しなければならない」と強く思い込んでしまうこともあります。
確かに、きちんとした質のものを人様に提供しようとする姿勢は、私たち日本人の美徳だと思います。
真面目で丁寧な姿勢があるからこそ、高い品質の商品を生み出し続けることができているからです。
ただ、それも行き過ぎるとマイナスになります。
きちんとした質のものにこだわり過ぎて、1行も文章が書き始められないようですと、経験値が貯まりません。
経験値が貯まらないと、文章力はいつまでたっても向上していかないのです。
また、最初から質にこだわり過ぎることで、せっかく文章を書いてみたいという素敵な気持ちが芽生えたのに、その気持ちがだんだん萎んでいってしまいます。
したがって、文章力向上に向けて必要な経験を積むために、また、文章を書きたい気持ちを大切にするためにも、まずはたくさん書いてみることをお勧めします。
とりあえず何でもいいので書き始めてみれば、後から書き直していくうちに経験値も貯まっていくからです。
しかも、書き始めてみると少しずつ楽しくなってきて、エンジンが本格的にかかり始めることも多いです。
そして、たくさん書いてみたら、その中から良いと思うものだけを残して、それを磨き上げていきましょう。
質は量をこなすことから生まれてくると言って良いと思います。
文章指導をしてきた私の経験からしますと、多くの生徒さんたちは、書く量を積み上げていくうちに自然と質も向上していきました。
そこで、最初は文章の細かいルールなどはあまり気にせずに、思い浮かんだ言葉をたくさん書いていくことから始めてみましょう。

3-2.好きな作家の文章を真似して書いてみる
職場の好きな先輩や上司、テレビの向こうの格好良いスポーツ選手など、憧れの対象がいるのは幸せだと思います。
憧れの気持ちは、物事に取り組む際の強い原動力になるからです。
文章を書く場合も同じです。
好きな作家がいると、その作家に近づきたい気持ちが湧いてきて、「自分もそのような文章を書いてみたい!」という強い動機が生まれるからです。
したがって、好きな作家を見つけたら、とりあえずその文章の好きな箇所を書き写してみることをお勧めします。
書き写していくうちに自分の文章力が向上していきますし、何よりも、萎みかかった書きたい気持ちが復活してくることが多いです。
しかし、「それではただの真似ではないか」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
心配ご無用です。
物事を身につける時は、最初は真似から入るのが効率的だからです。
そして、憧れの作家の文章を書き写すことに慣れてきたら、次第に自分の色を付け加えていきたくなるものです。
自分の色を付け加えていくうちに、最初は借り物だった文章が次第に独自性ある自分だけの文章になっていきます。
まさに「守破離の教え」といえます。
最初は上手な人の真似をしたり、先生から教わった基本を忠実に守ることから物事の練習を始めます。
次に、基本を当たり前にこなせるようになったら、次第に自分の色を付け加えて、良い意味で基本を破る段階に進みます。
そして最後に、自分の色をさらに付け加え続けることで、基本を踏まえつつも、人の真似から離れた自分独自のスタイル(=文体)ができあがるのです。
英語の勉強においても、「英作文は英借文」という言葉があります。
生まれながらに英語を聞いたり話したりする環境で育ってきたわけではない人は、いきなり英作文を書くことはできません。
そこで、最初は基本となる例文をたたき台にして、英文の中の単語を入れ替えながら、次第に自分が伝えたい英文に仕上げていく練習をするのです。
したがって、ペンが止まってしまった場合には、憧れの気持ちを取り戻すために、そして、文章力向上のために、好きな作家の文章を真似して書いてみましょう。

3-3.書けない時は取材・構成をやり直してみる
仕事においても勉強においても、迷ったら原点に戻るのがリカバリーするのに有効です。
そこで、文章を書きたい気持ちがあるにもかかわらず、ペンが止まってしまった場合には、原点に戻るつもりで、もう一度取材をやり直してみると良いでしょう。
取材は、テーマに対する自分の心の動きを取り戻してくれます。
もう一度取材対象と向き合い直すことで、以前には感じなかった新たな心の動きが生まれることもあります。
取材し直すことで新たな題材カードができたならば、また構成を練り直せばいいのです。
取材と構成に戻ってやり直してみることで、書きたい気持ちが自然と復活してくるでしょう。
したがって、ペンが止まってしまった場合には、一歩後退二歩前進のつもりで、取材や構成をやり直してみることも、書きたい気持ちを復活させるための特効薬だと思います。
私の経験上、長い文章になればなるほど、ゴールまでまっすぐ順調に書き進められるわけではありません。
取材・構成と執筆との間を行ったり来たりすることを繰り返しながら、徐々に完成に向かっていくものだと感じています。
せっかく抱いた書きたい気持ちがまだ残っているのであれば、この行ったり来たりのプロセスをむしろ楽しみながらやるようにしましょう。


3-4.人と対話してみる
文章を書きたい気持ちがあるのにペンが止まってしまう場合には、題材メモと構成メモを片手に人と対話してみるのもお勧めです。
人と対話することで、自分の頭の中でモヤモヤしていたことが次第に明確になってくることが多いからです。
対話によって考えが整理され、明確になってきますと、書きたい気持ちが復活してきて、止まっていたペンが再び進み始めます。
実際、小中高生の生徒さんに作文や小論文の書き方を指導しますと、たいていの子が最初はペンが止まりがちです。
そこで、文章を書くための下準備として私と一緒に作ってもらった題材メモと構成メモを片手に、私から色々とインタビューしてみます。
すると、文章に書いて説明することには心理的抵抗感があった子も、口頭ではすらすらと自分の伝えたいことを話してくれます。
私からは、
「今話してくれたことを書いてくれれば大丈夫だよ。
説明が凄く分かりやすくて、君が言いたいことが具体的に伝わってきたから。」
と話します。
すると、その子はパッと表情を明るくして、
「えー、そうなんだ!
今、口で説明したことを文章にすればいいんですね!」
と理解してくれます。
このように、ペンが止まってしまった場合には、いったんペンを置いて人と対話をしてみると、書くべき文章を具体的に思い浮かべやすくなります。
いざ原稿用紙に向かうとペンが止まりがちだった子であっても、指導者との対話によって、書くべき文章のイメージが自然に湧いてくるようになるのです。
周りに論文の指導者がいない場合であっても、家族や友達などの身近な人に話してみるだけでも十分に効果があります。
周りにそういう人がいない場合は、伝えたい相手を具体的に思い浮かべて、一人喋りをしてみるのも効果的です。
もちろん、話し言葉と書き言葉は違いますので、口頭による説明は後から書き言葉へ修正する必要があります。
それでも、質問と応答を中心とした人との対話は、文章を書き続けるための大きな原動力になってくれます。
したがって、ペンが止まってしまった場合でも、それにめげずに執筆を続けていくためには、自分が書きたいと思っているテーマについて人とどんどん対話をしてみましょう。

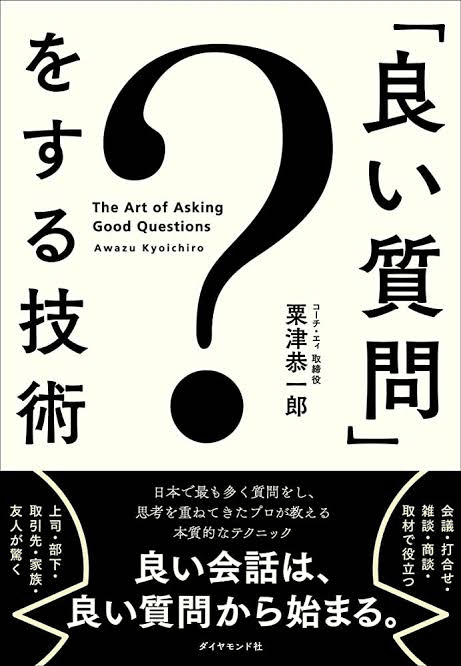
3-5.書く前に期待値を引き下げてみる
近い未来への理想像を持つことは、人が成長を続けていくためにはとても大切なことです。
ただ、これも、きちんとした質のものを提供しなければならないと思い込み過ぎている心理状態と同じで、行き過ぎるとマイナスになります。
普段、自分はそれ程プライドが高くないと思っている人でも、心のどこかで期待値を高く上げ過ぎてしまっていることがあるかもしれません。
確かに、自分を成長させるような良い意味での完璧主義ならば素晴らしいと思います。
しかし、自分を縛り付けるような悪しき完璧主義に陥ると、次第に文章が書けなくなってしまいます。
いきなり立派な文章を書かねばならないと思い込み過ぎることで、期待値を自分で引き上げてしまい、書けなくなるのです。
そこで、ペンが止まってしまった場合には、知らず知らずのうちに引き上げてしまっている自分への期待値を引き下げてみてはいかがでしょうか。
○悪い意味での完璧主義を捨てること
○「(良い意味で)初めからいきなり上手い文章など書けるわけはない」と謙虚な気持ちになること
○無理に背伸びをせずに、等身大の自然体な自分を受け入れること
○「今は上手く書けなくても、書き続けていくうちに次第に上手くなっていけばいいや」と長い目で捉えること
○人の目を気にし過ぎずに、良い意味で図太くあること
決して卑屈になるのではなく、むしろ、上がりすぎた期待値を引き下げてみることで、本来の自分の心の動きを取り戻すことができます。
そして、その心の動きを「人に伝えたい、文章に書いてみたい!」という気持ちが自然と復活してきます。
なお、「自分が書いた文章を人から馬鹿にされたらどうしよう....怒られたらどうしよう....。」などと他人の目を気にし過ぎるあまり、書けなくなってしまうこともあります。
大丈夫です。
人はそんなに自分のことを見てくれてはいません。笑
ブログやTwitterなどに自分の文章を投稿しても、最初のうちはほとんど誰も見てくれないことが多いです。
ちょっと悲しいですが。笑
誰も見てくれない期間のうちに、書き上げた文章を何回も推敲して再投稿することで、人から見られても大丈夫な文章に生まれ変わっていきます。
また、最初は下手な文章でも、一生懸命に自分の思いを伝えようと丁寧に書き続けていると、その姿勢を認めてくれる人が1人、また1人と増えていきます。
これは私自身がTwitterを1年以上毎日投稿し続けてみて、実感してきたことです。
最初は下手でも、誠実な姿勢で丁寧に書いた文章は、必ず人の心に伝わるものです。
ポイントは、100人の人全員に伝わる文章を書くのではなく、自分が最も伝えたい1人の人を具体的に思い浮かべて、その人に伝わるように丁寧に文章を書いていくことです。
そうすれば、不安な気持ちよりも、伝えたい気持ちの方が勝ってきて、文章を書き続けることができるようになります。
以上をまとめますと、知らず知らずのうちに高め過ぎてしまった自分への期待値を引き下げてみること、そして、自分が伝えたい1人の人に向けて、誠実かつ丁寧な姿勢で文章を書いてみることをお勧めします。


3-6.文章を書けるようになるメリットを思い浮かべてみる
書きたい気持ちがあるにもかかわらず、もしペンが止まってしまったら、文章力を向上させた場合の未来のメリットを思い浮かべてみるのもお勧めです。
高校受験や大学受験の時に勉強のやる気が失われてしまった場合の対処法としては、志望校に合格した後の未来を思い浮かべて見るのが有効だったりします。
それと同様に、文章力を身につけたらどのような明るい未来が待っているかを具体的に考えてみますと、またやる気が出てきて、ペンが進み始めたりします。
人間は、言葉を使って自分の周りの世界を認識し、他の人とコミュニケーションしていく生き物です。
また、コミュニケーションの重要な手段として、手紙やビジネス文書などで文章を交わし合うことが昔から行われています。
特に現代では、仕事でもプライベートでも、SNSやメール、LINE、chatなどの様々なツールを使い、文章によるコミュニケーションが頻繁に行われています。
どんな人であっても、文章を書くことからは逃げられない時代になっていると言えるでしょう。
そうしますと、文章力を高めておくことは、現代を生きる上でとても重要であり、かつ、有効であることが分かります。
人前で話すのがあまり得意な人でなくても、文章力を高めておくことで、仕事でもプライベートでも自分のことを理解してくれる人を増やしやすくなります。
そのため、自分の考えや理由をきちんと周りの人に伝えて良好なコミュニケーションを図っていくためには、日頃から少しずつ文章力を磨いていくことをお勧めします。
しかも、自分が書いた文章をブログやSNSなどに公開し続けますと、学校や職場といった普段お付き合いのある人たちとはまた別の人たちと交流が生まれることも多いです。
それによって、今自分がいる世界が全てではないのだと思うことができます。
仮に学校や職場の人たちと人間関係が上手くいっていない場合でも、文章を発信することで、外の世界に自分のことを理解してくれる人を増やすことができるのです。
つまり、ブログやSNSに公開した文章が一人歩きして、自分の代わりに自分自身のことを語り続けてくれるようになります。
そうすると、その文章を読んでくれた人のうちの何人かが、自分のことを理解してくれたりします。
中には共感して下さる方も現れたりします。
そこで、今、人間関係に悩んでいる人ほど、文章を書き続けて発信していくことで、外の世界に自分のことを理解してくれる人を増やしていきましょう。
さらには、文章の書き方は一度身につけてしまえば、その先ずっと活用し続けられるものです。
つまり、文章力とは資産性があるものと言えます。
確かに、文豪のような名文や美文を書けるようになるには修行し続けることが必要です。
しかし、少なくとも仕事やプライベートで相手に伝わる文章の書き方を身につけるのは難しくありません。
しかも、文章力というものは、しばらく使わなかったからといって忘れてしまうものではなく、一度身につけたら、その先ずっと自分のコミュニケーション生活のために役立ち続けてくれるものです。
他にも色々と文章力を向上させるメリットは考えられますが、長くなりましたので割愛させていただきます。
読者の皆様がそれぞれに文章力向上のメリットを思い浮かべてみていただければ幸いです。
今後、別の記事で文章力を向上させるメリットについて詳しく書いてみたいと思います。
以上より、もしペンが止まってしまった場合には、文章力を向上させるメリットを具体的に思い浮かべてみることをお勧めします。
書きたい気持ちが自然と復活してきますので、ぜひやってみてください。

4.「執筆」についてのまとめ〜やっぱり書きたい気持ちを大切にしよう〜
伝えたい気持ちが頭の中でモヤモヤしているにもかかわらず、文章を書けない状態がずっと続くのはもったいないです。
確かに、文章を書いて発信することで人から馬鹿にされたり、怒られたりしたらどうしようといった不安な気持ちが生まれるのも分かります。
しかし、不安な気持ちよりも、やっぱり、自分自身が書きたいと思った気持ちの方を大切にしてもらえたらと思います。
人間は、自分の気持ちや考えを言葉にして発信することで他者と交流が生まれ、この社会の中で生きている実感を得られる生き物だからです。
いわば、文章を書くことは、この世界に自分が生きていることの存在証明をすることだとも言えるでしょう。
最初は、自分だけが読むための純粋な日記から始めてみても良いでしょう。
また、Twitterなどの短い文章を書くことから始めるのもありだと思います。
とにかく最初は、文章を書くハードルをできるだけ低く設定して、自分の心が動いたことを少しずつ文章に書いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。
書きたい気持ち、伝えたい気持ち、日々の生活の中で心が動いたことなど、自分の気持ちを大切にして文章に書き続けることで、人生を充実させていくことができるようになるからです。
したがって、文章術のテクニックを学ぶのももちろん大事ですが、それ以上に、まずは自分の書きたい気持ちを大切にしてみてください。
書き続けることで少しずつ自分の心が整うようになり、きっとより良い人生を送れるようになると思います。
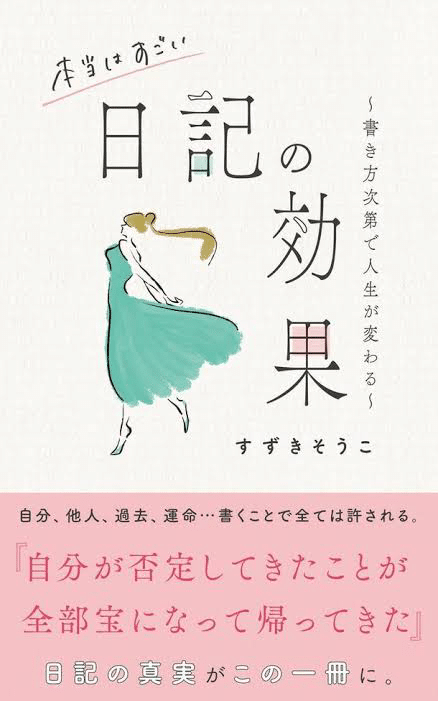
最後までお読みいただきまして、どうもありがとうございました。
今回は、書くモチベーションが続くための気持ちの整え方について、私の経験から得た気づきや学びをご紹介してみました。
この記事をお読みいただいて、少しでも文章を書くことが好きになってもらえたら嬉しいです。
これからも、「書きたい気持ちはあるのにどうやって書いたらいいのかが分からない」「書く習慣をどうやって身につけていったらいいのかが分からない」とお悩みの方のために、私の文章指導経験から得た気づきや学びをご提供していきたいと思います。
この試みに共感して下さる方は、これからも応援して頂けますととてもありがたいです。
それでは、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
戦略マスター頼朝
