
<第18回>30分から1時間で記事1本を書く文章作成術〜時間制限のメリット〜【文章の書き方入門講座】
今回は、「まとまった時間が取れないと、なかなかnote記事1本を書く気になれない…。」と悩んで、文章を書き始められない人向けの内容になります。
何を隠そう、私もそういった考えに陥ることがよくありました。笑
ただ、そんなふうに考えていると、いつまでたってもnoteを書くことをサボり続ける日々が続き、自分が嫌になってしまいがちです。
本来は文章を読むのも書くのも好きな自分であるはずなのに、これはとてももったいない状態だと思います。
そこで、逆転の発想を取り、あえて時間制限を設けてみたらいかがでしょうか?
「30分しか時間が取れないなら、30分で書ける内容だけを書いてアップするぞ!」
というふうに、先に時間制限と覚悟を決めてしまうのです。
そうすることで、
「30分しか時間を取らないでいいのなら、何とか時間を捻出できそう!」
と思うことができ、noteの執筆画面を開く気持ちのハードルを一気に下げることができます。
また、適度に締め切り効果が働きますので、ダラダラと文章を書くこともなく、目の前の記事執筆に集中して書いていくことができるようになります。
ちなみに、29分43秒で書いてみた記事がこちらです。↓
それでは、どのようにして30分から1時間以内に1本の記事を書いていけば良いのかについて、
1.テーマ決め
2.取材
3.構成
4.執筆
5.推敲
といった各プロセスごとに説明していきます。
(以下の内容は、800字から1500字程度の小論文を60分以内で書き上げなければならない試験を受ける受験生の方にも役に立つ内容です。)

1.テーマ決め〜好きなものや書きやすいものを最優先
そもそも30分から1時間以内という短い時間制限を設けていますから、テーマ決め自体であれこれと悩んでいる暇がもったいないです。
そこで、自分が一番書きやすそうな仕事や日常生活、趣味をテーマにするのが良いでしょう。
仕事のコツや、日常家事の知恵、お金の稼ぎ方、子育て、推し活についてなどなど、自分が日頃から携わっているものであれば、何かしら心が動くことがあるはずで、テーマも思い浮かんできやすいと思います。
要は、好きなことや強く関心を持っていることなど、その時に書いてみたいと自分の心が素直に思ったものをテーマにするのが良いでしょう。

2.取材〜自分の頭の中に取材
正式なレポートや論文を書く場合ならともかく、自分自身の日記の延長線上として書くような、エッセイのような記事を書く場合には、取材の対象は自分の頭の中になります。
つまり、自分で自分の頭の中に取材していくのです。
(ちなみに、試験会場で受ける小論文試験の場合なんかも、自分の頭の中に取材するしかないといった点では同様ですよね。)
書籍や動画、ネットや図書館の資料、あるいは取材対象者などを取材しに行く必要がありませんので、短い時間でも書く題材を集められます。
具体的なやり方としては、書くと決めたテーマに関して思い浮かんだことを2つか3つメモに書き出していきます。
手書きのメモも手っ取り早いですが、私のように散歩をしながらスマホの音声入力で文章を書いていくタイプの人であれば、スマホのメモ機能やnoteの下書き機能に思いついたことを箇条書きで書いていけば充分です。
また、思いついたことはどれも、テーマに関して自分の心が動いたものになりますので、「自分らしい」内容の文章を書くための題材としてもってこいです。
独自性ある文章かどうかは、事実をただ並べたり、まとめたりするのではなく、自分自身の体験から来る気づきや学びといった自分なりの解釈を、素直な形で文章に盛り込むことができているかによって決まるからです。
事実や情報を上手くまとめるのも大変な作業ではありますが、それは今やAIがやってくれる時代になっています。
したがって、独自性ある文章にするためには、やはり、自分自身しか体験していない事実から得た心の動きを題材にするのが良いでしょう。
具体的には、
事実(経験) →
その時の自分の心の動き→
なぜそう思ったのかの理由
をメモ書きに書いていくと、この後の構成作業がやりやすくなります。
なお、注意点としては、30分から1時間という短時間で書き上げなければならないので、書くべき題材は3つ以内に絞った方が良いと思います。
それ以上多くなりますと、短時間で書き上げることが難しくなり、再び、書き進められないという心理状態に陥ってしまいかねないからです。
題材を3つ以内に絞ることで、書くべき内容や分量に対する心理的なハードルを下げることができ、気軽に書いてみようという気持ちが復活してきます。

3.構成〜代表的な型に当てはめ、noteの下書き機能を活用
正式なレポートや論文を書く必要がある受講生の方の場合には、取材で集めてきた題材をカードに書き、そのカードを並べ替えしながら構成を練る方法を私は推奨しています。
しかし、この記事の冒頭でお伝えしましたように、そういった正式な内容の文章を書くわけではない場合には、自分の頭の中に取材して思いついた題材のメモを見て、「どういう順番で書いていけば、読者の方に伝わりやすいだろうか」を考えて、題材と題材を矢印でつないで、書くべき順番を決めていけばそれで充分です。
スマホやnoteの下書き機能を活用してメモ書きしているのであれば、コピー・アンド・ペースト機能を使って、書きたい順番に題材を並べ替えるだけでいいでしょう。
正式な内容の文章であれば、この構成作業もカード法を使ってじっくり考え抜く必要がありますが、そうでないフランクな内容の文章の場合には、この構成作業にもそれほど時間をかけなくて良いでしょう。
要は、自分が伝えたいことが誤解なく読み手に伝わるような題材の配列であれば充分だからです。
構成の内容としては、
①テーマ
②意見(結論)
③理由
④具体例
⑤まとめ
などが順序よく配列されていれば、意味が通る文章になります。
時間がない時は、意見(結論)と理由だけでも書いてあれば、自分が伝えたいことが読み手に伝わります。
なお、代表的な構成の型を知っておくだけでも、時間短縮になります。
どんな題材をどういう順番に並べて書いていけば読み手に伝わる構成になるのかについて、あれこれと悩まなくてすむからです。

4.執筆〜スマホの音声入力機能をフル活用
執筆段階からはより一層時間を短縮することができます。
テーマ決めと取材、構成までが文章を書く上で最も時間がかかるからです。
執筆作業ではスマホの音声入力機能をフル活用していきます。
20年以上前の音声入力ソフトでは、誤変換率が高く、また、音声を認識しない箇所があったりと、イライラさせられたり、自分の声にコンピューターが慣れるまではかえって時間がかかったりしたものでした。
しかし、現在のスマホは音声入力機能が発達しており、ほとんど誤変換がなく、歩きながら話したことでもきれいに文章に文字起こししてくれるので、大変便利です。
私もちょっとした文章でしたら、通勤や散歩の途中で、しかも歩きながら、音声入力機能を活用して文章を素早く書くことができています。
実際、ほぼ毎日X (旧Twitter)に4つから8つほどポストを投稿していますが、これは全て通勤の行き帰りに歩きながら、音声入力で文章を作成しています。
最近は良い文章のネタが思いついても3歩歩いたら忘れる自信がある私。
— 戦略マスター頼朝@小論文・面接指導のプロ講師/文章術でブランディング (@6VQGPJH3FHYoZn6) October 10, 2022
そんなわけでスマホのボイスメモやTwitterの音声入力機能は欠かせない。
便利な時代になったもんだ。
ただ、弊害として年々手書きの字が汚くなってきている。
頭脳というものは、使わない機能はどんどん退化させてしまうそうだ。
鉄は熱いうちに打て
— 戦略マスター頼朝@小論文・面接指導のプロ講師/文章術でブランディング (@6VQGPJH3FHYoZn6) March 13, 2023
良いと思う気づきや学びが思い浮かんでも、それが2つ同時とかだと数分後には忘れてしまうようになってきた。
やはり、おじさん化している。笑
だからスマホをできるだけすぐに手に取って、音声入力でTwitterの下書き機能を活用している。
それがそのままツイートになることも。
何か言いたいことを思いついた時に、好きにツイートしている私に年末年始などという死角は無い。笑
— 戦略マスター頼朝@小論文・面接指導のプロ講師/文章術でブランディング (@6VQGPJH3FHYoZn6) December 31, 2022
Twitterのこのお手軽さこそが、1日も休まずにコツコツとやり続けられる理由かもしれない。
あと、音声入力機能にも感謝しかない。笑
読んで下さる方が1人でもいる限り、休日も発信し続けたいと思う。
寝転がりながら
— 戦略マスター頼朝@小論文・面接指導のプロ講師/文章術でブランディング (@6VQGPJH3FHYoZn6) May 8, 2023
デスクワークタイプの仕事をしているせいか、しかも、歳をとってきたせいか、家に帰ると机に向かって何かをするということが億劫になってきた。
それでも文章は書きたい。
そんな時に便利なのが音声入力機能。
寝転がりながらでも書きたい文章をかける。
おじさんに優しい世界。笑
音声入力機能を発達させてくださった技術者の皆様には本当に感謝したいですね。
音声入力で誤変換される箇所も全くないわけではありませんが、ほんの少しですので、修正するのにもそれほど時間がかかりません。
この優れた音声入力機能を活用して、構成メモを見ながら素早く文章を書いていくと良いでしょう。

5.推敲、その他(装飾)〜最小限の時間でチェック
執筆作業を終えたら、一息ついた後で(そのくらいの時間の余裕はあると思います)、推敲作業に入ります。
まず、音声入力で誤変換された箇所や誤字・脱字などを修正していきます。
この推敲作業も慣れてくると、それほど時間がかかりません。
3000字程度の文章量であれば、3分から5分程度で作業を完了することができると思います。
また、読みにくい箇所や意味が伝わりにくい表現が見つかれば、そこは手入力で書き直しします。
スマホに向かってしゃべることに慣れていけば、構成メモを見ながら思い浮かんでくる言葉を文章にするのに慣れていきますので、だんだんと読みにくい箇所や伝わりにくい表現も減っていくことでしょう。
それ自体が時間短縮になっていきます。
最後に、時間が余れば、小見出しをつけたり、重要な部分を太文字に変えたり、写真画像を挿入したりといった装飾をつけて終了です。
これは必ずしもやらないといけないわけではなく、売れてるnoterさんの記事を拝見しても、装飾がほとんどなく、シンプルな見栄えになっていることも多いです。
そのため、装飾作業はあくまで「時間が余れば」やる程度で良いと思います。
大事なのは、「あれもこれもやらなければ!」と気負い込んでしまいますと、本来大切なはずの文章の執筆作業への心理的ハードルが上がってしまいますので、そうならないように気をつけることです。
そのための方策として、あえて自分から時間制限を設けるといったことをしていくわけです。
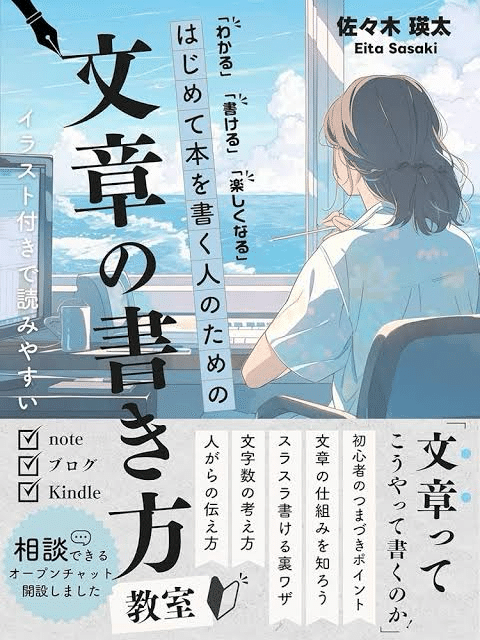
6.まとめ〜頼朝メソッドのポイント
以上の時間短縮のための文章術をまとめます。
◯最初から自分で執筆時間の制限を設ける。
◯制限時間内に書ける内容だけしか書かないといった覚悟を決める。
◯テーマはその時に自分の心が最も動いて、かつ、書きやすいものを選ぶ。
(自分にとってできるだけ身近な内容のものがお勧め)
◯自分の頭の中だけに取材し、テーマに関して書く内容(題材)を3つ以内に絞る。
◯代表的な構成のパターンを活用し、それに題材を当てはめていく。
◯執筆はスマホの音声入力をフル活用し、できるだけ短時間で書き上げる。
◯推敲は明らかな誤字・脱字の修正や読みにくい部分の手直しだけに留める。
◯装飾作業は「時間が余れば」やるくらいにする。

最後になりますが、仕事が立て込んでいたりすると、家に帰ってからもうひと踏ん張りしてnoteの記事を書こうという気にはなかなかなりませんよね。
私も夏期講習や冬期講習の時期は、生徒・親御様への対応や授業準備などに追われて、なかなかnoteを書く時間や気力・体力を維持することができない場合が多いです。
それでも、書きたい気持ちはあるのに、ずっと書けないでいるのはもったいないと思います。
そこで今回、「30分から1時間以内で書くための手軽な方法や考え方を身につけてみてはいかがでしょうか」とご提案させていただきました。
文章を書く行為は、自分の頭の中の整理だけにとどまらず、周りの人に自分という存在を理解してもらうのにも役に立つものです。
また、モヤモヤした気持ちや考えをデトックスする効果もあると思います。
そのため、休みの日だけでも30分から1時間以内の時間をとって、その時に自分が書きたい内容の文章を書いてみてはいかがでしょうか?
私もこれからコツコツと書き続けていければと思っています。
今回の内容が読者の方のお役に立てていたなら、とても嬉しいです。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。
またお会いできたら幸いです。
戦略マスター頼朝
