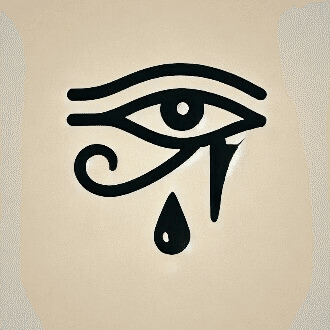📖言葉と物 魔界討魔伝
ミシェル・フーコーの『言葉と物』は、知識がどのように構築され、表象されるかを深く探究した作品です。1966年に発表されたこの重要な著作は、人間の理解を歴史を通じて支配してきた変遷する枠組みを考察しています。フーコーは、知識の基盤を再考するよう読者に促し、普遍的な真理の概念に挑戦します。そして、私たちの知的構築物がいかに流動的で偶然的なものであるかを明らかにします。
フーコーの主張の中心にあるのは、「エピステーメー」という概念です。これは、特定の時代において何が知りうるか、語りうるかを規定する根底の枠組みを指します。彼は綿密な分析を通じて、このエピステーメーがいかに進化してきたかを示します。ルネサンス期の類似性に基づく秩序から、啓蒙主義時代の分類への重視、そして現代の個別的主観性への焦点へと移り変わる中で、フーコーは言葉と物(言語と対象)が静的なものではなく、文化的・知的な力によって絶えず再構築されるものであることを明らかにします。
『言葉と物』が特に際立っているのは、学術的な議論を超え、人間の理解の本質について好奇心を持つ誰にでも響く普遍性です。思想の歴史的な変遷をたどる中で、フーコーは言語、知識、権力の間に存在する複雑な関係を明らかにし、私たちが世界を認識する方法が決して客観的ではないことを思い出させてくれます。
フーコーの作品は単なる批評にとどまりません。それは、新しい視点で世界を見るよう促す招待状でもあります。言葉と物の間の固定的な境界に挑みながら、彼は私たちの認識の前提を問い直し、人間の思考の複雑さを受け入れるようにと鼓舞してくれるのです。
言葉と物の全体の章立ては10章で、それがまた2~8節くらいで区切られている。
時系列で読むというよりは分類のほうが意味合いが強くて、最初から最後に向かって読もうとしても、最初から分からない言葉は出てくるし、分からない言葉は索引に戻って読み進めるので、別にどこから読んでもよい体裁になっている。
タイトル通り言葉と物についての本だが、言葉についてはいろいろ出てくるが、物については言葉が指示していたり、いなかったりするものについて書いて有ったり、それを過去の哲学者がどういったか、ということがあるが、特徴として同時代人(1950年代~60年代)の人はほとんど出てこないので、意識しすぎたのかなかったことにしたかったのか、という思いを込めて転生したらミシェルフーコーだったという体裁で読もうと考えたが、日によって楽しいことや興味は変わるので図解してもいいんじゃないかという気もしてきた。
が、そういう図解はネットにありそうだ。
やっぱりあった、それも結構たくさん。
「これが私の18世紀」というのが6章8の図に集約されている。
境界と動きと顛末が書かれていて、ヒッピアスのほうがまだエレガントというような変なしくみの機械のようなものが書かれている。
実際は6-7の論旨を追えば図の説明になっている。図中の文・博・富はそれぞれ文学、博物学・富を意味していて。6-7の論旨だけ取り出すと「価値と言葉」みたいな論旨になるだろう。
人は金で動くわけだが、欲望するには言葉がいる、というしくみ。
そして言葉なんだからそこには分類があって機能があるだろうという話。19世紀になってそれがヴァーチャル(仮想)なものになった。
いいなと思ったら応援しよう!