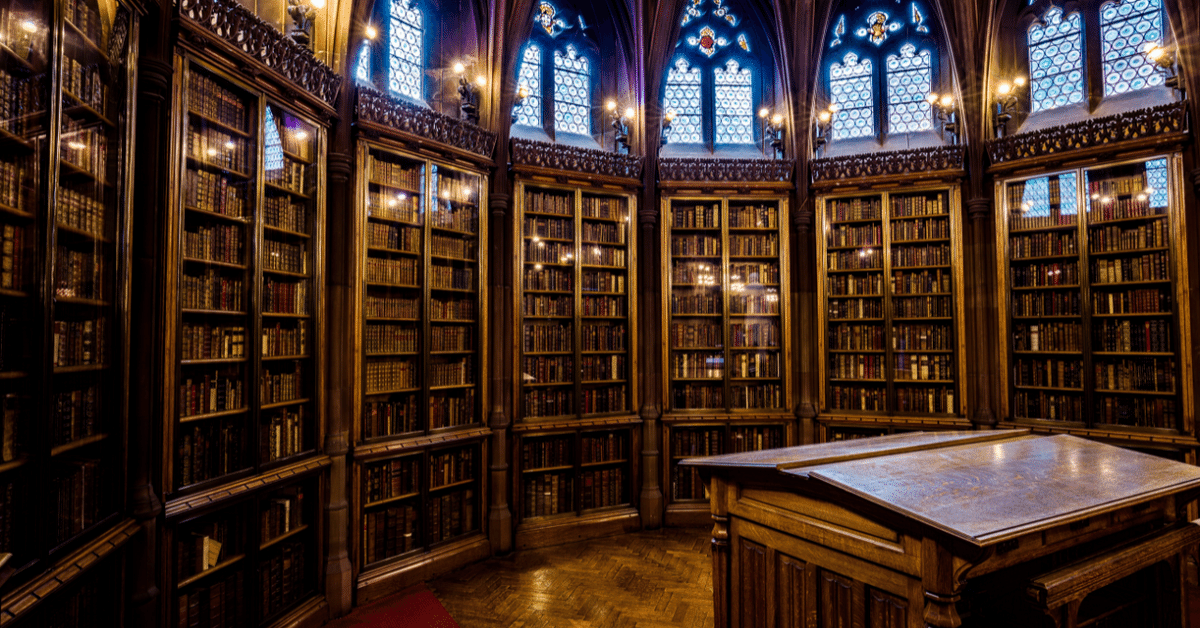
図書館制度・経営論レポート
図書館制度・経営論の合格レポートです。
レポートの丸写しは評価の対象外や不正行為とみなされる恐れがありますので、参考程度にとどめてください。
個人情報や詳しい調査内容などは伏せております。
◆設題
「図書館経営の基本思考」における「未来思考」の5点について簡潔明瞭に説明した後、その「未来思考」を受けて、今後の専門職としての司書のあるべき姿を論じるとともに、それに伴う図書館運営のあり方を、貴方自身の考え方を含め論じて下さい。
◇解答
1.はじめに
「図書館経営の基本思考」における「未来思考」の5点について簡潔に述べ,さらに今後の専門職としての司書のあるべき姿を論じ,図書館運営のあり方について意見を述べる。
2.「図書館運営の基本思考」における「未来思考」について
図書館政策にも,質の高い未来を予想できる情報をどれだけ収集できるかが大変重要である。こうした情報は大きく5つに区分することができる。
⑴文教政策情報
国や地方自治体等の教育行政に関する情報のことである。大学図書館では,平成3年に制定された,新「大学設置基準」によって,その後の図書館政策は大きく影響した。
⑵社会変化情報
図書館は社会変化に合わせて発展し,変化を察知し対応していかなけらばならない。社会変化には4つの要因を上げることができる。
①情報環境の変化
図書館は,変化に対応できる施設・設備を用意し,柔軟な運営システムや組織の構築が必要である。特に,情報機器や周辺環境は将来図を想定したうえで整備し,高度情報化社会に対応するために,情報処理管理者的な資質を持った専門職員を採用するなど,人的資源にも配慮が必要である。
②高齢化社会
今後さらに加速することが予想されているため,図書館の施設・設備をもっと高齢者向けにし,利用者の変化に合わせて図書館も変化しなければならない。そのためには図書館政策の計画において,人口動向情報の重要さを認識する必要がある。
③高度学歴社会
国民の多くが高学歴になり,高度学歴化社会が生まれている。こうした人々の利用にも対応できるよう,図書館員にはレファレンス力と専門性が強く求められるようになる。
④少子化社会
子供の少子化により,公共図書館では,児童・婦人中心の利用から,成人・高齢者中心に展開されることも予想される。この変化により,児童室の設計や運営など様々なところに影響を及ぼすことが考えられる。
⑶図書館界の変化情報
様々な図書館団体で決議された,方針・方策は十分考慮しなければならず,関係団体の動向情報は,図書館政策に不可欠である。また,図書館経営にとっては図書館そのものが,経営の合理化等により,自主的・主体的に変化するなど,各図書館事情の動向に関する情報も大変重要である。さらに,図書館は,私立の公共図書館を除けば,全て親機関があるため,親機関の方針は直接図書館経営に影響を及ぼしてしまう。
⑷出版界・情報産業界の変化情報
資料形態に電子資料が加わったことで,出版形態が変化し,図書館政策に大きく影響している。また,インターネットによる情報調査が拡大したことによって,図書館本来の使命が認識されつつある。
⑸マーケティング変化情報
利用者が求めている社会的ニーズとマーケティング情報を把握し,自館調査を行うなど,図書館の健全な発展に寄与する必要がある。
3.今後の専門職としての司書のあるべき姿
図書館での司書は,単に司書資格があるから,専門職と見ることはできず,司書資格を生かしてさらに,豊かなキャリアを持たなければならない。そのためには今後さらに,司書の育成として計画的な研修制度が必要である。その中でも特に,未来予測できる研修と,利用者の自立性を高める利用教育のための研修が必要である。研修を行うことで,司書としての専門的業務が磨かれ,利用者へ十分な指導が行えるようになり,利用者が自立して図書館を活用できるようになる。研修を通して,図書館学の専門知識と情報学知識及び主題知識が有機的に結びついた時,司書本来の力が発揮することができるだろう。このレベルのサービスを実現してこそ,専門職の確立が自他ともに成される。司書の能力が高まることは即ち,図書館としての付加価値が高まるということである。
4.図書館運営のあり方について
図書館運営を安定的に行い,高いサービスを確保するためには,図書館理念を明確にし,そこから導き出される目的実現のために努力しなければならない。その目的実現を具体的に果たすものの一つとして図書館計画がある。先見性を持った計画案を作成し,年次計画に反映させる必要がある。また,自己点検・評価義務が法的に課せられ,図書館が自ら活動の評価を行うための試みが成されている。
〇〇図書館で調査・インタビューを行ったところ,外部評価として,〇〇市役所全窓口で窓口サービスに関するアンケート調査が期間を設けて実施され,その後,利用者からの意見や要望などをまとめた評価と改善策などが,〇〇市HP内で公表されていた。また,〇〇図書館内に設置している「意見・要望カード」には,利用者から日々様々な意見や要望が寄せられている。こういった利用者などの評価により,図書館の運営はより良いものに改善されていると言えるため,利用者の声も重要視されるべきである。
5.おわりに
近年では情報化や少子高齢化などの,社会の変化が図書館の運営にも大きく影響している。図書館の3要素である,空間・人・資料の充実や,レファレンスサービスなどの基本的サービスの他,今後はさらに社会の変化も取り入れ,未来を見据えた図書館運営が必要不可欠である。
文字数 2095文字
文献
<編著>手嶋 孝典『図書館制度・経営論(第2版)』学文社 P64-65,P78-81,P84-89
文部科学省 『これからの図書館像』(最終閲覧日〇〇〇〇/〇/〇)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/giron/05080301/001/002htm
文部科学省『図書館の設置及び運営上の望ましい基準の見直しについて(報告書)』(最終閲覧日〇〇〇〇/〇/〇)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/019/houkoku/1330338.htm(PDF:1170KB)
〇〇市HP『窓口サービス向上の取り組み』(閲覧日〇〇〇〇/〇/〇)
~感想~
講評では、学習・理解はよくできており、論述内容も理解できます。参考文献から文中に効果的な引用文を用いり、引用文献としての活用があるとさらによき!とのことでした。
このレポートはかなりテキストを読み込み、参考にして作成した記憶があります。こちらも字数内におさめるのはなかなか難しかったです。
