
【1人の男と2人の女】与謝野鉄幹・晶子・山川登美子を巡る物語1/3(山川登美子篇)
山川登美子篇→与謝野晶子篇→鉄幹篇の順でお読み頂くと、内容が分かりやすくなっております。
----------------------------------------------------------------
1902年10月。
京都から乗った汽車の窓外は、郷里、小浜が近づくにつれ小雨模様となった。10月でも北陸の雨は小さな針のように冷たく意地が悪い。
その冷気は、車内にまで及んでいた。
山川登美子は、隣りに座る夫、山川駐七郎の寝顔をまじまじと眺めた。僅かに、青白いのは、結核菌に侵されているせいか、寒さのせいかは分からない。
登美子は自分の襟巻を外すと、駐七郎の首にかけた。
車窓のうそ寒い風景を眺め、思えば遠くへ来たものだと思う。実際は、故郷へ戻るのだから、遠くではないはずなのだが。にも関わらず、そう思うのは、やはりここが自分のいるべき場所だと飲み込めぬせいか。
隣りにいるのがあの人ではなく、駐七郎であることに、まだこだわっているせいなのか。
無理もない。
わずか1年前まで夢にまで見た東京で暮らしていたのだ。
あの人のそばで歌を作り、あの人の作る雑誌「明星」へ投稿していた。あの人に歌を褒められること、あの人に歌を叱られること、あの人に声かけてもらうこと、あの人に触れられること、その全てが幸せで、その声に、指に、身体中の細胞が泡立った。そんな感覚、生まれて初めてだった。
与謝野鉄幹…わたしに、初めての幸せを沢山くれた人。

駐七郎が身じろぎをし、登美子は我に返った。
何を考えている。
今や、わたしは夫のある身。
あの人だって今はもう、隣りにあの女がいる。
そこまで思いが巡ると、気持ちは整理したはずなのに、悔しさに歯軋りしたくなる思いが突き上げた。
それをどうにか堪える。
「何だこれは?」
目を覚ました駐七郎が首に巻かれた女物の襟巻を不審そうにつまんでいる。
「申し訳ありません。差し出がましいことを。でも、寒さがお身体に障ったらいけませんので」
駐七郎はしばらく黙って襟巻を摘んでいたが、やがて手を離した。
「今、どの辺りだ?」
「さて…若狭あたりかと…」
「そうか…着いたら起こしてくれ」
「はい」
駐七郎は再び、襟巻に触れると言った。
「降りたら、外すぞ。肺病といえ、女物の襟巻をして家の門はくぐれん。気でも触れたかと思われる」
「勿論でございます」
「だがな…それまでは借りる」
「はい…」
駐七郎は、そのまま再び眠りに落ちていくかに見えたが、ふっと薄目を開けて登美子を見た。
「お前は…寒くないか?」
「大丈夫でございます。どうか、お気になさらずに」
「…悪いな」
駐七郎はしばらく登美子を見ていたが、呟くように言うと、目を閉じた。
軽い駐七郎の寝息を聞きながら、登美子は思った。
与謝野鉄幹がどうした。
そしてあの女、かつては姉と慕ったあの女、与謝野晶子がどうした。
今は、この人だけ。
一筋の矢の如く、この人を慕い、尽くしてみせる。
そこに、何の不純も後悔も妥協もあるものか。
嘘と思うなら、今この皮膚を切り、その下に流れる血の濁りなき赤を見るがいい。

----------------------------------------------------------------
山川登美子が夫と列車で郷里へ向かった秋より2年前。
1900年、4月。
21歳の山川登美子は大阪のミッションスクール、梅花女学校(現在の梅花女子大)に研究生として通いながら、半年前に創刊された雑誌「明星」へ短歌を投稿していた。
それが「明星」の主宰者、与謝野鉄幹の目に留まり、社友となり、そこで1つ年上の鳳晶子(のちの与謝野晶子)とも出会った。


小浜(福井県)の裕福な士族の子女として、大切に、しかし裏を返せば「籠の中の鳥」のように育てられてきた登美子にとって、鉄幹は歌で自分を新しい世界へ引っ張り上げてくれる、眩しい存在だった。その眩しさが、憧れが、恋心に変わるのは時間の問題だった。
そして、自由奔放に、自分の心に正直に強く生きる晶子もまた、登美子にとっては憧れであり、甘えられる姉の様な存在だった。
晶子もまた、鉄幹に恋していると知るまでは。
その年の秋、3人は京都、栗田山へ紅葉狩りに出た。

散々歩いて結局その夜は、栗田山麓の永観寺に宿を取った。

しかし通された部屋は15畳はあろうという大部屋で、3人では広過ぎた。真ん中にポツンと置かれた掘り炬燵で暖を取った。それでも寒くて、登美子は晶子にぎゅっとくっついた。
鉄幹には、流石に恥ずかしくてくっつけなかった。
「とみちゃん、大丈夫?」
晶子は登美子の腕をさすりながら、気遣ってくれた。
「何もこんな大部屋でなくともな」
鉄幹が苦笑する。
頭上の小さな電球に照らされた鉄幹の顔は赤黒く、どこか怖かった。
「この灯りを消しましたら、真っ暗で何が起きてもわかりませんね。声さえ押し殺せば」
澄ました顔で晶子が言い、登美子はドキッとした。
「何なら、とみちゃん試してみたら?今夜」
「な、何を…」
「おい、あんまり登美子をからかうな。登美子はな、汚れを知らぬ白百合※1なんじゃ」
※鉄幹は日頃から登美子を「白百合」に喩えていた
「あら、白百合とて、ただ可憐に咲くだけならいずれ枯れるだけよ、そんな純潔に意味はないわ」
「……」
「やめんか。登美子が困ってるだろ。それより登美子、お前、あの話はどうなった?」
「あの話って?」
2人がこちらを見る。
登美子は、父より故郷で見合いをするように命じられていることを、鉄幹に話していた。
引き留めて欲しいなど思わなかった。
ただ、口惜しくて、寂しくて、言わずにいられなかっただけだ。
「小浜の父から、縁組を勧められているんです」
「えっ!?相手は誰よ?」
何も聞いていなかった晶子が驚く。
「山川の本家に養子で入った方です」
「なるほどな。登美子の家は士族。お父上からしたら一族の血を絶やすわけにはいかんのだろう」
すると突然、晶子が立ち上がった。
「何それ。で、とみちゃんはそのまま郷里に帰って結婚するわけ?」
「多分…そうなると思います。父には逆らえませんから」
「そう、じゃあその人の顔、見たことあるの?声は?匂いは?どんな風にお箸を持ち、どんなふうに筆を持ち、どんな字を書き、どんなふうに…どんなふうに…あなたの髪を撫でてくれるの?ねぇそれを全部、ちゃんと知ってのこと?」
顔や声は知っている。
話したこともある。
けれど、詳しいことは知らない。
手も、まだ繋いだことがない。
けれど、仕方ないではないか。
わたしだって、悔しいし、怖いし、寂しいのだ。
けれど晶子にはわからない。
あなたは自由で強いから。
沈黙を破ったのは、またも晶子だった。
「良いわ、結婚するというならそれでいいわ。とみちゃんの自由よ。でもね、あなた、歌も捨てる気!?」
カチンときた。
何もわかってない。
何がわかるというのか。
「わたしの自由!?わたしにそんなものない!わたしだって、東京で鉄幹先生のそばでもっと歌を作ってたかった!あなたにはわからない、わたしの悔しさなんてわかるわけない!」
「わからないわよ!大切なものがあるならね、戦っても、傷ついても守りなさいよ、この意気地なし」
パンっと、音が響いた。
手の痺れで、自分が晶子の頬を張ったのだと、気づいた。
謝らなくては、そう思うのだが、言葉が出てこなかった。
「ふん。そんな目つきもできるんじゃない、お嬢さん。そっちの方がずっといいわ。ねぇ、先生」
鉄幹が苦笑する。
「2人とも、喧嘩はもうその辺でいいだろ。土産屋で買った団子でも食おう」
団子を食べながら、なおも3人で話した。
鉄幹が登美子に言った。
「登美子、歌は続けなさい。やめるにはもったいない。お前の歌には品がある」
「はい、時間を見つけて必ず」
「それと、矛盾するようだが、嫁ぐからには家を守り、夫を大切にしなさい。それがお前の歌をさらに研ぎ澄ませる」
「……はい。辛抱します」
「わたしも、楽しみにしてるわよ」
そこで晶子が登美子の方へ体を乗り出してきた。
「それで、どんな人なのよ。会ったことくらいはあるんでしょう?相手の人」
「えぇ」
「かっこいいの?」
「優しい方だとは思いますが…体はあまり強くないようです」
「ふーん。何してる人なの?」
「外務省で、最近までメルボルンへ行っていたとか…詳しいことはわかりません」
「ボンボンとお嬢さんか。お似合いじゃない」
「そんな言い方、やめてください」
「あら、怒ったの?冗談よ。もう決めたんでしょ?だったらこのくらい、笑って流しなさい」
「……そうですね」
結局その夜は、夜通し話した。
晶子にはやんや言われたが、でも、楽しくて、この時間が愛しくて、眠ることなどできなかった。
晶子も鉄幹も、同じ気持ちだったら嬉しい、そう思った。
朝、寺を出る時、晶子に言われた。
冗談めかしていたが、目は笑っていなかった。
「登美子、いいのね?あなたが結婚するってことは、先生とのことは、「そういうこと」で、いいのね?」
その問いに、登美子は一遍の歌で返した。
「それとなく紅き花みな友にゆづりそむきて泣きて忘れ草つむ」
譲りがたい想いも人も、晶子、みなあなたに譲る。
それでいい、そう、覚悟を決めた歌だった。
朝日が、眩しくて、目を閉じたら瞼の裏が真っ赤に染まった。
その赤を、未だに、夢に見る。
赤くて、暖かくて、振り返れば鉄幹と晶子が……
----------------------------------------------------------------ゴォー!っと汽車が蒸気を吐き出し減速する音で、目が覚めた。
慌てて見ると、窓外は既に暗かった。
「起こせとは頼んだが、終点で起こすとは、お前は車掌か?」
自分まで寝てしまったことを詫びる登美子に、駐七郎はそんな皮肉を言っただけで、笑って歩き出した。
「仕方あるまい。今日は敦賀で泊まろう」
「はい。……あのっ」
登美子は駆け寄って、駐七郎の首から襟巻を取ろうとした。これ以上、恥をかかせてはならない。
「あぁこれな。こんな夜更けだ。誰も見ていまい。もう少し、借りてもいいか?」
「あ、はい」
「悪いな。首筋に、お前の匂いがするというのも悪くない」
そう言って笑った。
「はい…」
登美子は駐七郎の隣りに並ぶと、そっとその手を掴んだ。
寒くなど、なかった。
わたしはもうこの人の匂いも声も、どんなふうに笑うかも、どんなふうにわたしを抱きしめるかも知っている。
ひなびた宿で質素な夕飯を済ませ、登美子は駐七郎にお茶を淹れた。
部屋にはもう、こたつが出ていた。
「お前も少し休みなさい」
「はい」
駐七郎と向かい合うようにこたつに入ると、冷え切ったつま先がじーんとした。
「結婚してまだ1年というのに、こんなことになってしまってすまんな」
「いいえ。今はしっかり休んでご病気を治す時です。わたしにできることなら、何でもやりますから」
駐七郎は少し俯いていた。
「時にお前、私と籍を入れる前は東京にいたんだったな?」
「あ、はい。母校で研究生をしていました」
駐七郎は頷くと言った。
「専攻は英語だったか?」
「はい。駐七郎さんも語学は堪能ですよね。外国で働かれていたのですから」
「それほどでもないさ。登美子、私が死んだらな、お前はもう一度勉強するといい。英語でもいいし、他のものでもいい。とにかく、女1人、生きていける術を身につけることだ」
「そんな…そんなこと仰らないでください」
「私は真面目だ。こんな身体になってしまい、家長の責すら果たせていないが、それでも私なりにお前の幸せを考えている」
「……今はまだ、先のことは考えられません。少しでも長く、そばにいさせてください」
こたつ布団を、ぎゅっと掴んだ。
部屋は暖かいのに、体の震えが止まらなかった。
いつの間に、駐七郎が隣りにきていた。
その着物の袖に、登美子はしがみついた。
風に、ガラス窓がカタカタ鳴っていた。
----------------------------------------------------------------ふーっと長い息を駐七郎は吐いた。
痩けた頬に生気は既にない。
「今日は気分が良い」
実家の離れで、駐七郎は静養していた。
登美子は毎日看病をした。
「何か、話してくれないか?」
「話?」
「あぁお前とこうして穏やかに話せることも、もうないだろう」
「……」
「何でもいい。聞かせてくれ」
「私ごときに、駐七郎さんを満足させられるようなお話などございません」
「何でもいいんだ。河岸に渡る時は、お前の声を聞いていたい」
「そんなことを仰られるなら、余計何も話せません」
登美子は立ち上がった。
涙がこぼれるのを、堪えられそうになかった。
着物の裾を、掴まれた。
強い力だった。
振り向いて、駐七郎を見た。
「頼む」
登美子は座り直すと、天井を見上げた。
何を話せばいいのか。
ふと、言葉が出た。
「私、歌をやっていたんです、東京で」
「ほぉ」
「「明星」という短歌の雑誌があって、そこの社友になって…その雑誌に掲載されたこともあるんです」
「……」
「歌の仲間と、旅行に行ったりもしました」
「…楽しかったか?」
「はい」
「戻りたいか?」
「え?」
今度は駐七郎が天井を見上げていた。
「私は奪ってしまったのかもしれないな。お前から、大切な時間や仲間を」
「そんなことはありません」
「私もな、初めはこの結婚は半ば義務のようなものだった」
「……」
「山川の家を守るのも養子の勤めだ。肺を病んだ私に、他に良い縁談のあるはずもないしな」
「……」
「だが、お前と過ごしたこの1年で気持ちは変わった」
「……」
「結核を宣告されてから、覚悟は決めていたはずだが、お前と会ってから、この世を去り難くなっている」
「……」
「しかし、定めは定め。変えられるものでもない。むしろ、1年で良かったのかもしれない。私が死んだら、お前は帰れ。お前が元いた場所へ」
「……」
「いいな?」
「……」
「返事は、どうした?」
駐七郎が手を伸ばす。
その手を、握りしめた。
「嫌です」
一言、振り絞るのがやっとだった。
駐七郎は何も言わず、もう片方の手で、何度も登美子の髪を撫でた。その細く硬い、節くれだった感触を、忘れまいと願った。
----------------------------------------------------------------
1904年、駐七郎と死別した登美子は、再び上京した。
教師を目指し、日本女子大学英文科予備科に入学すると、再び「明星」へ短歌を投稿し始めた。
晶子と鉄幹にも再会した。
その時2人はすでに夫婦であり、晶子はセンセーショナルな処女歌集「みだれ髪」で世に知られる存在となっていた。
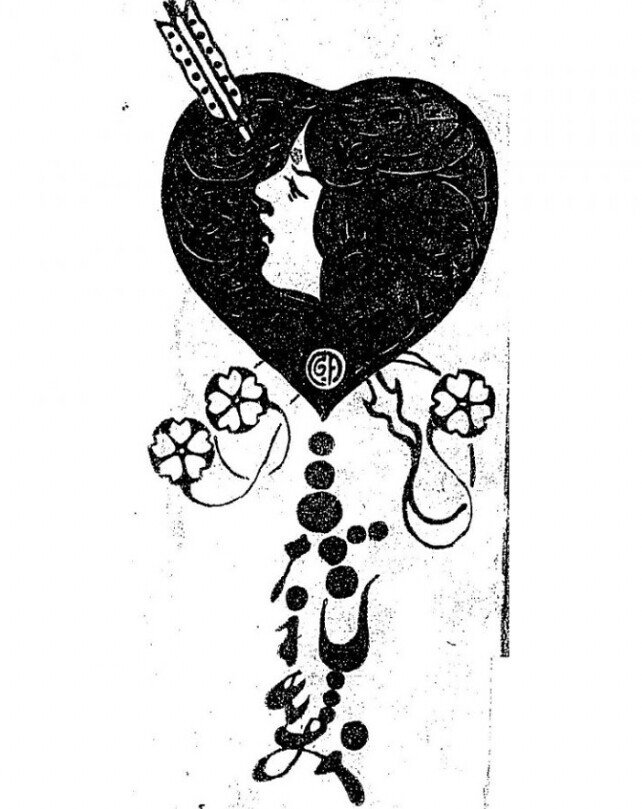
しかし、溝を開けられたとは思わなかった。
鉄幹に会えば、封じたはずの恋心がまたうずいた。
それを恥ずかしいとも思わなかった。
短い時間ではあったが、夫である駐七郎を支え、慕い、最後まで尽くした。その矜持が、逆に鉄幹への恋心を肯定していた。
何を恥じよう。
わたしは親の言いつけを守り、やるべきことはやったのだ、精一杯。
夫のことは忘れまい。
けれどこれは、わたしの恋だ。
「歌やいのち涙やいのち 力あるいたみを胸は秘めて悶えぬ」
「明星」で、登美子は鉄幹への想いを正面から歌った。
この恋が、叶うものかどうか、それは問題ではなかった。
歌うこと、恋すること、もう一度自分自身を生きること、25歳で未亡人となった登美子には、それが必要だった。
可愛い「妹」であり、歌人仲間であり、恋のライバルでもある登美子の「明星」復活に、晶子も歌で返した。
「みだれ髪を京の島田にかへし朝 ふしてゐませの君ゆりおこす」
妻としての余裕か。
鉄幹と共に暮らす朝の一場面を生々しく歌ったものだった。
けれど、登美子は怯まなかった。
面白い、そう思った。
歌とはこうでなくては。
これからは、私も私の胸の内を高らかに歌おう。
1人の女性として。
鉄幹への叶わぬ想いはあれど、登美子の心は晴れやかだった。
また、歌に戻ってこれた。
また、晶子と鉄幹と共に歌を作っていける。
そんな折、鉄幹から歌集出版の提案があった。
晶子と、同じく「明星」の歌人である増田雅子との3人の連名で、ということだった。
連名でも自分の歌が本になるなら嬉しかった。
「髪ながき 少女とうまれ しろ百合に 額は伏せつつ 君をこそ思へ」
鉄幹がつけてくれた愛称「白百合」と題した歌を登美子はこの歌集『恋衣』に131首載せた。

この恋が枯れるか、わたしの歌が尽きるか、賭ける想いだった。この恋心の純心を、正義を、世に問いたかった。
しかし、時代の風は逆に吹いていた。
歌集に収めららた晶子の反戦の詩「君死にたまふことなかれ」が体制を批判しているとして、『恋衣』が出版停止に追い込まれたのだ。
登美子の歌に問題があったわけではない。
しかし、煽りを受け、登美子自身も大学を停学になった。
登美子は憤った。
自分の停学など構わぬ。
だが、『恋衣』の出版停止は納得できなかった。
こんなことがまかり通っていいのか。
国家がその大きな手のひらで、個人の想いを捻り潰していいのか。
人は国家に生きるにあらず。
日々、泣き笑い、慈しみ、生きている。
その土の上にしか、個人の想いはない。
それを歌えないなら、なんの為の歌か。
誰が為の歌か。
「おとなしく 母の膝よりならひ得し 心ながらの歌といらへむ」
幼き頃、母から教わった、心からの歌を歌って何が悪いのか。
登美子は、初めて上京した時の「恋に恋するだけの少女」ではもはやなかった。
結婚し、夫の看病を経て、死別を経験し、そして再び歌の世界へ戻ってきた。
そのことが歌人として、1人の女性として、登美子の視野を広く深くしていた。
屈するものか。
歌っていこう。
女性らしく、しなやかに、朗らかに、凛として。間違いは間違いだと、好きなものは好きだと、嫌なものは嫌だと。
そしていつかもう一度、歌集を出そう。
わたし個人の歌集でなくともいい。
いや、歌の仲間と一緒の方がむしろいい。
もう一度出すのだ。
短歌復権を賭けて。
しかし、1905年11月。
『恋衣』発刊から10ヶ月後、登美子を病が襲う。
夫と同じ、結核だった。
駐七郎が、呼んでいるのか。
自由にしてくれるのでなかったのか。
もう少し、歌わせて欲しい。
いつかはあなたのそばへ還るから。
口惜しかった。
何故今なのか。
今からなのに。
ここからもう一度、新しい歌を歌おうと思っていたのに。
----------------------------------------------------------------失意のうちに、登美子は東京を経った。
京都にある姉の嫁ぎ先で療養することになったのだ。
鉄幹と晶子が、別れの挨拶に来てくれようとしたが断った。2人にまで病をうつしてはならない。
以前、同じように東京を離れる時、わたしは晶子に鉄幹を譲った。
その時は悔しさと未練があった。
けれど今は短歌の未来を晶子と鉄幹へ託す想いだった。
この2人を失ってはならない。
悔しさは今回だってある。
けれどそれ以上に祈る想いだった。
必ず見せてくれる。
この2人なら、新しい時代の新しい短歌を。
「その願いは、受け取れないわね。あなたもやるのよ。わたしたちと共に」
晶子の手紙に、涙が溢れた。
溢れた涙が落ちて落ちて、手紙が破けた。
破けた手紙を両手で握りしめたまま、登美子は泣き続けた。
温かくて、ありがたくて、悔しくて、どうにもならなかった。
----------------------------------------------------------------京都で療養を始めて1年。
姉夫婦はよくしてくれるが、肩身が狭いことには変わりない。
布団に入って仰向けで、天井を見上げてふーっと長く息を吐いた。いつか、夫も同じようにしていたのを思い出して、おかしくなった。
あの時の、夫の気持ちが今ならわかる。
あの時は、看病する身だったので、さぞ辛かろうと思っていたが、いざ自分がその身になってみれば意外にも、さにあらず。澄んでいて、気持ちが良い。
体はしんどいが、頭は、気持ちは、澄み渡っていく。
今ならかつてない歌が書ける。
そう思えた。
まだ歌える。
なら歌おう。
今のわたしにしか歌えぬ歌を。
上手い下手は問題ではない。
病床で、登美子は今までとは全く異なる歌を作り始める。
「おつとせい 氷に眠るさいはひを 我も今知る おもしろきかな」
ふと、氷上に穏やかに眠るまるまる太ったオットセイの姿が浮かんだのだ。凍てつく氷の上も悪くない。この熱に火照る身体を冷やしてもくれよう。
また、時に孤独に苛まれ、こんな歌も詠んだ。
「わが柩 まもる人なく行く野辺の さびしさ見えつ 霞たなびく」
結核で逝くわたしを、送ってくれる人は少ないだろう。
寂しいが、それでいい。
死んでまで人の情を求めんとは強欲というもの。
けれど私を灰にする火は、煙は、願わくば、空高く昇って欲しい。そしてそこから見渡せたらいい。この世界の三千里を。そこから見える景色はさぞや爽快だろう。
鉄幹にも、晶子にも、見せてやりたくなるほどに。
もしかして、その時、隣りには駐七郎がいるかもしれない。それもいい………
少し、眠っていた。
肩を強く揺すられ起こされた。
姉の顔がすぐそばにあった。
実家の父が危篤だという。
姉はこれからすぐ発つらしい。
胸が騒いだ。
姉には「あなたはここにいなさい」と言われたが、親の一大事に安穏と寝ていていいものか。
父に、縁談を勧められなければ、ずっと東京で歌を作っていただろう。
意に沿わぬ結婚を強制する父を恨んだこともある。
運命を人のせいにしていいのなら、父のせいだ。
父が言うから結婚し、結婚した相手が結核で、そのせいで自分まで結核になった。何もかも、元はと言えば父のせいなのだ。
けれど、そうは思わない。
今ここにいるわたしは全て、わたし自身が決めたこと。
誰かのせいにしてはもったいない。
この人生は、わたしがわたしとして、味わい尽くすのだ。
むしろ父には恩しかない。
わたしを大切に育ててくれ、女だからと低く見ず、高い教育を受けさせ、東京にも出してくれた。
その大きな翼のような愛情に、最期、少しでも応えなくて良いのか。良いわけがない。
動かぬ身体がもどかしい。
動かぬ……?
いや、そうと決まったわけではない。
無理をすれば京都から小浜まで行けぬことはない。
まだ動く。
今ならまだ動く。
命惜しさに、無理をせず、生き長らえようとするから、動かぬと思うのだ。
ここで死なんと決めれば動かぬものではない。
布団で死のうが、小浜への道中で倒れようが同じこと。
それなら、向かおう、父の元へ。
行かなくてはならない、娘として。
伝えなくてはならない、一言。
育ててもらった、慈しんでもらった、案じてもらったことへの感謝を。
ここで伝えずして、何が歌人か。
そう思ったら底知れぬ力が出た。
マグマのように、身体の奥底から突き上がってきた。
まだこんな力が、わたしに残っていたか。
でも同時に感じていた。
これは、命を燃やして出てくる力だ。
本当は、最後の最後まで取っておくべき力だろう。
この火が消えたなら、もうわたしに病と戦う力は残っていまい。
それでもいい。
行こう。
力を使うべきは、今だ。
姉夫婦には黙って夜半過ぎ、家を出た。
11月の夜風は身に染みた。
襟巻を、ぎゅっと巻きつけたら、ふと、懐かしい誰かが守ってくれている気がした。
なんとか、父の最期には間に合った。
けれど、思うような言葉は出なかった。
感謝の気持ちをうまく言えた気もしない。
父が逝った夜から、高熱が出て、意識を失った。
目覚めた時には、父は既に骨になっていた。
ポカンと、胸の奥に穴が空いた。
「山うづめ雪ぞ降りくるかがり火を 百千(ももち)執らせて御墓まもらむ」
出来るなら、父の墓のそばにいたかった。
けれどそれもこの身では叶わない。
結局、そのまま実家の離れで療養を続けることとなった。

窓から、小さな中庭が見えた。
椿が雪を被ったまま咲いていた。
あの花が落ちるまで生きられるかどうか。
最近は、意識が混濁することも多くなった。
目覚めているのか、夢の中なのか。
もう、どちらでも構わなかった。
ぼんやりする意識の中で、自分の来し方を振り返った。
29年か。
よく生きた方だな。
負け惜しみでなく、そう思った。
恋もした。
結婚もした。
歌も作った。
上出来だと思った。
なのに、悔しかった。
寂しかった。
やれるべきはやったと思うのに、何もやれてない気がした。
もう力の入らぬ腕で、畳を叩いた。
力の限り叩いているのに、パタパタと、乾いた小さな音しか出なかった。
笑えてきた。
悔しさに、畳を叩くことすら許されぬ身か。
力を抜いた。
もういい、そう思った。
よくやった。
誰が認めてくれずともいい。
よくやったのだ、わたしは。
これ以上、どうやれというのだ。
これ以上、どう生きろというのだ。
何か、歌おうと思った。
言葉は何も、浮かんでこなかった。
ただ、うっすらと誰かの顔が浮かんできた。
男の人だ。
父か、駐七郎か、鉄幹か…
必死に目を凝らした。
誰かが、遠くから呼んでいる気がした。
けれどその声は、判然としなかった。
----------------------------------------------------------------
1909年4月。
雪深い北陸の地に桜の咲く頃、山川登美子は旅立った。
享年、29歳。
登美子の才能と夭折を惜しんで、鉄幹は惜別の歌を贈っている。
「君なきか 若狭の登美子しら玉の あたら君さえ砕けはつるか」
この歌に、空の上から彼女はなんと返したか。
案外、微笑むだけで、何も返さなかったような気もする。(終)
----------------------------------------------------------------
あとがき
引き続き、与謝野晶子、鉄幹の物語をお楽しみください。この記事と連動した、インタビュー形式の記事となっています。
これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。
