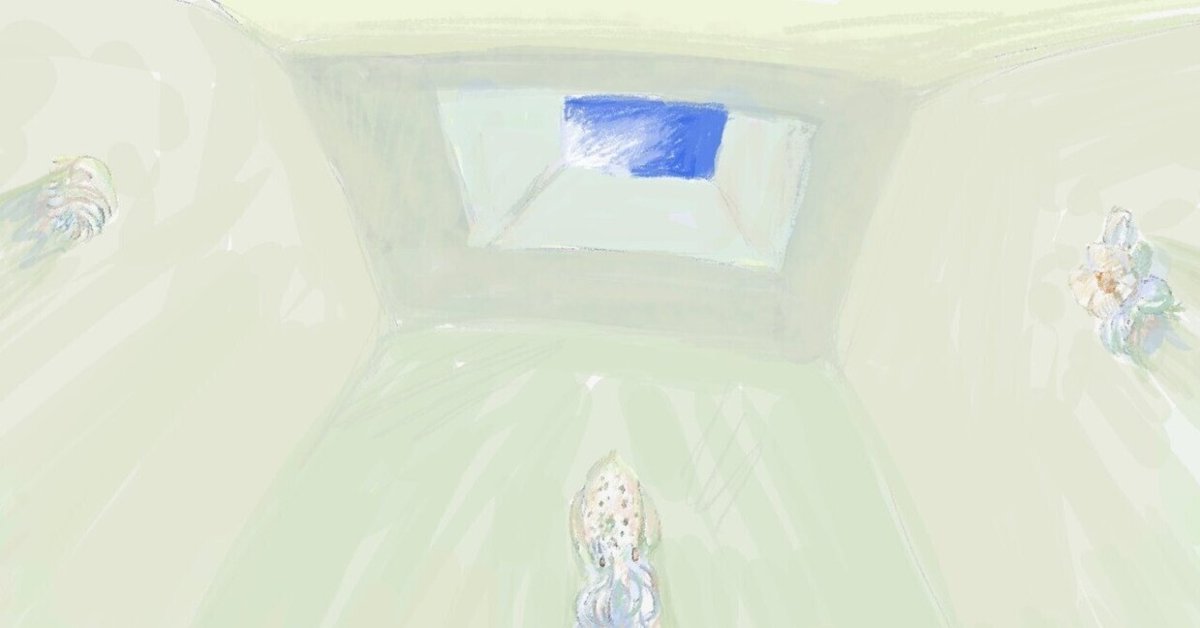
ほしのこえと出会った日
中学生のころ、父がある短編アニメーションを僕に教えてくれた。それはほんとうに短いアニメーションで、その頃の僕にはそれじたい新鮮だった。近未来の日本で、深宇宙探査のために国連所属のパイロットとなった少女、少女とメールを交わす少年の物語は、アスファルトの湿る中学生の日常から高濃度のSFへと遷移し、しかしなお映画の真ん中には、亜空間ワープをするたびに離れていく、小さな液晶画面と心もとないアンテナと電波とがかすかにつなぎとめる二人の心の距離が、そのどうしようもない切なさが、2年4か月15日の時間相対距離が、やや拙くも精神の生きた、なによりも新しい表現によって、たしかに鋭くつらぬかれていた。
アニメーションの題は、「ほしのこえ The voices of a distant star」。
僕がSF小説を読んだり、SF映画を観たりすることのきっかけは、たぶんこの作品だったようにおもう。
僕はこの作品に恋をした。一目ぼれだった。見たことのない緑色の光を、呟くような独り言の、漂うように連なる言葉、言葉、言葉。静かな孤独と、すがすがしいほどの痛々しさと淋しさが、映像の一片一片からくまなく僕を照らし、染みこんでいった。はじめて、アニメーションの監督というものを、その個人を、個人として意識した。
「秒速5センチメートル」と「雲のむこう、約束の場所」を観て、「星を追う子ども」を観た。「言の葉の庭」を父と劇場で観た。監督を調べて、過去の作品を漁った。「彼女と彼女の猫」が、本当の意味の、ファンタジーでない日常を、白と黒とグレーと言葉によって、電車の音、重い金属のドアの閉まる音、お湯の沸く音によって描くのを観た。ファルコム時代の「イース」オープニング映像、「BITTER SWEET FOOLS」、「Wind -a breath of heart-」、「はるのあしおと」。おそろしく美しく、おそろしく日常的で、おそろしく現実感があり、おそろしく魅力的な映像たちが、一人の作家によって生み出されていたのを知った。もちろん作品によって方向性や完成度の差こそあれ、彼は明らかに革新的な映像作家であることに違いなかった。
彼は、2000年代初期の混沌とした時代感、そして生命のある映像と孤独の言葉とを、ひとつのアニメーション芸術として融合し、まさに昇華させたのだ……
新海作品に出逢ってからいくばくかの年月が経ち、僕は大学2年か3年ほどになっていた。僕は編集室にこもって、自分のシナリオで撮ったSF映画を編集していた。編集は泊りこみで、様々な人が出入りをしていた。外界と隔絶されながらも、いくらかの情報と噂が耳に入ってくる。
そのときは、ちょうど一本の新作長編アニメーションが公開されたばかりだった。代わる代わる訪れは去る人々は、口をそろえて話す。
「君の名はみた?」
それは、あの新海誠監督の、待望の新作だった。
待ちわびていたはずのものだった。
しかし、なにかがおかしかった。
様子がちがっていた。
街頭に、書店に、テレビコマーシャルに、Youtubeに、インターネットのすべてに、新作アニメーションの絵が、セリフが、音楽が、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、くりかえし、繰り返されていた。
アップ・テンポのいやに爽やかな歌が、過剰なほど演出された美麗な映像と行儀のいいキャラクターデザインと作画が、宣伝用の短い映像群が、耳を塞いでも目をつむっても、目に、耳に流れ込んできた。新海誠。新海誠。新海誠。新海誠。新海誠。新海誠。新海誠。君の名は。君の名は。君の名は。君の名は。君の名は。君の名は。新海誠。新海誠。新海誠。君の名は。君の名は。君の名は。君の名は。新海誠。新海誠。君の名は。君の名は。君の名は。
頭がおかしくなりそうだった。
離婚し、別居していた父と連絡をとって、映画を観に出かけた。
食事をした。
チケットを二枚とり、指定のシアター番号を目指した。
音の反響の少ないはずの劇場内へ入った。
座席を見つけて座った。
予告編はまだ始まっていなかったが、僕はもう劇場を出たかった。
満席だった。
隣に座った小学生が喚いている。家族連れとカップルが、高校生の群れがひしめきあっている。ざわつき。会話。ポップコーン。コカ・コーラ。群衆。人ごみ、人いきれ、満員御礼。
すべては完全に壊滅していた。
映画ははじまった。隕石が落ちてくる。うつくしい映像。青い映像。「おれここユーチューブでみた!」映像。映像。「ピリリリリリリリリ」。「あ、やばい。」座席が揺れる。映像。「ほらここ、このあと知ってる!」映像。映像。映像。
すべての終末だったようにおもう。
叫び喚き興奮する小学生を注意し、3分後に再び喚きだした彼の口を手で覆い、静かにと指をたてながら、僕は絶望していた。完全にではなく。小学生を鎮め、背後の着信音を耐え、ポップコーンを貪る音を無視し、ひたすらに耐えた。
映画はやがて終了した。父と劇場を出、食事をし、別れた。
僕は絶望していた。完全に絶望していた。希望はなかった。喚く小学生もポップコーンも、もはや忘れていた。それは作品ではなかった。それは商品だった。それはポップコーンで、またコカ・コーラだった。スマートフォンの着信音だった。女子高生の胸を揉んで喚く小学生だった。
僕には認識することが難しかった。これは誰のアニメーションだったろうか。このアニメーションをつくった人は、過去に何をつくったのだったか。僕は何に恋をしたのだったか。何が僕をSFに連れ出したのだったか。頭がおかしくなったかもしれなかった。
この商品について、僕は話すべきことをもたない。どのような意匠も、世界観も、設定も、メッセージも、物語も、映像も、言葉も、すべて無意味だった。僕には無価値だった。心が死んでいた。なにも生きていなかった。生きているものを見いだせなかった。二度と、観たくないと思った。嫌いだった。
監督はその後、「天気の子」を公開した。それはポップコーンの味がした。ハンバーガーの味がした。
「すずめの戸締まり」が公開された。観なかった。
彼はどこへ行ったのだろう。別人かもしれない。あるいは、名義を貸しているのかもしれない。
彼はなにを思い、あれらの商品をつくることにしたのだろう。なにかしらの意図、思惑があるのかもしれない。お金を稼ぎたかったのかもしれない。アニメーションの仕事の機会をつくって、公共事業をしたかったのかもしれない。わからないが、すくなくとも、あれらの商品をつくるのなら、彼でなくてもよかっただろうと思う。綺麗なそれらしい映像、それらしい演出術とセリフ回し、名義、初期設定だけ貸し出して、あとは商人たちに任せればいいのだ。
いや、あるいはそうだったのかもしれない。
愛しいほどの切なさと孤独、それが彼の作家性だった。
ヴェラシーラは、いま、どこを飛んでいるのだろう。
彼はもう、戻らないだろう。
