
エベルの地とヨクタンの地~ヘブル人の故郷を探る④~
前回⇒ペレグとヨクタンのつづき。
さて、今回はヘブル人の始祖エベルの二人の息子、ペレグとヨクタンの子孫が暮らしていた土地を探しに行く。
さっそく、行ってみよう♪
ヨクタン人の居住地
まずは、ヨクタン人の居住地から見ていこう。
ヨクタンは、アルモダテ、シェレフ、ハツァルマベテ、エラフ、ハドラム、ウザル、ディクラ、オバル、アビマエル、シェバ、オフィル、ハビラ、ヨバブを生んだ。これらはみな、ヨクタンの子孫であった。
彼らの定住地はメシャからセファルに及ぶ東の高原地帯であった。
(創世記10章26~30節)
創世記を書いたのはモーセと言われている。
モーセはヨルダン川を渡らなかったが、その手前には行っている。
出エジプト後に40年間放浪したイスラエル人は、現在のイスラエルの南を回って東に出て、ヨルダン川を渡ってカナンの地に侵入している。
だから、上の節に書かれている東の高原地帯というのは、イスラエルから見て東の高原地帯とほぼ同じことになる。
色別標高地図を見てみよう。

カナン入りしたあとのイスラエル人の居住地と、その東の高原地帯をを〇で囲んでみる。

「メシャからセファルに及ぶ……」のメシャとセファルの位置はわかっていない。だが、高原地帯というだけでもだいたいの見当はつく。
イスラエル人から見た東の高原地帯とは、緑〇に囲まれた一帯である。
非常にざっくりだが、ヨクタン人はこのあたりのどこかに広がって住んでいた。
さらなる論拠とその説明は、話が飛んで長くなるので、ここでは省かせてもらう。
拙書『エデンの園の本当の場所』に一部詳述している。
ヘブル人の居住地
つぎは、ヘブル人の居住地を探していこう。
前回で解説したとおり、ヘブル人の始祖はエベルである。
では、エベルの土地とはどこであったのか。
モーセ五書のひとつ、『民数記』にはこのような記述がある。
「諸々の船がキティムの岸から来て、アシュルを苦しめ、エベルを苦しめる。しかし、彼はとこしえに滅びに至る。」
(民数記24章24節)
これはユーフラテス河畔のペトルにいた預言者バラムの預言である。
モアブの王バラクは、預言者であるバラムにイスラエルの民を呪うよう依頼したのだが、神が呪わないものを呪うことはできないとして、結局バラムはイスラエルを祝福した。
上の節はバラムが帰途につく前に、周辺諸国に対して語った預言の最後の部分である。
キティムというのは古代キプロスのことであるという。
しかし、エレミア書の2章10節には「キティムの島々」と言う表現があるので、キティムの領域にはキプロス島以外の別の島々も含まれていたようだ。
いずれにせよ、地中海の島々である。
地中海から来た船が悩ますのはアシュルとエベルである。
これはどういうことだろうか?
地図で見ると事態が飲み込みやすくなる。

これは地中海からメソポタミアへの軍事侵攻である。
もし、地中海からメソポタミアに軍隊を送ろうとするならば、キプロスに拠点を置き、港湾都市であるウガリットから上陸して、通商路を通ってユーフラテスに至るというのは、かなり合理的な侵入経路かと思われる。
ウガリットより南方から上陸すると、海とユーフラテスとのあいだに横たわる荒野を行軍する距離が長くなり、南へ行けば行くほど非効率になる。
狙いがメソポタミアの中心部ならば、ウガリット近辺から上陸するのが最善・最短である。
そして、ウガリットとアシュルのあいだにある土地。
ここがエベルではないだろうか?

この土地には紀元前の3千年期から存在する都市エブラがある。
エブラ遺跡(テル・エル・マルディーフ)で発掘された粘土板からは、のちのイスラエル人に見られる人名とかなり似た名前が見つかっている。
都市エブラ。
エベルEberとエブラEblaの名前に関係があるかどうかは不明だ。
現在、本やwikipediaに書かれている名前の由来はすべて推測である。本当のところはまだわかっていない。
ただ、聖書の記述を調べると、どうしても都市国家エブラの領域がエベルの地と重なってしまうのだ。
しかも、エブラの支配領域は、ヨクタン人の居住地とそう離れてはいない。
もし、紀元前3千年期の都市エブラの支配領域がエベルの地であるとするならば、ヨクタン人との位置関係はだいたい下のようになる。
(※紀元前3千年期とは、B.C.2XXX年代のことである。)

ヨクタンの土地のほうが広いが、このあたりには大きな町があった形跡はなく、古代から一貫して過疎地であった。
一方、エベルの土地はユーフラテスと地中海のあいだの主要交易路に位置しており、人と物の往来が多く、より豊かであった。
もとも住んでいた土地を二つに分けたというより、ヨクタンのグループがエベルの土地から出て行った可能性の方が高そうだ。
「アシュルとエベルを悩ましたもの」の正体
では、『民数記』で預言された「キティムの岸から来てアシュルとエベルを苦しめるもの」とは何だったのか?
「ああ、神が定められたのなら、だれが生きのびられよう。
諸々の船がキティムの岸から来て、アシュルを苦しめ、エベルを苦しめる。しかし、彼はとこしえに滅びに至る。」
(民数記24章24節)
この時のバラムの預言が示唆する地中海からの侵略の候補はいくつか挙げられる。
エジプトのトトメス3世によるシリア遠征。
ヒッタイトによるミタンニへの遠征。
「海の民」の襲来。
基本、陸路で北上するエジプト軍だが、領土が地中海に面しているため船で乗りつけることも可能だ。
トトメス3世の遠征ではエブラも征服されている。しかしユーフラテス川を渡ったとはいえ、アシュル地域のメソポタミア諸都市を破壊したという記録はない。
民数記24章の翻訳で「エベルとアシュルを苦しめ」の苦しめるは完全に苦しめるというような強い調子のため、破壊のかぎりをつくすレベルでないと当てはまらない。
なので、エジプトではない。
ではヒッタイトは?
ウガリットはヒッタイトの覇権のもとにあり、真偽は不明だがキプロス(アラシヤ)もヒッタイトの覇権のもとにあったかのような文書も残されている。だから、ヒッタイトはキプロスからウガリット経由で軍隊を上陸させることは可能だ。
シュッピルリウマ1世のミタンニ遠征時にヒッタイト軍はエブラよりも南のカトナを滅ぼしている。
しかし、アッシリアに関してはむしろ同盟してミタンニを攻撃させており、このときにヒッタイト軍がアッシリアを苦しめるということはなかった。
なので、ヒッタイトも違う。
となると、残るは「海の民」である。
海の民はウガリットを滅ぼした。そして、ユーフラテス河畔のエマルも滅ぼした。
両都市は破壊されたあと、再興することはなかった。
エマルはウガリットとアッシリアの中間に位置している。

ウガリットは滅ぼされたが、より南の港湾都市シドンやティルスは無事であった。
シドンとティルスも豊かな港湾都市だが、そこが襲撃の対象になっていないということは、海の民の目的は、キプロス⇒ウガリット⇒メソポタミアという海からアッシリアへの最短ルートを取る計画的な軍事行動であったということだ。
あるいは、シドンとティルスが海の民と通じていた可能性はある。
しかし、海の民の狙いが単なる略奪だとは思えない。
彼らが来襲したタイミングで、ヒッタイトは滅び、アッシリアは衰退し、エジプトとギリシアは戦い、勝利している。
沿岸を荒らす海賊レベルの話ではない。
海の民のしたことは征服活動である。
ヒッタイトが海の民に滅ぼされたという確たる証拠はない。むしろ、北方の敵に攻められたとする説のほうが主流となっている。だが、タイミング的にも海の民の関与がないとは思えない。
彼らはアッシリアへ最短距離で乗り込んだように、ヒッタイトへも最短距離で進軍したはずだ。
北のカシュカの勢力は、ヒッタイトの混乱に乗じて乗り込んだだけではないだろうか?ヒッタイトの軍が南方で海の民と交戦中に背後をついただけではないだろうか。
ウガリット最後の王アンムラピがアラシヤの王に宛てた悲鳴のような文章には、ウガリットの軍隊がヒッタイトの土地にあり、軍船はアナトリア南西部のルッカにあるとある。
つまり、海の民はアナトリア南西部から上陸して、先にヒッタイトを攻撃していた。救援要請を受けたウガリットは自軍をアナトリアに送っており、そのあいだに海の民の別動隊に攻め込まれてしまった。
ウガリットとエマルは滅び、アッシリアは混乱に陥ったためにこの時期の記録はほとんど残っておらず、何が起きたのか今となってははっきりとは分からない。
わかっているのは。ウガリットからエマルに至るエベルの地が蹂躙されたことと、突如アッシリアが衰退したこと。
それから、存在したはずの攻撃者が侵略した土地を支配することなく、忽然と姿を消していること。
この状態はバラムの預言と合致する。
預言では、船で乗り付けた何者かは滅びに至ることになっていた。
同じ時期、アッシリアより南のバビロニアは無事であった。同じく、エベルの地より南の、イスラエル人が居住するカナンの地も無事であった。
おかげで、聖書にはその混乱の記載がなく、紀元前1200年のカタストロフに関する文書の手掛かりは非常に乏しくなっている。
「海の民」とはいったい何者であったのだろうか?
「海の民」に関しては、当ブログではリビアの王をトップとする諸国連合軍であると認識している。その解説は『実在したアトランティスシリーズ』をお読みいただきたい。
アッシリアは海の民軍に蹂躙されたものの、迎え撃って敵を殲滅させ、滅亡を免れたのだろうか?
もしそうなら、戦勝記念碑や、王の功績として書き残されているものが残されていてもよさそうだ。しかし、今のところ、そういったものは発見されていないものと思われる。
海の民ミステリーはまだ終わらない。
***
ペレグとヨクタンの居住地を解説するだけのつもりが、大きく脱線してしまった。
しかし、聖書を歴史書として味わうには脱線も必要である。
次回は、エベルの子孫であるアブラハムたちが、エベルの地ではなくアラムの地にいた理由を追っていく。
つづく。
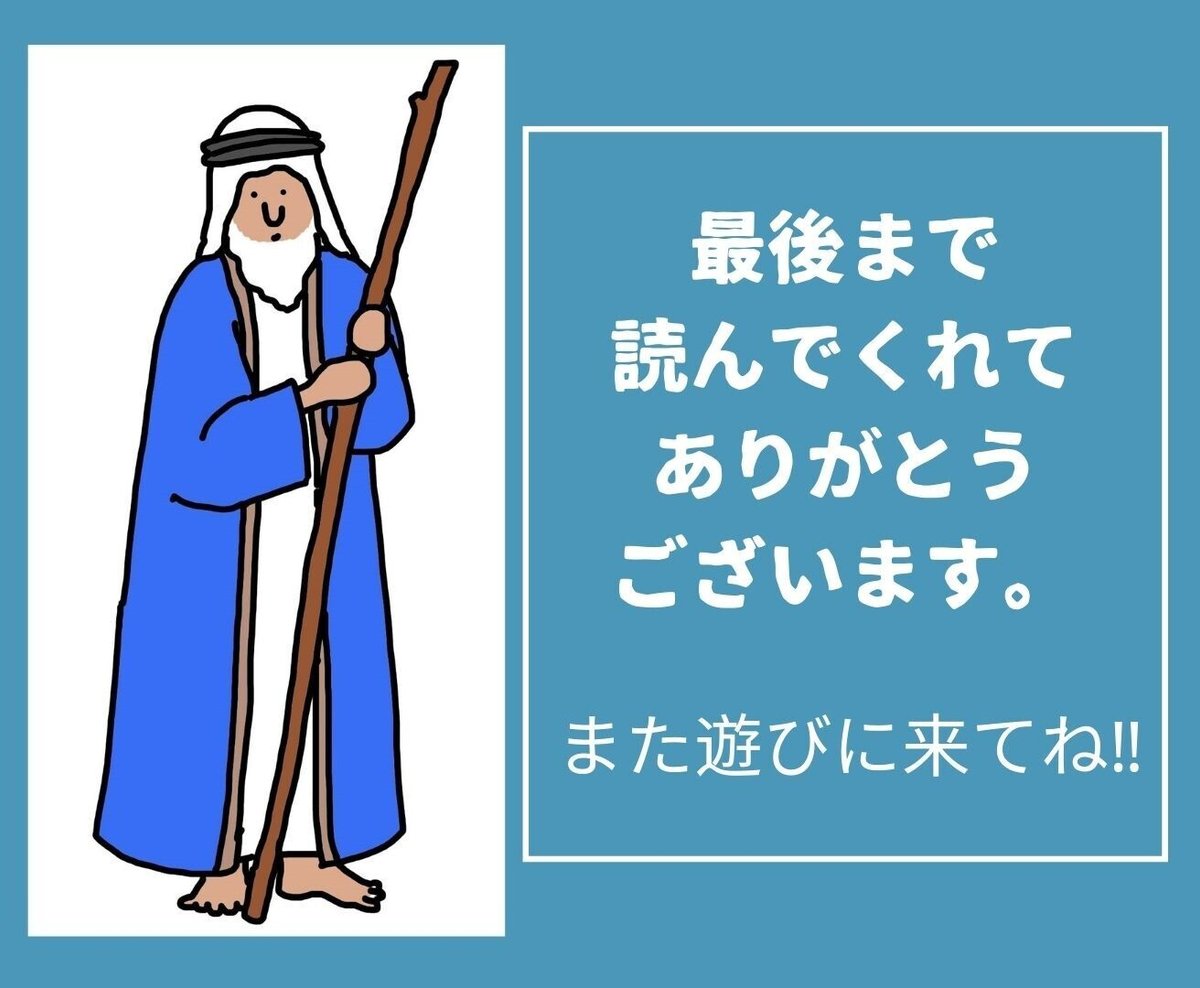
いいなと思ったら応援しよう!

