
一番好きなゲームを語る #2 ラブムー 「パックランド」
まえがき
本記事はゲーム・映画・アニメなどの、エンタメを愛する者が集うコミュニティ「game game」による動画「一番好きなゲームを語る」を鼎談形式で書きおこしたものです。
なお、発言内容の一部に正確ではない情報も含まれていますが、会話のニュアンスを写し取るため、そのまま掲載しています。明らかな間違いには適宜注意書きを添えていますので、あらかじめご了承のうえご覧ください。
「一番好きなゲームを語る」とは…
参加者のひとりが一番好きなゲームをただ語る、という企画。
今回は文筆/詩作/翻訳/ゲームの記事執筆などを手がけるラブムーさんが、自身にとって特別なゲーム『パックランド』を語ります。

canavis:
「一番好きなゲームを語る」2回目で、ラブムーさんの『パックランド』ってことで、今日は聞き手を私、canavisとよごえむさんで、ラブムーさんを迎えて『パックランド』を語っていただこうと思います。よろしくお願いします。今回の司会進行役のcanavisです。
まず軽く自己紹介をしたあと、改めてラブムーさんのプロフィールを深くやってこうかなと思うんですけど。
よごえむ:
よごえむ(林與五右衛門)です。ゲームライターとしてGame*Sparkやインサイドなどで執筆活動の他、ゲッコーパレードという集団で演劇などの活動をしています。
ラブムー:
ラブムーです。ゲームとポップカルチャーを愛しております。文筆や翻訳をしていて、今はゲーム翻訳とゲーム記事を書いたりするのをメインでやってます。よろしくお願いします。
canavis:
で、ちょっと深く聞いていこうかなと思うんですけど。まずラブムーさんって、出身地ってどこなんですか?
ラブムー:
出身地!?そこから?(笑)いや、全然いいんですけど。出身地ね。僕、東京です。
ちょっと東京の中心地からはちょっと外れたというか、別の文化があるようなところなんですけど、多摩地区というところで。
canavis:
はい。
ラブムー:
うん、立川とか府中とか国立とかか、その辺りですね。
canavis:
なるほど。
ラブムー:
出身地はなんかやっぱりゲームに(関係しますか)?
canavis:
そうですね。ラブムーさんのブログで実は知ってたんですけど、改めてどういった形でゲームと出会ってたのか聞きたくて。『パックランド』以前にゲームとどうやって出会ってたのかなと思って。
ラブムー:
はい。『パックランド』以前だと、自分は電子ゲーム、それは任天堂のゲーム&ウオッチなんですけど。そういうんじゃなくて。もっとなんか、パチモンっていうか(笑)、よくわからないメーカーが、そのゲーム&ウオッチに追随しようとして出してた、ちょっとインディー感のある電子ゲームをよく遊んでたんですよね。
それが多分ゲーム体験の最初だとは思うんですけど。だからビデオゲームとは言えないのかな。で、その後にファミコンとか『パックランド』とかとの出会いがあったっていう感じですかね。
canavis:
わかんない人もいるかもしれないけど、LSIゲーム(電子ゲーム)っていう。ビデオゲームとかとはまた違った表現の仕方で、なんて言うんでしょうね。
ラブムー:
携帯ゲームに近い形をしてるんだけど、もっと薄型で。ゲーム&ウオッチもだけど、時計とゲームを合体したみたいな。

よごえむ:
先にキャラクターパターンとかがもうすでに書き込まれていて、画面の中に。それを表示させることによって、今のビデオゲームみたいなような自由度はないけどある程度決まったパターンの中でゲームができるっていう感じのやつですよね。
ラブムー:
よごえむさんとcanavisさんはその手のゲームはやりました?
canavis:
ゲーム&ウオッチじゃないんですけど、自分の子供の頃にたまごっち前にテトリスのキーチェーンのゲームが流行った時期があって、もうすでにゲームボーイもポケモンもあったんですけど、なぜかみんなそれを買ってたんです。キーチェーンっていうのが可愛いからっていうのもあると思うんですけど。その流れを受けて、たまごっちもあってって形で。
いわゆるセガの出してるゲームギアとか、任天堂のゲームボーイとは違った形の携帯ゲームというか。LSIゲーム的な文化っていうのは自分の時代はまだ親しみがあったんです。
ラブムー:
なるほど、ハマってたんですか?
よごえむ:
多分、canavisさんと近いというか。キーチェーンテトリスとかもあったし、ゲーム屋さんに売ってるのじゃなくて、お土産屋さんとかホームセンターとか行くと、おもちゃコーナーみたいなところでLSIゲームが売ってて。ミニ四駆のパチモノのLSIゲームみたいなやつとか。『爆走グランプリ』っていうLSIゲームとか。あと、釣りのLSIゲームとかありましたね。
ラブムー:
『川のぬし釣り』みたいな?
よごえむ:
『ぬし釣り』じゃないんですけど、釣り竿みたいな形をした、リールを巻く動作が入ってるLSIゲームとかありましたね。
canavis:
LSIゲームってゲームセンターにおけるエレメカに近い…エレメカって、『ワニワニパニック』とか『UFOキャッチャー』とかだと思うんですけど。なんかあの関係にちょっと近いなって。ビデオゲーム以前の原始的な「ゲームに近い遊び」っていうとあれですけど。LSIゲームってゲーム&ウォッチの『ボール』とかわかりやすいんですけど、お手玉をゲームにして。
ラブムー:
ありましたね。あれとかデザイン、すごいアートっていうか、今見ても可愛いですよね。
canavis:
可愛いですよね。だけどなんかちょっと難しいですけど、ビデオゲーム的な発想じゃないかなって感じがしてて。
ラブムー:
じゃない。でも、あの感じが自分はすごい好きだったんですよね。あと、『オクトパス』とか。絶妙な虚無感っていうか、あの形態でしか出せない味がありましたよね。
あと『モンスターパニック』っていう電子ゲームがあったんですけど、それはそれほど面白くなかったんですけど(笑)、よく覚えてます。
canavis:
ラブムーさんはLSIゲームが原初的なゲーム体験だったんですね。
ラブムー:
そうなんですよ。それをなんか物置き部屋でやり続けるっていうのが、自分の原初的なゲーム体験だと思うんだけど。
canavis:
で、その後ファミコン、というか家庭用ゲーム機かPCかゲームセンターかってあるんですけど。どの?
ラブムー:
僕ね、実はゲームセンターなんですよね。ファミコンはまだそこまで興味がなかったのと、あと高かったし。買ってもらえる人って結構少なかったんですよね。自分も買ってなくて、代わりにゲームセンターに行ってアーケードゲームを色々見てて。アーケードゲームの衝撃が大きかったかな。で、1番その衝撃が大きかったのが今日紹介する『パックランド』っていうゲームなんですけど。
canavis:
ゲームセンターって近所の子どもが入れる感じみたいな?
ラブムー:
近所のおにぎり屋さんがなんか副業でゲームセンターもやってるっていう。
canavis:
おにぎり屋さん?おにぎり屋さんの副業がゲームセンターっていいですね。
よごえむ:
駄菓子屋とかじゃなくておにぎり屋さんなんですね。
ラブムー:
でも、駄菓子屋とおもちゃ屋さんもゲームセンターみたいなことをやってた。2階とか使って。だけどそれはおもちゃ屋さんの片隅にあるゲームコーナーであって、ゲームセンターじゃない。おにぎり屋さんの方はガチなゲームセンターだった。
よごえむ:
「ゲームセンター」を経営してたんですね。
ラブムー:
うん。多分おにぎりより収入はそっちの方が多かったと思うんだけど。元はおにぎり屋さんだった。
canavis:
で、『パックランド』にそこで出会った。
ラブムー:
そう。そこで他のゲームにも色々出会ってるし、多分その前にもいろんなゲームを見てるんだけど、そこで見たってはっきりと今、記憶として、原体験として残ってるのが『パックランド』しかない。

canavis:
『パックランド』しかない。なるほど。
ラブムー:
うん。『くにおくん』とかも多分あったと思うんだけど。『くにおくん』かな、『ドルアーガ』とかかな。わかんないですけど。色々他にも名だたるゲームはあったはずだけど、その衝撃とか、記憶の鮮やかさみたいなのはもう『パックランド』1本だけ。
canavis:
なんで『パックランド』に特別注目したんですか?注目をしたっていうか、衝撃を受けた?
ラブムー:
それは多分さっきcanavisさんも言ってたけど、やっぱりグラフィックの強烈さがあったのかなっていう風に思いますね。なんかちょっとサイケデリック感っていうか、ディズニー感みたいなのとか、色彩が強かったから。あと自分はスヌーピーとかね、アメリカのコミックとか好きだったから、そういう意味でストライクだったんだと思うんですよね。だから人によって色々違う、「アーケードゲームこの1本」ってのはあると思うんだけど、僕の場合はたまたまそれが『パックランド』だったということ。
canavis:
『パックランド』この動画の真ん中にも画面があるんですけど。このゲーム、確か1984年かな。
ラブムー:
そう、84年ですね。僕がプレイしたのはもうちょっと遅いけど。
canavis:
アーケードゲーム。1984年にナムコから出た横スクロールのアクションゲームで、歴史的なことははっきり言えないんですけど、『スーパーマリオ』的な空が青くて、キャラクターが左から右に前進していって、敵があって最後にゴールがあるみたいな。横スクロールアクションゲームの作り方の雛形みたいなのがこれでできたのかなって。
ラブムー:
ありますね。『スーパーマリオ』も、やっぱり僕はちょっとそっち寄りの意見っていうか、これがあったから『スーパーマリオ』ができたんじゃないかなっていう風に、今も思っている。あと『スーパーマリオ』と違うところは、左に戻れる(左右にスクロールする)っていうところ。
canavis:
このゲームはワンラウンドごとに行きと帰りが設定されてて、行きは左から右に。で帰りは右から左に。
ラブムー:
そうそう、帰りは右から左に行くし、帰りは靴をもらってるから空を飛べるんですよね。
canavis:
だから、帰りでちょっと遊びが違うっていう。
ラブムー:
違う違う。で、音楽も変わるから、そこもいま思うと衝撃的だった。そこはどうですか、canavisさんとよごえむさんは。そのゲームデザインはちょっとなんか思うところというか、衝撃とかなかったですか?
canavis:
話がちょっと最初のグラフィックの話に戻っちゃうんですけど、キャラクターが元々、パックマンってデフォルメされてるんですけど、漫画的なデフォルメ感があっても、絵として省略されてるところはないんですよね。『パックランド』って。
ラブムー:
省略されてるところがない?
canavis:
『スーパーマリオブラザーズ』を見てもらうと、なんか、マリオの顔がなんだかわかんないじゃないですか。想像するしかないっていうか。でもこれはパックマンの顔が抽象化されてないというか。キャラクターも敵も描かれてるっていうのは、この時代のゲームのグラフィックがどこまでできてたか、ちょっと全部はわかんないんですけど、でもすごいなあって。
ラブムー:
でもそれはやっぱアーケードだったからってのもあると思いますよ。このあと『パックランド』、ファミコン版で『スーパーマリオ』の後に出たけど、相当チープな感じだったし。モンスターとかの顔もかなりドット感があったから。それでもいい移植だったと思うけど、僕は。だけど、当時アーケード夢中になった人たちは、ファミコン版のパックランドが出た時、「うわ、やっぱこんなんなっちゃったか」って思ったと思う。だから、そこはいまcanavisさん言ったのって、やっぱり『スーパーマリオ』とかはうまかったんですよね、ドットでマリオを表現することが、きっと。

よごえむ:
最初からファミコン向けですもんね。最初から家庭用に作られてるっていうものと、元々アーケードにあるものだから、そこは確かに。
ラブムー:
僕は『スーパーマリオ』をやったとき、『パックランド』に比べると、なんかしょぼいゲームだなって思ったもん。
いや、もちろんそれはネガティブな意見だけじゃなくて、スーパーマリオすごいなってのもあるんだけど。なんか『パックランド』に比べると、リッチさのないゲームだなって思ったんですよね。『パックランド』がやっぱり最初に来ちゃってるから。
canavis:
で、ゲーム的には、キャラクターを動かすのがレバーじゃなくてボタン制御だったところ。
ラブムー:
実はそう。あれはね、ちょっとなんとも言えないとこなんですけどね、なかなかあれでプレイできる人っていないと思うから。当時うまい常連の人とかはあれでもできてた気がするけど。
canavis:
このゲームってAボタンで右で、Bボタンで左で。両方同時に押すとジャンプだったかな。
ラブムー:
いや、3つボタンがあって。ジャンプボタンは分かれてる。だから計3つで、ジャンプ・左・右っていう。
canavis:
で、3つのボタンがあって、レバーがないんですかね。
ラブムー:
レバーはない。だから、『ハイパーオリンピック』とかに近い感じ。
よごえむ:
だから、かなり削ぎ落とされてるというか、本当に操作のためだけの汎用性がない感じ。
ラブムー:
そうなんですよ。あれの理由っていうのは、プレイ時間を短くしてインカムを稼ぐためっていう説もあるんですよね。
レバーにしちゃうと、滑らかに操作してクリアできる人が増えちゃうから。
ボタン操作で難易度を高めてインカム数を稼ぐみたいな…でも、わからない。もしかしたらそういう理由じゃなくて、アクションの独自性のためにボタン操作にしたのかもしれないけど。
よごえむ:
そうですね。でも実際アーケードで去年遊んだ時、やっぱりボタン操作だからの良さは確かに感じたんですよね。
ラブムー:
ミカド(高田馬場ゲーセンミカド)ではそこまで再現っていうか?
よごえむ:
ボタン操作でしたよ。
ラブムー:
そうなんだ。ファミコン版とかはもうみんなファミコン十字キーで操作できちゃうから、ボタン操作でやるって人いないんですよね。ほとんど。でもアーケードだったら、あれはボタンでやるべきものなのかもしれないです。さっきYouTube配信した時は、ちょっと自信なかったから、ファミコン操作にしちゃったけど。
canavis:
いい意味でキャラクターの制御がちょっとままならないっていうのが面白いなぁって。
ラブムー:
でも、コントローラー操作でもプレイの面白さっていうのはそこまで変わらないというか、むしろ操作しやすくなるから、ちょっと自分は今から『パックランド』をプレイされる方にボタン操作をおすすめするかって言ったら、しないですね。もしアーケードアーカイブスでプレイするんだったらパッドで操作してもした方がいいんじゃないかなって思っちゃう。
canavis:
でもボタン操作で、なんかランゲームに近い感覚はちょっとあるというか。
ラブムー:
それは確かに。
canavis:
マリオって左を向くことが容易にできるっていうか。『パックランド』も容易にできるんですけど、ボタン操作だと右に行くより、左に行くのが、ちょっとこれ、感覚でしかないんですけど、若干、心理的負担があるっていうか。どちらかというと常に画面右側に行きたがる性質がちょっとある感じがするんですよね。
よごえむ:
どっちの方があるってことですか、それは?
canavis:
『パックランド』の方が。マリオも前進するゲームなんですけど、マリオは止まって行動することがあるじゃないですか。止まって、ジャンプして。『パックランド』も、止まるっちゃ止まるんですけど、基本的に前進をずっとしていきたくなるっていうか。
ラブムー:
走り続けなくちゃいけないみたいな感じがあるのか。
よごえむ:
『パックランド』の方が連続性があるっていう感じがして。連続性がすごく強くて。で、マリオはやっぱりアスレチックっていうとこもそうなんですけど、直線的というよりかは、割と上に行ったり、下に行ったりっていう。キャラクターが小さいっていうのも多分あると思うんですけど。
ラブムー:
うんうんうん。
よごえむ:
『パックランド』は右左戻れるっていう、右左のスクロールの広さみたいのは、『パックランド』の方がやっぱりあって、それが多分、直線的な連続性を生んでるんだと思うんですけど。マリオの場合は後ろに戻れないっていうのもあるんだけど、上下の感覚みたいなのはマリオの方があるかなっていう気がしますね。
ラブムー:
エレベーターみたいな仕掛けもありますもんね。
よごえむ:
実際、画面が切り替わって、地下に行ったりとかっていうのもあったりするんで。『パックランド』の面白いところは、行きと帰りがあるっていう。
で、帰りで音楽とか、操作感とかが変わる。それがマリオで言うところの、もしかしたら海底ステージとかあの辺の感覚なのかもしれないですね。
canavis:
行きはマリオ的な感覚があって、帰りは、ちょっとバルーントリップ感があるっていうか。
ラブムー:
それ、結構新しいっていうか、いまハッとさせられたんだけど、バルーントリップ感ってのは確かにある。バルーントリップって任天堂のあれですよね。
canavis:
バルーントリップって、『バルーンファイト』っていうゲームが昔あって。
ラブムー:
当時HAL研の岩田(聡)さんがメインで作った。
canavis:
ゲームモードが2つあって、固定画面の風船を取り合って、要はシューティングゲームをバトルにしたような感じのゲームでいいのかな。バルーントリップはあとスクロールしていって星に当たらないようにうまくコントロールしながらキャラクターを当てないようにしていくっていう。
よごえむ:
バルーントリップも右から左へのスクロールなんですよね。
ラブムー:
たしかに。
canavis
うん、もっと言っちゃうと『ハローキティワールド』になっちゃうんですけど、『ハローキティワールド』はちょっとマニアックすぎるので。
ラブムー:
それは知らないです。
canavis:
『ハローキティワールド』ってサンリオが出してるやつで、ハローキティが風船を持っていて、ボタンを押すと風船を飛ばして上昇できるっていう、バルーンファイトとマリオを合体させたようなゲームって言ってしまっていいのかな。
ラブムー:
ファミコンですか?
canavis:
ファミコンであるんですよ。
作ってるのが名前が開発会社マリオっていう形になってるんですかね。実際は任天堂らしくて。任天堂のバルーンファイトの続編的ゲームって語ってしまっていいのかな。
ラブムー:
そうですね。だから任天堂とその『パックランド』の関係みたいなのはその後もずっと指摘されてるんだけど。つまり『スーパーマリオ』は『パックランド』を参考にした部分があるんじゃないか、みたいな。そこまで宮本さんに突っ込んできた人はいないけど、宮本茂自身が、なんか『パックランド』には若干影響受けたみたいなこと、ちょっと出典わからないんだけど、言ってたインタビューがあって。
canavis:
それ、なんか結構近くによごえむさんが見てたような気がした。
よごえむ:
そうですね。私が見たのは、飯野賢治さんがいろんな方にインタビューする『スーパーヒットゲーム学』ってやつで。
で、宮本さんにに聞いてた時に『パックランド』とかのことを聞いてて。ただ直接的に『パックランド』を参考にしましたみたいなことは言ってなくって、ナムコのことを元々すごい尊敬してて、偉いなみたいな感じで見てて。
で、当時スクロールするゲームが割と出始めたというところで、ナムコがついに『パックランド』でアスレチックみたいな感じのジャンプゲームでスクロールするのをやり始めたってのを見て、それでマリオをやる機会というか、きっかけというか。そういう気持ちになったみたいなことはおっしゃってましたね。
ラブムー:
だから間接的な影響というか、当時やっぱりゲームメーカー的にも切磋琢磨してたところがあったと思うし。
よごえむ:
思いますね。だからついに、だからナムコがやったかっていうところで。
ラブムー:
だからそういう話を聞くと、いまのパックマンとそのマリオっていうのの違いっていうか、ポジションのことを考えると、ちょっと複雑な気持ちになるところがあって。やっぱりパックマンって僕にとってはヒーローで。マリオと同じくらい、あるいはマリオ以上に。だからマリオはこうして今も進化し続けているなか、パックマンも頑張ってもらいたかったんですけど、もう今パックマンって本当にもう隠居した人みたいになっちゃってるじゃないですか。キャラクター的にもゲーム的にも。
よごえむ:
なんていうか、殿堂入りしたキャラですよね。もう。
ラブムー:
でも殿堂入りしちゃうのかっていうとこないですか?
よごえむ:
結局隠居できるっていうのは多分殿堂入りしたからで、マリオの場合はまだ現役っていうか。まだ普通にそこで一線張ってるっていう。
canavis:
ちょっと『パックランド』っていうゲーム自体が、当時のことはわかんないですけど、ゲーム性がマニアックっていうところがちょっとあるのかもしれないっていうか。
ラブムー:
『パックランド』マニアックだったのかな。僕はマニアックっていう印象は当時はなかったんだけど。
canavis:
マニアックというかキャラクターをボタンで制御するっていう遊びが、ちょっとトリッキーすぎてそこが良くも悪くも結構、特徴的すぎるっていうか。先に進み過ぎてたって言い方になってしまうのかわかんないんですけど。横スクロールで空も大地もあって、っていう時点で既に新しいゲームだったんですけど、それよりさらに追加で新しいことしてマリオの遊びよりニッチになった感はあるんじゃないかなって。
ラブムー:
それは確かにあるけど。でもそういう意味で言ったら、プレイステーションの時にはまだチャンスがあって、『パックマンワールド』っていうのが出たんですよ。あの時はまだマリオも確か『マリオ64』とかの頃で(※『マリオ64』は1996年、『パックマンワールド』は1999年発売)『パックマンワールド』がうまくいけばまだパックマンってその命脈があったと思うんですけど。
よごえむ:
一応今もパックマンの3Dゲームって出てはいるにはいるんですよね。
アクションゲームとかはあるんですけど。なんかいろんなゲーム出してはいるんだけど、第一線級のメジャーになってるかというと。遊べばもちろん面白いんですけどね。
ラブムー:
僕のなかでは今ではマリオとソニックに「及んでない」じゃないけど、ちょっと別のところに行っちゃったなっていうのがある。
canavis:
結構パックマンの横スクロールのアクションゲームって、『ハロー!パックマン』とか、あと、なんだっけ。
よごえむ:
あと『パックインタイム』。海外のゲームのキャラクターを変えたやつね。

canavis:
はい。でも、『ハロー!パックマン』とか『パックインタイム』って、結構作りがやっぱり変なゲームになっちゃう。『パックランド』の続編じゃなくて、なんか全く別のゲームを毎回毎回出してる。
2Dマリオみたいな進化とまた違ってて、続編が全く別のゲームでしたみたいなことになってしまう。
ラブムー:
確かに。中身だけ変えましたみたいなね。そういう感じがある。
canavis:
マリオでアイテムが増えましたとか、世界が増えました、仲間が増えました、って進化って分かりやすいじゃないですか。でもパックマンの続編はなんか全く別のアイデアをなんか出してくるような感じがちょっとあるというか。
ラブムー:
しかもなんか全部外すみたいな、そのアイデアを。いや、だって去年『スーパーマリオワンダー』が出た時に、すごい悔しいっていうか、この感じって、なんか『パックランド』やった時の感じに似てるなって思って、自分は。
そのワクワク感とか不思議な感じ?これをほんと、本来はやっぱパックマンでやってもらいたかったっていう風に自分は思ったんですよね。だから、それぐらい『マリオワンダー』は自分はすごく良かったんだけど、これは『パックランド』やった時の感動にめちゃくちゃ近いなってことを思って。ちょっと自分は複雑な思いを感じましたね。

よごえむ:
『パックランド』のキャッチコピーが「不思議なことが当たり前」みたいな。キャッチコピーとかまさにそういう感じですもんね。
ラブムー:
そうですよね、ワンダーっぽい。
canavis:
ナムコの昔のゲームって、なんかやっぱり、特徴がありすぎるっていうか。なんて言うんでしょうね。
ラブムー:
canavisさんが前に言ってた『ゼビウス』の話とか。『ゼビウス』に感じる唯一無二の話をしてたじゃないですか。『ゼビウス』に感じる虚無感じゃないけど、なんていうのかな。
canavis:
『ゼビウス』の空が寂しいっていうか。画面がすごい明るいけど、画面がめちゃくちゃ、暗く感じるっていう、昔のゲームの。なんかそういうものを感じますよね。
ラブムー:
『ゼビウス』もそうだし、やっぱ往年のナムコのゲームってそういうのがあるなと思ってて、それは『パックランド』にもあるし、『ゼビウス』もすごいあるし。あの頃のナムコのゲームってそういうものを有していて、だから僕は『パックランド』にそれを見たのは、そのナムコの魅力っていうことだと思っていて。当時のナムコだけが持っていた魅力。
だからcanavisさんがゼビウスに感じたものとか、自分が『パックランド』に感じたものとか、『スカイキッド』とか『ドラゴンバスター』に感じた人とかもいると思うんだけど、だからやっぱり自分は今回の放送で言いたいのは、『パックランド』もそうなんだけど、あの頃のナムコの凄さみたいなことはちょっと強調したいかな。
たとえばタイトーも大好きだったけど、例えば『影の伝説』とか、めちゃめちゃアーケードで見た時に衝撃を受けて。すごいゲームだなと思ったんだけど、それはやっぱりナムコのゲームから受ける衝撃とは違うんですよね。ナムコのゲームはもうあの頃のナムコしかない。タイトーもあるのかもしれないけど、『影の伝説』には確実に何かあるとは思うんだけど。
ちょっと話は逸れちゃうけど、だから当時のナムコは凄かったっていうことを、今回の放送ではいくら強調しても強調し足りないというか。
canavis:
そうですね。
ナムコはリアルタイム世代じゃないんですけど、やっぱりデザインがいいっていうか。
ラブムー:
いいっていうのは、センスがいいみたいな?
canavis:
センスがいいです、はい。
ラブムー:
それはだから、当時のナムコ、ギリギリファミコンからスーファミぐらいの頃のナムコで、バンダイナムコになってからは自分の印象は全く違くて。でも一応、パックマンのリメイクとか、パックマンのまとめたパックマンコレクションみたいなの出してくれるから感謝してるんだけど。
よごえむ:
ラブムーさん的にはプレステぐらいからのナムコだとどういう感じなんですか?
ラブムー:
僕はプレステ時代からはもうナムコはあんまりっていう感じがあったかな。『ミスタードリラー』とかもあんまり好きじゃなかった…「好きじゃない」っていうのはいいゲームだなと思ったけど、ナムコらしいゲームだなとは思わなかった。リッジレーサーとか鉄拳とかは前衛的なナムコ感みたいなものはあったけど、自分が求めてたナムコ感ではなかったですね。
よごえむ:
だから多分そこらへんで多分ナムコ自体がもう潮目を変えた、自覚的に変えてるところも多分あるだろうし、だからこそこう、往年のナムコに感じていたものが多分消えているんだろうなっていう。
結構、自己言及的になってますね。プレステの頃のナムコって、ゲーム起動した時にプレステ版とかだと『ギャラガ』が遊べたりとかっていうところはもう結構、なんかもうそこでひとつ時代が変わってる感じがありますよね。
ラブムー:
それはある。だからそういう意味では、その時代のナムコにこだわりすぎるというか、そこに魅力を感じすぎちゃうと、やっぱりちょっとレトロゲーマーみたいな感じになっちゃうんですよね。それはちょっと良くないなとは思うんだけど。
コメントが来てますね。entupsetさん。
「レバーのオンオフだけでなく、ボタン連打移動にしたことによってプレイごとに操作感が変わるので、操作のアナログ感を出したかったのだと想像しますね。」
たしかに。
ラブムー:
なるほど。
canavis:
なんかこうね、アクセルとブレーキの感覚かなって感じもちょっとあります。車で言う。
ラブムー:
そうだね。だから、さっきcanavisさん言ったランゲームに近いっていうところは確かにあったのかもしれないですね。
よごえむ:
連打した段階で、あとはもう押しっぱなしにしておけば、基本的にはダッシュスピードを保てるんで、『パックランド』って。
ラブムー:
たしかに。
よごえむ:
そこら辺もやっぱりなんかレースとかランゲームとかに近いところもあるし。翻ってじゃあマリオはどうやってスピード出してるのかっていうと、キーの補作とBボタンを押すっていう手段をとっていて。1個のボタンでそれを連打することにより出すっていう手法を取るか、2つのボタンの操作でやるかっていうとこの違いなんですね。
ラブムー:
ただ、ジャンプアクションとしての難易度は確実に上がってしまうんだけど。『パックランド』って結構ジャンプアクションとしてのテクニックを要求してくるんですよ。マリオ並みに。だから、そこのバランスがちょっとおかしいような気がする。
よごえむ:
ジャンプ台とかの操作、かなり難しいんで。
ラブムー:
そう。プールのジャンプ台とかは、十字キーを連打する方が難しかった印象がある。
よごえむ:
そうですね。うん。キー連打の方が難しいですね。ボタンの方があそこは絶対いいと思いますね。
ラブムー:
だからentupsetさんがおっしゃったように、操作のアナログ感を出したかったってのはあると思うけど、『パックランド』のこっちに要請しているゲーム内容って結構アスレチック的なところもあるし、ランゲーム的なところもあるから、(3ボタンでの)操作性に若干無理はあったのかなっていう感じは自分はしてるけど。
よごえむ:
割とその、プールの所とかは結構普通に殺しにかかってるというか。コインを失わせようという感じが結構強い。あそこはだって連打をしないと渡れないので。
canavis:
じゃああと聞いておきたいのは、なぜ『パックランド』が1番好きなのかっていうことですね。
ラブムー:
やっぱり『パックランド』がなかったら、いま多分こうしてゲームをやり続けて、今ゲーム関係の仕事をしてることもなかったと思うんですよね。だから、それぐらい魅力を感じたっていうことなんだけど。『パックランド』が1番好きというよりは、『パックランド』によってゲームの世界を選んだきっかけになったっていうことなのかな。
だから、うん、「人生を変えた」じゃないけど、そのくらい影響力が強いゲームだったっていう。それが『スーパーマリオ』の人って、多分自分の世代だと多いと思うんだけど。僕は『スーパーマリオ』だったら、人生変わらなかったかもしれない。『パックランド』じゃないと。
canavis:
なぜ『パックランド』?マリオじゃなくて?
ラブムー:
なぜ?なぜか…やっぱり『パックランド』はストライクだったからかな。その、音楽にしても、グラフィックにしても。さっきもやってて思ったけど、その、ドアがあって、落っこちたら妖精の国だったみたいな、そういうビートルズっぽいというか、『サージェント・ペパーズ』みたいなサイケ感とか。
うん。だからもう本当好みだったというか、ある種の一目惚れみたい。一目惚れって、なんかこう、ある意味説明がしづらいと思うんだけど、一目惚れ感があったゲームが『パックランド』。最初の一目惚れが『パックランド』で、それがずっと続いてるっていう意識があるから、やっぱり『パックランド』を選ばざるを得ないっていうところはある。
canavis:
なるほど。
ラブムー:
ちょっと答えになってないかもしれないけど。はい。そういうゲームがやっぱり「1番好きな」っていう枕言葉をつけたいかな、自分は。1番優れたゲームとか、1番「グッときた」とか、やっぱりうまく言葉にできないところはあるかな。だから言葉にできないっていうことが理由になっちゃってるって意味で、あんまり答えにならないんだけど、一目惚れ的なところが大きいかも。
canavis:
なるほど。
ラブムー:
で、そういう魅力を当時のナムコは持っていたと思うんですよね。もちろん『スーパーマリオ』も持ってたし、『スーパーマリオ』がすごい好みだったっていう人はいると思うんだけど。僕はちなみに『スーパーマリオ』やった時に思ったのは、ちょっと不気味なゲームだなと思ったんですよね。『スーパーマリオ』の方は。うん、なんか怖いというか、どっちかっていうネガティブな印象を持ったの。決して明るい方じゃなくて、ダークな印象があったんですよね。
最初に見たキャラがそのクリボーじゃなくて、メットだったのかな。確か友達の家で見た。メットもちょっと暗い印象だし、地下とかも暗い印象だし。
ちょっと不気味な印象があったんですよ。『パックランド』は不気味なんじゃなくて、本当にサイケデリックさとブライトネスというか……自分にとって。いい意味でほんとに光みたいなゲーム。『ドルアーガの塔』とかもちろん大好きなんだけど、ドルアーガは光ではないんですよね。
よごえむ:
うん。『ドルアーガ』はたしかに光ではないですよね。閉塞感が強いですよね。
ラブムー:
『ドルアーガ』も大好きで、もう同じぐらいっていうかゲーム性的には『パックランド』よりも影響受けてるところもあるかもしれないんだけど。あるいは『ウィザードリィ』でもいいんだけど、やっぱり『パックランド』は自分にとっては光だなあ。
canavis:
そうですね。空も開放的な空、やっぱり青い空ってなんか開放的な感じもします。
ラブムー:
うん。で、夕暮れになってもね、なんかその夕暮れ感がすごくいいんだけど。スーパーマリオは5面とかで夕暮れになるんだけど、それがすごいなんか気持ちが重くなる夕暮れなんですよね。
canavis:
確かに。行って帰ってくるってのも、なんかいいですよね。冒険じゃなくて。
ラブムー:
そうそうそう、行って帰るっていうのも。あと、空を飛べるっていう開放感も自分は好きだし。
おふたりはどうですか。スーパーマリオと比較した時に、『パックランド』に関して、こう劣ってるとか、比較して何か思うところはありますか?
canavis:
『パックランド』と『スーパーマリオ』って出た時代関係の話になってくると、『パックランド』がルーツで、マリオはその影響だって話になっちゃうんですけど、『パックランド』はやっぱりマリオと違ってアスレチックのゲームじゃないなっていう印象があって。あんまり自分やり込んでるわけじゃないので偉そうに言えないんですけど。
ラブムー:
アスレチックというのは?
canavis:
確か動画の最初の方に行ったかもしれないけど、ブロックづたいに行って細かい足場がないところをうまくコントロールしていくっていう感じのゲームがマリオで。『パックランド』は敵が出てきて、それをなんかこう、ジャンプでポンポンポンポン避けていったりはするかもしれないんですけど、どっちかっていうとマラソンに近いっていうか。
よごえむ:
それは確かにそうですね。
canavis:
マラソンのゲームだなって感じ。なんか横スクロールアクションゲームって、うん、基本的にレースゲームになっていくと思うんですよね。ソニックがいちばんわかりやすいんですけど、マリオもそうなんですね、こじつけっぽいけど。レースゲームになってるっていうか、『パックランド』はマリオよりもちょっとレースゲームに近くて。さっきも言ったようにボタンで制御してくっていうのが、アクセル・ブレーキっていう。
ラブムー:
でもさっきやってて思い出したんだけど、『パックランド』には『ドラゴンバスター』みたいな要素もあって、鍵を探して、ドアを開けていくとか。
canavis:
『くにおくん』とかああいうのはちょっと省いて、マリオとか、『パックランド』とか、ソニックとかは、レースゲームに近いっていうか。敵との応対を重視しないっていうか。マリオはもっとアスレチック寄りで、『パックランド』はマラソン的というか、レースゲームぽいっていうかそんな感じはある。
ラブムー:
わかります。それはとくに今考えると、そうかもですね。
canavis:
なんかこう、ルーツ的な感じがするけど、でも、なんかこう、マリオもソニックも違うゲームだし、マリオも『パックランド』も違うゲームなんですよね。
ラブムー:
マリオと『パックランド』とソニックの世界のどれかに入らなきゃいけないとしたら、どれに入ります?
canavis:
『パックランド』かなって感じは。どれに入るかって言うとあれなんですけどマリオって、『スーパーマリオ1』→『2』→『3』ってあって。『3』になって、やっと漫画的な表現が手に入ったような気がして。要は、グラフィックが良くなって、なんか、クリボーがクリのモンスターだっていうのが分かるような絵になってるっていうか。
ラブムー:
『2』ってディスクシステムのあれですよね。
canavis:
まあ、変わってないんですけど、ほぼほぼ変わってないんですけど。
『3』でだから、表現が『パックランド』に近づいたってこともないけど、ブロックもあって、雲に確か顔が描かれてるのは3だった。
ラブムー:
そうだったそうだった。
canavis:
なんかより漫画に近い形で、マリオは人だってわかるし。
ラブムー:
ああ、それは確かにそうかもしれない。あ、コメントが。
canavis:
はい、コメント来てます。
パックランドを見かけた時の場所やシチュエーションなどはまだ記憶に残っていますか?
ラブムー:
そうですね。その、ゲームセンターのおにぎり屋さんの併設されたゲームセンターで見て、なんか大学生みたいな人とかがたくさんプレイしてて、早くやりたいなと思って、50円玉を握りしめてた記憶とか、なんかよく覚えてますね。そういう、シチュエーションの記憶も込みで覚えてるっていうところが、やっぱり大きいかな。
canavis:
そうですね。自分は『パックランド』じゃないですけど、ゲームセンターのゲームで触れたのは、 駄菓子屋さんが最初で。『メタルスラッグ』で。
ラブムー:
うまい棒とか売ってるんですか?
canavis:
うまい棒とか売ってたりとかするような、おばあちゃんがやってるお店で。『メタルスラッグ』がそこにあって。
ラブムー:
『メタルスラッグ』が(笑)。何台ぐらい筐体があるんですか?
canavis:
で、一旦やる時、電源をコンセントに入れて、自分で入れてくれて。
ラブムー:
50円ですか?100円?
canavis:
50円だったかな。
ラブムー:
おばあちゃんは『メタルスラッグ』をやるんですか。
canavis:
おばあちゃんはやらないですね。メタルスラッグが置かれてた理由は謎なんですけど。
でもなんとなく『メタルスラッグ』って覚えることがあんまないゲームなんで、ゲームの型がしっかりしてるっていうとあれですけど。
ラブムー:
『メタルスラッグ』名作ですもんね。で、それを駄菓子食べながらやってたと(笑)。
canavis:
よごえむさんはなんかもう、駄菓子屋さんとかあんまない時代でしたか。
よごえむ:
いや、駄菓子屋はあったんですけど。駄菓子屋にはゲームなかったんですよね。駄菓子屋はお菓子とタバコしか売ってなかったです。
お菓子とタバコしか売ってなかったんで、ゲームがなくて。あとローラースケートしか売ってなかった。
ラブムー:
それはでもストイックですよね。
canavis:
ローラースケートが置いてあったってのは、ちょっと衝撃的な感じがしますよね。
よごえむ:
ローラースケートがいつまでも売れずに。
ラブムー:
ホコリをかぶって(笑)。
よごえむ:
そうホコリをかぶってた。
canavis:
アーケードゲームに最初に触れたってのはどんなタイミングでしたか。
よごえむ:
アーケードはなんだろう、自分の母方の祖父母のところに預けられてた時に、たしかね、港にソフトクリーム屋があって。ソフトクリームとか、なんか軽食を出してくれるとこがあって、そこに格ゲーが置いてあったんですね。やっぱSNKが強かったんでしょうね。ネオジオとか。
多分『サムスピ』だったと思うんですよね。たしか『サムライスピリッツ』が置いてあって、多分アーケードで初めて遊んだのはそれが最初の気がしますね。
ラブムー:
じゃあ初代『サムスピ』がアーケード系では最初?
よごえむ:
『サムスピ』、多分。いや、初代じゃないかも。『サムスピ』の何かですね。でもわかんないから、とにかくボタンを叩いてましたね。なんかよくわかんないけど。
ラブムー:
卵つつむさんからのコメントです。
このサイケっぽいアニメ風原色アートってあまりフォロワーいないし無二の魅力感じるのわかります
canavis:
そうですね。
ラブムー:
ありがとうございます。
よごえむ:
『パックランド』ってこう、マリオとの比較をしすぎるのもちょっとどうかなと思うんですが、地上がちゃんと書かれてるってとこが違いますよね。奥側に向かってね。マリオは横真っ二つなんで。
ラブムー:
うん、確かに。そこの違いは大きいのかもしれない。
よごえむ:
やっぱ奥行きがありますよね。マリオって多分今に至るまであんまり奥行きを書かないんで、『マリオワンダー』ですら奥行きあんまないんで。だからスタイルは全然違うかなっていう。
ラブムー:
「奥行き描かない」って確かにあるかも。でも、なんかの時にすごい奥行き書くんだなって思ったんですよね。マリオが。なんだっけな、『スーパーマリオ3Dワールド』かもしれないけど、『3Dワールド』は厳密には2Dじゃないけど。
canavis:
『ペーパーマリオRPG』って、なんか『パックランド』っぽいっていう感じが。
ラブムー:
はい、確かに。絵も世界観も。
canavis:
ちょっとベルトスクロール視点っていうとあれだけど。
よごえむ:
あとちょっと面白いのが、『パックランド』遊んでると、パックマンがちょっと蛇行しながら進んでいくんですよね、アニメーションが。そこら辺の細かさとかもちょっと面白いというか。ただ、まっすぐ行くわけじゃなくて、ちょっとだけ蛇行して進んでるところとか、確かにあったりとか。
あとステージとかが全部「トリップ」っていう。「TRIP 1」とかってなって、旅行なんだなっていう。ちょっとした旅行というか。なんか気分の軽さみたいのも。
ラブムー:
そうですね。トラベルじゃなくて、トリップなんですよね。
よごえむ:
そうそう、なんか行って帰ってくるよみたいな。ちょっと行ってくるわみたいな感じ。ちょっと軽々と世界を飛び越えてる感じも。
ラブムー:
そうかも。なんかその「トリップ」っていうのは、なんかある種のドラッギーな感じも有してるのかもしれないなとも思って。ディズニーランド的な。

よごえむ:
感じますよね、ゲームのシステムとかの部分は置いといて、全体として感じる身軽さみたいなものは、マリオよりはあるかなっていう。実際のところ、
『パックランド』の方がちょっと重たいんですけど。雰囲気としての身軽さみたいのは、『パックランド』の方があるかなって気がしますよね。
ラブムー:
そうですね。そうそう『パックランド』は、だからやっぱり「夢の世界」っていう感じが強いのかな。僕は、スーパーマリオはちょっと悪夢じゃないけど、何かそういう重みがあるんですよね。
水中ステージも、自分にとってはすごい重みというか、負荷がある感じ。でも、だから別に『パックランド』は『スーパーマリオ』より優れているとか、オリジンであるとかっていうことを今回言いたいわけではなくて。ただ、『パックランド』が自分の1番の好みだったし、これまでもずっと原体験みたいなものとして残っているということを言いたかったんですけど。
よごえむ:
でも、『パックマン』というものを横スクロールに仕上げちゃうっていうのが、なんかなかなか考えてみると、不可思議な感じでもありますね。で、一応、やっぱりパックマンであるっていう前提を活かして、パワーエサとかを食べるとお化けを食べられたりとか、フルーツがあったりとかっていうところを生かしてるわけですけど、『パックマン』にあった逆襲とは結構ちょっと違うというか。お化けに対して逆襲する感じとかも、すごいゲーム的にめちゃくちゃ効果的なのかっていうと、そういうことではないんですよね。わざわざこう、行って戻って。
ラブムー:
わざわざやるほどのことでもないってこと?パックマンの場合は、必要不可欠ですもんね。
よごえむ:
それがストレスの解放にもつながるし。自分のこれまで受けてた、追いかけられる側から追いかける側になるっていう鮮やかさはあるんだけど、『パックランド』はなんかそれは別になんかしなくてもいいっていうか。
ラブムー:
それはほんとそうだ。たしかにそうですね。無駄ではないけど、ボーナス的な行為なんですよね、あれは。言ってしまえば。うん。だからそこまでの必然性は確かにない。マリオのスターと比べるとどうだろう。
よごえむ:
そうですね。マリオのスターはゲームのガワのデザインとして多分作られたものだから、合致してるんだと思うんですけど。『パックランド』は多分先にまずパックマンっていうゲームのキャラクターとしてありきだから、そこら辺は結構違いそうですよね。パックマンである以上はそれを入れておかないといけないっていうか。
ラブムー:
確かに付加価値的に作られたものなのかな、じゃああれは。そうかもしれない。それは言われるまで気づかなかったな。
canavis:
マリオの、というか横スクロールの アクションゲームになってくると、固定画面のゲームの時代…時代で変わるもんじゃないけど、詳しくは言えないんで雑に語ってしまうと、敵を全部倒すってのが基本にあるじゃないですか、ゲームの目的で。
ラブムー:
画面上の敵をね。
canavis:
ちょっとマリオに例えちゃうんですけど、マリオって別にコインを全部集めなくても、クリアできるし。敵を無視しても、キノコを取らなくてもとりあえずゴールを目指せば、クリアできるって。有利になるけど無駄なことができるってのもゲームの進歩としてあったのかなって。固定画面から横スクロールにいく時に。全部倒さなくてもいいとか、アイテムを取らなくてもいいっても、とってもいいとか。
ラブムー:
『パックランド』も、でもただゴールするだけでいいって意味では、そういう融通無碍さはあると思うけど。スーパーマリオの方があるのかな。
よごえむ:
うーん、どうなんでしょうね。
canavis:
どうなんでしょうね。ちょっとごめんなさい。雑に言い過ぎた。
よごえむ:
でもマリオの方が攻撃的ではあると思いますよ。『パックランド』よりは。
ラブムー:
さっきの話に戻っちゃうんですけど『影の伝説』をプレイした時に、ジャンプした時に上にもスクロールするってのが、ものすごい衝撃で。
よごえむ:
ああ、そうですね。
ラブムー:
上にも世界が、木の上があったり、飛べるんだっていうのがあって。『パックランド』だと飛べるんだけど、1画面固定というか、さらに上までスクロールするわけではないんですよね。もし『パックランド』が空もスクロールしてたら、もっと『パックランド』のこと好きになってたと思う。
よごえむ:
そうですね。うん。確かにいけてもおかしくないような感じはありますよね。靴を持ってて上に行ける感じ。
ラブムー:
そうそうそう、屋根とかにも登れるじゃないですか。でも、その屋根に登れるっていうのも、さっきよごえむさん言った奥行きの視点から言うと、おかしいんですよね。
だって、奥の建物の建物にそのまま登っちゃってる(笑)。
よごえむ:
そうそう。そこらへん2Dの矛盾がある。
ラブムー:
うん。
よごえむ:
でも、絵的なところで言うと、やっぱりあれは明らかに魅力で。だから、そこらへんのことを差し引いても、やっぱり他の2Dアクションとはこう、見た時の魅力っていう面で言うとすごくあるし、上に上がれるっていうのも、多分初めてやった時にはあんま気づかないと思うんですよね。
ラブムー:
登れるってこと?そういえば、2人はあれやりました?『パックランド』のファミコン版。
canavis・よごえむ:
やってないですね。
ラブムー:
ファミコン版もぜひプレイしてほしいんですけど。っていうのもファミコン版だと、屋根に登る必要がもっと出てくるんですよ。
アーケード版はおまけじゃないけど、「あ、登れたんだ」みたいな感じなんだけど、ファミコン版の方はもうちょっと、さっきcanavisさんが言ってたアスレチック要素がちょっと増えていて。屋根に登るアクションがもっと必要になってくるから、ゲーム性はけっこう変わってきちゃうんだけど。ただ、魅力はこれ(アーケード版)と比べると劣るかな。初代『スーパーマリオ』と比べても魅力はちょっと劣ると思うんだけど。

よごえむ:
ファミコン版はさっき自分も画像検索とかして見てたんですけど、かなりキャラクターもちっちゃくなってるし、画面構成もだいぶマリオ的な感じというか。
ラブムー:
そうそうそう、だいぶマリオ寄りになってる。
よごえむ:
だいぶゲームの感じが変わりそうだなって自分は思ったんですけど、そういう屋根の上に登る必然性が出てきてるっていうこともかなり違うんですね。
ラブムー:
で、子供の頃、やっぱりアーケードゲームをしょっちゅうできるわけじゃないから、ファミコンで『パックランド』が出たっていうんで、もう喜び勇んで買った(買ってもらった)んですよ。で、やってみて、ものすごい落胆と同時に、でもこれで家で『パックランド』ができるんだっていう思いもあって。やっぱそれは『スーパーマリオ』の感じとは全然違って、諦めと喜びが綯い交ぜになったような気持ちがあったんですよね。ナムコのファミコンゲームって結構そういうところがあって。『スカイキッド』とか『メトロクロス』もそうだけど、ファミコン版に移植されると大体しょぼくなるんだけど、それを我慢しなきゃいけないっていう気持ちと、やれるんだっていう喜びと。
よごえむ:
当時の感じとしてもそうだし、いまそれを見ると、なんかまた別のものとしてこう評価するという軸もまた生まれてくると。
ラブムー:
それはありますね。ただ、やっぱりファミコン版の方をやるよりは、ナムコのゲームって初代プレステで出た『ナムコミュージアム』をやった時とか思ったんですけど、やっぱりアーケードのナムコっていうのが偉大だったんだなっていう。ファミコンの時は嬉しかったけど、あれは妥協の嬉しさだったんだなっていうのはあって、真骨頂はやっぱりアーケードにあったんだなっていうことを自分は凄く思ったかな。
よごえむ:
全体的にやっぱり、ナムコに限らずですけど、当時のゲームでもそうですかね。各メーカーってめちゃくちゃ特色があるので、音にしろ、グラフィックにしろ、なんかこのメーカーっぽいなってわかるような。
ラブムー:
あるあるあるある。『グラディウス』をやった時とかも、これはナムコじゃないんだけど、アーケードのを見た後にファミコン版の『グラディウス』をやった時とかも、嬉しいけど、凄く複雑な心境ではありましたもんね。なんでこんなにレーザーが途切れるんだとか(笑)。
よごえむ:
よく言われますよね。私はそれ、ニチブツにすごい感じる。
ラブムー:
ニチブツあれですよね、シューティングの。
よごえむ:
そうですね、『テラクレスタ』とか『セクロス』とか。
ラブムー:
ああ、やってないなぁ。
よごえむさんがニチブツでいちばん好きだったのは?
よごえむ:
『マグマックス』です。
ラブムー:
やってないや、調べてみる。それは移植されたんですか?
よごえむ:
移植はファミコンでされて。アーケードは今「アーケードアーカイブス」とかも出てますね。
で、やっぱそのアーケードにしかない感じっていうのは、なんか自分は全然リアルタイムじゃないんですけど、特にニチブツのゲームにはとても感じますね。
ラブムー:
これか。これ、今日買ってやってみます。
canavis:
コメントが来てますね。
当時、アーケードだとスコアの重要性が高かったので(ハイスコア集計があった時代なので)、スコア効率性を考えるとパワーエサからモンスターを倒して得点を稼ぐ必要性はあったと思います
ラブムー:
それは確かにおっしゃる通りですよね。だから当時のゲームって、名前を残せるんで、そこにプライオリティっていうか、わざわざコインを入れてゲームをやる意義がものすごいあって。ハイスコアクレジットってあるじゃないですか。あそこに名前を刻むことがものすごく、うん、価値のあるというか、嬉しい時代だったんですよ。だから『パックランド』も『ドルアーガ』でもそうなんだけど、スコアっていうのが、今以上に意味…意味ではないけど、重要な時代だったんですよ。
よごえむ:
やっぱりスコアの地位がやっぱり全然高い。
ラブムー:
だから、『パックランド』においても1位を取るっていうことが、それは結局抜かれてしまうんだけど。そこに残すっていうことがものすごい重要だった時代で。だから、それは確かにentupsetさんがおっしゃるように、「スコアを残す重要性」だったのかもしれない。
よごえむ:
そうですね。
ラブムー:
そう、それ忘れてた。なんかスコアを残す意義ってものすごい高かったんですよね、当時のアーケードって。
それが存在意義みたいな感じで。だから自分だったら「I.H」とかってもう刻んでしまったら、なんか1日ずっと誇らしい気持ちでいられるっていう。
今のアーケードアーカイブスのゲームとかって、一応オンラインハイスコアみたいなのはあるけど、見るともう絶対に到達できないようなスコアを叩き出してる人がたくさんいるから。
よごえむ:
完全にやり込みを極めた人が。
ラブムー:
うんうん。僕なんか、ああいう人への憧れがすごい強いんですよね。うん、きっと本当にちゃんとやってるんだろうけど。だから、『パックランド』をやってても、すごいハイスコアを刻んでる人がいるんだけど、こういう人ってどういう人なんだろう…ってすごい考えちゃう。
この令和に、『パックランド』の1位をオンラインに残すことを生きがいにしてる人っていうのがいるんだなと思って。だからファミコン版『パックランド』をぜひ今回canavisさんとよごえむさんに『パックランド』を今回自分のオススメでやっていただいたけど、ファミコン版もちょっとね、贈りたい気持ち。
よごえむ:
いまも遊べますもんね。ファミコン版も。
ラブムー:
ファミコン版は、今はあれじゃないと遊べない。なんか抱き合わせみたいなやつ。※Switch『ナムコットコレクション』で単体購入することができる。
よごえむ:
そう、ナムコのコレクション系のやつ。(※NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 2)
ラブムー:
わざわざあれを買わなくてもいいとは思うんだけど。感想は聞きたいですね。アーケード版の『パックランド』と比べた時の。
canavis:
うん、なるほど。その後のゲームの趣味みたいなのに『パックランド』って影響されてますか?
ラブムー:
その後のゲームの趣味か…。
canavis:
ゲームを見る時の視点とかって。
ラブムー:
いや、影響してないかもしれない。もう、これはこれでちょっと別の世界にあるもので。
だからいまもそのスヌーピーとか『パックランド』とか、そのアメリカっぽい可愛いものとか好きだけど、それが今ゲームを選ぶときの趣味に影響してるかっていうと、あんまり影響はしてないかもしれないですね。今だって『パックランド』的なゲームってないと思うし、自分もそういうゲームを探そうとかはないし。なんかありますか?これに近いゲームって。逆に聞きたい。
canavis:
『パックランド』に近いもの…。
ラブムー:
『パックランド』が好きな僕におすすめしたい2Dアクションとか。ちなみにいちばん最近近いなと思ったのは『マリオワンダー』だった。
canavis:
なんでしょうね。ナムコって横スクロールアクションゲームなんなんだろう。
よごえむ:
全然違うってこと承知であれだけど。2Dアクションだと私はあれかな、『レイマン』かな。
ラブムー:
『レジェンド』はやってないけど、1本は『レイマン』やりました。
よごえむ:
『オリジン』は最近やったんですよね。
ラブムー:
はいはいはい。でも、近いんじゃないですか。

よごえむ:
うん、あれはなんか、絵的な面白みとか。『パックランド』も思ったんですけど、結構当時にしては、アニメのなんかやられた時のやられモーションとか、すごい細かいなと。よくわかんない「あ、ここ、こだわるんだ」みたいなところの感じは、『レイマン』もそう。
ラブムー:
あ、それはわかります。あと、なんか絵的にも結構近い。
よごえむ:
うん、なんか「絵」ですよね。やっぱり『レイマン』はけっこう。
ラブムー:
『レイマン』は『レジェンド』が素晴らしいって知り合いのゲームライターさんに勧められて。そっちはできてないんだけど。
よごえむ:
私もまだ『オリジン』しかやってないんで。
ラブムー:
それはちょっとわかる気がします。
よごえむ:
あと、あれですね、ちょっと今回語るにあたっては、ちょっと手に負える人がいないかもしれないですけど、一応アクションの3Dパックマンももう何作かは出てるわけじゃないですか。
canavis:
はいはい。
よごえむ:
だから、その、よく2Dマリオ・3Dマリオとか、2Dゼルダ・3Dゼルダとか、2Dソニック・3Dソニックとか、よく比較されるわけじゃないですか。なんか2Dパックマン、3Dパックマンみたいな観点からこう比較したものとかもあればなんか聞いてみたいですね、人にそういうのは。
ラブムー:
それで言うと、お2人はプレイされてるかわかんないけど、パックマンの抱き合わせでゲームセンターにいるパックマンみたいなのが最近、去年?出て。なんだっけ、『パックランド』もできるやつ。
よごえむ:
あれですか『パックマンミュージアム+』。

ラブムー:
『パックマンミュージアム+』だ。そうそうそう、『ミュージアム+』でできるやつで、パックマン…ごめんなさい。ちょっと若干酔っぱらって記憶が曖昧になってるんだけど(笑)、スマホバージョンで出たパックマンをコンシューマーに移植したやつ。
よごえむ:
はい、『ミュージアム+』、私も今回の配信に向けてちょっと買ってやってたんで、色々。
ラブムー:
じゃあできるかも、『パックマン256』っていう。
よごえむ:
『256』ですね。あれすごい面白かった。

ラブムー:
あれよかったですよね。
よごえむ:
はい。あれはめちゃくちゃ面白いです。
ラブムー:
あれはなんか現代のパックマンとしてすごい。しかもある種のアートだなと思う。
よごえむ:
そうですね。『スペースインベーダーエクストリーム』とか、あと『テトリスエフェクト』とか、ちょっとそういう気がある感じもあります。
ラブムー:
あるある。そっち系。ちょっとチャットのところに貼るんで、ぜひ。今聞いてくださってる方も。まだちょっと放送できますか。ちょっと飲み物を取ってきたいんですが、まだ続けて大丈夫でしょうか?
canavis:
はい、まだ全然オッケーですよ。
ラブムー:
はい。じゃあちょっと飲み物取ってきます。
よごえむ:
でもなんかあれですよね、システム的な、多分その『パックマン256』とかは、ちゃんと昔の『パックマン』のゲームシステムを使って いるっていう感じではあるんですけど、キャラクターとしてのパックマン、アスレチック的な、アクション的なパックマンとかの視点でももうちょっと比較とかがあると面白いかなと思いますね。2Dアクションとしての『パックランド』とかと、3Dの『パックマンワールド』とかそういう視点での話とかもできると面白いかもしれない。
canavis:
そうですね、『パックランド』。そういえばちょっと上からの、マリオと違う視点の画面構成って、『ワギャンランド』からも継承されてるなって思いがあって。
よごえむ:
そっか、『ワギャン』もナムコですか。確かにそうですね。パックマンに限らず、ナムコの2Dアクションって、そもそもどういうのがありますかね。私、実はあんまりナムコに馴染みがないんですよね。
canavis:
『ワギャンランド』が2Dであと、なんだろうね、マリオ的な全年齢が遊べるような横スクロールのアクションゲームって、『妖怪道中記』とかもそうかな。あと『風のクロノア』はやっぱり大きいですかね。あと『ワギャンランド』。
よごえむ:
『妖怪道中記』もあれですね、ちょっと奥行きがありますね。やっぱり見てみると。
ラブムー:
『妖怪道中記』は素晴らしいっていうか、『パックランド』並みに印象的なゲームではありますね。
canavis:
『パックランド』の画面の視点がちょっとマリオと違って視点がちょっと上からになってるかなって。
ラブムー:
canavisさんは『妖怪道中記』やってる?
canavis:
『妖怪道中記』はなんかPCエンジンでやりましたね。
ラブムー:
え、それはめちゃめちゃレアだと思うけど。
よごえむ:
『パックランド』はPCエンジンでも出てますよね。
ラブムー:
出てますね。あれはかなりアーケードに近いらしくて、自分はプレイできてないんだけど、PCエンジン版が1番好きっていう人もいて。
よごえむ:
やっぱりアーケードのナムコが好きな方は、割とPCエンジンを結構評価するか。
ラブムー:
そうそう、さっきなんか配信してる時に聞いたんだけど、『源平討魔伝』もPCエンジン版が出てるらしくて。
よごえむ:
そうですね、ファミコン版が全く違う。
ラブムー:
ファミコン版は、だってボードゲームですから(笑)。
よごえむ:
そうですね。そういうところも含めて、やっぱり皆さんの評価は高いですよね、PCエンジン。
ラブムー:
PCエンジンは、だからそういうナムコゲーの。でもそれぐらいじゃないかな。『パックランド』と『源平討魔伝』と『妖怪道中記』ぐらい?
よごえむ:
あと、『ワンダーモモ』。
ラブムー:
『ワンダーモモ』プレイできてないや。面白いですか。
よごえむ:
いや、私もやったことないんですけど。でも確かに評価は高いですよね。全体的に。
canavis:
あとキャラクターゲームになっちゃいますけど『平成天才バカボン』か。
ラブムー:
え?『天才バカボン』?
canavis:
『天才バカボン』のゲームがあるんですよね。
ナムコからファミコンとゲームボーイで出してるやつで。
canavis:
なんかあんまり語られてないんですけど、すごいゲームでして。
ラブムー:
『天才バカボン』。ゲームボーイアドバンス?
canavis:
ファミコンで出てます。ファミコンとゲームボーイで。自分がやったのはファミコン版なんですけど、後で動画で見てほしいんですけど。ゲーム内容はナムコ版の『プリンスオブペルシャ』なんですよ。
ラブムー:
ナムコなんだ、これ。こんなのがあったんだ。知らなかった。91年。
canavis:
91年で、ファミコン後期なんで、グラフィックもちょっと高いレベルになってて、ゲームのテンポっていうか、操作がマリオ的じゃないんですよ。
ラブムー:
うん、なんて言うんだろう、これは…。
canavis:
まあ『プリンスオブペルシャ』ですよね。途中でボスと戦うところだけ戦闘が発生するってのが『プリンスオブペルシャ』的っていうか。
ラブムー:
うんうん、パズルゲームっぽさもあるのかな、けっこう。よごえむさん、これ知ってました?
よごえむ:
前にcanavisさんから話を聞いたことがあって。
canavis:
はい、『プリンスオブペルシャ』だったっていうのがあって。バカボンを使ってキャラクターゲームで、ファミコンでってなってくると、マリオ的なゲームをイメージするじゃないですか。マリオとかロックマンとか。だけどなぜかファミコンのバカボンは、『プリンスオブペルシャ』フォロワーのゲームになってて。
ラブムー:
ダッシュもあるんだ。
canavis:
はい、ダッシュもあるんですよ。そう、これもボタンで押してダッシュするっていう。
ラブムー:
いや、これなんか思ってたよりよくできてそうだけど、当時だったら絶対やりたかったけど、今やるのは辛そうだなっていう感じはある。正直。
canavis:
結構辛いゲームではあります。
ラブムー:
なんか傘でなんかパラシュート落下みたいなのしてる。いま動画で見てて。いや、これなかなか味わい深いですね。今やったらできないかもしれない。
canavis:
高いところが落ちるとダメージを食らうんですよね。
ラブムー:
うんうん。
canavis:
だから傘を使って降りないといけないんですよ、いちいち。
ラブムー:
ダメージを軽減するってことか。
canavis:
なくすためにこう。なんかちょっとPCゲームっぽいっていうとあれですけど。
ラブムー:
うん、ぽいぽい。なんか今、Steamとかで、これに近いの出したら売れそうな感じもする。
よごえむ:
それをバカボンでやってるっていうのが。
ラブムー:
今やったらきっと、なんかちょっとね、『アトランティスの謎』を思い出すようなところもあるかな。『アトランティスの謎』って知ってます?ゲームもなんか非常にマゾ感が強いっていうか、個人的に愛憎溢れる…あ、entupsetさん
アーケード系ならマーベルランドなどもありますね
よごえむ:
はい、ありますね。これも移植されてたかな、『マーベルランド』は。
ラブムー:
ありがとうございます。『マーベルランド』今ちょっと調べてみます。横スクロールアクションですよね。あ、これもナムコなんだ。結構知らないの多いな…。
あ、これ知ってる知ってる、でも知る人ぞ知るっていうか、結構ファンが多いですよね、これは。
よごえむ:
うん、そうですね。隠れたファンがいる隠れた名作的な感じの。
ラブムー:
Wiiの時にバーチャルコンソールであった気がする。これ。
canavis:
『マーベルランド』も『パックランド』もそうなんですけど、画面がポップな分ノスタルジーを感じるというか、デパートの上にあるゲームコーナーのことを思い出しちゃうっていうか。
よごえむ:
『マーベルランド』がそもそも遊園地っていうテーマがあるので。
ラブムー:
あるんですか。
canavis:
『パックランド』も『マーベルランド』も、なんかノスタルジーがあるっていうか。
もしかしたら、リアルタイムでやってた人もゲーム画面から謎のノスタルジー感を同時に味わってたんじゃないかって気もするんですよね。
よごえむ:
なんかね、書き割り感があるんだよな、書き割りっぽさががあるっていうか。
canavis:
『クインティ』もすごいノスタルジー、すごいポップさと。あのポップさの感じが現代にはないポップさなんですよね。
ラブムー:
わかる。軽さみたいなね。
canavis:
そう。なんか、なんていうか、アメリカの文化みたいなものにまだなんか憧れがすごいあった時代のポップさなんですよね。『クインティ』も『パックランド』も。
ラブムー:
うんうんうん。わかる。軽みっていうかね。今、entupsetさんが言った『マーベルランド』もそうなんだけど。さっきよごえむさん言ってた『レイマン』とかもそうなんだけど、軽みみたいなものがありますね。
canavis:
デパートの上のフードコートって、今はなんかラーメンとかあるけど、昔はなんかポップコーンとか、ホットドッグとか、ハンバーガーで。
よごえむ:
ジャパナイズドはされてるんだけど、やっぱり単純にそういうものに対しての屈託のない憧れは確かにあると思う。
ラブムー:
確かにそうですね。あの感じはいまあまり無いし、日本のポップカルチャーで言うと、あの感じ、SEKAI NO OWARIとかに引き継がれてるのかもって思う。
canavis:
あの時代の感覚って、欧米に対する憧れがやっぱり昔はまだ今より強くて、そのポップさはナムコのゲームには、『パックランド』しかり引き継がれてると思うんですよね。
ラブムー:
それはあるかも。で、自分は世代的にそういうものへの憧れはものすごい強い時代だったから、自分もやっぱりそういうのがずっとあるし。それはもはや無いものなのかもしれないけど。
canavis:
うん、ですよね、ポップコーンの機械だったり。
よごえむ:
うんいまだと無いかもしれないですね。私も歳は違うけど、なんとなく残滓は感じるところもあるし。
ラブムー:
感じます?よごえむさんの中にも。
よごえむ:
わかりますよ、なんかそれはわかる。ユートピアというか。
ラブムー:
やっぱ僕、アメリカに感じるものなんだけど、今のアメリカじゃなくて。
よごえむ:
そうそう。そうだし、それも実際にその当時の本当のアメリカかどうかはともかくとして。
ラブムー:
そうかも。なんか、カリカチュアライズされた別のアメリカ。
よごえむ:
日本人のフィルターを通して見た、日本から見たアメリカに対する憧れを日本的にこう表現したものがそのイメージになってるってところはあって。
で、それの感じの結構身近な感じがあるのが多分ナムコで、もうちょい大人びてると、セガっぽくなるんだと思う。『アウトラン』とかはもうちょいこう…。
ラブムー:
でも、アメリカはなんか、カルチャー誌的なアメリカなんですよね。雑誌『ポパイ』とかのアメリカ。
あの映画のシーンに憧れて、アメリカの深夜飯を作ってみよう。次の日はアレンジレシピも楽しめる。#popeyewebhttps://t.co/ECos8rfFVM pic.twitter.com/ZJB9QOsXdn
— POPEYE (@POPEYE_Magazine) June 1, 2024
よごえむ:
本格的な本当のアメリカなのかっていうと、ちょっと違うんだけど、やっぱり。でももうちょいナムコより、若干のリアリティがある気がする。
ラブムー:
あるあるある、本当に。ポップコーンを買ったり、映画を観たりとか。映画の影響が大きいのかな。僕はだから、そういう意味ではずっとそういう架空のアメリカへの憧れを抱き続けたいなという気持ちはあるんだけど、なかなかそれに応える、応えてくれるような作品っていうのは少ないですね。
canavis:
こういうのの究極系が自分は『MOTHER2』だったんですよね、やっぱり。
ラブムー:
あー、それはわかるな。すごく。でも、あれって糸井重里の目を通したアメリカなんだよなっていう感じもする。
canavis:
まあそうなんですけど、やっぱりロールプレイングゲームってなってくると、『パックランド』も物語はあるんですけど、とはいえ物語がないっていうか。
ラブムー:
それで言うとやっぱり究極で言うとcanavisさんが、第1回でやった『moon』なのかなと思う。アメリカみたいなものを超越して、ある種の桃源郷っていうか、究極の場所みたいな。
canavis:
あれはなんか、この時代から続いてたものの系譜の最後に『エヴァンゲリオン』があるみたいな。
ラブムー:
『エヴァンゲリオン』感も確かにある。だからあそこにはすべてがある感じがするんですよね。
canavis:
最後の締めがやっぱり、『パックランド』とはなんか真逆のものに最後辿り着いちゃうって感じがちょっとあって。
よごえむ:
『moon』は壊れた後の何かって感じがすごくある。
ラブムー:
え、でもそれがリアルですよね。
よごえむ:
もちろんそうですね。
canavis:
『パックランド』はテーマパークの中にいるけど、『moon』はやっぱりテーマパークの外に出なきゃいけないっていうとこがあって。
ラブムー:
そう。『moon』は毒がある。毒というか、現実をちゃんと見せようっていう。だから『エヴァンゲリオン』でいうと『Air/まごころを、君に』的なものがすごいある。
canavis:
テーマパークを外から眺めてる人のゲームですよね、『パックランド』は中にいる。
『moon』はテーマパークかもしれないけど、テーマパークなんだよな、なんですよね。ああ、ここってテーマパークなんだよなっていう。
ラブムー:
確かに。でも、僕は『moon』のそのテーマパーク的なところにずっといたいなと思うところがある。ROMの基板を見たくないっていうか。
よごえむ:
なるほどなるほど。それもわかりますよ。だし、そもそもそういう疑いが多分ないので、『パックランド』的なものっていうのは。
ラブムー:
ないないない。ないけど、でもそれってすごい強みだと思うんですよ、『パックランド』の。「永久機関」っていうか。
よごえむ:
やっぱりいま多分そういうのがなかなかないですよねっていう話っていうのは、そういうものを強度のあるものとして出すっていうことがむしろできないというか。
ラブムー:
それはゲームとして?
よごえむ:
何かしら裏付けがないといけないかのような、掛き割りが裏が無いと、描いておかないといけないっていうところがあって。
ラブムー:
嫌な言い方すると意識高くないといけないっていうのかな。メタ視点に立たないといけないみたいな。
よごえむ:
むしろこの一個の『パックランド』的な世界を作るっていうのが、やっぱりなんか別の強度があるはずなんですよね。
ラブムー:
でも、現代においてそれは困難になってるってこと?
canavis:
難しいところなんですけど、仮にして、マリオぐらい徹底的に––『ペーパーマリオ』とかは別にして––『マリオワンダー』とかになるんですけど、ストーリーを語る意味があんまりないものを作るってなってくると、逆に解像度がすごく要るような時代になったんじゃないかなって気がして。バックボーンを知らなくても楽しめるみたいな。
ラブムー:
いやだから、かなり厳しい時代になったってことですよね。マリオぐらいにならないと。
canavis:
難しい。マリオぐらいになって。ソニックとかだとちょっと語らなきゃいけないっていうか。
ラブムー:
ソニックは語るんですか?
canavis:
語ってるよね?
よごえむ:
ソニックは語るようになりましたよね。
ラブムー:
『ソニックアドベンチャー』やってないからなぁ。
よごえむ:
『アドベンチャー』から語るようになったかなっていう気はありますけど。やっぱりスーパーマリオに比べると、割りとかっちりとやってるなっていう気がしますね。
canavis:
ソニックとかシリアスを挟まないとちょっといけないっていうか。メガドライブのソニックみたいな、メガドライブの『ソニック2』ぐらいのポップカルチャーの憧れを無邪気にゲームにただただ入れてればいいっていうのが、ちょっともう難しい。

ラブムー:
もう通用しない?
canavis:
シリアスというか、批判じゃないけど。たとえば『カップヘッド』とかって毒があるじゃないですか。
よごえむ:
うん、ある。明らかに毒がありますね。
canavis:
ありますよね。で、『ロックマン』も『ロックマンX』とかになってくると、ちょっとシリアスに入らないと、って感じになって。
ラブムー:
そう!だからやっぱりそういう意味で、大人にならなきゃいけないっていうことなんじゃないですか。やっぱり大人っていうか、意識高くならなきゃいけないっていうか。
canavis:
ポップなものを表現する時にちょっと批評が入んないと。
ラブムー:
入る入る。だからパックマンはそれをもう拒否したんじゃないですか。もう。『パックランド』とパックマンはもうそれを拒否して、永遠のなんかライ麦畑に居続けることになっちゃったんだけど。でも、ソニックとマリオはまだそれをやってて。マリオなんてすごいと思う、そういう意味では。最新作の『マリオワンダー』でも、ちゃんとその夢の世界みたいなものも表現し続けているわけだから。
canavis:
でも、マリオも今までのマリオに対してちょっと変わってきて。やっぱり、ピーチ姫っていうのがさらわれるだけっていう設定から外されてて、ピーチ姫も別のゲームではあるけど、主人公になったりとか。
よごえむ:
マリオの場合特定のイメージが逆に無いっていうか、やっぱり。マリオの映画が出た時もそうでしたけど、マリオってこういう人だよねみたいなイメージがないから。
ラブムー:
ない。「無」っていうこと?
よごえむ:
いろんなものに変われる、変化できるっていう強みがあって。パックマンの場合は割と早い段階でキャラクター性を獲得したので。そこから意外と広げないで、毒みたいなものとかも入れずに割と今に来てるっていう。ある種ピュアな。
ラブムー:
ピュアですね。だって今の公式パックマンのXのツイートとか見ると、パックマンがいろんなところに行くんだけど、もう本当、何も批評性とか何もないですもんね。「パックマン楽しそうだな」っていうみたいな。
今日は #防犯の日 😎
— パックマン公式_JP (@BNEI_PACMAN_JP) July 18, 2024
防犯対策には自信のありそうな #パックマン ですが...?
皆様も防犯対策は万全で挑みましょう!✨#pacman pic.twitter.com/csKxAWpXXG
よごえむ:
そこらへん言うと、ソニックって最初からクールみたいなキャラクターを、最初から作るつもりで作ってて。世界観みたいなことで言うとソニック3以降からは、割と自然を守るみたいなところとかも、意外とあったりとか。
ラブムー:
そうなんだ、エコ的な感じ。ソニックはなんか戦ってるってイメージある。確かに。
よごえむ:
ソニックって国際的というか、ワンワールド的な感じの「世界の守護神」みたいな感じがちょっとあるんですよね。マリオとかあんまないんだけど、そこらへんは。
ラブムー:
たしかに。
よごえむ:
なんかドラゴンボールの孫悟空みたいな感じにちょっとなってきちゃって、ソニックが。
ラブムー:
それはよごえむさん的には遺憾なことなんですか?
よごえむ:
遺憾でもないけど、でもそろそろなんか別のがあってもいいかなっていう。
ラブムー:
でも、ソニックってそういう存在ですもんね。やっぱりハリネズミのように、こう、回り続けて、戦い続けなきゃいけないし、もう最初から決定されてる気がする。そういう意味では、もう、パックマンは永遠の夢の中に。
canavis:
マリオもソニックもちょっと面白いことに、映画版だとなんかダサいキャラクターになってるってところがちょっとあって。ダサいって言うとあれだけどマリオもソニックの映画版も弱い人間っていう。
ラブムー:
ソニックの映画版は見てないからわかんないなあ。
canavis:
ソニックの映画版も、言い方が難しいですけど中二病の男の子みたいに見えるというか。もっと言うと、小学6年生みたいなキャラクターなんですよね。力を持った小学6年生みたいなのが。
ラブムー:
ちょっとパワーを持て余してるみたいな。
canavis:
持て余しちゃってっていう。で、バディを組むのが中年男性ってところがソニックの映画の面白いところで。小学6年生のイキった、なんか微笑ましい子とおっさんが解決していくみたいな話なんですよね。
ラブムー:
そのおじさんは誰なんですか?
canavis:
実写の。映画のオリジナルキャラクターで。
ラブムー:
じゃあソニックはずっと小6的な。
canavis:
小6的な。クールなキャラクター像ではないんですよね。
よごえむ:
クールになりたいやつですよね。
canavis:
クールになりたいけど、なんかなりきれないっていう、ゲームとちょっと違うというか。マリオも、生活があまりうまくいってないしっていう。
ラブムー:
マリオはそうですね。僕、ルイージの方がある種、色々感じちゃうんだけど。屈折というか…なんていうんだろう、ミドルエイジクライシス的なものとかを持ってる気がして。
canavis:
映画版のマリオは、映画になっちゃうと、マリオもソニックも自分のキャラクターに対する批判・批評というか。
ラブムー:
批評性みたいなこととか。
canavis:
ちょっと、あるかな。そんな感じがするっていうか。
ラブムー:
無邪気ではないってことだ。パックマンは無邪気だから、常に。
よごえむ:
パックマンも映画になってくると、どうなんでしょうね。
ラブムー:
パックマンの映画ってあるんでしたっけ?
よごえむ:
映像化はされてるんで。
ラブムー:
されてるされてる。アニメありましたよね。
よごえむ:
そうですね。CGアニメのもあるし、昔『パックランド』はそもそもアメリカでアニメ化されてるんですもんね。あとは単純にゲームのアイコン的なキャラクターとしてね、出てくることもあるし。ピクセルとか。
ここらへんアニメ見てないんで、私わかんないんですよ、どういう風にパックマンが描かれてるのか。
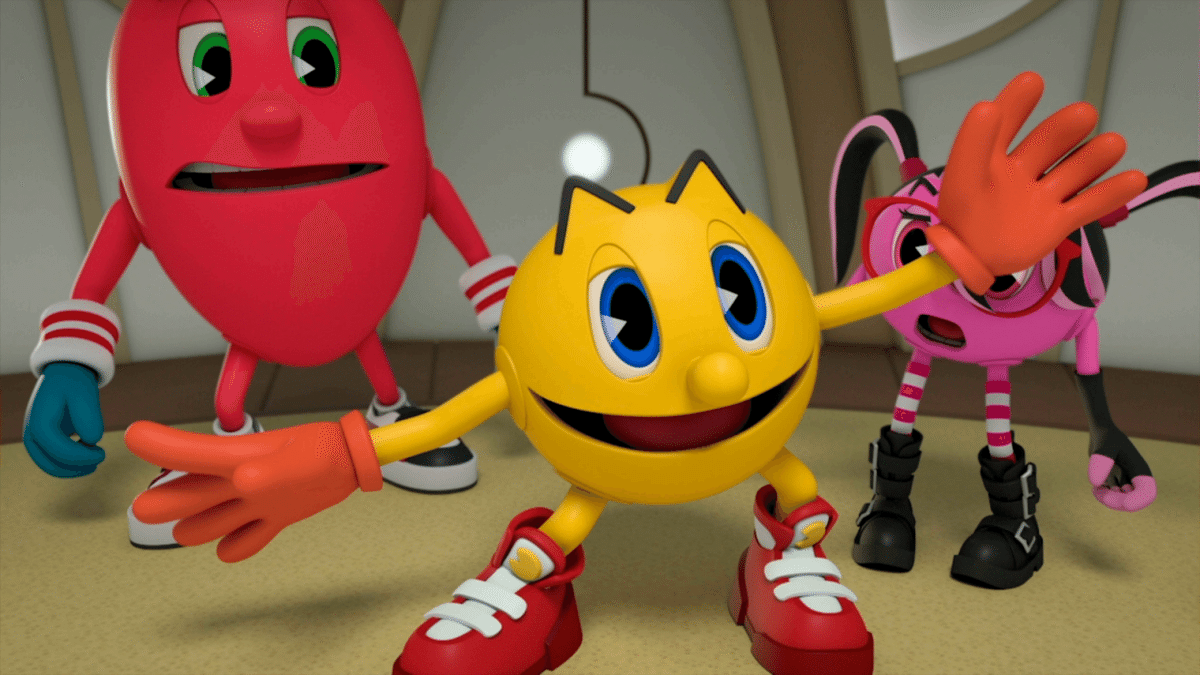
ラブムー:
いくつか見たけど、やっぱりパックマンなんですよね。なんていうか、何もない。「無」なんですよね。マリオとかとは違う。
よごえむ:
喋るんですか?
ラブムー:
喋る喋る。だからアメリカの高校生みたいな感じなのかな。
よごえむ:
ああ~。
ラブムー:
だからまあ、キャラクタライズドは失敗したんですよね、パックマンは。だから、ソニックとかマリオに比べると本当にパックマンは微妙なキャラで…メディア展開的には失敗したっていう…。
よごえむ:
何かあれかもしれない、パックマンのある種キャラクター的な面でも商業的な面でも、姿を変えたやつって、もしかしたらカービィなのかもしれないですね。
ラブムー:
あー、『星のカービィ』。
canavis:
なんかね、食べるってことが。
ラブムー:
あー、でもそれ、凄く鋭い意見かもしれない。
よごえむ:
カービィの付け入る隙のある感じと、どこにでも何とでも親和性があるっていう。
ラブムー:
わかるわかる、遍在する感じっていうか。カービィはパックマンなのかも(笑)。カービィはパックマンっていうか、パックマンを換骨奪胎した存在なのか。
よごえむ:
なのかもしれないなって、今ちょっと思いましたね。
ラブムー:
それ、でもすごい、素晴らしい指摘かもしれない。素晴らしい指摘だけど、僕はカービィがそこまで好きじゃないから(笑)、ちょっとあれなんだけど。
よごえむ:
いや、だからなんかやっぱ違うんだと思うんですよ、パックマンの中にある純粋性みたいなものとは、かなり違うんだと思うし。商品展開的な意味でもキャラクター展開的な意味でも結構違うキャラクターだなって。
ラブムー:
でも、カービィっていう存在を創設するときにパックマンっていう存在は確実にあったのかもしれないですよね。
canavis:
あとパックマンはこう、 アメリカのコミックス的なキャラクターがルーツにあると思うんですよね。うんうんうん。でもカービィは多分サンリオなんですよね。だから要はカービィの方が日本人が持ってるメルヘンっていう世界観の先にあるから。
ラブムー:
いやそれはそうですけどね。カービィの女性ファン層ってめちゃめちゃ多いんですよ。これはなんか自分は前に仕事で調べたんだけど、本当にカービィって女性ファンがめちゃめちゃ多くて、だからサンリオのファンとかなりかぶるところはあると思う。
canavis:
ある意味、なんかこう、カービィってなんかマリオより映像化もあって、多分マリオよりキャラクター展開ってコントロールしやすいと思うんですよね。
よごえむ:
キャラクタービジネス的な意味で言うと、本当にカービィってマリオ以上に成功してるキャラクターだなって思います。
canavis:
なんか確かにね、やっぱなんかこう、キャラクターのルーツみたいなものっていうのが、やっぱ日本の人が得意とするものなんで。
ラブムー:
いや、でもカービィってすごい可愛くて、あざとくて、だけどすごい無っぽいじゃないですか。虚無感っていうか。
canavis:
でもカービィは、とはいえ毒があるので。
ラブムー:
そうそう、あるあるある。
よごえむ:
その「毒もある」っていうところも含めて、やっぱりパックマンとは違ってて。逆に言うとパックマンは毒がないから、その毒のないところが好きっていう人のことももちろんわかるんだけど、その毒のある感じのところっていうのもあるし、キャラクターとしての展開としては、非常に有効だった。
ラブムー:
そう、優れている。毒がないと生き残れないっていうことなのかもしれない。だからパックマンは生き残れなくて、カービィは生き残り、人気を博したってことなのかもしれないなと思うけど。
canavis:
ちょっと話に戻っちゃうんですけど、パックマンはやっぱアメリカのキャラクターを意識してるから、日本人がアメリカの生活をイメージするのは限界があるっていうか。日本の人にもできるかもしれないんですけど、ミッキーマウスのシリーズをやっていきましょうって、ちょっと難易度高いと思うんですよ、日本で。
ラブムー:
スヌーピーとかね。
canavis:
スヌーピーのオリジナルのキャラクター展開をしていきましょうって。
ラブムー:
そうですね。だって『ピーナッツ』よりパックマンが人気が出ることはまずあり得ないわけだから、そういう意味でも限界はあるのかも。存在に。
canavis:
日本オリジナルのスヌーピーをやりましょうってなったら、『コボちゃん』になっちゃうみたいな、難しいと思うんですよね。
ラブムー:
『コボちゃん』になるんだ(笑)。まあでも、『コボちゃん』かもしれない。
canavis:
だからアメリカナイズされてるキャラクターを日本人がなんかこう展開させようって、結構難しいのかなって。
ラブムー:
それはそうかも。まあだからスヌーピーが限界、なのかな。
canavis:
スヌーピーは輸入品だから大丈夫なんですけど。
ラブムー:
『コボちゃん』なのかなそれは……なんか他にありそうな気がするけど。『クレヨンしんちゃん』とか?
canavis:
『ピーナッツ』っていうか、植田まさし先生は多分『ピーナッツ』の影響をかなり受けてるってだけですが。
ラブムー:
そうなんですか。
canavis:
絵の感じが。あと話のナンセンスさが。
ラブムー:
そうですね。うんうん。確かに。
canavis:
まぁそれは置いといてって話です。すいません。はい。
ラブムー:
そうですね(笑)。だから毒が必要で。カービィはじゃあ、パックマンを換骨奪胎して、生き残ったというか人気を博した国産パックマンってことか。
よごえむ:
まあパックマンは…。
canavis:
国産ですけどね。
ラブムー:
僕の中では、パックマンは日本のキャラクターではないんですよね。どちらかというとアメリカの存在なんですよね、パックマンって。
よごえむ:
アメリカ的なイメージを持っている、帯びているキャラクター。
ラブムー:
そうそう。だから、かなりカービィとは異なる存在なんだけど。でも、やっぱりそうなんですね。うーん、でもそれ、すごい指摘だな。カービィがパックマン、パックマンを換骨奪胎したというか、パックマン的な存在として人気を博し続けている。で、パックマンは死んだっていう。パックマン・イズ・デッド。
よごえむ:
でも、パックマン自身もかなり女性からのゲームとしての人気が非常に高かったっていうのは、歴史的に知られてることではある。
ラブムー:
でも、かつてでしょ、それ。今のZ世代のパックマンのパックマンって言ったって、それなんですか?ってことになるんじゃないですか。
よごえむ:
もちろん。それはかつて。だから、そういう呼び水として呼び込むことに関しては、やっぱりちゃんと成功したっていうところはあって。
ラブムー:
パックマンの功績。
よごえむ:
でも、そのピュアさみたいなところっていうのは、逆にいまは変わるかどうかっていうよりも、むしろそこをずっと大事にした方がいい気もしなくもないですね。
ラブムー:
それでいうと、ちょっと最後にというか、これは言いたいんだけど。ニンテンドースイッチで、この間まで『F-ZERO 99』が出る前に『パックマン99』っていうゲームがあって。あれ僕すごい大好きだったし、パックマンを現代においてみんなにその魅力を伝えるのに凄く適したゲームだと思ったんですけど、配信中止になっちゃったんですよ。
よごえむ:
そうですね。
ラブムー:
だから、結構そこですごい挫折感というか、パックマンは終わった。パックマン、あれはパックマンを現代に蘇らせようとする動きだったのかどうかわからないけど……『パックマン99』すごい面白かったんですよ。やりました?
canavis:
やったかな?『テトリス99』はやったか。『PAC-MAN99』はどうだっけ。
ラブムー:
でも覚えてないぐらいでしょ。で『F-ZERO 99』の方はけっこうやってるでしょ、canavisさん(笑)。
canavis:
1回やったんですけど、なんかちょっと合わなくて。
ラブムー:
そんなもんですか?合わなかった?
canavis:
なんかそんな、なんかががっつり掴まれるものってなかった気がする。
ラブムー:
なんで?「F-ZERO」すごい好きだったでしょう?
canavis:
好きなんですけど、なんだろうな、
ラブムー:
競い合う感じがダメだったってこと?
canavis:
「F-ZERO」が好きな理由って、まず『F-ZERO X』は言わずもがな、すごいインパクトがあるゲームなんですよね。
ラブムー:
64の?
canavis:
はい、64の。他の「F-ZERO」シリーズって、なんか基本的に攻略していくゲームっていう捉え方だったんで。
ラブムー:
ここでちょっと右に倒れるみたいな。
canavis:
そうそう。そうなんですよね。
ラブムー:
そういうんではないですもんね。なんかデスゲームっていうか。そういうものでは確かになくなってるけど。じゃあ、あんまりハマらなかったってことですね。
canavis:
基本的にマリオカートより『F-ZERO』が好きな理由って、もしかしたら攻略することとか、自分の中であるから。対戦するもんじゃないっていうか。
ラブムー:
よごえむさんは『F-ZERO99』と『PAC-MAN99』はやりました?
よごえむ:
やってないですね。どっちも全くやってないですね。
ラブムー:
え、それもまたすごい(笑)、それはもうやってられるかみたいな?
よごえむ:
いやいや、そういうことじゃないんですよ。あんまりそこまで『F-ZERO』に対しての思い入れがなかったのと、実はパックマンというかナムコ自体が––自分はラブムーさんと逆で––ナムコに出会ったのが結構遅かったっていうか、だから。
ラブムー:
何歳ぐらいの時ですか?
よごえむ:
やったっていう意味で言えば、小学生とかかもしんないですけど、でもちゃんと意識して、自分でゲーム買ってみたいな意味で言うと、多分中高ぐらいですね。中学生か高校生ぐらい。
ラブムー:
それは何のタイトルですか?
よごえむ:
多分『ソウルエッジ』とか『ソウルキャリバー』とか。
ラブムー:
『ソウルエッジ』ね。『ソウルエッジ』最高。PS版のですよね。いや、あれはナムコ感が凄くある良いゲーム。

よごえむ:
そこからで。もちろんすごい大好きなんですよ。『ソウルエッジ』も『ソウルキャリバー』も。ナムコのゲーム今もすごい好きなゲームたくさんあるんですけど。普通に面白いから好きだし、もちろんめちゃくちゃ評価してて大好きなんだけど。思い入れとかってなると、ちょっと変わってきちゃうんですよね。出会ったのが多分、遅かったからかもしれない。
ラブムー:
思い入れはないっていう。
よごえむ:
ノスタルジーみたいなのがあんまり多分ない。
ラブムー:
それはでも、世代的なものなのかな。
よごえむ:
もちろん、もっと小さい頃とかに…たとえば、なんだろう、なんでもいいけど、『風のクロノア』とかしてたら違ったのかもしれないです。けど、割ともう中学生・高校生ぐらいになってる段階で遊んでたので、面白いなと思ってハマったりして、『ソウルエッジ』とかもやってて、今も大好きな格ゲーだったりしますけど。
ラブムー:
今も『ソウルエッジ』やるんですか?
よごえむ:
今もたまにやりますよ。だからそれはあるんですけど。うん、だから、その、全体的なナムコに対しての
ラブムー:
思い入れがない?
よごえむ:
熱がそこまで、っていう感じですね。だから本当に、今回の配信に向けて『パックランド』も遊んだりとか、ここ1年くらいで、なんか結構、ナムコの古いタイトルを遊んでみようかなみたいな、色々知れて面白いなっていう感じですねいまは。
ラブムー:
僕が好きだったかつてのナムコは、現代にはもうないんだって思います。もうアーカイブになってしまったと思うんだけど。
よごえむ:
だから『パックマンミュージアム+』とかでいま遊んでみて、もちろんアレンジされてるものとかもあるんですけど、これらのゲームって往年のタイトルもそうだし、 往年のものを現代風にアレンジした、イメージを持ってきたものとかっていうのが、たくさんあると思うので。そういうナムコ性みたいなものっていうのを味わうっていう意味ではすごい良かったですね、自分的には。
ラブムー:
『パック&パル』はどうでした?
よごえむ:
『パック&パル』はね、なんか不思議なゲームでしたね。
ラブムー:
パックマンのガールフレンド(ミル)がでてくる。

よごえむ:
そうですね。なんか結構全体的に『パックマン』初代のもののアレンジ的なものがやっぱり多かったかなという。
ラブムー:
最初のやつの焼き直しみたいな。
よごえむ:
そうですね。で『パックマニア』とかもあったりとか。
ラブムー:
『パックマニア』はでもかなり、革新的なゲームではあったと思うんですよ。焼き直しではないっていう。ポリゴンを使ったパックマン。
よごえむ:
ポリゴンっていうか斜め視点。
canavis:
クォータービューですね。
よごえむ:
なんかジャンプができたりとかね。
ラブムー:
そうそう。僕はそこまで好きではないんだけど『パックマニア』は。

よごえむ:
基本ルールはあんまり変わらないので。
そういうものに対して触れたりとか、音楽とかも、この時のナムコサウンドってこんな感じなんだなとか。
ラブムー
じゃあ『パックマン256』は?
よごえむ:
『256』は面白いですよね。現代的なゲームとして、過去のものを作ってるっていうか。
ラブムー:
じゃあコレクションの中で1番好きだったパックマンは?
よごえむ:
あー、どれでしょうね…。
ラブムー:
PSのとかも入ってたと思うけど。
よごえむ:
あれも面白かったですね『パックンロール』とかもね。『パックンロール』面白いけど…。
ラブムー:
パックマンじゃなくてもいいだろうっていう?

よごえむ:
っていう、なんかちょっと疑問符はあるんですけど。でも、あれかもしんないですね『パックマン・チャンピオンシップエディション』。
ラブムー:
あ、でも、スイッチで配信してたやつ(PAC-MAN99)は、基本的にその『チャンピオンシップ』を踏襲してますよ。あれをオンラインでできるようにしたって感じで。音楽がテクノとかで凄くかっこいいんですよ。あと『ドルアーガの塔』にもなったりするエキスパンションセットを2500円ぐらいで買うと、『マッピー』とかいろんなナムコゲームの音楽をつけられて、自分もマッピーになったりするっていう、めちゃくちゃ、古参ナムコファンをもう取り込もうとしてる姿勢が感じられたんだけど。
よごえむ:
そうですね、それを良しとしてみるかどうかですよね。なんか、むしろ私の場合は後から出会ってる人間だから。どっちかっていうと、めちゃくちゃ興味があるというわけじゃないけど面白いかなとは思いますけど。でも、そうじゃないんだよなって思う人もいるかもな、とは。

ラブムー:
僕はその、よごえむさんやってるかわかんないけど、ナムコ関係でいちばんやってほしいなと思うのは、『妖怪道中記』と『源平討魔伝』。別に和だからっていうことではないんだけど(笑)、雰囲気的に。もし機会があれば。
よごえむ:
そうですね。今も遊べるアーケードアーカイブスとかもあるし。
ラブムー:
canavisさんはあれですもんね。『妖怪道中記』も『源平討魔伝』もやってるもんね。
canavis:
はい、一応遊びましたね。
ラブムー:
うんうん。そっか。なんかちょっと話が脱線しちゃったけど。ナムコはだから自分にとっては大事なメーカーだけど、自分がかつて愛したナムコはイズ デッドだと思う。デッドというとあれだけど。
canavis:
そうですね、ちょっと時代的に変わらざるを得ないってところは、やっぱりありましたしね。バンダイとも、ってなってきて。
ラブムー:
今のバンダイナムコのゲームをやってナムコを感じたりすることっていうのは、ないからね。
canavis:
そうですよね。なんかハイブリッドな会社になっちゃいましたよね。でも、そうは言っても『アイドルマスター』も「テイルズ」シリーズも、ナムコから出てきたっていうことは不思議じゃないゲームではあるんですよね。
ラブムー:
「テイルズ」ってロールプレイングゲームのテイルズ?
canavis:
ナムコって多分大作RPGってものはなかったと思うんですけど。でも戦闘がアクションゲームみたいになってるっていうのは。
ラブムー:
なんだっけ、『貝獣物語』っていうのがナムコから出てた気がする。
canavis:
ありましたし、『女神転生』とかもあるんですけど。『女神転生』はアトラスに行っちゃったし、『貝獣物語』は確かハドソンに行っちゃったんですよね。
ラブムー:
canavisさんは『女神転生』も好きだったんですか?
canavis:
『女神転生』はやってないんですよ。やってないんですけど、でもテイルズは戦闘がアクションゲームみたいな。バトルのシステムがちょっと特徴があったりとかするってのは、なんか彼らが、ちょっとナムコっぽいっていうとあれですけど。
ラブムー:
(canavisさんの中の)ナムコっぽさってなんなんですか?
canavis:
ナムコっぽさって僕の子供の頃の印象なんですけど、ナムコのゲームって変なゲームを作ってるなって、なんか王道じゃないなって。なんかちょっとずらしてくるなって感じがするっていうか。『パックランド』もしかり。
ラブムー:
ちょっとニッチな感じ?
『ゼビウス』の話はすごいわかりやすかったんだけど。他になんか、ナムコっぽさってどういう意味なんだろうって思う。
canavis:
ナムコっぽさって何かっていうと、そうですね、なんなんだろう…。
ラブムー:
すごい知りたい。ナムコしかない、なんかカラーみたいなの。
canavis:
なんなんでしょうね、ナムコっぽさっていうと…『アイドルマスター』とかって、『子育てクイズマイエンジェル』とかが先にあったと思うんですね。
ラブムー:
それもナムコっぽさなの?
canavis:
『アイマス』とかのルーツってナムコが出していた『ゆめりあ』ってゲームわかりますか。ギャルゲーみたいなこと出してたりとかしてて。『アイドルマスター』に向けての布石もあったし、当時の アイドルマスターの受け入れ方って、ちょっとわかんないですけど、ナムコがまた変なゲーム出したぞ、みたいな雰囲気はちょっとあったと思うんですよね。
ラブムー:
第1作は2005年?
canavis:
アーケードゲームだったし、元は。『子育てクイズマイエンジェル』の流れを汲むギャルゲーというか。ナムコが出してもおかしくないような雰囲気も第一作は芽があったんだよなって気はしているというか。
ラブムー:
2005年はそういうムードがあったんだ?
canavis:
かな?『アイドルマスター』っていうのが、第1作目なんで、アイドルもののゲームって、多分あんまないと思うんで。
ラブムー:
自分の歴史にはないな。
canavis:
だから、こういうなんか先進的なゲームをナムコが出してくるっていうなんかものがあったから。第1作目に関してはナムコっぽいっていうか。ナムコって結構ゲームに関しての萌えの文化みたいなのも、結構最初からそれをポップにやってた会社だったと思うんで。
ラブムー:
そのイメージは自分は全然ないな、いや、ないっていうか、知らなかった。
canavis:
たとえば『ミンキーモモ』とか。
ラブムー:
あー、『ミンキーモモ』はありましたね。『ミンキーモモ』もじゃあ、繋がりなんですか。その『アイマス』の。
canavis:
そう。その流れだし、『子育てクイズマイエンジェル』とかもあったし。
ラブムー:
すごい勉強になる。
よごえむ:
『ミンキーモモ』じゃなくて『ワンダーモモ』。
canavis:
あ『ワンダーモモ』だ。そうだ、失礼しました。
よごえむ:
『ミンキーモモ』だと魔法少女アニメになっちゃいますよ。
canavis:
あと『ゆめりあ』とか。彼らが『アイマス』にたどり着くっていうのは、個人的には不思議なことじゃなかったんじゃないかなっていうか。当時の感じっていうか。
ラブムー:
『ワンダーモモ』『アイマス』っていう流れがあるのか。
canavis:
もっと言うと、なんかこう『ダンシングアイ』とか、色々あるような気がして。
ラブムー:
確かに。
canavis:
『アイドルマスター』自体も特殊なゲームだしねって、なんかその当時にしたら。
ラブムー:
canavisさんは『アイマス』がけっこう好き?
canavis:
いや実は、やってないんですけど。偉そうに語ってしまったんですけど、なんかあのゲームが出るってこと自体が、そんなに不思議なことじゃなかったんじゃないかなっていうか、当時。
ラブムー:
でも、アイマスの時って、もうバンダイと提携してた感じのイメージだけど、自分のなかでは。
canavis:
どうでしたっけ。
ラブムー:
わかんないけど。
canavis:
まだナムコの時代だった気がする。
よごえむ:
まだナムコだと思いますけど。もうでもほぼ合併が決まってたんじゃないですか。
ラブムー:
だって、そのバンダイとナムコが合併するっていうこと自体、僕はもう意味がわからないっていうか、別に悪いとかじゃないけど、もうなんていうか、自分の知ってるナムコではなくなったっていう感じだった。
canavis:
そうですね。
よごえむ:
平均化されたと思いますね。だから、バンダイナムコだけじゃなくって、結構いろんな会社がやっぱりそもそも残ってなかったりとか吸収されたりとかっていうこともあって。多分全体的に以前よりは平均化されているかなという風なところがありますよね、バンダイナムコ以外にも。タイトーとかもそうだし。
ラブムー:
タイトーはどうなったんでしたっけ。
よごえむ:
タイトーは今あれじゃないですか、スクウェア・エニックスの。
ラブムー:
中にあるんですか。
よごえむ:
たしかそうだと思います。あとハドソンもそうですね。コナミの傘下になったわけですし。
canavis:
ナムコっていうよりか、昔のゲームと今のゲームの作り方の違いだと思うんですけど。昔の、ゲームのアイデアって動詞で語られるみたいな、ワードあるじゃないですか。でも今はもうそれで語れるような感じじゃないっていうか。新規IPのゲームを作っても、死にゲーライクとかってなってきて。
ラブムー:
ソウルっぽいってこと?
canavis:
ルール1つで世界を変えてしまうようなゲームを作るのが難しくなってきたのかなって。
ラブムー:
なんか、そういうのは、自分にとっては『スプラトゥーン』が現時点での最後だったのかなって思うんだけど。
canavis:
ナムコで言うと『塊魂』。
ラブムー:
『塊魂』あんまりっていうか、ほぼプレイできてないな。でも、自分の親戚がいちばん好きなゲームだったって言うので、気になるんだけど。面白いんですか?
よごえむ:
『塊魂』は割と誰がやってもハマるみたいなところもあって、すごく間口が広くって、でもちゃんと極めようと思うと難しくて、っていう、面白さがあって。アート的な面白さもあるし、音楽もキャッチーだし。そこは割とパックマンとかみたいな感じはあるかもしれないですね。
ラブムー:
通じるところが。
canavis:
なんか、そういうゲームを作ろうとすると、やっぱちょっとインディゲーム的なものになってしまって。ナムコがやるのかって、できるのか、それをやるっていうのが。ちょっといま難しいのかな。『もじぴったん』的なゲームを作るっていうのが。
ラブムー:
いま『もじぴったん』の話をしようとちょうど思ってたんですよね。でもやっぱりいま思った、ナムコに対して感じてたのは、今で言うところの、いや、ちょっと前で言うところの「インディーゲーム的」なところで、自分はその、やっぱりマイノリティの人間だったから、どちらかというと。スーパーマリオとかコナミよりもナムコに。
ナムコがコナミよりマイノリティだったかどうかは実際のところはわからないんだけど、マイノリティに寄り添ってくれるような何かをナムコに対して感じていて。
だから自分がナムコシンパだったのは、結局自分がマイノリティだったからだなっていう風に思っていて。ナムコはバンダイナムコになった時に、もう自分にとってはもうそのマイノリティな存在ではなくなってしまって…ちょっと何言ってるかよくわからなくなってきたけど(笑)。
canavis:
やっぱなんか『パックランド』はマリオより先って言っても、『パックランド』にはやっぱりカウンターの匂いがするっていうか。ボタン操作で移動するってところは、やっぱりカウンターだなって。
ラブムー:
やっぱボタン操作のところが大きいのかな。ボタンの。
canavis:
ナムコの独特な感じってのは、なんかこう王道からやっぱりなんかちょっとずれちゃうっていうか。やっぱりテイルズにしても戦闘システムがコマンド式じゃないっていうところも、彼らが王道RPGを作ろうとしてても、なんか作れない感じがちょっと、『テイルズ』1に関してはなんかちょっとにじみ出てるかもしれないっていうか。
ラブムー:
『テイルズ』1?
canavis:
『テイルズオブファンタジア』ですね。
ラブムー:
「テイルズ」やってないからな。「テイルズ」は今からでもやるべきゲームですか?
canavis:
どうなんでしょうね。
よごえむ:
そこはなんとも言えないですけど。私は『ファンタジア』すごい好きだし。なんかcanavisさんが言ってることもわかるというか。ただ、逆に現代だと多分オーバーグラウンドすぎるんだと思うんですよね、その表現ってむしろ。
だからその当時としては、やっぱりカウンター的なところがあったってことは、当時の状況とかを見たらわかるんだと思うんですけど。多分、何も知らずにいま変わったゲームだと思って遊んでみると、––もちろんラブムーさんだったら時代背景とかわかると思うんで、あれですけど––そういう風な目で見ると、なんかすごいありきたりに感じると思うんですよね。
むしろ今、それがオーバーグラウンドになってて。だから、さっきおっしゃってた、そのマイノリティに寄り添ってた感じじゃなくなったっていうところっていうのは、やっぱりその、バンダイナムコになってからがオーバーグラウンドになってるんだろうなっていう。

canavis:
ていうか、バンダイナムコになったっていうよりかは、新規IPを作れない時代的なものってのがちょっと大きいのかなっていうのがあって。それとバンダイナムコになってしまったことが重なっちゃってっていう。
よごえむ:
まあまあ、そうでしょうね。
canavis
だから、バンダイナムコになったって、ロゴ的なものとか、ちょっとデザイン的なものとか、変わってしまったんで。無くはないけど、それ以上にちょっと時代的なもので。今もある意味セガらしさっていうようなものっていうのは、昔のセガと今のセガは全く違うし、スクウェアもエニックスもスクウェア・エニックスが継承してるものはあるけど、ちょっと違う。
ラブムー:
スクウェア・エニックスにはスクウェア、エニックスらしさっていうのはまだ自分はちょっとは感じるけど。最近の『ファイナルファンタジーⅦ リメイク』にしても『春ゆきてレトロチカ』とかもそうだし。「らしさ」みたいなのはあるかなと思うんだけど、バンダイナムコのカラーっていうのは自分は正直よくわからないですね。
canavis:
ある意味あんまり変わってないっていうのは、変わってないっていうか、原点回帰したかなっていうのは、フロムソフトウェアかなって。
ラブムー:
それは『エルデンリング』とかってこと?
canavis:
フロムソフトウェアって最初は硬派なゲームの会社。
ラブムー:
いや、そうですよね。そういう意味では変わってない。フロムソフトウェアは『キングスフィールド』出してる時と全然印象が変わってない。
canavis:
でもちょっと一時期、なんかこう、手広くゲームを出してたかなっていうのも、時期もちょっとあったと思うんですよね。決して高難易度じゃないっていう。でも、昔にまた戻って、高難易度のゲームっていうか。ニッチなゲームにまた戻ったような気がするっていうか。
よごえむ:
でもまあそれは、うーん…。
ラブムー:
僕はフロムソフトウェアは、なんかずっと印象は良かれ悪しかれだけど、変わらない感じがする。たとえば『エコーナイト』と『デラシネ』みたいなのも、イメージ近いし。
よごえむ:
別に全勢力を他のああいう硬派なタイプのゲームに傾けたわけじゃなくて、他のももちろん作ってるけど、基本的にどの世代でも硬派なものを作りながらも他のものもやるみたいなところもあるし。
canavis:
ああ、そうかもしれない。
ラブムー:
でもその硬派さみたいなものがもうなんかウリになっちゃってるところがある。
よごえむ:
今は逆にそうですよね。なんかソウル系というものがある種、系統立てられてて。で、『エルデンリング』とかの前評判も、やっぱりありきじゃないですか、ソウル系で、ダークファンタジーありきなものみたいな感じ。もうそこらへんのイメージが出来上がっちゃってる。
ラブムー:
そう、出来上がっちゃってるというか、頑固であり続けることがもう商業的な流れに結びついてる。だからすごい幸福な会社だと思うし、僕はフロムソフトウェアはすごい好きだし。だから何を言ったことにもならないけど、それを言うと。
よごえむ:
あと、さっきの合併したから変わったとかっていうのも、私も別にそれをそう思ってるわけじゃなくて。なんかそれは、さっき言ってたその時代的な流れみたいなところっていうのもそうだし。実態がどうあれ、やっぱりイメージっていうものがユーザーとかゲーマーの視線が多少なり変わると、会社自体も多分ちょっと変わってくると思うんですよね。
だから、ロゴとかってあくまでも見た目のものだけだっていうのは意見としてはあると思うんですけど、それが中身を変えちゃうことも多分あるとは思うんですよね、往々にして。だからそこらへんは、なんていうかイメージ的なものが変わったことによって…っていうのもあると思いますね。
ラブムー:
そうですね。いや、それはすごいわかるな。
よごえむ:
ちなみに私はラブムーさんとは真逆で、ナムコは割と自分が物心ついた時から、ずっとメジャーなものなんですよね。
ラブムー:
メジャーな存在なんだ、マイノリティーに寄り添う存在じゃなくて。それってバンダイナムコからじゃなくて?
よごえむ:
じゃないです。もう自分の中では、ゲームっていうものの中ではメジャーなものっていうようなものはナムコっていうイメージなんですよ。やっぱプレイステーションが勃興してるぐらいの世代なのが多分あるんだと思うんですけど。プレイステーションっていうのがメジャーなものにすげ替わった時代なので。それで、自分は任天堂ではなくてセガの方に思い入れがあって、熱を上げてたんで。だから自分にとっての(ラブムーさんが言う所の)ナムコはセガ。
ラブムー:
それはハードで言うと、任天堂の何が台頭してた時ですか?セガの何が台頭してたときですか?
よごえむ:
もうドリームキャストが終わる頃ですね。
ラブムー:
任天堂で言うと64かキューブの頃か。
よごえむ:
そうですね。ゲームキューブぐらいですかね。
ラブムー:
じゃあ、ちょっとアンチみたいな気持ちがあったんですか。任天堂アンチみたいな。
よごえむ:
アンチとかは全然ないです。任天堂アンチみたいな気持ちはなくて、若干、ちょっとメジャーなものが気に食わないなっていう気持ちもあって。その時はプレイステーションとかがあんまり好きじゃなかったりして。
で、やっぱナムコのゲームってやっぱプレイステーションでよく出てたんで、もうその頃ってもうだいぶメジャーだったんですよね、ナムコってもう。
ラブムー:
でも、その頃のナムコっていうと、プレイステーション2ってことですよね。
よごえむ:
プレイステーションからプレイステーション2くらい。
もうだいぶナムコってメジャーなんてイメージが自分の中にあったので。だから真逆なんですよ。だからさっき言ってたのと。
ラブムー:
でも、その頃の存在で言うと、自分もそうですよ。その頃のナムコっていうことで言ったら、完全に自分もそう。だから『もじぴったん』とか『ミスタードリラー』とか売り出した頃の、バンダイとの合併前のナムコって言うと、よごえむさんと同じ印象なんです。さっき言ったマイノリティに近い存在って言ったら、ほんとにファミコンとかスーファミ発売前までのナムコ。
よごえむ:
そうですね。だから、やっぱりそこら辺は、なんか世代的なものとか出会った場所とか時間とかのやっぱり違いで。
ラブムー:
それもあると思うし、よごえむさんがドリームキャストの頃のセガにハマってた頃っていうのと、僕にとってのナムコの印象ってのは結構近いと思う。
よごえむ:
だから、どの部分を知ってるかっていうところの違いがかなり如実に出たという気が。
ラブムー:
だから、やっぱりなんか、自分はナムコのいい時代に育てられた。今のナムコじゃなくて、ファミコン、80年代のナムコの良さみたいなものに涵養されたっていう意識がすごい強いのかな。
よごえむ:
やっぱり過去のものであっても、いま輝いてる会社っていうのは、過去自体がたとえその時にどうあれすごく輝いて見えるんですよね。どうだったかはわかんないけどっていうのか。やっぱ自分はそれは思ってたので。
さっきの話はなんか全然見てきた時代がとかがズレがあると、やっぱりそこに対する元々持ってる根っこのイメージが変わってくるっていう。それが面白かったですね。
ラブムー:
逆に、じゃあいまよごえむさんが1番輝いてるというか、1番好きな、好きなっていうとちょっとあれだけど、1番輝いてると思うメーカーはどこですか。
思い入れが強いとかでもいいんだけど、いちばん掛け値なしに好きなメーカー。
よごえむ:
掛け値なしに好きなメーカー…うーん。いや、思い入れはセガが。
ラブムー:
いちばん強い?今でも?
よごえむ:
今も強いですけど。うん。でもそれは多分、なんかラブムーさんの言うとこのナムコとかに近くて。バンダイナムコとナムコの感じの意味での、その古いものに対してのことであって。
なんだろうね…なんでしょうね。普通に好感を持ってて好きなメーカーはありますよね。サンソフトとかも好きだし。
ラブムー:
あ、今も?今のサンソフトのゲーム全然できてないな。『へべれけ2』もやってないからなあ。
canavis:
ゲーム会社に対する思い入れっていうものがなんかこう。Xboxってハードも売ってるけど、どちらかというとサービスっていうな感じじゃないですか。ソニーのゲームも時間が経てばSteamで買えるっていうか。
ラブムー:
たしかに、はい。
canavis:
ってなってきて、任天堂だけが任天堂のゲーム機で買える、いまだに。自分の目線ですけど。任天堂ファンはいても、なんかソニーとXboxのファンって公言するってことが、ちょっと昔より減ったかなって感じがする。ソニーらしさってなんか昔はあって、要は若さだと思うんですよね。それに対してもうセガはハードがなくなってちょっとイメージ的なものってのがピンとこない。
ラブムー:
確かに今のセガって言われても、そんなにイメージ湧いてこないですもんね。
canavis:
Xbox(Microsoft)って海外のゲームを出してくれる会社だったと思うんですけど。
よごえむ:
濃いメーカーだったなってのはある、昔のXboxは。
canavis:
でも今、海外のゲーム=「濃い」みたいなものないし、Xboxを通して海外のゲームをやるみたいな、良くも悪くもなんかこう。
ラブムー:
ゲームファンとしては、プレイステーションよりはXboxの方にいまだに、なんていうかワクワク感っていうか、未だにコアなゲームファンに応えてくれるっていうようなものを感じてはいますけどね。
プレイステーション5よりXboxの方に傾いているけど、気持ちは。ただ、実際的に便利なのはプレイステーションの方だし。
canavis:
でも、プレイステーションの若さ的なものはないなって。
ラブムー:
なんか、当時のインディー感みたいなの?『IQ』とか『Xi』とか、そういうのが出てた頃の。
よごえむ:
カウンターだったところからメジャー化していって、今はもう普通になってますからね。
ラブムー:
そういうゲームもちょっとありますよ。なんだっけ、なんだっけ、ちょっと『Xi』みたいなゲーム。
よごえむ
『Humanity』。
ラブムー:
そうそう『Humanity』とか。
よごえむ:
でもあれってカウンター的なものなのかな。
ラブムー:
あとPSVR2、PSVRとか。僕はもうVR大好きで、VR2はもう色々最悪だと思ってるから、ちょっとそこはもう評価できないんだけど。VRだってカウンター的なものだったと思う。
canavis:
うん。でもVRって言っても、もうすでにあるなって気がするというか。
ラブムー:
でもPSVRでしかできないゲームって当時いっぱいあって、それがものすごく良かったんですよ。PSVRでしかできない、もうSteamでもMETAQUESTでもできないようなゲームがたくさんあって、めちゃめちゃ尖ってたし、それはもうすごい当時の、いまcanavisさんが言ってたような、昔のPSの魂を感じるようなものがいっぱいあったんですよ。PSVR2からはほぼ無くなったけど。
canavis:
なんていうか良くも悪くも、信者的になるっていうのが、こう、任天堂とフロムソフトウェアだけになっちゃって。国内のゲーム会社だとね。海外もそうかもしれないけど。Ubisoftのゲームだから買うんじゃなくて、『アサシンクリード』だから買うとか、そういうことですよね。
ラブムー:
僕はUbisoftに関しては門外漢だからなあ。
canavis:
だから、そうそう。そういうことになって、UBIsoftのゲームだからじゃなくて、『アサシンクリード』だから買うとかだったりとか、ソニーのゲームだからじゃなくて、あれだから買うみたいな、なんかそういうことですよね。任天堂のゲーム全部買うわけじゃないけど、マリオだから買うとかさ、ゼルダだから買うとか。でも、マリオもゼルダも任天堂とすごく紐付いてて、離れないっていうか。
ラブムー:
紐付いてるっていうか、もうホントに任天堂は素晴らしいですよ。
canavis:
マリオ=任天堂っていうところになっちゃいましたよね。
よごえむ:
かなり属人的になっているってことですよね。そのタイトルに対しての属人感がとても強くて。
canavis:
『デス・ストランディング』もソニーのゲームだとは思わないじゃないですか。
よごえむ:
やっぱりクリエイター単位で買うとかってことももちろんあると思うんですけど。このタイトルのシリーズだから買うとか、もっと言えばこのゲームのコレクションだから買うみたいなことを思ったとしても、ナムコのゲームだから買ってみるかみたいな、そういうことはやっぱりなくなっているとは思いますね。
ラブムー:
減ってますね。で、いまcanavisさん言ったように、フロムソフトウェアと任天堂のゲームなら、買うっていうような気持ちは、自分の中にまだ残ってるな。
canavis:
その2社は、まだ残ってるっていうか。それは、良くも悪くもってところもあるんですけどね。なんかこう、任天堂に対して妄信してしまう人って、結構いるってのは、Twitter見てるとわかるんですけど。
ラブムー:
でもcanavisさんの中だったらオニオンゲームスのゲームだったら買うとかって、まだあります?
canavis:
実はオニオンゲームスのゲームが全部が好きかっていうと、そうでもないっていうか、買ってはいるけど。
ラブムー:
自分もそう。自分はどっちかってというと、オニオンゲームスのゲーム、ちょっと苦手、いや、苦手は言いすぎだな。ただ、西健一さんの作品が一番好きだから。
canavis:
そこまでは、ではないんですけど、もちろん好きなんですけど。
ラブムー:
うん。でも、もちろん『ストレイチルドレン』は買うけど。
canavis:
基本的にしょうがないんですけど、彼らに期待してしまうのは、やっぱりロールプレイングゲームですねってことですね。
canavis:
もちろん、『ブラックバード』好きなんですけど、
ラブムー:
うんうん、ちょっと怖いもの見たさって感じかな、あれは。
canavis:
あ、いいゲームだと思いますけど。
ラブムー:
いいんですか。
canavis:
そうは言っても『moon』とはやっぱり全然違うゲームだしっていう。
ラブムー:
そうですよね。
canavis:
『moon』を期待してるものであれを選んで手に入る人はいるけど、限られてるんじゃないですかねって。『moon』が好きだから『ブラックバード』もやりましょうとか、『勇者ヤマダくん』もいいですけど。それぞれよくできてるゲームだけど、なんかやっぱりラブデリック系とは違うっていうか。
ラブムー:
それはわかります。僕はふたりとすごく話したいのは『L.O.L Lack of Love』かな。あれは素晴らしい、『moon』を超える、超えかねないゲームだと思ってる。
そう、だからやっぱ言葉——『パックランド』もそうなんだけど、ゲーム内に言語がないユニバーサルデザインというか、言葉がない。やっぱり自分はなんかゲーム内に言葉がないゲームっていうのが好きなのかなとは思いますね。
テキストが出てこないゲーム。なんか日本語で、『スーパーマリオ』とでピーチ姫がさらわれて…云々みたいなことをキノピオは別に言ってもいいんだけど、そういうのがないゲーム。『パックランド』みたいに、その言語自体がないゲーム。
ちょっとこれ、この話は趣旨とずれちゃったかもしれないけど。テキストがないゲームって好きですね。
よごえむ:
いや、でもむしろ今、趣旨に戻ってきたんじゃないですか。『パックランド』から、どんどん、どんどん離れていったからな。ちゃんと『パックランド』に戻ってきた感じがあっていいんじゃないですか。
canavis:
ですね。
ラブムー:
そっか。『moon』はもう、バリバリテキストがあるでしょ。でも『L.O.L Lack of Love』ってテキストが全くないんですよ。
うん。で、自分がその原体験の『パックランド』に戻ってみると、テキストっていうものが、『ドラゴンクエスト』と『ポートピア連続殺人事件』みたいなテキストありきのゲームも大好きなんだけど、やっぱり言葉がないゲームがすごい(ゲームらしい)ゲームだなっていうのをすごい思うかな。
canavis:
『パックマン』と比べてでも『パックランド』って物語が発生したと思うんですよね。
ラブムー:
そうそう。でも、会話はないじゃないですか。「おかえり」とか。
よごえむ:
物語があるかどうかと、テキストで何かを語るかどうか、また別のあれですから。
ラブムー:
そう。『スーパーマリオ』だって言葉はあるから、なんか英語だけど、キノピオが、なんかピーチがさらわれて、次に行ってくださいうんぬんみたいと英語で語るんですよね。
だから、僕はその言葉がないゲームが好きだから、Playdeadのゲームも、canavisさんが好きな『風の旅ビト』とかもだけど、非言語なゲームって好きかな。
canavis:
そうですね。
ラブムー:
やっぱりそこ、自分すごい思うかな。言葉がすごいあるゲームと、言葉が全然ないゲームがあって、『パックランド』は本当にその言葉が全くないゲームで、言葉がないゲームをちょっとビデオゲームをビデオゲームオブビデオゲームって思っちゃってるところは自分はちょっとあるかも。だからロールプレイングゲームとかは違うんだけど。
よごえむ:
あれ。フェアリーランドに落っこちたってなんか言いませんでしたっけ。なんか出てませんでしたっけ。
ラブムー:
あ、ドアの下に落っこちた時?あの時英語出てきましたっけ。
よごえむ:
出てきてたような気がします。
ラブムー:
あー、出てきた気がする。出てきてるか。そうだ。じゃあじゃあ、別にスーパーマリオと差別化できないか。

よごえむ:
でもわかりますよ。なんか今このサムネイルのとこに映ってるこれの感じで、なんか言わないですからね、帰ってきてなんか。
ラブムー:
おかえりみたいなことはね。
よごえむ:
雰囲気を出してるだけで、別に。
ラブムー:
『風の旅ビト』の、なんか記号みたいでコミュニケーションしてくみたいなのもすごい好きだった気がする。
canavis:
ゲームって操作をするっていうのが、やっぱり映画とか小説とかと全然違うんで、言語を頼らないでメッセージを受け取るみたいなことが、1番容易い文化じゃないかなっていうのがあるっていうか。たとえば、朝起きてご飯を食べてって、電車で行きますみたいな。話があって、それを映画とか小説とかでもできるんですけど、ゲームでやると、段違いじゃないですか。メッセージが伝わってくるって。自分で操作しなきゃいけないから。
ラブムー:
その、「ナラティブ」という言葉はあまり使いたくないけど、そうですね。
canavis:
はい。
よごえむ:
でも、『パックランド』って、私は割と漫画っぽいと思いますけどね。でも、なんか映画とか、小説っぽいとかとは全然思わないけど、やっぱ、絵で見た時の感じなんですよね。なんか、どんだけのテキストが書いてあるかっていうより、その絵の連続の感じが割と『パックランド』ってそうかなと思ってて。漫画とかも、テキストない漫画とかあるじゃないですか。なんかあれを見てる感じなのかなという。
ラブムー:
確かに。それはよごえむさんにとっては好きっていうか、ポジティブなことなんですか?
よごえむ:
これはポジティブな意見。
canavis:
『シェンムー』とかって、なんかこう。
ラブムー:
出た、『シェンムー』(笑)。
canavis:
芭月くんが、家から出て、ゲームセンターまで、商店街を歩いていく道のりっていうか、港に行くまでのバスに乗っていく道って、何もないけど、なんかこう。言語化しにくいけど、操作をしてるっていうか。ロールプレイをしてるっていうか。コントローラーを触ってキャラクターを動かしてるだけで、発生する感情みたいなものってあると思うんですよ。
よごえむ:
だからまさに、シーンとか視点の連続みたいなものっていうのがやっぱりあって。いまcanavisさん『シェンムー』出してくれましたけど、結構私もそれは感じるところで、いまこの漫画の例え出したのもすごいそれを『シェンムー』とかに感じるところもあるし、『パックランド』もそう感じるんですよね、で、それは割と非言語的なものであるというところもあって。

canavis:
この『パックランド』って、「家に帰る」っていうところがやっぱり重要で。このゲームって、特に説明書とか読まない限り、バックボーンがわかんないじゃないですか。
ラブムー:
パートナーと子供がいたんだみたいなことが。
canavis:
妖精をあそこまで持ってって、じゃあ今度は浦島太郎じゃないけど、そこからもらってきたものを持って。浦島太郎的な物語だって、なんか実体験としてわかるじゃないですか。行って帰ってくるっていう、亀を届けて家に帰るみたいな。
ラブムー:
ああ、でも、それ子供の頃思った。これ帰った後にまた行かなきゃいけないのかっていう。またその夜中にそのモンスターが徘徊する町に行かなければいけないのかっていう、ある種の悲哀みたいな。パックマンのサラリーマン的悲哀みたいなものを感じましたね。家に帰って、家族もいるのに、またこの夜中に、しかも自分に対して悪意しかないであろうモンスターたちのいるところに。
よごえむ:
なんかモーレツ社員みたいですね。
ラブムー:
そうそうモーレツ社員的な。しかもなんか顔はニコニコしてるし、帽子の中に妖精がいるから、それを届けなきゃいけないっていう義務はもちろんあるんだけど、結局家に帰ってきてもトリップし続けなきゃいけないのかっていう悲哀はすごい感じましたね。
canavis:
『The Longest Road on Earth』ってゲームがあって。

ラブムー:
あれは大好きです。
canavis:
これもなんか物語がっていうか、ストーリーっていうか、ただ生活を切り取ってるだけのゲームっていうか。
ラブムー:
そう。でもあれ、音楽の力がめちゃめちゃ大きいでしょ。あれ、無音だったらだいぶ違うやつだと思うんですよ。なんか音楽に語らせてるっていうところはすごい大きいと思う。
canavis:
でもこれも音楽もそうだし、操作があるから成り立つっていう。
ラブムー:
そのインタラクティブ性みたいなのは確かに近いかも。
canavis:
『パックランド』はストーリーはあるとは思うんですけど、家に帰ってくる人の物語っていうところを、プレイヤーがどうしても操作で補完してしまうっていうようなことがあるから、やっぱゲーム。ゲームらしい。
ラブムー:
そうですね。なんか終わりがあるといいんだけど。確かこれエンドレスなんですよね。延々とやり続けなきゃいけないっていう。
よごえむ:
ステージもめちゃくちゃ多いですよね。
ラブムー:
延々と続くので。
canavis:
『ゼビウス』の時に言ったと思いますけど、『ゼビウス』の戦争が起きてんのに、静かな感じっていうか、やらない感じっていうかね。『ゼビウス』ってバックボーンの話がすごいあるとは思うんですけど、なんか探らない限り、なんかこの人たちなんで戦ってるのかどうかわかんないし。いま戦争のゲームを作るって言ったら、この音楽作れない、使わないでしょみたいな。
ラブムー:
どっちかというとアンビエントに近いですもんね。canavisさんがやってる音楽の方というかね。ゼビウスのあの音楽は素晴らしいと思うんだけど、あれが全然違う音楽だったら全然印象変わったんじゃないかな。だから、『ガンプの謎』やった時にちょっとがっかりしたのは、音楽がなんかあんな感じじゃない時があって。普通の、なんかちょっとコナミっぽいメロディアスな音楽が入った時とかがあって、それはちょっと『ゼビウス』っぽくないなと思って少しがっかりした。『ガンプの謎』もいいゲームではあったとは思うけど。
canavis:
文化が始まっちゃう、解像度がどんどん上がっていくとアクション映画の音楽っていうとあれだけど、戦闘の音楽になっちゃうっていうか。
ラブムー:
そうですね。だから、canavisさんが言ってたその『ゼビウス』の感じって、あの感じで戦争してるかもしれないっていうところが、すごくリアルな感じがするのね。アンビエントな、なんか牧歌的な音楽なんだけど、こう破壊の表現があってっていうことが、すごいリアルな感じがする。叙情性とかが皆無っていうのかな。
canavis:
そういう感じは、戦争中ずっと暗い場面じゃないしね、現実。カンカン照りなところで戦ってる時もあるでしょ。『Call of Duty』とかでは出てこない感じの戦争の絵なんですよね。
ラブムー:
『メタルギア』でもファミコン版でやった時、その段ボールを被ってなんか移動したりするのが楽しかったけど、『ゼビウス』に感じたものとは全く違って。やっぱりそれで考えると、そのナムコの良さっていうのはセンスの良さなのかな。
よごえむ:
それはあるんじゃないですか。それはすごいあると思います。そこは多分世代が、自分がさっき言ってたプレステ世代からになってもやっぱりめちゃめちゃ感じるところで。やっぱりセンスの良さっていうのは、好きだろうが嫌いだろうがちょっと認めざるを得ないところがナムコにはやっぱあるというか。
ラブムー:
ナムコに対して。
よごえむ:
やっぱ『リッジレーサー』とかもセンスいいなと思いましたもん。
ラブムー:
思いますよね。なんか『リッジレーサー』の良さって、そのcanavisさんが言ったその『ゼビウス』に感じるそのあの感じと引き継がれてる感じはちょっとする。

よごえむ:
そう。でも結構その割に身近な題材みたいなものというか、日本人にとって身近なものみたいなものを取り入れる…身近さみたいのも多分あるんですよ。テイルズシリーズも多分そうなんですよ。
ラブムー:
身近さがある?
よごえむ:
『テイルズオブファンタジア』とかも、なんていうかちょっとチャラいというか、ノリ軽いんですよね。
カウンター的に考えないと出てこないところっていうか、例えば『ドラゴンクエスト』とかでダンジョンとか入って、ダンジョンから帰るのめんどくさいなって思ったりすることがやっぱりあると思うんですよね。ってところで『テイルズオブファンタジア』とかだと、ボスを倒した後とかに「ここからパッと行きますか?」みたいになって、「パッと行く」「パッと行かない」みたいな選択肢が2つ出てきて。「パッと行く」を選ぶと勝手に帰ってくるんですよ、ワープして。
ラブムー:
ファストトラベルみたいな。
よごえむ:
そこら辺はやっぱなんかセンスがいいなっていう風に思います。
ラブムー:
じゃあ『テイルズ』にもそのセンスのさっていうのがあるんだ。
よごえむ:
あると思います。
ラブムー:
でも『テイルズ』と、よごえむさんがいちばん好きな『グランディア』と比べると、『グランディア』の方がロールプレイングゲームとしては好きですよね。
よごえむ:
もちろん。それはもちろん好みとしてはそうだけど、センスがあるっていう意味で言うと『テイルズ』の方が多分あると思います。
他のタイトルに対する心配りみたいなものも当然あるし。そうそう、そういうところはかなりあると思いますね。
ラブムー:
じゃ、『テイルズ』のJRPGとしての評価はすごい高い?よごえむさんの中で。
よごえむ:
作品によりますし、なんか単純に好き嫌いみたいなところで言うとまた別なんですけど、いま見て歴史的な驚きがあるかとかってところで言うとまた評価は変わってきますね。そこはまた全然違う話になってきちゃいますね。
ラブムー:
そうですね。好き嫌いと違いますもんね。何本ぐらいあるんですか、シリーズ。『ファンタジア』と全部のシリーズって。
canavis:
全部数えてるともうかなりあるんじゃない。
「ファイナルファンタジー」超えてるんじゃない?
よごえむ:
20くらいはありそう。
『ファンタジア』『デスティニー』『エターニア』『デスティニー2』……。
ラブムー:
それよごえむさん全部プレイしてるんですか?
よごえむ:
全部はやってないです、7割ぐらいはやってますよ。
canavis:
でも、このシリーズ、いちばんキツイところはナンバリングがついてないっていうところは、やっぱり数が何本出てるかわかんないところですね。「スーパーロボット大戦」何本出てるかって言われたらパッと出てこないですよ。
ラブムー:
絶対わかんない(笑)。
よごえむ:
そこが生き残ってる理由でもある気もしますけどね。なんかわかんないけど、RPG出てるかやってみるかっていう感じでやってる人も多分中にはいるはずなんで。別に世界観の繋がりとかもほとんどない。たまにありますけどね、『デスティニー』の次の『デスティニー2』とかっていうのはたまにありますけど、「FF」と一緒で––「FF」はナンバリングですけど––世界観も繋がりないし。
でもやっぱり今はオーバーグラウンド化してるから、そんなにめちゃくちゃ驚きみたいなものとか、カウンターみたいなものはあんまり感じないですけど、ナムコの全体的なセンスの良さみたいなのはやっぱありますよね。『エースコンバット』とかもそうなんじゃないですか。私はあまり詳しくないですけど。
ラブムー:
『エースコンバット』、それは僕もあまり語れないな。
canavis:
そうですね。
そんなところかな、そろそろ時間もあれだし。
ラブムー:
それじゃあ、ちょっとまとめ、巻きに入ってもらえますか。巻きに入ってもらうっていうか、canavisさんにまとめていただいて。
canavis:
そうですね。 最初の自分がいちばんフェイバリットにあげてた『moon』もそうですし、『パックランド』もそうですけど。
ラブムー:
でも『パックランド』、どういう風に位置づけられたのか、今回話しててもちょっとよく掴めなかったところはある。でもふたりの話でだいぶ多面的な話になったと思うんだけど、結局『パックランド』が自分は好みだった。その「相性」っていうのに帰着させちゃうのってあれかなと思うんだけど、結局好きだったものってそういうものなのかなって。なんか、たまたま一目惚れしちゃった人がたまたまこういう人だったからこういうものでしたみたいな。なんか事後的な話になっちゃうっていうか、理屈ではなくて。
canavis:
自分とラブムーさんの共通してるとこは、サブカルチャーの入り口だったからじゃないかなと思って。
ラブムー:
僕とcanavisさんの共通してるところがサブカルチャーっていうこと?
canavis:
文化的なもの、アメリカ文化だったりとか。
ラブムー:
趣味が似てるってこと?ざっくり言っちゃうと。
canavis:
こういう文化にハマるきっかけだったんじゃないのかな。どうでしょうね。いや、そういうことではない?
ラブムー:
どうだろう。なんか結局、今日やる前に配信で『パックランド』を久々にやってみたりしたんだけど、『パックランド』っていうのが自分のゲームとか、自分の人生の中でどういう位置付けだったのかっていうのは、正直、ちょっとよくわからなかったところがありますね。位置付けられなかったって。他のゲームだったら位置付けられるんだけど。『ドラゴンクエスト』とか『ポートピア』とかだったら位置付けられるんだけど。
でも、ふたりと話したおかげで、多面的にはなったと思うんだけど。よくわからなかった。なんかだから、好きになった人のどこが好きだったのって言われても、よくわからないっていう風になっちゃうのと同じことで。
よごえむ:
「いちばん好き」っていうのは、でも多分そういうことなんだと思う。「いちばん好き」って順位じゃないと思うんですよね。「いちばん好き」って多分特別な位置を占めてるっていうところでしかなくて、順位をつけてるとかではないんだけど、本当は。でも無理やり多分1位にしてるんですよ。
ラブムー:
そうそうそう。だから、言葉にちょっとできないところがあるから、こうやって話し続けてても、やっぱり位置付けようとはしてるんだけど、どっかでこう位置づけまいとしてるところが自分の中にあるから。うん、難しいな、この話は。
『moon』の話の方がもうちょっと自分は話しやすいんだけど、『パックランド』はちょっと難しかった。だから、よごえむさんのいちばん好きなゲームを語る時をすごい楽しみにしてますね。
よごえむ:
う、うーん……。
canavis:
じゃあこんなところかな、今日。
ラブムー:
うん。でも、ありがとうございました。凄く楽しかったし、いろいろ思うところがありました。なので、またよろしくお願いします。よごえむさんの1番好きなゲームの時もぜひ呼んでください。
よごえむ:
(かしこまって)はい……。
canavis:
というわけで、本日は皆さんありがとうございました。

あとがき(ラブムー)
「次はラブムーさんの一番好きなゲームについて語りませんか?」Game Gameのcanavisさんにお誘いしてもらった時は少し迷った。選ぶゲームを迷ったわけではない。まっさきに浮かんだゲームは——もちろん『パックランド』だ。これまでも、これからもそう答えることだろう。
ただ、「どうして『パックランド』が一番好きなのか?」と自分に問うてみると、それは容易に浮かんで来なかった。たぶん心のどこかで言語化することを放棄して(あるいは拒んで)いたところもあるように思う。
でもゲームっ子時代に出会った『パックランド』を、ゲームについて書くことを(一応の)稼業にしている中年男性となった今、ゲームを愛する人たちと忌憚なく語り合うことができたら、どうして自分が『パックランド』が一番好きなのかを得心できるかもしれない。そう思った。
結果約3時間、canavisさん、よごえむさんと『パックランド』について語らせてもらうことになったわけだが、こうして音声での放送をよごえむさんに編集してもらったものを読んでみると、自分が、普段ゲームについて語っている時とはだいぶ違った状態になっていることがよくわかる。「一番好きなゲーム」に対して、できるだけ客観的になろうとしているのだけど、全然なれていない。何か「別のスイッチ」が入ってしまっている。
「この別のスイッチ感」には既視感がある。
それは若かりし頃、学生時代に同級生たちと話している時、その場にいない好きな人が話題に上ってきた時に感じる「あの感じ」に近い。その人について自分だけが知っている(と勝手に思っている)「何か」をほのめかそうとしたり、他の誰かがその人について言ったことにやたら食ってかかったり、自分はその人を(恋愛感情によって)特別視しているわけではない、と振る舞おうとしてかえって早口になったり、妙なことを口走ってしまったりする。記事末尾でよごえむさんが語っているように、「一番好きなゲーム」について語るというのは、やはりそういうことなのだろう。
それでも、ゲーム愛もゲーム造詣も深いお2人のおかげで、『パックランド』という作品を2024年現在から検証したり、他作品と比較して再評価したりと、これまで1人では思いもつかなかったことを話せたこと、そして何より、「一番好きなゲーム」について語らうことが、今なお自分に特別な興奮をもたらしてくれることを久方ぶりに実感できたことがありがたかった。
(いささか酔っ払いながら)『パックランド』についてお2人とたっぷり語らえたことは、幼少期の自分と現在の自分を接続させるうえでも、凄く大事な機会になったように思う。
自分とゲーム以外のカルチャーも通じるところの多いcanavisさん、世代は違えど僕のリアルタイムのゲームカルチャーに精通していて、ゲームへの強い拘りと優しい目線をお持ちのよごえむさん。今回、相手がお2人でなかったら、これほど融通無碍で長丁場の鼎談にはならなかったはず。この場をかりて感謝。
最後に。お読み頂いた方にはわかるように、べらぼうに長いこの鼎談だが(『パックランド』について、これほど長く語られた記事がかつてあっただろうか?)、この記事を読んで40年前にリリースされた不思議なゲームに興味を持ってくださったり、「自分の一番好きなゲーム」に思いを馳せるきっかけになれば、ゲーマー冥利に尽きます。ラブムー
いいなと思ったら応援しよう!

