
後頭下筋群のリリース前に確認したい触診
固有感覚は身体の動きや位置を認識しますが、頸部固有感覚においては、前庭機能や眼球運動と協調して姿勢制御に関与します。
— タツ @ アスレティックトレーナー / 理学療法士 (@tatsu_bridge) May 6, 2020
姿勢制御に関与する頸部固有感覚は、第2〜3頸椎の固有感覚や頭板状筋、頭半棘筋、後頭直筋、頭斜筋、頭最長筋などの筋感覚が重要! https://t.co/GiC4xK9F1m
頚部の治療するならコレは必読! https://t.co/87EQCSUql4
— だいじろう☀️5/16〜17無料オンラインセミナー開催💪 (@idoco_daijiro) May 6, 2020
「後頭下筋群と眼球運動には強い関係性があること」
— Yoshiki@エコーと足部大好き (@PtGekikara) May 6, 2020
閉眼した状態で、眼球を左右に動かすと後頭下筋群が若干収縮している感覚はありますもんね🌟
あと、受容器が多い事初めて知りました❗️ https://t.co/aPgDk846tl
この記事面白い!
— たくみロドリゲス@運動器理学療法士 (@TakumiRodrigues) May 6, 2020
後頭下筋群って頭部前方偏位などで、リリースすることが多いですが、単体での筋を意識してアプローチできていなかったです。
なぜか、腹筋群や背筋群というと、一つ一つの筋を評価するのに、頸部になった瞬間に、”群”という言葉でまとめてしまっていました。
勉強になりました😆 https://t.co/nV30JBt3L3
みなさん、嬉しいツイートありがとうございます✨
ツイートを拝見するたびに、活動を続けられる元気をもらえます^ - ^
👇ここから本文にはいりまーす👇
Forward Head Postureの人に対して後頭下筋群へアプローチすることって、鉄板中の鉄板です。
ただ、そのアプローチがより適切にできているか、今一度立ち止まって一緒に考えてみませんか?✨
後頭下筋群の解剖学的おさらい
後頭下筋群は4つの筋の総称
❶大後頭直筋
❷小後頭直筋
❸上頭斜筋
❹下頭斜筋

プロメテウス解剖学コア アトラスよりはいはいはいはい。こんな感じでしたね。
学生のときに国試のために必死で覚えた記憶があります笑。
では、起始停止はどうでしょう。
大後頭直筋 👉 C2棘突起〜後頭下項線の中間1/3
小後頭直筋 👉 C1後結節〜後頭下項線の内側1/3
上頭斜筋 👉 C1横突起〜後頭骨の大後頭直筋停止部の上部
下頭斜筋 👉 C2棘突起〜C1横突起
さて、お次は作用です。
大・小後頭直筋、下頭斜筋👉片側の収縮で同側に回旋、両側の収縮で頭を後屈
上頭斜筋👉片側の収縮で同側側屈、対側に回旋。両側の収縮で頭を後屈
上頭斜筋だけ仲間はずれ。。。
上位頸椎の大切さ
ここで疑問。なぜ後頭下筋群はここまで重要視されるのか。
1つ目には、Forward Head Postureでは後頭下筋群が短縮してしまうこと。
2つ目には、頸椎の可動域の中でも上位頸椎が占める割合が大きいこと。
3つ目には、後頭下筋群には筋紡錘がたくさんあって受容器の役割が大きいこと。
4つ目には、後頭下筋群と眼球運動には強い関係性があること
5つ目には、頸部痛との関係性があること
Joint by Joint Theoryの考えでは、下位頸椎は安定性・上位頸椎は可動性関節としての役割があって
だから、Forward Head Postureになると上位頸椎の可動性低下を安定関節である下位頸椎が代償してしまってさまざまな不具合が出てきます。
後頭下筋群へのアプローチを繊細に
よくあるのは背臥位で頭蓋骨を頭側へ牽引する方法。
でも、これだとざっくりとしたアプローチなので、個別にしようと思うとやはりそれぞれが1番牽引される向き・短縮される向きを理解しておいた方が良い。
☝️頭部肢位の違いが後頭下筋群の形態に及ぼす影響☝️
伸張位(ストレッチ)にするには頸部屈曲。さらに左側後頭下筋群を選択的にするなら右回旋、右後頭下筋群を選択的にするなら左回旋
短縮位(リラクゼーション)にするには頸部伸展
頸椎で押さえておくべき触診ポイント
☝️チャンネル登録もよろしくね笑☝️励みになります笑
「じゃぁ、早速後頭下筋群にアプローチしよう!」。。。の前に、ぜひ頸椎の触診を( ̄▽ ̄)
形だけを真似するんじゃなくて、運動・解剖・生理っていう本質を理解することが何よりも大切だと思う。
押さえておきたい触診箇所は、C2棘突起とC1横突起。これができるためには乳様突起の触診ができること!
後頭下筋群の解剖学的トリビア
はい、これ。この記事をまとめだすまで全然知りませんでした笑。というか純粋にびっくりしました(僕の、知識不足なだけですが...)
後頭下筋群と硬膜って、軟部組織を通じて繋がってるんですね。。。
後頭下筋群のレベルって脳幹があるわけで、そう考えると恐ろしいほど重要な筋。
メンバー紹介
エコー担当:志水さん

Twitter:エコーと肩についての情報をわかりやすく発信しながら、これからのセラピストの生き方についてもつぶやいています。
note:【Twitterの『わかりやすい』を、『臨床で使える』】をコンセプトにコンテンツを発信😁
YouTube:エコーや肩関節について分かりやすく発信中。その名も「Shimizu Log」
触診&エコー担当:Yoshikiさん

Twitter:理学療法に対する有益な情報を発信中
YouTube:触診・エコー画像を配信中
運動器エコーカレッジ:解剖生理学を基礎として客観化を図り、エビデンスと技術を融合する。優良なエビデンスや、エコーで可視化、cadaverの実際など、様々な知識を放出していきます。今後開始予定。
治療担当:たくみロドリゲスさん

note有料マガジン
・運動器リハのすべて:運動器に関する内容を見て・聴いて覚えられるよう、記事と動画コンテンツを週2回配信中
・実践!ゼロから学べる足の臨床:足のスペシャリスト5人によるマガジン。足の機能解剖から評価・エクササイズ、靴など基礎的な内容からマニアックな内容まで配信中
・実践!ゼロから学べる肩肘の臨床:足のスペシャリスト5人によるマガジン。肩肘の機能解剖から評価・エクササイズ、エコーなど基礎的な内容からマニアックな内容まで配信中
臨床の限界を追求した情報サイト CLINISCIANS
臨床家のための無料ブログを投稿中!
ライタープロフィール
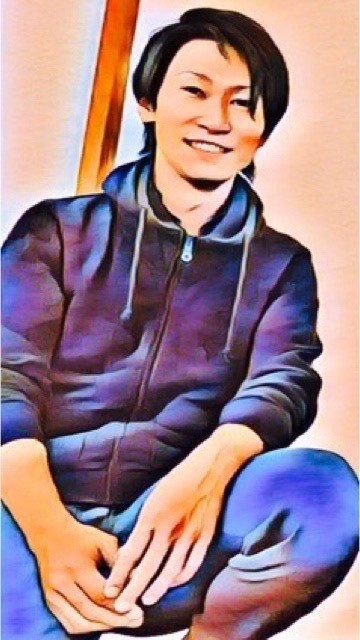
運動器リハの中でも下肢疾患が大好き。今は上肢の魅力にも取り憑かれ、日々勉強中!
Twitter:触診・臨床について発信中 ✨
YouTube:触診動画を配信中✨
みなさんからの「いいね」・「スキ」・「フォロー」が僕のエネルギーの源になります。どうぞ、よろしくお願いいたします!
いいなと思ったら応援しよう!

