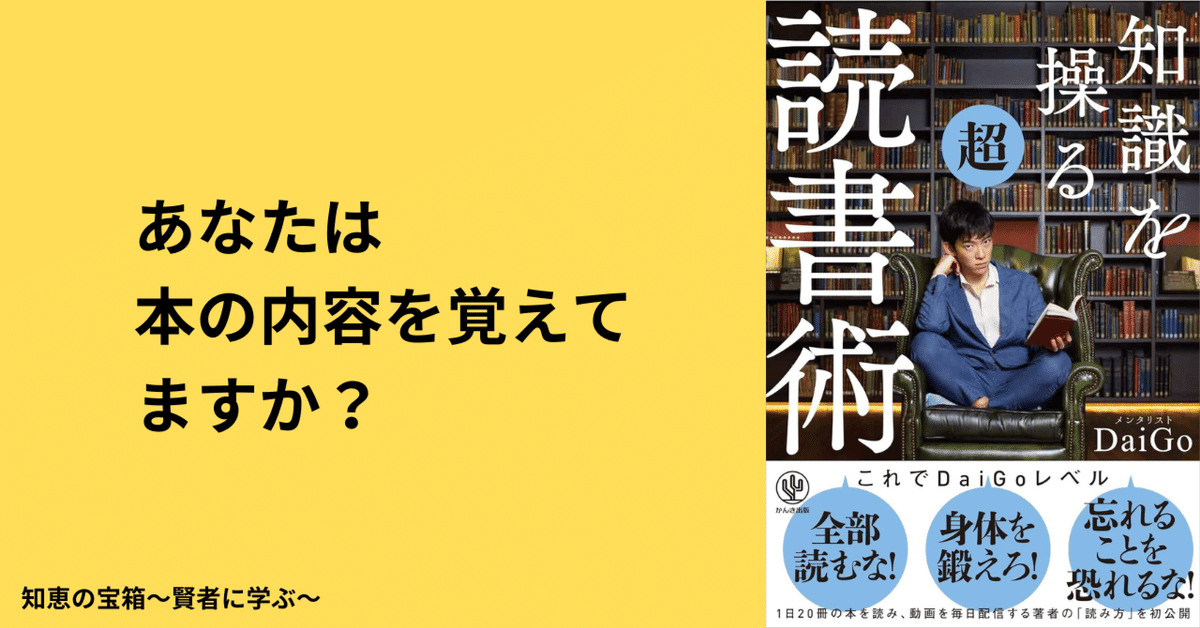
【9限目】読む読書から活かす読書にする「5つの戦術」
あなたは、読んだ本の内容をどの程度覚えていますか?
分かります。
忘れますよね!
僕だって読んだ本の内容なんて、ほとんど忘れてましたよ!笑
せっかく読書しても忘れてるなんて、一体なんのための時間だったんだと自問自答したくなります笑
というわけで今回は、読んだ本の内容をできるだけ記憶に残し、活かしていくための記事を書いていきます。
【本記事の内容】
本を読む効率を上げ、読む読書から活かす読書にする方法
前回と同じく「知識を操る超読書術」というメンタリストDaiGoさんが書かれた本の内容を中心に書いていきます。
実は読書という行動の効率を最大化させたい!という思いから、本書を手に取ったんですよね…。
つまり僕もあなたと同じように、「本の内容を忘れる」ということに悩んでいたうちの一人だということです。
ちなみにですが、現在でも忘れます笑
さすがに全部は覚えてられません…。
ただ、本書のテクニックを活用し、紙にメモを取っているので忘れても思い出すことができます。
つまり、今までとは違い、ただ「あー!読み終わった!終了ー!」とはならないわけです笑
以前よりも1冊読むのに時間がかかるようになりましたが、その代わり本の内容に没頭できている感覚です。
本の内容をほとんど忘れてしまうので、もっと記憶に残して活かしたい
これから読書をしたいので、正しい本の読み方を知りたい
このようなかたにとっては、有益な記事となると思います。
あなたも一緒に、読書の効率を最大化させましょう!
①読む読書から活かす読書にする「5つの戦術」

本を読む理由を3つカードに書き、栞にする
読み始める前にその本に書いてある内容を予想する
本の内容をマインドマップのように視覚化する
書かれている本の内容と、別のことをつなげる
読み終わったあとで、「要するに」何が書かれていたのか考える
この5つが現在、実践しているテクニックです。
実際に本書で紹介されているテクニックとしては、
「予測」読み
「視覚化」読み
「つなげ」読み
「要するに」読み
「しつもん」読み
なのですが、僕がまだ「しつもん読み」をマスターできていないため、今回はそちらを省き、別の章で書かれている別のテクニックを入れて5つ紹介させてもらいます!
1.本を読む理由を3つカードに書き、栞にする

脳は、意味のある文章に惹かれる。
こちらは、本書で紹介されている「メンタルマップ」と言うものです。
本を読む理由を「カード」に3つ書きます。
そしてそのカードを「栞」として使用します。
すると「なぜその本を読もうと思ったのか?」と言う気持ちをすぐに確認できるため、モチベーションが途切れにくくなります。
むしろもっと先を読みたくなることすらあります笑
ちなみに僕は、どの章から順番に読んでいくかもカードに記入しておきます。
これにより読書中に迷子にならなくて済みます笑
僕は現在、ダイソーで買ってきた無印の「情報カード」を使用しています。
100円で100枚入りなのでバンバン使える優れものです!
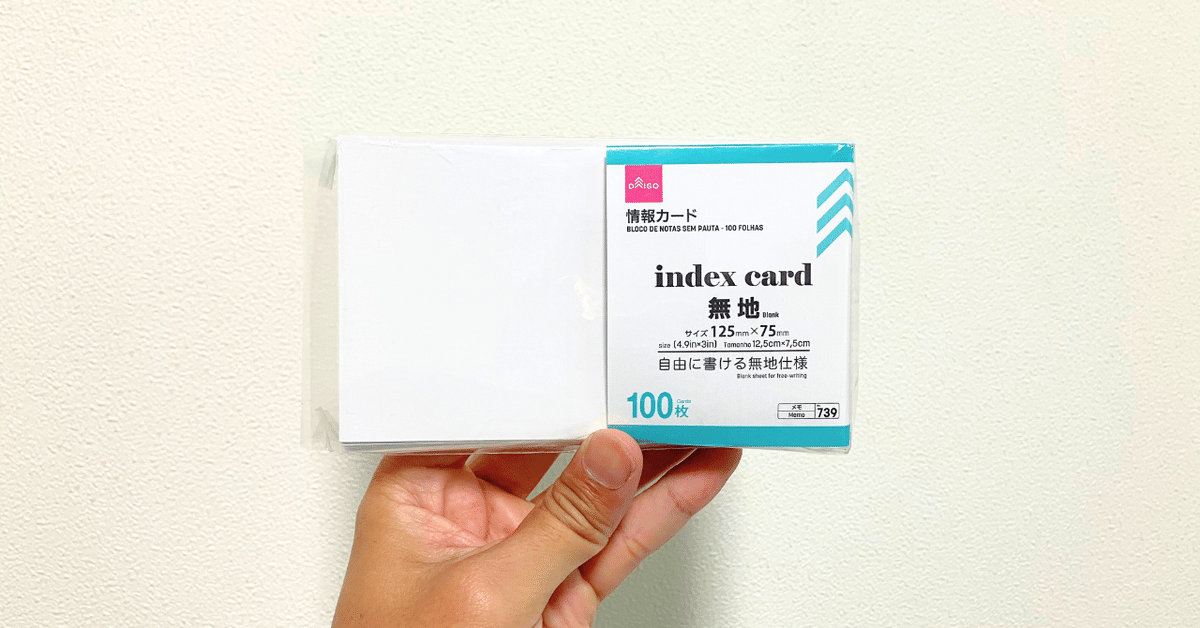
2.読み始める前にその本に書いてある内容を予想する

本を開く前に内容を予測しよう。意外性があるほど、記憶に刻まれる。
こちらは、本書で紹介されている「予測読み」と言うものです。
読む前に、その本にどんなことが書かれているのか予想します。
これを僕はタイトルと目次の内容から、まず本全体に書かれている内容を想像してA4の用紙に記入します。
そして新たな章を読み始めるごとに、その章に何が書かれているのか予測してそれも記入しておきます。
読み終わった後で、実際にどのような内容が書かれていたか確認します。
予想が外れても大丈夫です。
むしろ「外れた方が記憶に定着しやすい」とのこと。
意外性がある方が、覚えることができるのです!
3.本の内容をマインドマップのように視覚化する

文章のビジュアル化ができると、忘れることなくすぐに思い出すことができる。
個人的に、僕が最も効果を感じているテクニックです!
本書には「視覚化読み」と書かれています。
まずは章を読み進めていきます。
するとその中には、その章の内容を象徴するようなキーワードがいくつか出てきます。
それをA4用紙にひたすらメモしていきます。
そしてひとつひとつのキーワードを、関連性のあるものへとつなげていきます。
「マインドマップ」を作るような感覚ですね!
これを作成しておくと、後から見返したときにその章に何が書いてあるのかをすぐに確認することができます。
そして内容を徐々に思い出すことができるのです!
メモやノートは、記憶をさせる「第2の脳」。
メモの魔力という本には「メモ書き」は「第2の脳」と書かれています。
まさにその通りだと実感しています。
書いておくことで、いつでも思い出せる…。
パソコンで言うと外付けハードディスクのようなもの。
人間も、記憶容量を増やすことができるのです!
4.書かれている本の内容と、別のことをつなげる
こちらは「つなげ読み」と紹介されているテクニックです!
今読んでいる本の内容を、別の本に書かれている内容とつなげて読むことで、記憶の定着を上げるというもの。
別の本の内容だけでなく、自分の経験や世界で起きている事象などとつなげてもオッケーだそうです!
読んだ本の数が増えると、「あ、これに似たことがあの本にも書いてあったな…。」ということに遭遇しやすくなります。
記憶の定着という効果だけでも十分に嬉しいことですが、他の本にも書いてあるということはそれだけその内容が「重要」だということ。
本の内容をつなげればつなげることができるほど、自分にとって大切な情報が研ぎ澄まされていくわけです!
5.読み終わったあとで、「要するに」何が書かれていたのか考える

こちらは「要するに読み」というテクニックです。
まさに「要するに」何が書いてあったのか、読み終わった後、自分の言葉で書くことです。
僕はひとつの章を読み終わった後にその章の「要するに」を書き、一冊読み終わった後は本全体の「要するに」を書きます。
すると書かれていたことを、自分の言葉で端的に表現することができるのです!
内容を「思い出す」という作業を自然とすることになので、記憶の定着が期待できます。
何度も思い出すことで「短期記憶」から「長期記憶」となるのです。
長期記憶とは、要するに自分にとって重要な情報で覚えておかないと困ることです。
短期記憶は、長期記憶とは反対ですぐ忘れます笑
この辺りのところを突っ込んでいくと、ややこしくなるので今回はやめておきますね!
最後までお付き合いいただき、ありがとうございます!
今回の記事はいかがでしたか?
本を読んでるんだけど、イマイチ役立っている気がしない…。
ただ読んでいるだけになっている…!
そんなお悩みを持っているかたをイメージして書きました。
同じ悩みを持っていたひとりの仲間として。
僕はせっかく読書をするなら、その情報をしっかり活かして現実を変えていきたいと考えています。
そのためにもまずは、読書の内容を自分に落とし込む。
そうすればマインドが整い、自然と行動が変わります。
ただ読むだけではなく「活かす読書」へ。
あなたも一緒に、知識を操りませんか?
次回の記事では、僕が持っている知識をもっと上手く表現することを決意して、本記事を書き終えたいと思います。
それではまたお会いしましょう!
追伸
最後に今回参考にさせてもらった「知識を操る超読書術」のリンクを貼っておきます。
本書を読めばもっと詳しい知識が手に入ります。
ぜひ一度、手に取ってもらえればと思います!

