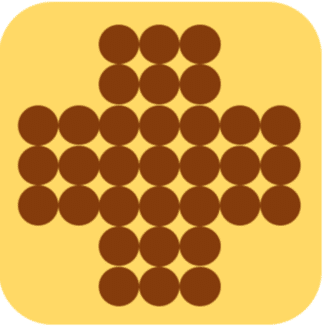米澤玩具のプラステンplusten(1) 英語を読み間違えるんです
米澤玩具が発明したプラステン(plusten)って見るたびに毎回いつも、英語表記のほうをラジくまるは読み間違えてしまうんです。
あくまでも私の場合は、ですけど。
だいたいは
pulse stain (短い信号が汚れている?)
っていう風に読み間違えます。
この感覚、英語が母国語のヒトにはわかってもらえるんじゃないかなーと思うんですが、いかがでしょうか。
英語表現としては plusten というスペリングは、とっても不適切なんです。この内容を英語で言いたい場合は
Plus-Ten
という風に (ー:ダッシュ記号)を入れないと英語世界では意味が通らないです。あと左端を大文字にするのもかなり大事。
***
ここで突然ですが「プラステン」製造販売元の米澤玩具のお話をします。
米澤玩具(株)→ヨネザワ(株)→エスパルが吸収合併→セガが吸収合併
米澤玩具というおもちゃ会社の製品の中で、最も有名な商品は何かと言えば、1978年発売の「サイモン:Simon」という「短期記憶力」の電子玩具と言い切ってしまっても間違いではないでしょう。
ゲーム内容は比較的単純な「短期記憶力」系の遊び(ゲーム)なので、2025年現在は、とても簡単にスマホやPCでエミュレーション可能です。
*エミュレーション:PCとかの仮想画面上にて、1978年当時の見た目と動作を再現すること。
「インテルはいってる」というキャッチコピーで有名な、CPUメーカーのインテル社が開発した初期型CPU、8086の発表は1978年です。
そこから想像できる通り、サイモンが発表されていた1978年の頃は、汎用型書き込み可能ICチップ(プログラマブルICチップ)はまだ発明されていないのです。(プログラマブルICチップの製品化は、たぶん1985年頃のはず)
このプログラマブルICチップの前時代と後時代とで何が違うのかというと、個人レベルでこういう「サイモン」みたいなゲーム機を自作できるか、それとも個人には不可能か、という大きな差として現れます。
2025年現在は、東京・秋葉原の秋月電子に行けば、一般人でさえも「プログラマブルICチップ」を購入できますから、時代の大きな変化を感じてしまいます。
プログラマブルICチップは誰でも簡単に購入できますが、そこにゲームプログラムを書き込む技術力があるかどうか、さらにはハンダ付けとかして、その完成製品の表面に、プッシュボタンやらLEDやらをくっつける手の器用さがあるかどうか?というのは別の話です
サイモンはTexas Instruments社製 TMS1000というICチップを採用していました。TMS1000は、ズバリ言ってしまえば超安価なCPUです。当時のアメリカで「最安値」なCPUだったらしいですよ。
これに、記憶力系のゲームプログラムを入れたROMメモリチップを接続して商品化したわけです。
TMS1000は、この1978年当時「電子ピコピコゲーム」の用途に、引っ張りだこ&バカ売れ状態だったとのことです
***
さて、超長文でサイモンにまつわるお話をしてしまいました。
ちょっとラジくまるが暑苦しいヒトになっちゃって失礼しました。
大学生時代に本気でPCプログラミングやってたもんで、この手の話はどうしても語り口が熱くなってしまうんです。お許しください。
ということで「プラステン」のお話は、来週に続きます。
いいなと思ったら応援しよう!