
北薩リハフォーラム2024を開催しました
こんにちは。グループ経営企画室 杉元です。
11月30日(土)に薩摩川内市国際交流センターにて北薩リハフォーラム2024を開催しました。今回は『「災害リハ」を考える』というテーマで2名の講師をお招きし多数の方にご来場いただきました。

今回の記事では2名の講師による講演に加えて、九州電力株式会社川内原子力総合事務所様による事例発表をレポート形式でまとめましたので是非最後までご覧ください。
事例発表「九州電力が取り組む原子力防災支援について」
九州電力株式会社川内原子力総合事務所

原子力災害対策重点区域(PAZ・UPZ)について
PAZ:原子力施設から概ね5㎞圏内。事故の状況に応じて、放射性物質が放出される前の段階から予防的に退避を行なう区域。
UPZ:原子力施設から概ね5㎞~30㎞圏内。原則として屋内退避とし、その後は発電所の状況に応じて避難や一時移転を行なう区域。
原子力災害発生時における防護措置について
発電所がある地域で、震度6弱以上の地震が起きた場合など
・警戒事態
→放射性物質の放出はないが、PAZ内の要支援者は避難する。
・施設敷地緊急事態
→事故が進展し、放射性物質放出の恐れがある場合、PAZ内の要支援者は避難する。
・全面緊急事態
→事故がさらに進展し、放射性物質放出の可能性が高まった場合、PAZ内の要支援者以外の住民が避難を開始する。UPZ内の全ての住民は屋内退避。
その後、放射性物質が放出された場合、UPZ内の住民は屋内退避を継続。放射線量のモニタリングの結果、基準値を超える地域は自治体からの指示に基づき一時移転を行なう。
九州電力の取り組みについて
現在、内閣府を中心に、国・地方などが参画した原子力防災協議会が発電所の立地地域ごとに設置されており、防災計画や避難訓練の強化が図られている。九州電力もこの協議会に参加しており、原子力防災への積極的な取り組みを行なっている。
万が一、原子力発電所で事故が発生した場合、事業所の責務として住民避難などに関する最大限の支援を行なうこととしている。
具体的な支援について
九州電力は原子力防災支援に関する主な取り組みとして、以下の項目を実施している。
・輸送力支援
→PAZ内の要支援者避難支援を行なうことから、福祉車両やバス、運転手の確保。車椅子等の移動介助知識も必要となるため、社員への教育や訓練を実施し、避難支援の実効性向上を図っている。
・避難退域時検査
→UPZ内の住民が避難や一時移転をする際、車両や衣服に放射性物質が付着していないかの検査を行ない、付着が確認された場合は、除染を行ない避難所へ迎える準備をする。
・生活物資の備蓄支援
→食料品や電化製品などの生活物資を、放射性防護対策施設に備蓄している。
・燃料補給支援
→オフサイトセンター、放射線防護対策施設、モニタリングポストなどの重要施設で停電が長引き、非常用発電機の燃料が無くなる可能性が生じた場合、九州電力により燃料取引先を通じて燃料補給を実施する。
鹿児島に住む我々にとって、原子力発電所はとても身近なものであり、災害時の想定もしなければなりません。今回の事例発表を通して、万が一への意識づけや知識の蓄えができたのではないかを思います。
講演1「JRATって何?鹿児島の災害リハビリテーション活動」
講師:鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 リハビリテーション医学 客員研究員 医師 緒方 敦子 先生

「JRATとは?」
JRATの正式名称は、一般社団法人 日本災害リハビリテーション支援協会(Japan Disaster Rehabilitation Assistance Team) 。2011年の東日本大震災を受け、避難所での生活を行う人たちへリハビリテーション的視点でのコーディネートの重要性が説かれ、同年4月にJRATの始まりとなる支援10団体が設立された。2013年7月には、前身団体から「大規模災害リハビリテーション支援団体関連団体協議会」となったことで「JRAT」としての活動が始まり、2020年4月に、13の団体からなる「一般社団法人 日本災害リハビリテーション支援協会」となり現在の形となった。
JRATは、日本語での文字通り、多職種による「災害リハビリテーション」を行う団体である。
「災害リハビリテーション」とは何か?
JRATは災害リハビリテーションを以下のように定めている。
「災害リハビリテーションとは、被災者・要配慮者の生活不活発病および災害関連死等を防ぐために、リハビリテーション医学・医療の視点から関連専門職が組織的に支援を展開することで、被災者・要配慮者等の早期自立生活の再建、復興を支援する活動である」
災害時に多くの人々は、避難所での生活を余儀なくされる。避難所での生活は、周囲への配慮や、物理的な生活環境が異なることで、心も体も弱まってしまう恐れがある。そうした中で、災害リハビリテーションの役割として、いつもの生活とは違う環境で、普段と変わらない生活が送れるように、環境を整える支援を行うことである。
「JRAT」の具体的な活動について
まず前提として、JRATは避難所における、直接的なリハサービスの提供は行っていない。では、JRATは具体的にどのような活動を行っているのだろうか。JRATが担う大きな役割の一つとして、「避難所における多方面への提案」がある。具体例として、以下の5つがある。
1.避難時環境評価
これは主に、避難所における責任者等への提案である。段ボールベッドの導入や段差の解消、運動スペース設置の必要性等を、リハビリ的視点から提案する。
2.要配慮者に関するリハトリアージ
被災時にはリハビリの必要な人が多く存在する。そうした中で、限られた人員で活動を行うために、リハビリの優先順位を決めて提案する。
3.福祉機器の適切供給
災害時には、普段絶えず供給されている福祉機器(医療材料)が十分に供給されない可能性がある。その中で、本当に必要な材料をリハビリの専門職がみることで、状況に応じた適切な供給に繋げる役割を担う。
4.被災者の活動参加への提案
1における避難所の環境評価を行ったうえで、参加者が自ら役割を担い、活動に参加できるような提案を行う。動きの少なくなった人へ体操を促す等、生活不活発病防止のためには、この活動が非常に重要である。
5.リハビリ関係者への自立支援
被災地で実際にリハビリを行う専門職の人たちに対して、災害時リハビリの知識を持ったJRATの人たちが助言を行うことで、適材適所の活動を促すことに繋がる。
このように、JRATの活動はあくまで、「提案」ベースであるが、この役割が災害時の混乱期においては、大きな役割を持っている。
「JRAT」が活動するうえで
JRATが活動をするうえで、大切にしていることがある。それは、「医療の場」でなく、「生活の場」に足を踏み入れることへの自覚である。その一瞬でなく、継続的に責任を持って活動を行うために、活動報告を綿密に行うことや、他の専門職との連携や協働を怠らないことを重要視している。
「JRAT」の鹿児島での活動
JRATは各地域での活動を行っている。鹿児島における「鹿児島JRAT」は2018年の5月に設立され、多職種による5つの団体が加入している。
鹿児島JRAT 活動報告 - 一般社団法人 日本災害リハビリテーション支援協会
〇活動実例
・2011年 新燃岳の噴火
・2016年 熊本地震
・2018年 西日本豪雨
など
〇主な活動内容
・災害リハビリテーションの啓発活動
・災害リハビリテーション活動に必要な研修会
・協力医療機関のネットワーク構築
など
~質疑応答~
ー行政との繋がりが大事とあったが、行政との関りを持つにはどうすればよいか?
県が主催の災害リハに関する研修が開かれることがあるので、それに参加する。
ー実際に現場に向かうなどの活動はできないが、JRATに関わり、勉強をするにはどうすればよいか?
JRATのホームページをみたり、地域JRATの行う研修会に少しでも顔を出す
事で、コミュニティに交わり、情報共有を行う。

講演2「熊本JRATの教訓を伝承するーリハビリ専門職が自然災害に備える方略ー」
講師:山鹿温泉リハビリテーション病院 総合リハビリテーション部部長 熊本災害リハビリテーション推進協議会 事務局次長佐藤 亮 先生

環境因子の破綻
災害が起こると、環境因子が大きく破綻する。これは、発災直後だけでなく、復興段階にいたるまで、環境・コミュニティともに大きな変化が生じる。発災すると、避難所での生活を余儀なくされる人が多数存在する。災害時は、応急住宅などに移り住み、復興期になるとそこから出て、別の場所へ移り住んだりと、フェーズごとの変化に対応できるような、リハビリ的視点が大事である。
フェーズに応じた活動
・応急修復期
→発災後4日~1ヶ月の時期。この時期には、リハビリトリアージが求められる。
・復旧期
→2ヶ月~6か月ほど経った時期。この時期には、生活不活発病予防への介入が求められる。医療チームで協議を重ね対応措置を行うことで、活動を促す。
・復興期
→6か月~1年が経った時期。この時期よりJRATの活動から、地域リハビリテーションへの移行が始まる。
事前知識の重要性ー熊本地震を例にー
熊本地震の際に、とある県立高校の体育館に多くの人が集まった。しかし、熊本では、指定避難所は自治体により定めらており、県の建物である体育館は避難所には指定されていなかった。それを知らない人たちは、家の近くの体育館を目指して、それを受け入れるしかない、学校側は混雑した環境を生むこととなった。このように、災害に備えた事前の知識の共有といったことが、熊本地震の例で顕著となった。
また、福祉避難所の受け入れにも注意が必要である。福祉避難所は、ハザードマップの危険区域外に指定される。水害の場合などは、そのような事情から福祉避難所への避難が可能だが、地震の際はどこが揺れるか分からないため、実際には避難所として開かれない可能性がある。
災害医療対応の原則
大規模災害時における、基本的なマネジメントの考えとして、「CSCATTT」というキーワードがある。
この「CSCATTT」というキーワードは、7つの単語の頭文字を取ったものであり、以下の7つである。
Command and control(指示命令と協働)
Safety(安全の確認)
Communication(情報の伝達)
Assessment(評価)
Triage(トリアージ)
Treatment(治療)
Transport(移送)
専門職の災害に対しての方略
JMATを含め、様々な団体で活動する専門職は、災害発生時に十分に力を発揮する必要がある。その中で大事になるのが、人材育成だ。実際の被災現場で活動出来ていない団体や人は多数いる(JRATの実際の活動数17団体)。その中で災害が発生した際に、活躍できる人材の育成が求められ、そこでは、熊本地震をはじめとした、経験が必要となる。また、熊本地震の際にみられたような混乱により、生活不活発病などの二次被害を生み出さないためにも、地域住民に対する平時の取り組みも、専門職の視点が大事である。
JRATの後にそれをどう地域リハビリテーションにつなげるかといったことを意識するのも、重要である。
「火事場の馬鹿力」は存在しない。今できることしか、災害時にはできないため、平時でのリハビリの勉強はもちろん、それにプラス災害医療を学んでいるとより力となる。
~質疑応答~
ーこれから先の多職種連携はどのように行われるか
「食」に関してでいえば、入れ歯の問題であれば歯科医師など、姿勢の問題であればPTなど、その人が必要としていることの中で、自分の専門知識がどう活きるかを考える。
ー様々な県のJRATがどのように連携するのか
本部により支援先が決まる。被災地の思いに寄り添う必要がある。そのため、その地域の考えにあった支援を行うために、どの県からどのチームが行っても同じことができる体制をつくる必要がある。

今回は多くの専門職の方々にも参加していただきました。
参加者の感想をご紹介します。
今回、「災害リハ」について、実際に災害の体験・活動をされた先生方の公演を聞くことができたことは、とても貴重な経験でした。災害はいつ起こるかわからないため、講演の中にもありました、「平時にできないことは有事にできない」という言葉にあるように、常日頃より準備や対策など考えておかなければならないことを再認識することができました。
また、災害の現場においては、様々なチームが入ってきます。多職種連携で対応していくことになるため、看護師としてリハ的視点から学ぶことができ、とても勉強になりました。私も災害支援ナースとして登録していることから、常に今後起きうる災害に対して、想定対策を行っていきたいと思います。
今回、緒方先生は「JRAT」という組織について、詳しくお話をしてくださいました。今回の講演では、学生も含めて多くの専門職の方が訪れました。講演を聞いたことで、専門職の方々の活動の選択肢の一つになったのではないかと思います。
佐藤先生の講演では、実際に起きた2016年の熊本の大地震での教訓から、様々な視点でのお話をされていました。被災地での実際の活動から得られた知識による本公演は、専門職にとって、いつ起きてもおかしくない事態への、大きな備えになったのではないかと思います。
今回のリハフォーラムを通して、参加した専門職の人もそうでない人も、「災害」という誰もが、いつ遭遇してもおかしくない事態に対して、十分な知識を得ることができたのではないのかと思います。
この社内報をみて興味を持った方がいれば、是非JRATのHP等も訪れていただければと思います。
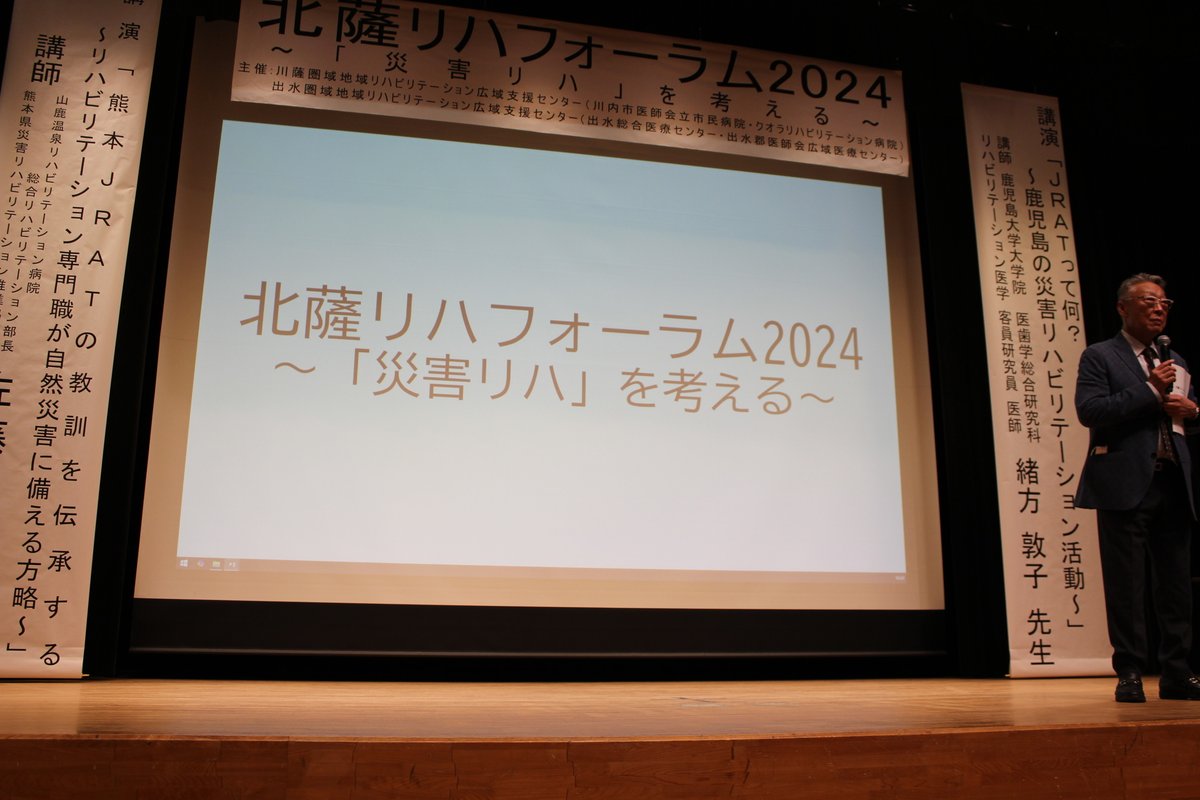
【北薩リハフォーラムの目的と歴史については以下の記事をご覧ください】

