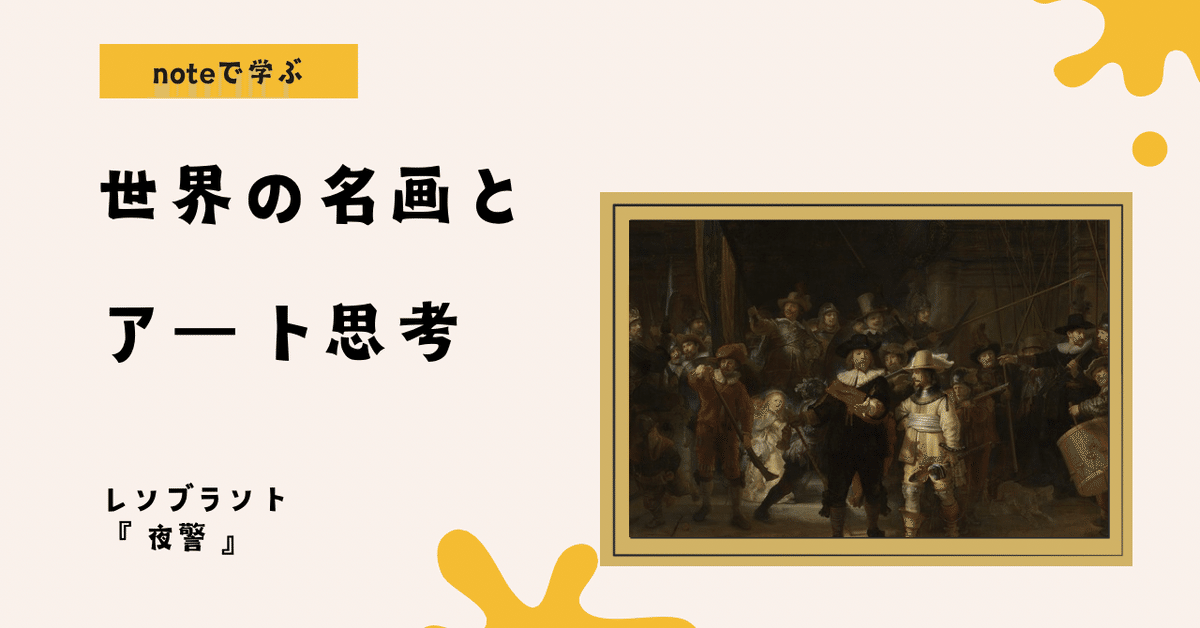
【 noteで学ぶ 世界の名画とアート思考 】 「レンブラント『夜警』の真実:動き出す肖像画がアート史を変えた理由」
= こんな人におすすめの記事です =
「 “ アート ”や“ アート思考 ” ってどうやら大事そうなんだけど、アートの見方もそもそも何なのかも、全然わからない。…でも、我が子に“ アート教育 ”はさせたい! 」
これ、僕の欲求です(苦笑)。
でも、あるある、ですよね?
ですが、なかなかどこを調べたらいいか分からないし、これらの情報にたどり着けないことがしばしば。
…ということで、このnoteでは、『 世界の名画とアート思考 』を週に1つずつお届けしております。皆様の一助になれたら嬉しいです!
なお、『 他にもこんな展覧会がおススメですよ! 』というものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。教えてくださった方に、1コメントにつき100円をnoteのサポート機能でプレゼント!
= そもそもアート思考って? =
色々と言われてはいますが、
「 過去の状況を理解し、その中にある問題点や疑問を発見し、これまでに無い新しい価値観や方法を提案する思考法 」
と僕は理解しています。ここを意識しての名画を観察すると、“ あ!この名画はこういう観点でアート思考を取り入れているんだ! ”と理解しやすくなるので、おススメでございます。
= 今週の名画:夜警 =
動き出す肖像画:レンブラント『夜警』がもたらした衝撃
1642年、オランダのアムステルダムで制作されたレンブラント・ファン・レインの『夜警』。単なる集合肖像画の枠を超え、物語性と躍動感を備えたこの作品は、アート史に革命をもたらしました。本記事では、その芸術的革新性、歴史的背景、そして同時代作品との比較を通じて『夜警』の魅力に迫ります。

光と影が作り出すドラマ:レンブラントの芸術的革新
レンブラントの代名詞ともいえる「明暗法(キアロスクーロ)」は、『夜警』において頂点に達しています。画面中央に配されたキャプテン・フランス・バニング・コックと副官ウィレム・ファン・ルイテンブルフは光に照らされ、まるで舞台のスポットライトを浴びる俳優のように浮かび上がります。一方、周囲の弓兵たちは暗闇の中に沈むことで、光と影のコントラストが鮮烈な印象を与えています。
この非対称な構図は、17世紀オランダの伝統的な集団肖像画とは一線を画すものでした。それまでの肖像画は、人物を整然と並べた静的な構成が主流でしたが、レンブラントは大胆にも「動き」を取り入れ、弓兵たちが一斉に行動を起こしている瞬間を描き出しました。
オランダ黄金時代と『夜警』の誕生
『夜警』が生まれた背景には、17世紀オランダの社会的・経済的繁栄があります。この時代、商業の発展と市民階級の台頭が文化を支え、集団肖像画が盛んに制作されました。『夜警』は、アムステルダムの弓兵隊によって依頼され、市民たちの誇りと連帯感を表現する目的で描かれたのです。
しかし、完成当初の評価は決して芳しいものではありませんでした。依頼主たちは従来の整然とした構図を期待していたため、このダイナミックな画風に驚きと戸惑いを覚えました。それでも、後世の芸術史において『夜警』は、市民肖像画の枠を超えた革新的な作品として高く評価されています。
革新性と同時代作品との比較
『夜警』と同じ時期に制作された他の作品と比較してみましょう。例えば、スペインの巨匠ディエゴ・ベラスケスが手がけた『ラス・メニーナス』は、静的な画面構成ながらも、鑑賞者を巻き込む視線の操作で革新を示しました。一方、フランス・ハルスの『騎士の肖像』は、動きを抑えつつも人物の内面を引き出す描写が特徴です。これらと比べて、『夜警』は動きのある構図と大胆な光の演出で、観る者をその場に引き込みます。
また、レンブラントの技術的な緻密さも注目に値します。衣服や武器の質感描写、光と影の中に隠された細部までが丹念に描かれており、そのリアリズムは他の追随を許しません。特に、中央の小さな少女が持つ黄色い衣装は、画面全体のアクセントとして観る者の目を引きつけます。
アムステルダムで『夜警』に出会う旅
現在、『夜警』はアムステルダム国立美術館(Rijksmuseum)に所蔵されています。この美術館はオランダの国宝ともいえる名作を数多く展示しており、アートファンにとって必見のスポットです。
所在地: Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam, Netherlands
電話番号: +31 20 674 7000
最寄駅: アムステルダム中央駅からトラムでアクセス可能
同館では、レンブラントが活躍したオランダ黄金時代の他の名画も一緒に鑑賞できます。さらに、期間限定の特別展示では、彼の版画作品も公開されています。アートの聖地アムステルダムで、『夜警』の迫力をぜひ体感してください。
* レンブラント *
レンブラント・ファン・レイン(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)は1606年にオランダのライデンで生まれました。幼少期から学業で才能を発揮し、14歳でライデン大学に進学しましたが、芸術への情熱が勝り画家の道を選びました。アムステルダムでピーター・ラストマンに師事した後、自らの工房を持ち、独自のスタイルを確立。特に「光と影」の対比を強調した「明暗法(キアロスクーロ)」の技術は彼の代名詞となり、肖像画や歴史画で高い評価を受けました。生涯を通じて数多くの作品を制作しましたが、経済的困難や個人的な悲劇にも見舞われ、1669年に亡くなるまで波乱の人生を送りました。
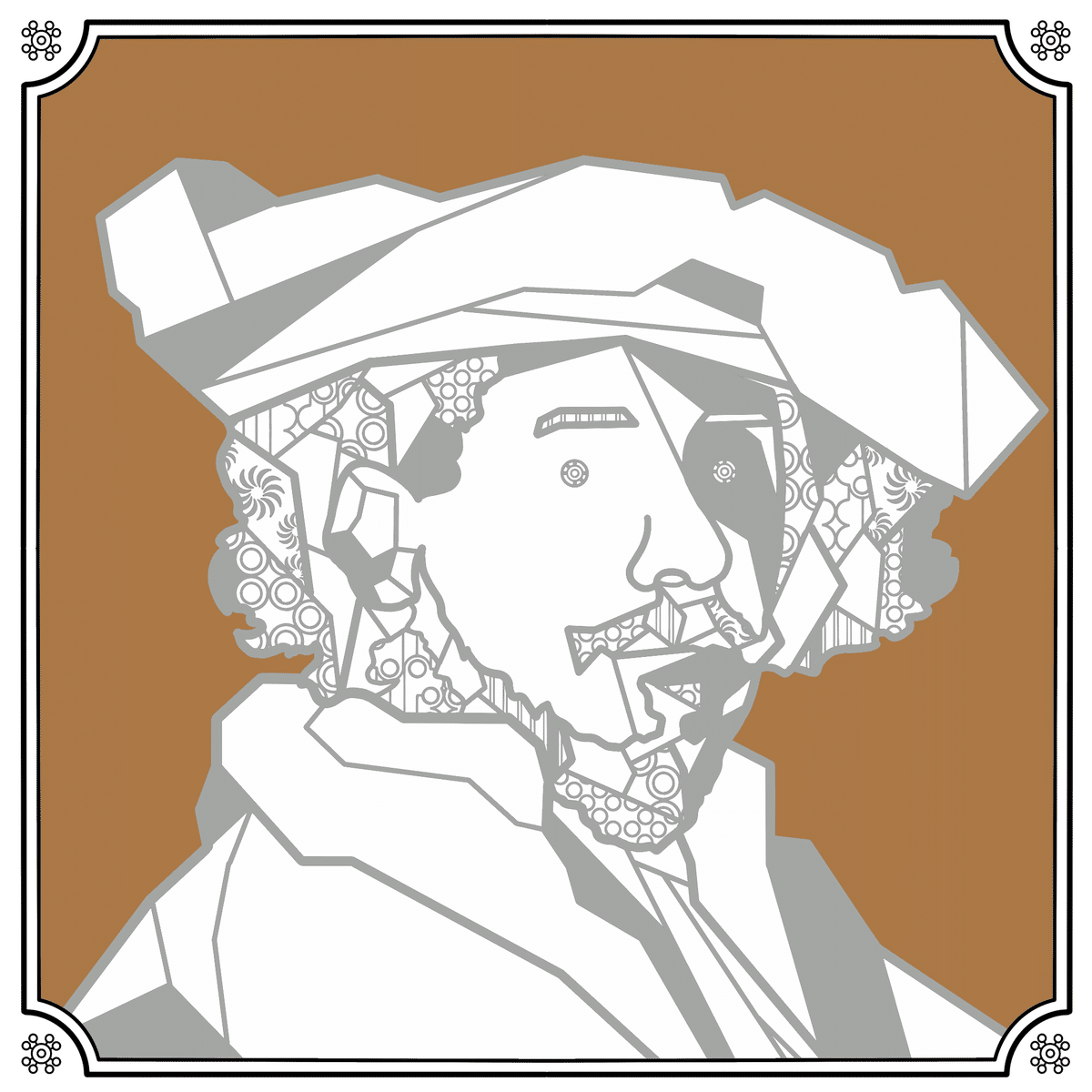
* 合わせて読みたい関連ブログ *
実際のアムステルダム国立美術館の様子が分かります。素敵な雰囲気です…
* 引用
イノベーション創出を実現する「アート思考」の技術
「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考
アート思考 ビジネスと芸術で人々の幸福を高める方法
= あとがき =
noteをご覧いただきありがとうございます。

会社員の傍ら、上海で塗り絵本作家になりました、KENTA AOKIと申します。日本・中国を拠点に、個展をしたり、アジアやアフリカの子供たちと塗り絵イベントを行ったり、塗り絵本を出版したり、そういった作家活動を行っております。
作家活動を進める中で、美大卒でもない、若輩者の私は、“ アート ”に関して日々色々なことを学び、そのうえでアート作品を創るようにしております。というのも、“ 美大卒でもない ”というのが結構コンプレックスなんです。
ただ、そんなことを続けていく中で分かってきたのは、
「 アートを学ぶ方法って色々あって、美大の知識は勉強したらつけられるかも!? 」
「 アートって実は科学的かつ論理的で、むしろ理系向きかも!? 」
「 アートを届けるには、ビジネスの知識も必要なんだな 」
でした。
学べば学ぶほど、アーティストだけが“ アート ”を学ぶ・理解するのは非常にもったいないなと思ったのと同時に、もっともっと“ アート思考 ”を応用すると、おもしろいものやサービスが生まれるんじゃないかと思いました。
日々本を読み、実戦しながら、学んでいる僕がこれらを伝えていくことで、よりリアリティを持って、学びが共有できたら嬉しく思います。僕と同じ境遇にある方々に届き、共感頂けたら更に嬉しいです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
いいなと思ったら応援しよう!

