
「あの日」から12年~3.11を読む~vol.1 学校で
※全3部作
「あの日」から12年が経った。長くもあり短くもあり。
皆さんは何を思い「あの日」を過ごし、何を思いながら今日まで過ごしただろうか。
ーーーーー
1.
今週、人生で初めて宮城県石巻市を訪問した。
とあるきっかけで知人が4月に開催する石巻での芸術祭・個展・ワークショップの設営をお手伝いさせていただくことになり、
その顔合わせとして今回石巻を訪れることになったのだ。
たどり着いた石巻の市街地は昭和さながらの建物たちと現代風リノベーションされた建物たちが混ざり共存している、無秩序な街並み。
新旧の時代文化が混ざり合うこの街並みに新鮮さを感じながら、
レンタルチャリで石巻市街地を周ることにした。
中心部から海沿いに向けて10分ほど走っていく。
すると、下の写真のような小学校が海を向いて聳え立っていた。
いや、正確には小学校「だった」場所だ。

石巻市立門脇小学校。
2015年春に惜しくも閉校してしまったが、それまでは石巻の子供たちの学び舎として地域に根差し、長年生徒たちと地域を支えてきた学校であった。
「あの日」が来るまでは。
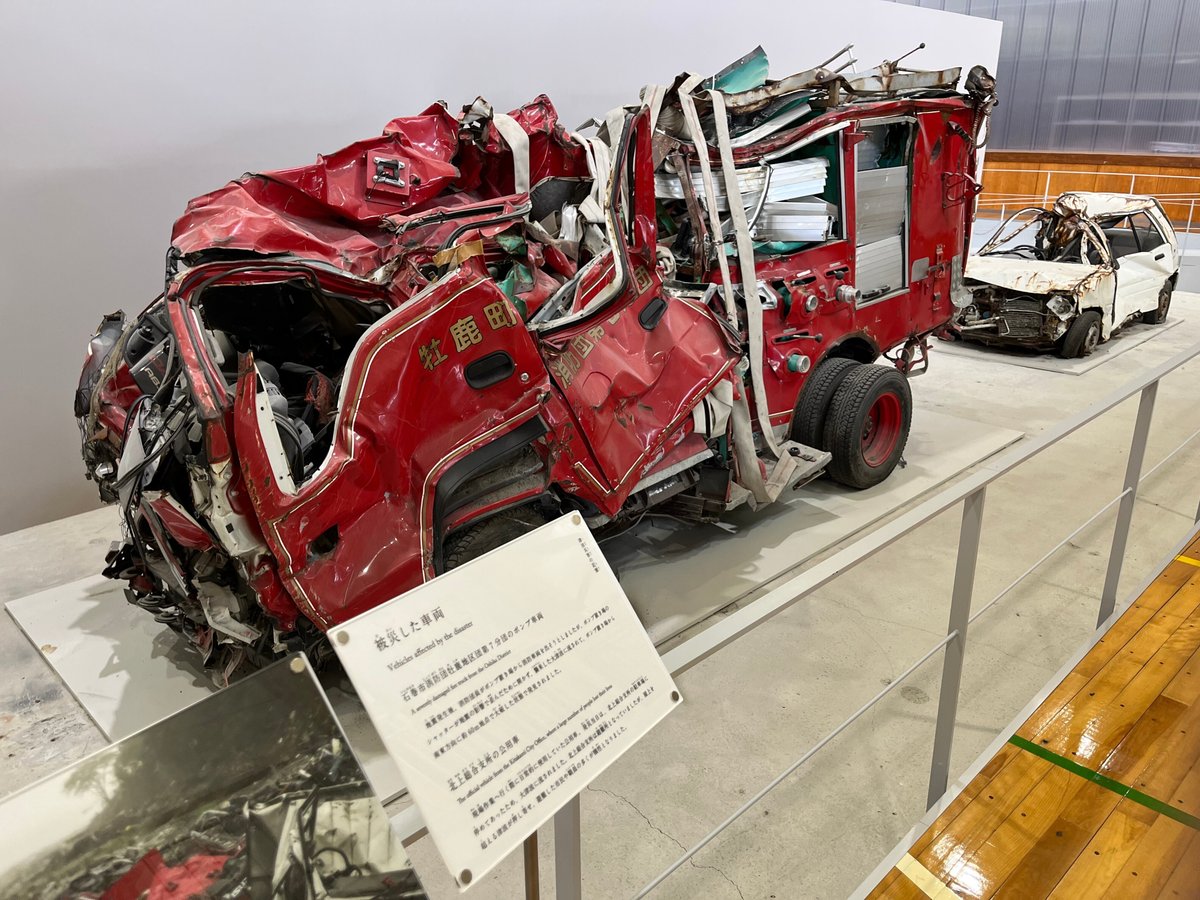
2.
「あの日」、
この小学校は震度6強の地震で打ちのめされ、
8.6mもの巨大な津波により打ち砕かれた。
2011年3月11日 東北地方太平洋沖地震が発生。
学校にいた児童・教職員らは訓練どおりに日和山へと避難しました。
地震から約1時間後、大津波が襲来。
津波火災が発生し、校舎は炎に包まれました。
南浜・門脇地区では500人を超える方が犠牲となりました。
(中略)
門脇小学校は津波火災の痕跡を残す唯一の震災遺構であり、避難を考えるとき垂直避難だけでは難しい一面があることを伝えています。
https://www.ishinomakiikou.net/
「あの日」、たった1時間で黒い巨大な水の壁に襲われ押しつぶされ、
この学校は殺された。
東北沿岸各地でもこのような学校の遺構は何箇所かあるが、
この門脇小は特にその中でも助かった生徒と教師たちが多かった学校として有名だ(全校生徒中224人が助かったものの、下校途中の生徒7人・校庭に避難してきた多くの住民が亡くなった)。

場内で放映されていたドキュメンタリーを観て、壮絶な事実を目の当たりにする。
津波と火災から逃れるため全校生徒・教師たちは屋上に逃げ込み、
そこから教室の教壇を梯子代わりにして裏山の日和山に避難。
とてつもなく重かったであろう教壇を教師全員で必死に担ぎ上げ、
「火事場の馬鹿力」のごとく全員を救出させたという。
上級生たちは率先して背の小さい下級生たちをおんぶしたり靴を貸してあげたり、助け合いながら避難場所まで連れてってくれたという。
当然大勢の人たちがいるものだから、全員救出させるには難しい。
身動きの取りにくいお年寄りの方々には、逃げ遅れて間に合わなかった方もいたらしい。
それでも最後まで全員を救出させ、全員で助かろうと総出で取り組み、
逃げ延びようとしていた。
驚きと同時に、胸の奥からこみ上げてくるものがあった。
もし自分がそんな状況に落とされたとき、
果たして自分は全体を見て適した行動が自分にはできるだろうか?
相手を思いやって行動することができるだろうか?
まさに全員で助け合いながら避難した形跡。
そこには「全員で生き延びよう」とする意志と情愛があった。
3.
「あの日」東京で過ごしていた自分からすれば、
この地域で「あの日」を過ごしていた人々はどのような光景を目にしたか、
どのような経験をしたか、
どのような想いで今日まで生きてきたか、
簡単に想像できるものではない。
ただできることは、
このようにかつて人々が懸命に生きようとしていた場所に赴き、
その当時に思いを馳せること。
そしてこれだけ人々が強烈な意志と情愛をもって助け合い、
生き延びた場面があったということを知ること。
それらを「まず知り」、そして「共有する」。
そんなシンプルなことこそが次の時代へと繋がり、新たな時代を作り出すのではないだろうか。
ーーーーー
現在この小学校は「遺構」として残り、
現世に向けて「あの日」何が起こったかを黙して伝えている。
かつて子供たちの営みがあったこと、
生徒と教師と地域の方々総出で
ともに励み、学び、悲しみ、楽しみ、喜んだ息吹が
存在していたこと。
必死に肩寄せ合い生き延びようとしたこと。
すべて克明に残し、現世の人たちに伝えている。
