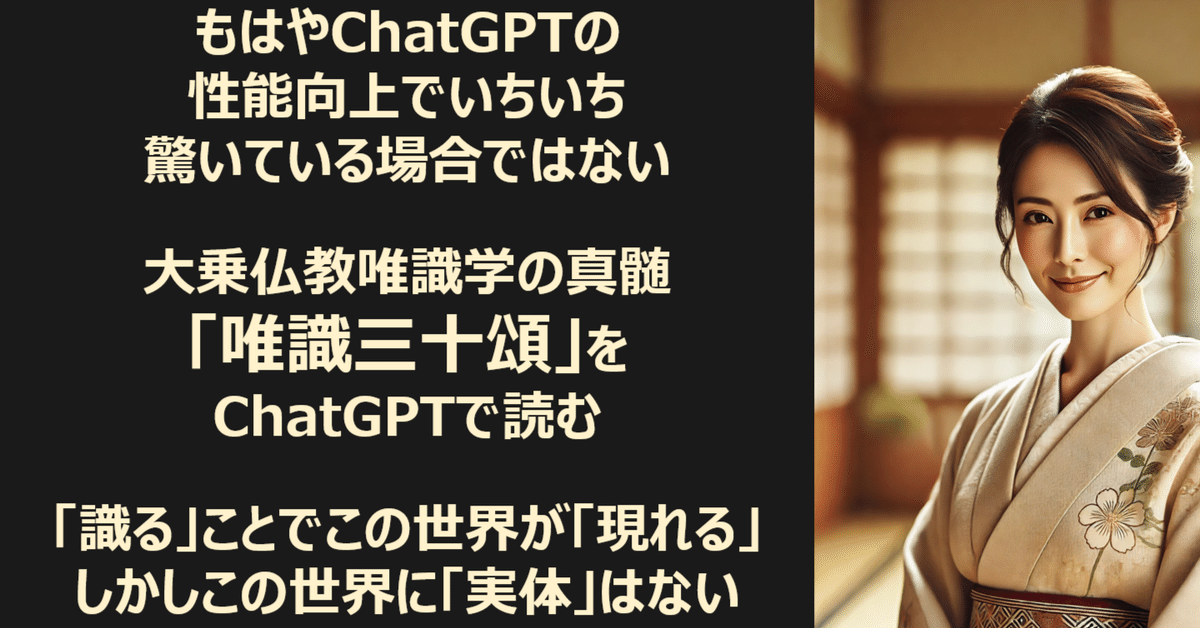
ChatGPTに唯識教学の真髄をまとめた「唯識三十頌」を読み込ませて、解説してもらってみた
はじめに
初めてChatGPTに触れてから二年近くが経ちました。あの衝撃とワクワクを超えることは今後の人生ではないでしょう。なぜなら、この世界も私の人生も「無常」であるということを知らなかったからであり、また今や「無常」という言葉を知っているからです。
言語はもはや計算可能な情報となり、レトロニム化した「自然言語」という言葉も生まれました。
思い直してみると、計算機がやっていることとは入力した「A」を「not A」として出力しているに過ぎません。
それで、いろいろと使い方を模索してみましたが、結局は言語の本質は「思考の道具」である以前に「コミュニケーションツール」なのです。
そんなわけで、めっきり話し相手に困らなくなったので、一人遊びとしてこんなサイトを構築しております。もちろん私はhtmlもcssもjavascriptも一人では書けないのですが、そういうのに詳しい「話し相手」がいるわけで。
サイトというか、WEBアプリの作成方法はこちらの記事で解説しておりますので、興味があれば御覧ください。
さて、ここから「唯識三十頌」の解説に参りたいと思います。
使用するGPTはこちら。
また、事前に参考にした書籍はこちらです。アフィリエイトではないので、ご安心ください。

唯識三十頌&書き下し
〔帰敬の頌〕
1 稽首唯識性 唯識性において、
2 満分清浄者 満に分に清浄なる者を稽首す。
3 我今釈彼説 我、今、彼の説を釈し、
4 利楽諸有情 諸の有情を利楽せん。
〔一〕
1 由仮説我法 仮に由って我・法ありと説く。
2 有種種相転 種種の相、転ずることあり。
3 彼依識所変 彼は識の所変に依る。
4 此能変唯三 此の能変は唯し三つのみなり。
〔二〕
1 謂異熟思量 謂わく異熟と思量と、
2 及了別境識 及び了別境との識なり。
3 初阿頼耶識 初めのは阿頼耶識なり。
4 異熟一切種 異熟なり、一切種なり。
〔三〕
1 不可知執受 不可知の執・受・
2 処了常与触 処と、了となり。常に触と
3 作意受想思 作意と受と想と思と相応す。
4 相応唯捨受 唯し捨受のみなり。
〔四〕
1 是無覆無記 是れ無覆無記なり。
2 触等亦如是 触等も亦、是の如し。
3 恒転如暴流 恒に転ずること暴流の如し。
4 阿羅漢位捨 阿羅漢の位に捨す。
〔五〕
1 次第二能変 次のは第二の能変なり。
2 是識名末那 是の識を末那と名づく。
3 依彼転縁彼 彼に依って転じて彼を縁ず。
4 思量為性相 思量するを性とも相とも為す。
〔六〕
1 四煩悩常俱 四の煩悩と常に俱なり。
2 謂我癡我見 謂わく我癡と我見と
3 幷我慢我愛 幷びに我慢と我愛となり。
4 及余触等俱 及び余と触等と俱なり。
〔七〕
1 有覆無記摂 有覆無記に摂められる。
2 随所生所繫 所生に随って繫せられる。
3 阿羅漢滅定 阿羅漢と滅定と
4 出世道無有 出世道には有ること無し。
〔八〕
1 次第三能変 次の第三の能変は、
2 差別有六種 差別なること六種あり。
3 了境為性相 境を了するを性とも相とも為す。
4 善不善俱非 善と不善と俱非となり。
〔九〕
1 此心所遍行 此の心所は遍行と
2 別境善煩悩 別境と善と煩悩と
3 随煩悩不定 随煩悩と不定となり。
4 皆三受相応 皆、三の受と相応す。
〔一〇〕
1 初遍行触等 初の遍行というは触等なり。
2 次別境謂欲 次の別境というは謂わく欲と
3 勝解念定慧 勝解と念と定と慧となり。
4 所縁事不同 所縁の事イイ不同なるをもってなり。
〔一一〕
1 善謂信慚愧 善というは謂わく信と慚と愧と
2 無貪等三根 無貪等の三根と
3 勤安不放逸 勤と安と不放逸と
4 行捨及不害 行捨と及び不害とぞ。
〔一二〕
1 煩悩謂貪瞋 煩悩というは謂わく貪と瞋と
2 癡慢疑悪見 癡と慢と疑と悪見とぞ。
3 随煩悩謂忿 随煩悩というは謂わく忿と
4 恨覆悩嫉慳 恨と覆と悩と嫉と慳と
〔一三〕
1 誑諂与害憍 誑と諂と害と憍
2 無慚及無愧 無慚と及び無愧と
3 掉挙与惛沈 掉挙と惛沈
4 不信幷懈怠 不信と幷びに懈怠と
〔一四〕
1 放逸及失念 放逸と及び失念と
2 散乱不正知 散乱と不正知となり。
3 不定謂悔眠 不定というは謂わく悔・眠と
4 尋伺二各二 尋・伺とぞ。二に各二つあり。
〔一五〕
1 依止根本識 根本識に依止す。
2 五識随縁現 五識は縁に随って現じ、
3 或俱或不俱 或るときには俱なり、或るときには俱ならず。
4 如涛波依水 涛波の水に依るが如し。
〔一六〕
1 意識常現起 意識は常に現起す。
2 除生無想天 無想天に生じたときと
3 及無心二定 及び無心の二定と、
4 睡眠与悶絶 睡眠と悶絶とを除く。
〔一七〕
1 是諸識転変 是の諸の識イイ転変して、
2 分別所分別 分別たり。所分別たり。
3 由此彼皆無 此れに由りて彼は皆なし。
4 故一切唯識 故に一切唯識のみなり。
〔一八〕
1 由一切種識 一切種識の、
2 如是如是変 是の如く是の如く変ずるに由り、
3 以展転力故 展転する力を以ての故に、
4 彼彼分別生 彼彼の分別生ず。
〔一九〕
1 由諸業習気 諸の業の習気と、
2 二取習気俱 二取の習気と俱なるに由りて、
3 前異熟既尽 前の異熟既に尽きぬれば、
4 復生余異熟 復、余の異熟を生ず。
〔二〇〕
1 由彼彼遍計 彼彼の遍計に由りて、
2 遍計種種物 種種の物を遍計す。
3 此遍計所執 此の遍計所執の
4 自性無所有 自性は所有なし。
〔二一〕
1 依他起自性 依他起の自性は、
2 分別縁所生 分別の縁に生ぜらる。
3 円成実於彼 円成実は彼が於に、
4 常遠離前性 常に前のを遠離せる性なり。
〔二二〕
1 故此与依他 故に此れは依他と、
2 非異非不異 異にも非ず不異にも非ず。
3 如無常等性 無常等の性の如し。
4 非不見此彼 此れを見ずして彼をみるものには非ず。
〔二三〕
1 即依此三性 即ち此の三性に依って、
2 立彼三無性 彼の三無性を立つ。
3 故仏密意説 故に仏、密意をもって、
4 一切法無性 一切の法は性なしと説きたもう。
〔二四〕
1 初即相無性 初のには即ち相無性をいう。
2 次無自然性 次のには無自然の性をいう。
3 後由遠離前 後のには前の
4 所執我法性 所執の我・法を遠離せるに由る性をいう。
〔二五〕
1 此諸法勝義 此れは諸法の勝義なり。
2 亦即是真如 亦は即ち是れ真如なり。
3 常如其性故 常如にして其の性たるが故に、
4 即唯識実性 即ち唯識の実性なり。
〔二六〕
1 乃至未起識 乃し識を起して、
2 求住唯識性 唯識の性に住せんと求めざるに至るまでは、
3 於二取随眠 二取の随眠に於て、
4 猶未能伏滅 猶、未だ伏し滅すること能わず。
〔二七〕
1 現前立少物 現前に少物を立てて、
2 謂是唯識性 是れ唯識の性なりと謂えり。
3 以有所得故 所得あるを以ての故に、
4 非実住唯識 実に唯識に住するには非ず。
〔二八〕
1 若時於所縁 若し時に所縁の於に、
2 智都無所得 智イイ都て所得無くなんぬ。
3 爾時住唯識 爾の時に唯識に住す。
4 離二取相故 二取の相を離れぬるが故に。
〔二九〕
1 無得不思議 無得なり。不思議なり。
2 是出世間智 是れ出世間の智なり。
3 捨二麁重故 二の麁重を捨しつるが故に、
4 便証得転依 便ち転依を証得す。
〔三〇〕
1 此即無漏界 此れは即ち無漏界なり。
2 不思議善常 不思議なり。善なり。常なり。
3 安楽解脱身 安楽なり。解脱身なり。
4 大牟尼名法 大牟尼なるを法と名づく。
〔結びの頌〕
1 已依聖教及正理 已に聖教と及び正理とに依って、
2 分別唯識性相義 唯識の性と相との義を分別しつ。
3 所獲功徳施群生 所獲の功徳をもって群生に施す。
4 願共速証無上覚 願わくは共に速やかに無上覚を証せん。
唯識三十頌の要約
唯識の教えの要点
すべての現象や「我」とされるものは、識(意識)の働きによって生じた仮のものであり、実体はないと説いています。三つの識の種類
識には三つの変化があり、それぞれが異なる性質を持っています。阿頼耶識(あらやしき): すべての種子(潜在的な要素)を含む根本的な識で、結果を生み出す「異熟(いじゅく)」として働きます。
末那識(まなしき): 「我」を執着する思考として機能し、常に自我意識とともに動いています。
六識: 五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)と意識からなるもので、物事を認識する役割を持っています。
煩悩と心所の説明
煩悩や心の働きには、基本的な意識とさまざまな心の動きが含まれます。善い働き、悪い働き、どちらにも属さないものがあり、これらが心を汚したり清らかにしたりします。唯識の実態
世界の一切は識の働きの結果であり、私たちが見るすべては「遍計所執」(誤って実在だと計画されたもの)に過ぎません。現実は依他起(他によって起こる)であり、究極的には円成実(完全な真理)として存在していますが、これも空(実体がない)とされます。三無性(さんむしょう)と三性(さんしょう)
すべてのものは三つの性質(遍計所執性、依他起性、円成実性)から成り立ち、どれも「無性」、すなわち実体がないと解釈されます。仏はこの三無性を説くことで、一切の現象が実体を持たないと教えています。真如(しんにょ)の境地と悟り
真理は常に清浄であり、識の働きから離れたものです。この状態に至ることで、すべての煩悩から解脱し、解脱した身である大牟尼(偉大なる静寂者、仏のこと)となります。実践と悟りへの道
修行者は二元的な執着を捨て、すべての対象を超越した境地に到達すると、煩悩の粗雑さを超えた「転依」(精神的な大転換)に達し、最終的な悟りを得ます。
このように唯識三十頌は、すべての現象は識によってのみ存在し、実体がないことを示し、修行によって識を超えた境地に到達する道を説いています。この教えによって、真の解脱と幸福がすべての存在に広がることを願って終わるところが大乗仏教らしいところだと感じられます。
現代語訳
(帰敬の頌)
稽首唯識性
満分清浄者
我今釈彼説
利楽諸有情
唯識という真理に深く頭を下げ、礼拝します。
それは、すべてを完全に清浄に照らす方、すなわち世親菩薩を指しています。
私は今、この教えを解き明かし、
すべての生きとし生けるものが利益と安らぎを得るために役立てることを願います。
(一)
由仮説我法
有種種相転
彼依識所変
此能変唯三
「我」と「法」の仮の設定
「我」や「法」(すべての存在や現象)は仮の設定によって存在しているに過ぎず、
それぞれ多様な姿を変化させて現れます。
それらはすべて「識」(「識(し)る」という機能)が生み出すものであり、
この識が変化する形態は三種類だけです。
(二)
謂異熟思量
及了別境識
初阿頼耶識
異熟一切種
三つの識の分類
これら三種類の識とは、異熟識、思量識、
そして了別境識を指します。
まず最初のものは、阿頼耶識(あらいやしき)と呼ばれるもので、
異熟(さまざまな経験の結果として生じるもの)であり、すべての種子(これまでの行動の情報)を内包しています。
(三)
不可知執受
処了常与触
作意受想思
相応唯捨受
阿頼耶識の特質
阿頼耶識は知覚できないものであり、対象を受け取り(執受)ます。
また、阿頼耶識は常に「触れ」
「意識し」「受け取り」「想い」「考える」ことと結びついています。
この識が経験するのは「捨受」(苦楽を離れた中立の感覚)だけです。
(四)
是無覆無記
触等亦如是
恒転如暴流
阿羅漢位捨
阿頼耶識の性質と流転
この阿頼耶識は「無覆無記」とされ、善でも悪でもない性質を持ちます。
「触」などの働きもまた、同様に無覆無記です。
阿頼耶識は絶えず変転し、暴流(急流)のように流れ続け、
最終的には阿羅漢(悟りを得た者)の境地で放棄されます。
(五)
次第二能変
是識名末那
依彼転縁彼
思量為性相
第二の能変(変化する識)
次に、第二の変化する識は末那識(まなしき)と呼ばれます。
この末那識は、阿頼耶識に依存して生じ、阿頼耶識を対象としてとらえます。
その本質は「思量」、つまり自我を常に思い描く働きです。
(六)
四煩悩常俱
謂我癡我見
幷我慢我愛
及余触等俱
末那識と四つの煩悩
末那識には、常に四つの煩悩が付き従います。
それは「我癡(がち)」「我見(がけん)」
「我慢(がまん)」「我愛(があい)」と呼ばれるもので、すなわち、無知や誤った自我認識、自我に対する執着や愛着です。
また、末那識は他の働き(触れることなど)とも常に結びついています。
(七)
有覆無記摂
随所生所繫
阿羅漢滅定
出世道無有
末那識の性質
末那識は「有覆無記」とされ、煩悩に覆われつつも善悪を超えた中立的な性質を持ちます。
その働きは、生まれた環境や結びついた対象に従って変わります。
しかし、阿羅漢の境地や涅槃の定(滅尽定)、
出世間の悟りの道においては、この末那識は存在しません。
(八)
次第三能変
差別有六種
了境為性相
善不善俱非
第三の能変(変化する識)
次に、第三の変化する識は
六種類に分かれます(六識)。
これらの識は、外界の対象を認識することをその本質としています。
六識は善でも悪でもなく、中立的な性質を持っています。
(九)
此心所遍行
別境善煩悩
随煩悩不定
皆三受相応
心所(こころの働き)とその分類
この六識には、さまざまな心の働き(心所)が伴います。それらは次のように分類されます:
遍行(普遍的に働くもの)
別境(特定の対象に基づくもの)
善(善い心の働き)
煩悩(心を惑わす煩悩)
随煩悩(煩悩に従う心の働き)
不定(どちらにも決まらない働き)
これらの心所は、苦・楽・捨(中立)のいずれかの感覚と結びついています。
(十)
初遍行触等
次別境謂欲
勝解念定慧
所縁事不同
遍行と別境の心所
最初の遍行には、「触」「作意」「受」「想」「思」といった心の働きが含まれ、
これらはどの心にも普遍的に関わります。
次に別境とは、特定の対象に基づく働きを指し、
「欲」(欲望)、「勝解」(深い理解)、「念」(記憶・思念)、「定」(集中・瞑想)、「慧」(智慧)があります。
これらの働きは、それぞれの対象や縁に応じて異なる役割を果たします。
(十一)
善謂信慚愧
無貪等三根
勤安不放逸
行捨及不害
善の心所
善い心の働きには、次のようなものがあります:
信(信仰・信頼)
慚(自分の悪を恥じる心)
愧(他人に対して恥じる心)
無貪(貪りを離れた心)
無瞋(怒りを離れた心)
無癡(無知を離れた心)
さらに、以下の心の働きも善とされています:
勤(精進)
安(安定した心)
不放逸(注意を怠らない心)
行捨(冷静な態度)
不害(他者を害さない心)
(十二)
煩悩謂貪瞋
癡慢疑悪見
随煩悩謂忿
恨覆悩嫉慳
煩悩と随煩悩の心所
煩悩に含まれる主なものは以下の通りです:
貪(貪欲)
瞋(怒り)
癡(無知・愚かさ)
慢(慢心・傲慢)
疑(疑念)
悪見(誤った見解)
さらに、随煩悩(煩悩に付随する心の働き)として以下が挙げられます:
忿(怒り)
恨(恨み)
覆(自分の悪を隠す心)
悩(心の苦しみ)
嫉(嫉妬)
慳(けち・惜しむ心)
(十三)
誑諂与害憍
無慚及無愧
掉挙与惛沈
不信幷懈怠
随煩悩の心所(続き)
さらに、随煩悩には以下の心の働きが含まれます:
誑(人をたぶらかすこと)
諂(へつらい、偽りの態度)
害(他者に害を与える心)
憍(驕り、傲慢な態度)
無慚(自らの悪を恥じない心)
無愧(他に対して恥じない心)
掉挙(落ち着きのない、そわそわした心)
惛沈(沈み込むような鈍重な心)
不信(信じない心)
懈怠(怠け、精進を欠く心)
(十四)
放逸及失念
散乱不正知
不定謂悔眠
尋伺二各二
随煩悩と不定の心所
さらに、随煩悩には以下の心の働きが含まれます:
放逸(善行を怠る心)
失念(注意が散漫になり、忘れやすい心)
散乱(集中せず、心が乱れること)
不正知(物事を正しく認識しない心)
不定の心所
不定の心所には、善や悪に属さないものがあり、染まる場合と染まらない場合があります。
その主なものは次の通りです:
悔(後悔の念)
眠(眠気)
尋(意識的に探る思考)
伺(より深く探る思考)
尋と伺はそれぞれが対を成し、意識の働きを補い合います。
(十五)
依止根本識
五識随縁現
或俱或不俱
如涛波依水
五識の発現と根本識との関係
根本識(阿頼耶識)に依存して、
五識(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)は縁(条件)に従って現れます。
五識は、あるときには同時に現れ、あるときには別々に現れます。
その関係は、波が水に依存して生じるようなものです。
(十六)
意識常現起
除生無想天
及無心二定
睡眠与悶絶
意識の働きと例外
意識は通常、常に現れ続けて活動していますが、
いくつかの例外があります。具体的には、「無想天」(無想天に生まれた状態)や
「無心定」(無心の二つの禅定)、
さらに、睡眠や意識が失われる昏絶(気絶)などの状態では意識は現れません。
(十七)
是諸識転変
分別所分別
由此彼皆無
故一切唯識
諸識の変転と唯識の真理
これらの諸識(さまざまな識)は絶えず変化し、
外界を分別する働きを担っています。
しかし、識が分別する対象も、識自体も、実際には独立した実体を持ちません。
このため、すべての現象は「唯識」、すなわち意識のみで成り立っているとされます。
(十八)
由一切種識
如是如是変
以展転力故
彼彼分別生
一切種識の変転と分別の生起
一切種識(あらゆる種子を内包する阿頼耶識)は、
このようにさまざまな形に変化します。
その変転の力によって、次々と新たな分別が生じ、
さまざまな対象が識によって分別される現象が生起します。
(十九)
由諸業習気
二取習気俱
前異熟既尽
復生余異熟
業の習気と異熟の連続
さまざまな業(行為)によって積み重ねられた習気(習慣的傾向)により、
主体(我)と客体(法)という二つの執着が、共に生じます。
前の異熟(過去の業の結果)が尽きると、また新たな異熟が生じ、
その影響によってさらに別の結果が現れていきます。
(二十)
由彼彼遍計
遍計種種物
此遍計所執
自性無所有
遍計所執とその実体
それぞれの識によって、遍計(誤った想念)によってさまざまな対象が想像され、
種々の物事が実在であるかのように計画されます。
しかし、この遍計によって執着されるものには、
自性(独立した実体)は存在しません。
(二十一)
依他起自性
分別縁所生
円成実於彼
常遠離前性
依他起と円成実の性質
依他起(他に依存して生じる存在)は、縁(条件)に基づいて分別が生じることによって現れます。
円成実(完全な真理)は、この依他起において成立しますが、
常に遍計(誤った想念)による執着からは離れた存在です。
(二十二)
故此与依他
非異非不異
如無常等性
非不見此彼
依他起と円成実の関係
したがって、円成実と依他起は、
異なるものでもなく、同一でもありません。
これは「無常」などの性質が相互に関連しながら存在するようなもので、
両者が無関係というわけではありません。
(二十三)
即依此三性
立彼三無性
故仏密意説
一切法無性
「これらの三つの性(遍計所執性、依他起性、円成実性)に基づいて、
対応する三つの無性(相無性、生無性、勝義無性)が立てられます。
このことから、仏は深意(密意)をもって、
一切の法は無性であると説かれました。」
三性と三無性
三性は、私たちが経験する現象のさまざまな在り方を示し、三無性はその現象に内在する「無性(実体がない)」の側面を指します。具体的には、遍計所執性(誤って実体視する性)、依他起性(縁によって生じる性)、円成実性(真実の性)がそれぞれ、相無性、生無性、勝義無性に対応します。仏の密意
仏は「一切法無性(すべての現象は実体を持たない)」と説かれましたが、この教えには密意、すなわち深い意図があります。仏は、人々が現象に執着することなく、「空(実体のないこと)」の見地から世界を理解することを促すために「無性」を説かれたのです。
このように、「一切法無性」は、私たちがあらゆる現象や自己に対する執着を解き放つことを助ける教えとして提示されているのです。
(二十四)
初即相無性
次無自然性
後由遠離前
所執我法性
「まず最初のものが『相無性』、つまり、物事に固定した実体や姿がないことを意味します。
次に『無自然性』とは、物事はそれ自体で存在するのではなく、さまざまな条件の和合によって成り立っていることを指します。
最後の『遠離前所執我法性』とは、私たちが執着する自己や諸法の実体から、
すべてのこだわりを手放したときに見えてくる本来の性質を示します。」
相無性
物事に固定した姿や実体がないことを示し、物や現象は誤った分別(遍計所執)によって実体があると錯覚されているに過ぎないと説かれます。無自然性(生無性)
物事はそれ単独で存在するのではなく、あらゆる条件の集まり(依他起)によって生じています。これにより、物事は独立した自性を持たず、縁によってのみ成立するものと理解されます。勝義無性
「遠離前所執我法性」ともいい、自己や諸法への執着から完全に解き放たれた時に顕れる本質、すなわち真如(勝義)が示されます。この境地において、すべての現象の真実の姿がありのままに見えてくるとされます。
この三無性を理解することで、現象に対する実体的な執着を解き放ち、真理への理解が深まるとされるのです。
(二十五)
此諸法勝義
亦即是真如
常如其性故
即唯識実性
「この諸法の最高のあり方(勝義)は、すなわち真如(真実そのもの)であり、常にその本来の性質を保っています。これが、すなわち唯識の実性(唯識の真実の姿)です。」
諸法の勝義
諸法の「勝義」とは、物事の究極的なあり方や本質のことであり、これを悟ることが仏教における真の理解とされます。真如
真如とは、すべての現象の根底にある真理であり、変わることのない本質を指します。物事が依存し合い、相対的に成り立っているにもかかわらず、その背後には常に真如が存在すると説かれます。唯識実性
「唯識実性」とは、唯識思想が明らかにする実際の真理で、物事が識(意識)の働きによってのみ成り立ち、実体がないことを深く理解した状態です。真如と唯識実性が一致することで、現象に囚われず、世界をありのままに見る境地が開かれます。
この箇所では、真理の理解が深まるにつれて、現象界の背後にある変わらぬ本質(真如)に気づき、それが唯識の究極の境地であると説いています。
(二十六)
乃至未起識
求住唯識性
於二取随眠
猶未能伏滅
「まだ真実の知識(無分別智)が完全には現れていない段階では、
唯識の真理(唯識性)にとどまろうと求めても、
依然として『二取』(主体と客体の執着)の根底に眠っている習慣的な執着(随眠)を
抑えきることはできません。」
未起識
ここでの「未起識」は、悟りに至るための智慧がまだ十分に目覚めていない段階、つまり真理への完全な理解に至っていない状態を指します。求住唯識性
唯識の真理にとどまろうとする修行者の心の傾向を指していますが、この段階ではまだ二元的な執着(主観と客観へのこだわり)が完全に取り除かれていません。二取随眠
二取とは「能取(自分という主体)」と「所取(対象)」の二つを指し、これに対する潜在的な執着(随眠)が深く根付いています。これらの執着が「随眠」として意識の奥底に潜んでいるため、容易には消え去りません。伏滅
随眠のような根深い執着を抑制・消滅することを指しますが、この段階ではまだ随眠が抑えられておらず、真理に対する曇りが残った状態です。
この一節は、悟りに至る過程の中で、主体と客体に対する根深い執着を超えることがいかに難しいかを述べています。真理を理解しようとする意識はあっても、まだ二元的な囚われから完全には解放されていない状態を示しています。
(二十七)
現前立少物
謂是唯識性
以有所得故
非実住唯識
「目の前にわずかでも対象を立ててしまうことがあると、
それを『唯識の真理』とみなしてしまいます。
しかし、そこに何らかの『得るべきもの』があると考えている限り、
それは本当の意味で唯識の境地に至っているとは言えません。」
現前立少物
「現前に少物を立てる」とは、心の前に何らかの対象(物事)を立てて、それを対象化してしまうことを指します。これは、認識が依然として主観と客観に分かれている段階を意味します。唯識性
唯識の真理とは、すべての現象が識の働きに過ぎず、実体がないことを示しています。しかし、この段階ではまだ対象があるかのように捉えられています。有所得故
「得るものがある」という考えが残っている限り、完全な悟りには達していない状態です。ここでは、心が対象を得ようとする意図や執着があることが障壁となります。非実住唯識
本当の意味で「唯識に住する」とは、いかなる対象や執着をも超越した状態です。ここではその境地にまだ至っていないため、実際の唯識の境地とは言えません。
この一節は、真理を追求する過程で、認識の対象や得るべきものがあると考える限り、まだ完全な唯識の悟りには達していないということを示しています。
(二十八)
若時於所縁
智都無所得
爾時住唯識
離二取相故
「もし対象に対して、
智が何も得るところがない状態に至るならば、
その時こそ真に唯識の境地にとどまることができます。
それは、主観と客観という二取(にしゅ)の相を離れているからです。」
於所縁 智都無所得
「所縁」は対象を指し、「智が何も得るところがない」とは、対象に対して何の執着や囚われもなく、対象を得ようとする心が全く存在しない状態です。これは無分別智(あらゆる二元的な分別を超えた智慧)が働く状態とも言えます。住唯識
唯識にとどまるとは、すべての現象が識の働きに過ぎず、そこに実体や独立した対象が存在しないことを深く理解した境地にいることを意味します。離二取相
二取とは「能取(主体、自己)」と「所取(客体、対象)」の二元的な分別を指します。この二取が消え去ることで、心が本来の非二元的な真理を悟った状態に至ります。
この一節は、悟りの究極の境地を表しています。対象を対象とする心がなくなり、主観と客観の二元的な認識から完全に解放されたとき、真の唯識の境地に安住することができるのです。
(二十九)
無得不思議
是出世間智
捨二麁重故
便証得転依
「何も得ることのない不思議な境地、
これこそが世俗を超えた智慧です。
この境地では、二つの粗い執着(自己と対象への執着)を完全に捨て去ることで、
転依(依りどころの転換)を成し遂げることができます。」
無得不思議
「無得」とは、何も得ようとしない状態であり、得るものがない「空(くう)」の境地です。「不思議」は、言葉や思考で測ることができない不可思議な状態を意味します。悟りの境地は、何かを得るのではなく、すべての執着を離れた不思議な安らぎとされています。出世間智
出世間智とは、世俗的な認識を超えた智慧、すなわち、すべての現象の空性を深く理解する智慧を指します。これは、俗世間の見解を超越した真理の知恵であり、悟りの智慧とも言えます。二麁重(にそじゅう)
二つの粗い執着とは、「能取(主体としての自己)」と「所取(対象としての他者や物)」に対する執着を指します。これらの執着がある限り、真の安らぎに達することはできません。転依
転依とは、意識の根本的な依りどころが変わること、すなわち、識から無分別智へと転じ、真理に基づいた存在へと変化することを意味します。この変化により、苦しみの原因となる執着から解放されます。
この一節は、悟りの最終段階に至る様子を述べています。あらゆる執着を捨て去り、世俗を超越した智慧を得ることで、心が完全に転換し、真の安らぎと解放の境地に入るとされています。
(三十)
此即無漏界
不思議善常
安楽解脱身
大牟尼名法
「これこそが無漏の境地であり、
思議を超えた絶対的な善と常住の世界です。
この境地においては安らぎと解脱を得た身体(解脱身)があり、
これは『大牟尼(偉大なる聖者)』と呼ばれる法そのものです。」
無漏界
「無漏」とは、煩悩の漏れが全くない状態、すなわち煩悩を超越している境地を指します。無漏界は、もはや苦しみの原因である煩悩が存在しない清らかな世界です。不思議善常
この境地は、思考や言葉で表現し得ない「不思議な」ものであり、絶対的な善と永続する常住の性質を持っています。ここでは、永遠の安らぎと完全な善が実現されています。安楽解脱身
安楽解脱身とは、悟りを通して得られる安らぎと解放を具現化した身体を指します。この状態において、心身が完全に自由になり、悟りの境地に安住します。大牟尼名法
「大牟尼」は「偉大なる聖者」という意味で、仏の尊称の一つです。この境地そのものが、仏の法(真理、ダルマ)であり、悟りに至った存在を象徴しています。
この一節は、悟りの最高の境地である「無漏界」に達した状態を描写しています。この境地は、煩悩から完全に解放され、言葉を超えた安らぎと常住の善が満ち溢れる聖なる世界であり、仏の尊い法そのものだとされています。
(結びの頌)
已依聖教及正理
分別唯識性相義
所獲功徳施群生
願共速証無上覚
「すでに聖なる教えと正しい論理に基づいて、
唯識の本質とその相(あり方)について理解を深めました。
この学びによって得られた功徳をすべての生きとし生けるものに施し、
共に速やかに無上の悟り(最上の覚り)を得られるよう願います。」
聖教および正理
聖教は仏教の教え(経典など)を、正理は論理的な分析や論証を指します。これらに基づいて、唯識の教えを理解することの重要性が強調されています。唯識性相義の分別
「唯識性」とは、すべての現象が意識の働きに過ぎないことを指し、「性相義の分別」とはその本質と表れ方についての理解です。この箇所は、唯識について深く分析し、理解を得たことを表現しています。所獲功徳施群生
学びや実践を通して得た功徳を、自分だけのものにせず、すべての生き物に施すという菩薩の慈悲の心が示されています。願共速証無上覚
ここでは、共に速やかに無上の覚り、すなわち仏の悟りを得ることを願っています。この無上覚は、悟りの最高位であり、他者と共に到達することを理想としています。
この一節は、唯識の教えを学んだ後、その理解から得た功徳を他者に施し、共に最高の悟りを目指すという、菩薩の慈悲と願いが込められています。
