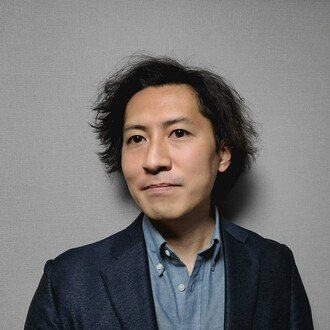意識すると身の回りにいろいろとあるピークエンドの法則
ピークエンドの法則とは、「人は自身の経験をもっとも感情がたかまったとき(ピーク)と最後の印象(エンド)で判断する」という意味を持った法則です。
1999年に発表した行動経済学者のダニエル・カーネマン氏の論文で、その言葉が登場しました。
ピークエンドの法則は、人間心理を利用した法則で、ひとが感じる価値観をコントロールできる手法なので、マーケティングにも有効です。
ピークをどこに設定するかは、その対象によって異なりますが、エンドは基本的に設定しやすいのです。
エンドは、それを見た(体験した)ひとからの評価を決定するタイミングでなので、特に重要だとされています。
身の回りにある事象をいくつか紹介します。
例えば、飲食店。
入店から席へのアテンドがスムーズではなく、あまり良くない印象を受けたとしても、食後にドリンクや味噌汁的なものがサービスで提供されると、良い印象を受けませんか。さらには、会計後のお見送りも良い印象を与えます。
例えば、花火大会。
花火大会の終盤は、必ずと言っていいほど、ここぞとばかりに花火を連発し、素敵なクライマックスを演出してくれます。
花火大会が終わったあとも、しばらく余韻が残っていますよね。
花火大会だけでなく、エンタメ演出における“緩急”は大切で、単調な部分と盛り上げる部分を明確に分けると、見ている方の評価が高いです。
コンサートでも映画でも小説でも、ピークとエンドを意識し、エンドでどう印象づけるかが重要です。
ビジネスの世界においては、最初の印象は良くても、最後にがっかりしてしまう(させてしまう)ということがないよう、ピークとエンドを意識して、エンドの設定を予め考えておくと、商談なり交渉なり面談などで、良い印象を与えられるのではないでしょうか。
自分自身もそうですが、提供している商品やサービスがどういったピークで、どんなエンドを持っているのか、把握してみると、新しい発見があるかも知れません☺
いいなと思ったら応援しよう!