
和歌のみちしば― 柿本人麻呂・臨死自傷歌 (みまからむとせし時に、自らをいたみて作れる歌) の謎
柿本人麻呂の辞世の歌が万葉集には採られている。臨死 ( みまか ) らむとせし時に、自らを傷 ( いた ) みて作れる歌と詞書にあり、この歌に対して、妻が返しの歌を詠み、もう一人別の人が、柿本人麻呂の心を推し量って歌を重ねるという一連の構成になっている。柿本人麻呂の辞世の歌の彫りを深くしている演出だ。
しかし、この一連の歌が、さまざまな解釈を許す揺らぎを持っている。その謎について考察してみたい。
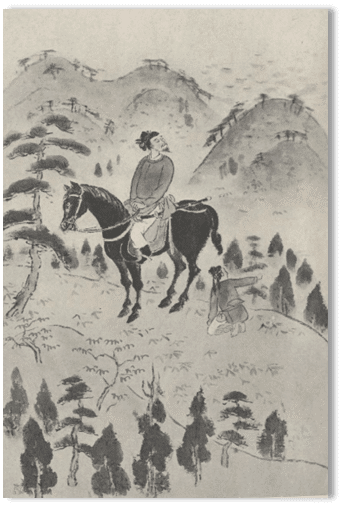
万葉集の該当部分を挙げる。
■ 柿本朝臣人麻呂の石見 (いはみの) 国に在りて臨死 (みまか) らむとせし時に、自らを傷 (いた) みて作れる歌一首
鴨山の岩根し枕 (ま) ける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ



最も素直に読み解いてみよう。
鴨山で、病臥し力尽き死を迎えようとしている。ここは野営の地。こういう処で死を迎えることになろうとは‥‥。妻は家で帰りを待っているであろうに。
それに対して妻の歌。
■ 柿本朝臣人麻呂の死 (みまか) りし時、妻依羅娘子が作る歌二首
今日今日と我 (あ) が待つ君は石川の貝に[一に云ふ 谷に]交りてありといはずやも
直 (ただ) の逢ひは逢ひかつましじ石川に雲立ち渡れ見つつ偲はむ

これもストレートに読み解いてみよう。
ただ私ばかりが帰りを待っていたあなたは、帰路の途次果てて、石川の、 貝が散らばっているような河原に置かれたままになっていたというではありませんか。
今はもはや、在りしあなたに会うことができないのなら、その石川の雲よ、立ち渡っておくれ。その雲にあなたを感じ取ろうと思いますから。
この歌の背景には、帰路にありながら妻のいる処までは帰り着けなかったという状況が先ず見えて来る。なぜ、鴨山や石川という名 ( 地名なのか? ) がぽつんと出て来るのか、貝に交じりてとは、比喩なのか、神儀的な、あるいは風葬の一種でもあるような営みを匂わせるのか、その場の実景そのものを暗示しているのか、といった解釈の分かれる問いが浮かんで来るが、この歌の往来だけなら、上の解釈で納得が出来ないわけでもなかろう。
しかし、これで終わらずこのあとに、こう続く。

■ 丹比真人 ( たぢひのまひと ) <名は欠けたり>柿本朝臣人麻呂が意 (こころ) に擬 (なずら) へて報 (こた) ふる歌一首
荒波に寄り来る玉を枕に置き我れここにありと誰か告げけむ
柿本朝臣人麻呂が意 ( こころ ) に擬 ( なずら ) へて報 ( こた ) ふる、と言っている。詠まれた歌の内容からみると、具体的には、死した人麻呂の心は、かつて人麻呂が瀬戸内海の沙弥島で、巌間の水死人を見て哀悼の気持ちを詠んだときの立場に、今は私 ( 丹比真人) がなり代わって詠む、と言っているように見える。
というのはこの一連の歌の直前に、ひとつながりで読むべき配慮をしたと思える形で、人麻呂が沙弥島、つまり海浜にいて詠んだ歌が置かれているのだ。その歌を下に掲げる。
讃岐の狭岑の島にして、石の中の死人を見て、柿本朝臣人麻呂の作る歌一首 并せて短歌
玉藻よし 讃岐の国は 国からか 見れども飽かぬ 神からか ここだ貴き 天地 日月を共に 足り行かむ 神の御面と 継ぎ来る 中の湊ゆ 舟浮けて 我が漕ぎ来れば 時つ風 雲居に吹くに 沖見れば とゐ波立ち 辺見れば 白波さわく いさなとり 海を恐み 行く舟の 梶引き折りて をちこちの 島は多けど 名ぐはし 狭岑の島の 荒磯面に 廬りて見れば 波の音 しげき浜辺を しきたへの 枕になして 荒床に ころ臥す君が 家知らば 行きても告げむ 妻知らば 来も問はましを 玉鉾の 道だに知らず おほほしく 待ちか恋ふらむ 愛しき妻らは
短歌
妻もあらば摘みて食げまし沙弥の山野の上のうはぎ過ぎにけらしや
沖つ波来寄する荒磯をしきたへの枕とまきて寝せる君かも
丹比真人の歌は、柿本人麻呂が死んだ場所を念頭に置いているとは思えない。切り離して読むべきである。人麻呂が死んだ場所は、鴨山の岩根のある場所であって、荒波の寄り来るような場所ではない、と考えるべきだ。丹比真人は、人麻呂の死に臨んだ心境を語りたいのであって、人麻呂がかつて狭岑の島にあったとき、まるで自分の行く末を見ていたように自らが語っていたよ、と丹比真人は指摘したのだ。
だからこそ、「意 (こころ) に擬 (なずら) へて」とあえてことわっている。
どこの誰とも知らない水死人を
「沖つ波来寄する荒磯をしきたへの枕とまきて寝せる君かも」
と人麻呂が表現して哀悼したときに、歌にはしなかったが、水死人の心を言えばこうであったことだろう思っていた、詠まれなかった歌。それが、丹比真人の詠んだ
「荒波に寄り来る玉を枕に置き我れここにありと誰か告げけむ」
なのだ。
なぜなら丹比真人は、人麻呂の死を、その水死人と同じような、不慮の死、無念の死として感じているからだ。
そして見逃してはならないのは、丹比真人の歌は、人麻呂が亡くなった知らせを受けた時の、妻依羅娘子の気持ちを汲んでいる歌になっていて、歌の目的は、あなたの夫 ( 人麻呂 )は、あなたのことを今はの際にも思っていたことでしょうという、妻依羅娘子に向けての哀しみの慰撫にあるのだ。
人麻呂の狭岑の島の歌に、「妻知らば来も問はましを」「待ちか恋ふらむ愛しき妻らは」という表現がある。人麻呂の最期の思いも、まったくこのとうりであったでしょうと示唆している。
そこから言えるのは、この臨死自傷歌群と称される一連の歌は、万葉集の真価とも真髄とも言っていい、愛する者の間、この場合は夫と妻の互いの思いやり、引きちぎられるような哀切の情を、最もよく伝える歌として採られ、構成されたのであって、それ以上の付随の情報を、ほのめかしたり、暗に読み取らせようとする意図も意識もないと考える。

つまり筆者の読み方では、こういう解釈だ。
「鴨山の岩根し枕ける」は、「草を枕に」という比喩よりもなお厳しい、野営を当然考えるしかなかった旅、を言っていて、その旅の途中で死にゆく人麻呂の無念を慮り、編纂者が「自らを傷 (いた) みて」と詞書に表現したものであろう。
「鴨山」は、この場面においては、鴨そのものには象徴性は感じ取れず、地名をおろそかにしない万葉集の性格を思えば、実際の地名であると思う。
その旅は、公的な性格のものであったとは考えられない。穏当に考えれば、人麻呂が病による死期を悟り、職を辞した上で、別れて暮らす妻依羅娘子のもとに一日でも早く帰ろうとした、その焦りから来る無謀な帰路であったのではないか。

人麻呂にはすでに多くの体力は残されていなかった。行倒れたということだ。当時すでに火葬が当然という考えをとりたい。しかし荼毘に付すために、遺体を速やかに然るべき場所へ運ぶだけの、従者の人数も用意もなかったということではないのか。とりあえずは従者たちは、獣に襲われないように、見通し風通しの良い河原まで遺体を運びおき、そこで荼毘に付す場所へどう運ぶか算段をしたと想像する。同時に妻依羅娘子には急報が手配された。
河原に置かれ、風に晒されているこの様子を知り、妻依羅娘子は、「石川の貝に交りて」と詠んだと解釈する。それは貝という無機質なものに悲壮で、空虚なニュアンスを持たせているのではなく、
遺体は今、河原の貝を、褥(しとね)として敷くような姿で置かれているのですね、
と愛する者の死をおごそかに飾りたいという心で使っている表現だろう。万葉集で詠まれる「貝」は、小さな魂を持った存在である。古来より日本人は、そういう見方をして来たのが、万葉集を熟読すればわかって来る。石川の貝は死を荘厳しているのだ。
「貝に交りて」という表現に、野ざらしになっている状況を印象してしまうと、水死というところに連想が及ぶだろう。そしてこの石川は、固有名詞の「石川」ではなく、石が水底に広く散らばっているのが透けて見えるような山間の川を言うと考える。そこは、「鴨山の岩根」の「岩根」が、象徴的な措辞であることと同種の表現と見るべきだ。
妻依羅娘子の二首目の「石川に雲立ち渡れ」の解釈は、亡き人の魂は、思いが深ければ、目に止まる雲となって自分の処へ渡って来る、という信仰が裏にあると考える。
令和5年3月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
