
本を作って、自分の人生も、読者の人生も良くなっていく。こんな素敵なことってありますか?
■「自分がいちばん自分を理解している」それはほんとうか?
「自分がいちばん自分のことを理解している」。そんなふうに思っていた時期がありました。「辻さんって○○な人だよね」「辻さんと○○さんって気が合いそう」……人からこんなようなことを言われることがあります。ぼくはこれがすごく嫌だったんです。「ぼくの何を知ってるんだろう?」なんて心の中で思っちゃっていました。(嫌なヤツだ…)
でも、ぼくは自分のことをぜんぜん理解してなかった。幡野広志さんの『うまくてダメな写真とヘタだけどいい写真』の本作りに携わって、そして自分自分も写真をはじめて、そのことを痛感しました。わかっていないことばっかりでした。

こんにちは。『うまくてダメな写真とヘタだけどいい写真』の編集を担当した辻です。この本を作って、写真が趣味になって、気づいたことがたくさんありました。
■ワークショップで濾過された内容が本のベースになった。
「辻さんって、写真にご興味はありますか? もしよかったら写真のワークショップに参加してみていただいて、興味を持っていただけそうだったら、書籍化の相談ができるとありがたいです。」
写真家・幡野広志さんのマネージャーを務めている小池花恵さんに声をかけていただいたことから、この本の企画がスタートしました。(念のため幡野さんのかんたんなプロフィールをご紹介しておきます。)
幡野広志(はたのひろし)
1983年、東京生まれ。写真家。2004年、日本写真芸術専門学校をあっさり中退。2010年から広告写真家に師事。2011年、独立し結婚する。2016年に長男が誕生。2017年、多発性骨髄腫を発病し、現在に至る。『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』『息子が生まれた日から、雨の日が好きになった。』(以上、ポプラ社)など著書多数。


ぼくは前から写真に対して苦手意識がありました。自意識過剰で人の目を気にしているので(人の目なんて気にしていませんよ〜という風を装いながら)、ぼくなんかがカメラを持って写真を撮っていたら「あいつカッコつけてる」って思われるんじゃないかと思っていたんです。でもそんな苦手意識とともに、写真を撮ることへの憧れもありました。心の奥のほうで「写真を撮ってみたい」という気持ちがたしかにありました。こんな機会はもうない。小池さんのありがたいお声がけに、ぜひぼくにやらせてください、とお返事をしました。


『うまくてダメな写真とヘタだけどいい写真』は、ワークショップ「いい写真は誰でも撮れる」をベースに、幡野さんが写真の仕事に携わり培ってきたことを、1冊にギュッと凝縮して書き下ろした本です。ワークショップは毎回10名から20名で行われ、これまで400人以上の方が参加されています。
この記事を書いている12月1日現在、ワークショップは38回開催されています。いまは「いい写真は誰でも撮れる その2」としてちょっと形を変えて継続しています。
ぼくは第1回目に受講者として参加して、そのあとはお手伝い(というかほぼいるだけですが…)として同席させていただいています。全ワークショップの90%くらいは参加していると思います。



幡野さんは写真のハードルを下げたい、写真の誤解を解きたい、という思いで小池さんと一緒にこのワークショップを実施なさっているわけですが、その気持ちはまじでほんとうです(ぼくが言うまでもないですが)。
幡野さんは誠実でした。ワークショップをよりよくすべく、内容を毎回ちょっとずつ変えていました。前回の参加者の質問を反映したり、当日までに体験したエピソードを新しく紹介したり、スライドに使用する写真を入れ替えたり、話す順番を変えたり……あげればキリがない。ぼくはワークショップの最中、幡野さんが話していることをパソコンでメモしながら聴いていたからその変化がよくわかる。
「ここの順番変えたんだ!」
「え、今回も内容変わってるじゃん!」
「これはじめて紹介することだ!」
心の声を発しながらキーボードをたたいていました。
幡野さんはこうしてどんどんワークショップの内容をブラッシュアップしていました。内容はどんどんろ過されて、大切な「伝えたいこと」の純度が高くなっていきます。その純度が高くなった「伝えたいこと」を次のワークショップでさらに濾過していくわけです。そうして洗練されたものが本のベースになっているのです。

■ぼくにとって写真を撮ることとはなんだろうか?
『うまくてダメな写真とヘタだけどいい写真』の第2章のタイトルは「写真を撮る理由」です。ぼくが写真をはじめたきっかけは当然「仕事」です。でも写真がたのしいと思ってからはもはや仕事は関係なく、ぼくの趣味になりました。でも「写真を撮る理由」は考えたことがなかった。
ぼくはなんで写真を撮るんだろう……?
その答えを見つけるヒントは、やっぱり本の中にありました。写真を撮るときのアドバイスとして、幡野さんは「見たものを撮ればいい」と言います。
人は好きなものしか写真を撮りません。好きな人のことは撮りたいけど嫌いな人のことなんか撮りたくないんです。これは視点でもおなじ。好きな人のことは見たいけど嫌いな人のことは視界にも入れたくないものです。
だから「見たものを撮る」でぼくはいいと思うんです。興味や関心があるから見ています。子どもの運動会では自分の子どもしか見ないでしょ。アイドルグループで推してるメンバーがいたら、その人のことばかり見ちゃうでしょ。好きだからですよ。
だから「好きなものを撮る」は「思わず見たものを撮る」でいいんです。
写真を撮ろう撮ろうと気負って、撮るものを探すのではなくて、日常の身の回りにある「見たものを撮ればいい」と。なにかにぱっと視線がいくとします。なぜ視線がいったかと言えば「好きだから」である、と。嫌いなものは見ないから、目にとまったものはぼくの好きなもの。だからそれを撮ればいい、と。
そうして見たものを撮った写真のデータをパソコンに入れて、ライトルームというソフトを使ってセレクトし、現像していきます。この作業をしていると、いままではっきりとは認識できていなかった「ぼくが好きなもの」を実感できる。だって、そこにはぼくが見たもの=好きなものがたくさん並んでいるんですから。写真を撮る、セレクト、現像、の作業を日々繰り返すうちに「そうそう、ぼくの好きなものってこういう感じだよね」となっていきました。


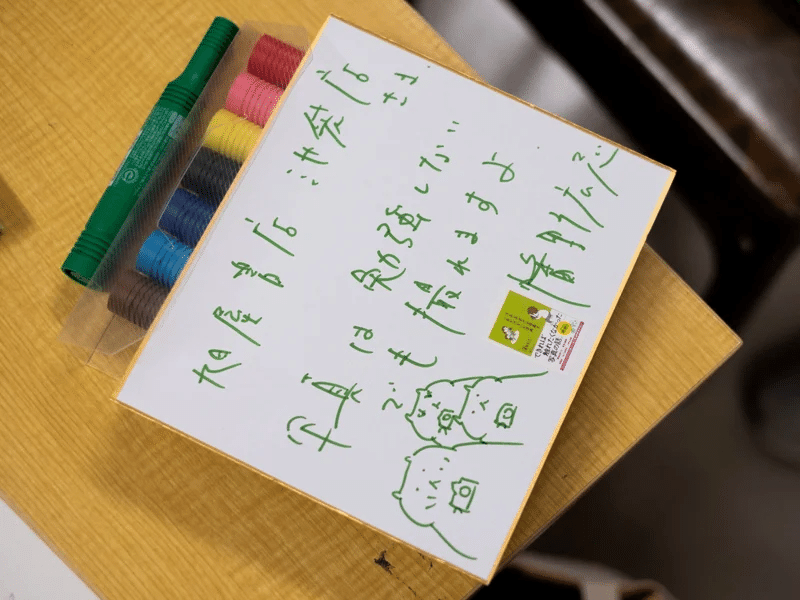
そこで気づいたんです。写真を撮ることは、「自分の好きを認識する」ことでした。もっと言ってしまえば、それは「自分を受け入れる」ことであり、「自分を肯定する」ことであり、「自分を理解する」ことだったんです。
これを飲み込めたいまなら、さきほどの「ぼくはなんで写真を撮るんだろう?」という疑問に答えられる。ぼくは「自分を理解したいから写真を撮っている」のだと思います。「自分を理解するのがたのしいから撮る」ともいえるかもしれません。本の中の幡野さんのことばに沿って言い換えれば、「自分がどんなことを好きなのか、自分に伝えたいから写真を撮っている」ということです。
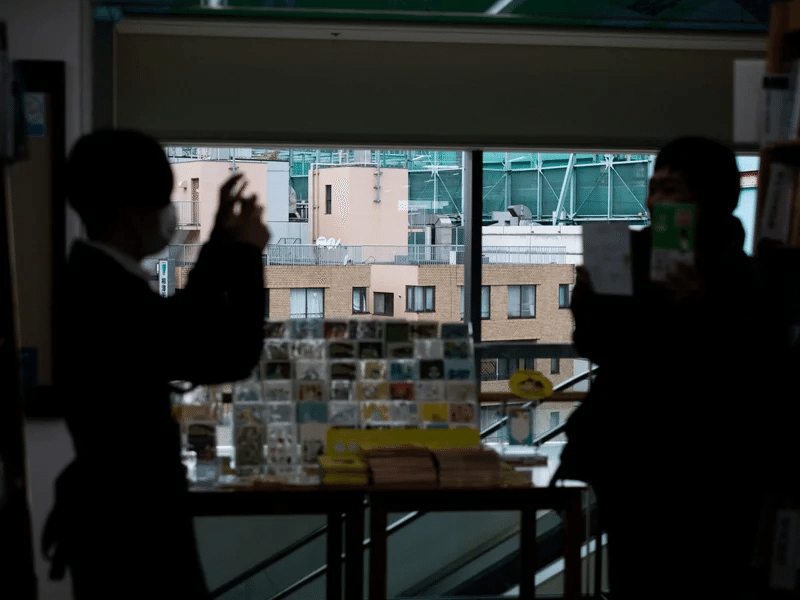


入社2年目、編集者になりたてのとき、週に1回の編集部のミーティングごとに企画(もしくは企画の種)を1本、プレゼンしていました。当時は「おれのセンス、どうだ!」という感じでいたのですが、今考えると、誰かがおすすめしているような「他人の好き」で考えていた企画がすごく多かった。「おれのセンス」でもなんでもない。「自分の好き」を自分でわかっていなかった。
ここ3年くらいで、やっと「自分の好き」で企画を立てられるようになってきたような自覚がありました。その当時はこんなふうに言葉にはできなかったけど、なんとなく感じていたんです。そんな自覚が芽生えてきたときに『うまくてダメな写真とヘタだけどいい写真』の編集を担当する機会を得て、幡野さんが「他人の好きではなく自分の好きで写真を撮ろう」と教えてくれた。「自分の好き」が大切なのは、本の企画も同じことでした。(「他人の好き」で企画を考えることは決して悪いことではないし、必要なことであるとも理解しています。ぼくは「自分の好き」で企画を立てて本を作るのが好きなタイプです。)
■ぼくは「伝えたい人間」だった。
「誰かに何かを伝えたい」これが写真を撮る理由だとぼくは思います。
何かを伝えたいのは食事や睡眠と一緒で人間の欲求のひとつだとぼくは思います。自分に何か大きな出来事があったらそれを誰かに伝えたいんです。伝えるというのはコミュニケーションだからです。
(中略)
何かを伝えたいから人は写真を撮ります。それが写真を撮る理由です。目の前で大きな出来事があったら写真や映像を撮るものです。空に虹がかかれば写真を撮るし、打ち上げ花火を見たら写真を撮るし、場合によっては命の危険があろうと撮ります。だから災害時や緊急時でも人は撮るんだと思います。
ワークショップでこの言葉を聞いて、そして本でこの言葉を読んで自覚しましたが、ぼくは「伝えたい人間」だった。何かを発表したい欲がぼくの中にははっきりありました。でもぼくは「自意識過剰」という言葉で、伝えることから逃げていた。伝えたい欲に栓をしていた。その栓を幡野さんが引っこ抜いてくれたんです。
ビンの先からコルクがポンッ! と勢いよく抜けて、そこからシャンパンが溢れてくるように、伝えたい欲がどんどん出てきました。驚いたんですけど、写真があると文章が書けるんです。写真が文章を導いてくれるという感じ。幡野さんのことばを借りれば「ことばがなければ写真は伝わらない」から写真を撮ったときの気持ちを文章にしていくと、それがどんどん膨らんでいく。あれも書きたい、これも書きたいとなってくる。書くのが楽しくなる。
いちど書いて、えいや、と発表してしまえば、それ以降の抵抗感は8割減。どんどん書けるようになっちゃう。SNSの投稿頻度はあがったし、noteも月に1回は書けるようになった。ぼくにとっては大きな変化です。

写真を撮ることで、「自分の好き」がわかって、自分をもっと理解できた。それとともに伝えたい欲が刺激されて、文章も書けるようになった。文章が書ければ、ぼくが写真をはじめてどんな気持ちでいるのかを伝えられるし(うまく伝えられているかどうかは置いておいて)、こうしてぼくが本作りとどんな風に向き合っているかも伝えれらるのです。「自分の好き」を発表しているとも言えるかもしれない。
自分の気持ちを発表できると、ひとつステップアップしたような、レベルアップしたような感覚になる。そうすると自分がちょっと好きになる。だから写真をはじめて、自分を好きになる方法さえも見つけてしまったんです。自分が好きになるってけっこうすごいことですよ。人生ちょっと変わりました。
ありがたいことに、すぐに重版がかかり、3刷目も決定。SNSは本を読んだ感想に溢れている。その感想をみると、ぼくとおなじような気持ちになっている人がいるんだと肌で感じられます。
やばい、自分の人生だけじゃなくて、人の人生にも影響あたえてる!
すべては幡野さん、小池さんのお力です。でも間接的にではありますが、ぼくはその一助を担っている。こんな素敵なことってありますか?

