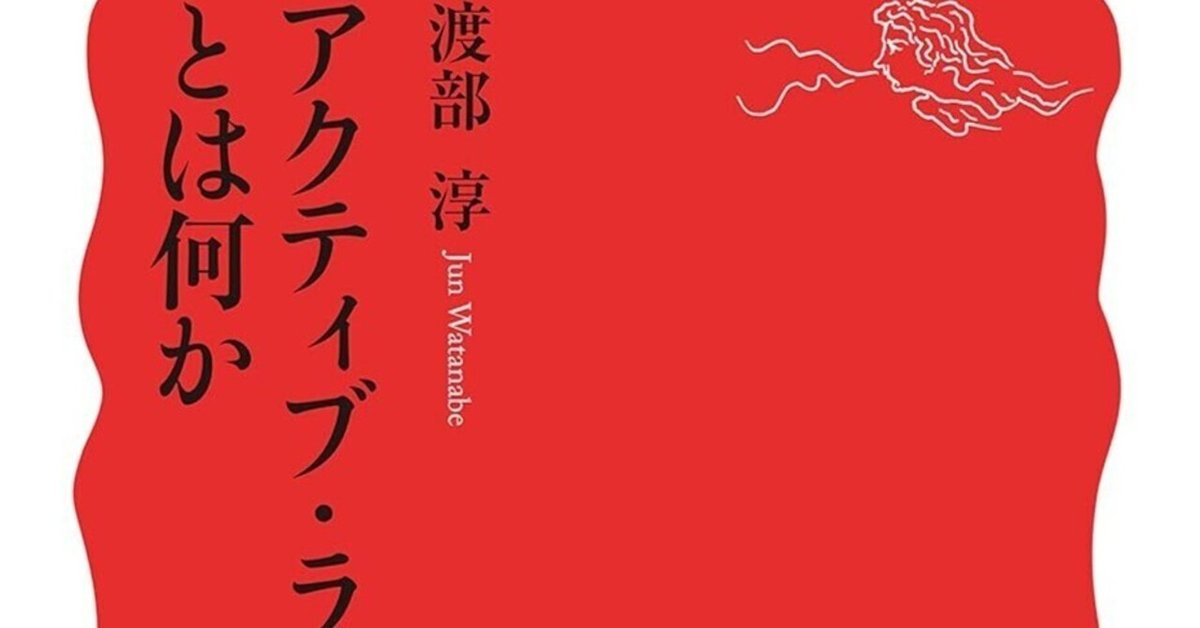
2021年度 下関市立大学 前期日程(全学科共通 小論文「論述(長文理解)」 模範解答
設問1
アクティブ・ラーニングは自立した学習者の養成をめざす。「自立」の意味は、豊かな学びを経験し、学びの作法を習得することにある。グループワークのような学習活動をとおして、学習者は他者との交わりにより、コミュニケーションのあり方に気づき、またグループでの自分の役割や自分自身の特質にも気づく。さらに、学習活動への積極的な参与により自信を得たり、新しい発見ができたりする。こうして、学習者は学びの達成感を得て、成長することができる。そのさい、自分の成長の評価を他者に依存するのではなく、自分で評価できるようになること自体が、自立した学習者としての成長でもある。このように成長できる者が自立した学習者である。(299字)
設問2
「自己の特質への気づき」は、他者の存在を意識したうえで自分の存在を自覚することであり、それには二つの側面があるという。ひとつは、自分の現状を相対化することで得られる気づきであり、これによって人間は、意見の異なる人々を尊重しつつ、交流できる存在になれるという。もうひとつは、アイデンティティの多重性への気づきである。これにより、自分のアイデンティティが学校の生徒、地域社会の一員、国民など多重であることに気づけるとされる。
これを踏まえて、私はアクティブ・ラーニングの必要性は認めつつ、あえて消極的な考えを提示したい。というのも、たしかに自己への気づきは自立した学習者の養成として必須ではあるだろうが、しかし「知識注入型授業」も子どもには重要だと思われるからである。たとえば、子どもは自由な発想で積み木遊びをするだろう。しかし、そもそも積み木が与えられなければ、せっかくの自由な発想も現実に発揮される可能性を失ってしまう。知識注入型授業はこの積み木を与える授業形態であると私は考える。したがって、アクティブ・ラーニングと知識注入型授業を並行しておこなうべきであるだろう。
(483字/400字詰め原稿用紙25行に収まることを確認済み)
