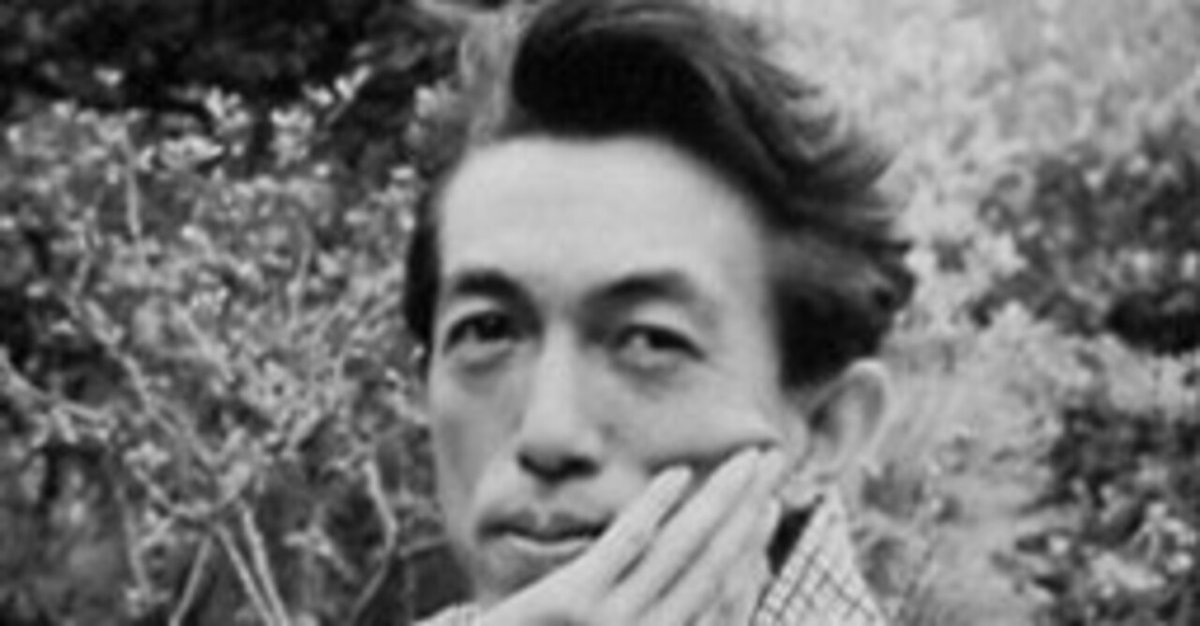
2021年度 慶應義塾大学 法学部 小論文(論述力試験) 模範解答
著者は聖書における「一匹と九十九匹と」という比喩を、政治と文学の差異として解釈する。つまり、政治はそれがどれほど善い政治であっても、九十九匹までしか救うことができないのに対し、政治によって救われることのない一匹を救うものこそが文学であるという。したがって、政治によって救われる者とその政治によって救われない者を救う文学とでは、救いの対象や目的、方法が異なる点において区別され、政治と文学の関係は対立的であるとされる。さらに著者は、政治と文学との対立の根底には個人と社会との対立があるという。つまり、一方において社会は個人を自らのうちに包摂し、社会から逃れる者を想定しないため、社会が許容するあり方以外に個人のあり方や価値を認めようとしない。他方で、社会正義が表では肯定されながら、その裏では個人は自らの価値観を実践しようとするエゴイズムを発揮する。しかし、著者は政治と文化との一致、社会と個人との融合を理想であるという。
社会と個人とのあいだには、社会規範の実践や社会の維持という社会の目的と、個人の自由や個人的欲求の実現という点の両立において、緊張や対立関係があるといえる。というのも、社会正義の実現や社会維持のために個人の行動を規制すれば、個人の自由が抑制される一方で、個人の自由や個人的欲求の実現が優先されるならば、社会秩序が脅かされることが危惧されるからである。それでは、社会と個人との一致という著者の理想を実現するためには、対立する社会と個人のあり方はどうあるべきだろうか。
著者は個人と社会の区別を認めつつも、相互のあり方を肯定し、尊重することを主張する。したがって、個人と社会のあり方を認めながら両者の一致を図るためには、「個人としての我々が作る社会」を志向する必要があると考える。というのも、社会は個人から独立したあり方をしているのではなく、社会を構成するのは個人としての我々一人ひとりであるからだ。それゆえ、我々にとって望ましい社会とは何かという共通善について、我々が合意を形成していく必要があるといえる。そのために、個人と社会のあいだとしての「公共」という場において、共通善についての熟議が不可欠となる。さらに、この熟議をとおして、私たちにとって望ましい社会の実現を図ることができたとき、社会と個人との緊張関係や対立は解消されると考える。(977字)
