
「あ、共感とかじゃなくて。」展

同じ心理学部卒のお友達に教えてもらいスタコラ一緒に行ってきた。
見知らぬ誰かのことを想像する展覧会
SNSの「いいね!」や、おしゃべりの中での「わかる~~~」など、日常のコミュニケーションには「共感」があふれています。共感とは、自分以外の誰かの気持ちや経験などを理解する力のことです。相手の立場に立って考える優しさや思いやりは、この力から生まれるとも言われます。でも、簡単に共感されるとイライラしたり、共感を無理強いされると嫌な気持ちになることもあります。そんな時には「あ、共感とかじゃなくて。」とあえて共感を避けるのも、一つの方法ではないでしょうか。
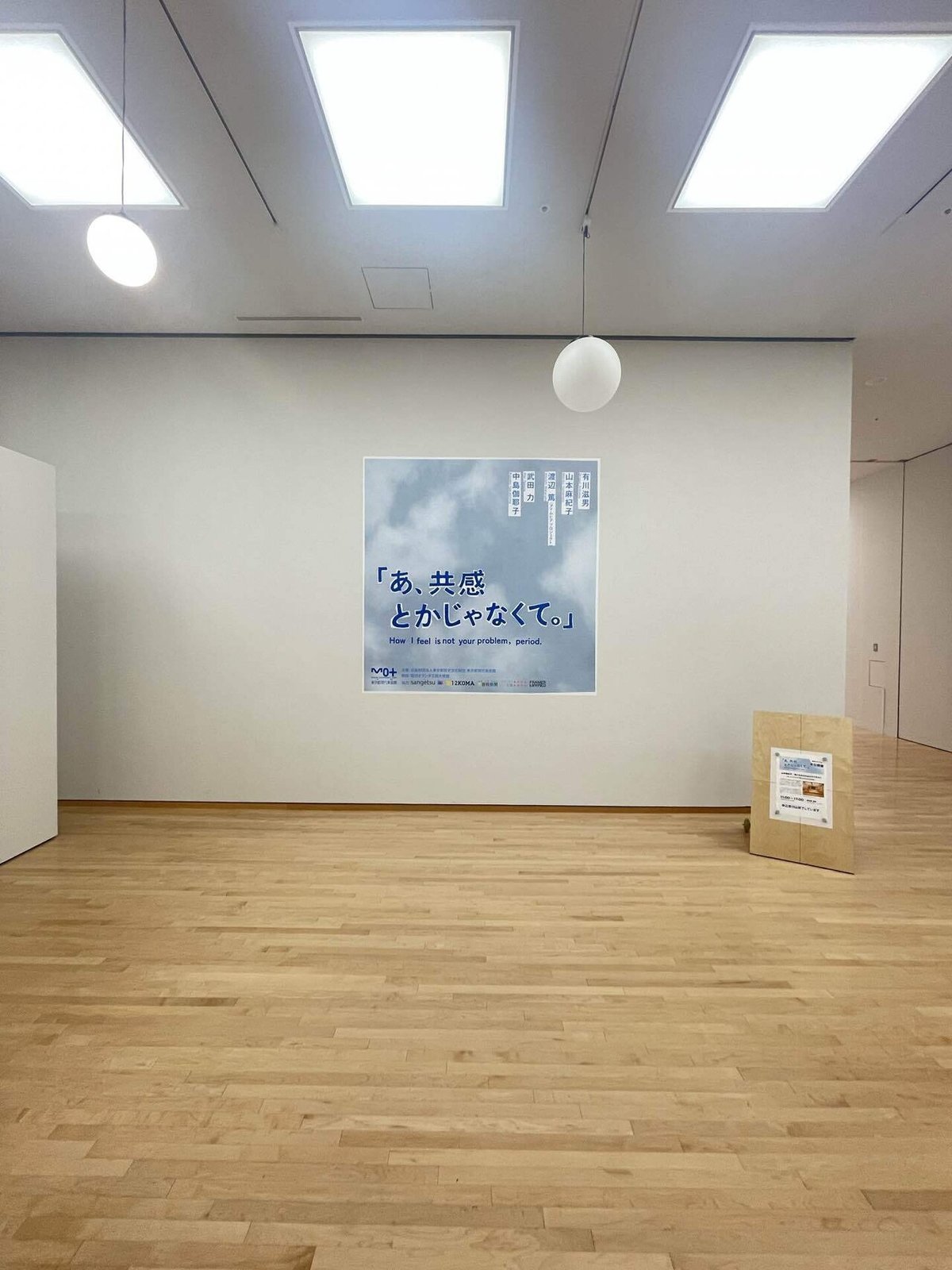
"共感" "気持ちが分かる"
そんな言葉がポジティブに使われることが多い世の中で、
一方的に共感を否定するのではなく、"共感できない" "気持ちが分からない"にも焦点を当てた展示会。とも表現したい。
「共感することが出来る」ということがポジティブな意味をもたらすのであれば「出来ない」ことはネガティブな意味であり、間違えているのか。
例えば世の中の『"普通"』とか『"世間体"』に共感出来なかった人間の居場所、生きやすさはどこに求めればいいのか。賞賛されるものに共感し適応出来なかった人間の尊厳はどこにあるのか。
ポジティブな意味で使っていた共感が、時に誰かにとって同調圧力や個性が迫害されていることに繋がっているのではないか。共感される数が多い方が正しくて、共感を得られないことが間違っているのか。
そんな根本的な"共感"という言葉の意味を考えるきっかけに。

共感という言葉を通して同意し認め合うことに正しさを求めるのではなく、自分以外の他者に対して、一人一人違うアイデンティティを持っているから分からないということを前提に置くことは尊重に値し、そして理解しようと考え続けることが重要である。答えを直ぐに求めるのではなく、自分の一部として考察していくこと。共感しなくても人々は繋がりあえるのだと自分は受け取った。
そのような前書きをある程度納得した上で鑑賞していたにも関わらず、この展覧会の中に溢れるたくさんの「"分からない!!!!"」に対して気付いたら分かろうと必死になってる自分がいた。
この「分からない」という感覚は、数え切れないほど人間がいる中で、世間、社会、に溢れていて良いはずなのに展覧会に来てまで分からない感覚にモヤモヤした。慣れていない感覚なのだろうか。
それは一体なぜなのだろう。
共感、自分のアイデンティティの認知を求め、そして過半数に寄せていかないと生きにくい社会で生きようとしているからなのか…


そしてこの展覧会は「ここに来れなかった人を想像するように」と何度か述べていた。
今まで訪れた展覧会でもそのようなコメントは勿論見たことがなかったし、現に、今目の前にあるものにフォーカスすることが"当たり前"で見えていなかった背景が沢山あったのだと気付かされた。

ここにいない誰かも含めたみんなで作りあげた展覧会。
来たくても来れなかった人、今この展覧会が開かれている中でも見えていない"孤独"の中で生きている人を考えること。それは最終形態が同調する共感で居場所を奪われた人たちに対して、寄り添い誰一人なく孤独を押し付けることなく繋がることの出来る未来に期待するものでもあった。
見終わった後、勝手に自分の経験に基づいて分かろうと動いてくれた脳みそたちが、どっと疲れを感じていたが残っていた 「あれはなんだったのだろう…」「どういう意図なのだろう」という感覚。
ここには好きか嫌いかなどというのは一切混じり合わず、分かりたいなと思う感情。これでOKなんだろうな。と今は満足気に浸っている。

私は友人とも同じでないのは当たり前。
違いを尊重し合う関係を大切にしたい。
勿論その中にある似た部分も同じくらいに。
