

plateau books
https://plateaubooks.thebase.inplateau booksは文京区白山に2019年3月にopenした新刊本屋です。 店名の「plateau」は平坦を意味します。 平坦で変化のない時間。そんな時間にゆっくり本を読む。 そんな時間を、それぞれの楽しみかたで過ごす場所になればと名付けました。 1970年代から精肉店として使われていた空間に、古家具をならべ、本を置きました。 新しく空間に役割をあたえることで、使われなくなった空間から、新しく価値が生まれました。 本屋として、本によって新しい価値、気づき、感情、行動など、 日常のなかで通過している時間に、変化を感じられるようになればと思っています。 中央のテーブルで読書やコーヒーを楽しんでください。 〒112-0001 東京都文京区白山5-1-15 ラークヒルズ文京白山2階 都営三田線白山駅 A1出口より徒歩5分 営業時間 / 12:00~18:00 営業日 / 土・日・祝日(不定休) ※年末年始・夏季休暇等の長期休暇はHPにてお知らせいたします。 ※注文確定のお知らせ、商品の発送は、営業日の土・日になります。ご了承ください。

ULTRA STUDIO|LANDSCAPE GOES DOMESTIC
気鋭の建築コレクティブ ULTRA STUDIO の思想や作品性が 凝縮された1冊 向山裕二、上野有里紗、笹田侑志の3人からなる建築コレクティブ「ULTRA STUDIO」。 本書は、彼らが2021 年に開催した個展『LANDSCAPE GOES DOMESTIC』の内容をまとめたもの。 展示されたドローイングや写真に加え、会期の最終日に行われたラファエル・バルボア、橋本圭央との座談会や、メンバーの向山裕二による文章「偶然の象徴」も収録。 展覧会の内容紹介にとどまらない、ULTRASTUDIO の思想や作品性を紹介する。
3,850円

コヴァレヴァ・アレクサンドラ+佐藤敬 / KASAほか|The Russian Pavilion in Venice Giardini
注目の若手建築家KASA 初の書籍 第17 回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展 2021 にまつわる作品集 本書は、異なる時期に作成された 2 つの作品で構成されている。 最初の作品は「Traces」と題され、第17回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展 2021 のロシア館 の展示物としてつくられた絵本。 もう一つはパビリオン再建の変遷について。写真や図面と、コミッショナーやキュレーター、そして同ビエンナーレの審査員長・妹島和世によるテキスト。 ロシアで出版され国内にはほとんど流通していない希少な一冊。
7,000円

GROUP(井上 岳+齋藤直紀)+石毛健太|ノーツ第二号「引越し」
活躍中の建築コレクティブ GROUP の インタビューを主体とした 自主制作本の第2号 第二号のテーマは「引越し」(Relocation)。家という物理的な生活環境や家族という共同体の枠組みについて、パンデミックを経た現在の視点から再考する。 家や引越し、家族、日常のことを題材にした作品を多く手がける小説家の滝口悠生、石毛健太、垂水五滴、黒坂祐からなるアート・コレクティブのURG、映像エスノグラファーとして移動する家族の研究を行う大橋香奈、モンゴルを専門に研究する文化人類学者である堀田あゆみらへの長文インタビュー、 濱田晋による写真作品、アウレリ& ジュディッチの未邦訳の論考の翻訳を収録。
2,970円

GROUP(井上 岳+齋藤直紀)+大村高広|ノーツ第一号「庭」第二版
活躍中の建築コレクティブ GROUP の インタビューを主体とした 自主制作本 ノート(note)という言葉には記録や注、覚え書きといった意味があるが、本書はさまざまな技術や知識、経験をもった人々との対話の記録と、それに併走するたくさんの注釈を束ねる。 第一号のテーマは「庭」。庭師であり美学研究者である山内朋樹 、都市生態学を専門とする曽我昌史、音楽家であると同時に人工知能の最前線に立つ土井樹、鳥取の山奥に移住し独自のコミュニティを形成している料理家の城田文子らへの長文インタビュー、高野ユリカによる写真作品、C.TH. ソーレンセンの未邦訳の論考の抄訳を収録。
2,200円

『HUMARIZINE』No.05 出版
寺内玲と松岡大雅によるデザイン事務所「studio TRUE」が、毎年1冊制作するZINE『HUMARIZINE』。HUMARIZINEは「人間的である、ということへの追求から社会を拓く」という意味。 【発行者より】 4号(2024年5月)のテーマは「出版」。 studio TRUEはこの一年でリソグラフを導入したり、出版にまつわる授業をやることになったりと、偶然にも出版に関わる複数の機会が重なりました。 それらのことを踏まえ、6冊目にあたる今号で「出版」について改めて考えを掘り下げる必要があるのではないかと考えました。 京大でアーレント研究をし、単著を出版した哲学研究者の林大地、本にまつわるあれこれをしている3人組、アラマホシ書房と一緒に、出版について多角的に向き合うことができた一冊です。 ◼︎仕様 A4、114ページ ◼︎目次 Book1 studioTRUE「ヒューマライジンの出版活動を振り返る」 これまで5年をかけて出版してきた5冊の自費出版誌「HUMARIZINE」と、1年取り組んできた印刷産業のリサーチ「月刊ヒューマライジン」を振り返ることを通じて、「出版」を考える。 Book2 林大地「ルネの山下さんインタビュー」 京都大学生協書籍部「ルネ」の書店員・山下さんへの計3回のインタビューを通じて「出版」にまつわる課題を考える。「出版社-取次-書店」の三層構造が抱える問題とは何なのか。 Book3 アラマホシ書房「出版日記」 何者でもない3人が、出版についての日記を、出版するまでの日記です。 本誌の制作過程を知るための副音声としてもお楽しみいただけます。 BOOK4 studioTRUE × 林大地 ×アラマホシ書房「鼎談:出版という希望」 「HUMARIZINE No.05 出版」に参加した3組、計6人による鼎談。それぞれの小冊子について相互に議論し、「出版」とはなんだったのか話し合う。 ◼︎その他 限定数のためお早めにお求めください レターパックライト(青・郵便受投函)での発送 店舗営業日(金土日)に発送
2,200円

『HUMARIZINE』No.04 TRUE
寺内玲と松岡大雅によるデザイン事務所「studio TRUE」が、毎年1冊制作するZINE『HUMARIZINE』。HUMARIZINEは「人間的である、ということへの追求から社会を拓く」という意味。 【発行者より】 4号(2023年4月)のテーマは「TRUE」。 2019年からHUMARIZINEを続けてきたれいぽんと松岡大雅は、2023年1月に「studio TRUE」というデザイン事務所を設立した。 自分たちでデザインという仕事をしていくにあたって楽しみがある一方で、あらゆる不安や焦燥感を感じる日々である。 そんな現実に直面する中、人生の先輩である面々にインタビューさせていただき今私たちが何をすべきか、何を考えていくべきかを聞かせてもらった。 インタビューにはれいぽん・松岡大雅だけでなく村松摩柊、佐野虎太郎、かねだゆりあにも同行してもらい、studio TRUEひいてはHUMARIZINEが目指している共同体をつくることを共に考えながら制作に加わってもらった。 ◼︎仕様 A4、82ページ ◼︎目次 ・はじめに ・対談|studio TRUE始動 ・インタビュー|まつざき淑子 市民活動と議員を掛けるなかでつくる社会 ・インタビュー|真鶴出版 來住友美・川口瞬 試行錯誤しながらふたりで生活し、仕事すること ・インタビュー|VUILD 秋吉浩気ー「独立」をデザインする ・インタビュー|永井玲衣ー絶望する社会からやってくる問いと共に生きる ・対談|おわりに ◼︎その他 限定数のためお早めにお求めください レターパックライト(青・郵便受投函)での発送 店舗営業日(金土日)に発送
2,200円

大竹央祐+平田悠『AlT』
写真家・大竹央祐と、編集者・平田悠による建築メディア。 毎号1人の建築家/一つの空間を取り上げ、紹介する。 空間は、床や壁、そしてそこに置かれた家具や文房具の輪郭線によって形づくられる。 立ち上がった建築の形が振る舞いに影響を与えるように、振る舞いもまた空間の在り方に作用する。 同様に、取り上げる空間に合わせてメディアの形式を変え、メディアの形式が写真やテキストに影響していく。 建築の形ではなく、そこに立ち現れる場を、写真や文章を通して捉えてみる試みだ。 創刊号で取り上げたのは、設計事務所OSTRによる「本庄西の現場」。 日々移り変わる「現場」の今を、新聞紙に転写した。 限定数のためお早めにお求めください。 ◼︎仕様 ブランケット判(545mm × 406mm)20ページ ◼︎目次 太田翔(OSTR)「本庄西の現場」 岡絵理子 「本庄の深い皺」 舩橋耕太郎(コムウト)「たまにやる運動」 板坂留五(RUI Architects)「居心地の良さについて」 山口陽登(YAP)「本庄西の現場はどこまで膨らむのか」 武井良祐(OSTR)「都市に開けた「孔」と明るい「奥」」 太田翔(OSTR)「本庄西の現場の続き」 ◼︎その他 レターパックライト(青・郵便受投函)での発送 店舗営業日(金土日)に発送
1,500円

本庄西施工地区『第壱施工地区』
大阪北区で施工会社「コムウト」を営む舩橋耕太郎が拠点とし運営するシェアアトリエ「本庄西施工地区」がつくるZINE。 第1冊目は2023年9月に開催したイベント「収穫祭」を中心に構成。 「本庄西施工地区」における、建築を介した活動から生まれつつあるネットワークが明らかに。 編集は舩橋に加え、シェアアトリエメンバーのtamari architects寺田英史、「収穫祭」からデザインを手がけるstudio TRUE。 限定数のためお早めにお求めください。 ◼︎仕様 本稿:A4、24ページ 作品ページ:A5折込、4ページ×10冊 ◼︎目次 [本稿] コムウト舩橋耕太郎 インタビュー「本庄西施工地区という活動のすべて」 −「施工地区」の流動性、「収穫祭」の継続性 − 大工から工務店、そしてアイデアの拠点「施工地区」へ − 金曜日に生まれるネットワークと村長の役割 収穫祭対話イベント スーパープレイ集 「捨てるかつくるか」 「住んで見返す」 「描くより先に」 「丁寧な始末」 [作品ページ] しせい 辺口芳典 大竹央祐 寺田英史 舩橋耕太郎 窪山洋子 フルマチスタジオ 岩崎裕樹 Jyu+ 永吉佑吏子 studioTRUE 寺内玲 松岡大雅 OSTR 太田翔 mtit 本岡一秀 伊藤祐紀 RUI Architects 板坂留五 haruka ashida architects. 芦田晴香tamari architects 寺田英史 的場愛美 金曜の会サークル 竹島瑠離 山口泰知 川向世瞳 杉田美咲 荒山和輝 ◼︎その他 レターパックライト(青・郵便受投函)での発送 店舗営業日(金土日)に発送
1,500円

緒方淳二「METHO」
デザイナー・緒方淳二が手掛けるファッションブランド「メソ(METHO)」のルックブック。 「服のかたちや生地を考える時、 どんな町の風と温度に触れているのかを想像します。 静かなひと気の無い通りで偶然向こうからいい服を着た人が歩いてきてすれ違う体験のようなものにずっと憧れています。 高層ビルが遠くに見える距離の意識 いつも関わりから溢れて、無視できないけれど、馴染むことも難しい そんな町を選ぶ人を想いながら服を作るのかもしれません」 緒方淳二 平成三年生まれ。エスモードジャポン東京校を卒業後、アパレルのパタンナー、 販売を経験。 2018 年独立し、2019 年レーベル「METHO」を設立。 「世の全ての物事は何かの途中で、自身なりの方法に辿り着くまで の活動である」をスローガンに掲げ不定期にコレクションを発表する。 写真、ページ構成:Im daehyn(イムテヒョン) スタイリスト:村田拓也 ヘア:橋本沙耶 メイク:SUMI
2,200円
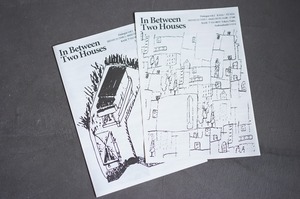
KASA+湯浅良介『In Between Two Houses / Dialogue vol.2 KASA・YUASA 対話録』(2023)
2023年3月末〜4月初旬に台東区BASEで開催された、若手の建築家 KASA(KOVALEVA AND SATO ARCHITECTS)と湯浅良介による合同展覧会のダイアローグ。それぞれが進行中の住宅プロジェクトをお互いにエスキースしあう中で繰り広げられた対話。2組の独自の作家性と、その共通性あるいは差異から、建築の「今」が浮かび上がる。 会場で限定販売されていたこちらのタブロイドを販売いたします。 店頭でも同時に販売しています。限定数のため、お早めにどうぞ。 タブロイド判(406mm × 272mm)8ページ ※半分に折って梱包 ※レターパックライト(青・郵便受投函)での発送 ※店舗営業日(土日)に発送 上記をご理解の上、ご購入ください。
500円

髙山かづえ 監修:難波里奈 『純喫茶レシピ おうちでできるあのメニュー』 (誠文堂新光社、2019)
変わらぬ、どこにでもある。そんな風に形容されるだろうか。急いでいるときも、ゆっくりと過ごしたいときも、必ずそのお店は待っていてくれる。別に、歓待を受けるわけではなく、むしろそっけないくらいだ。家とは違う、けれども落ち着ける居場所で、いただくことのできる味は、意外なほどに作るのが簡単ではない。おきまりのメニューのはずなのだけれど、自分でいちから作ることはあまりない。手軽に食べれる安定の味は、手間をかけた用意があって実現されている。きっと、誰かのために作られているのだろう。料理は、行き先があると、その手間が圧縮される。その方角は、自分自身だって良い。
1,540円

齋藤陽道 『異なり記念日』 (医学書院、2018)
いつもは賑やかな近所の深夜の静けさや、騒がしく流れ続ける店内放送、甲高い笑い声、いきおい良く出たおならの音。それらが聞こえないとは、聞こえなくなるとは、音以外でそれを伝えるとは、つい、その状況や手段のことを考えてしまいます。当たり前のこととして、自分の感じている世界だけから、物事を捉えてしまうからでしょうか。しかし、さまざまな世界を知っても、万能な感覚を備えることは困難でしょう。異なることを前にしたときの恐怖と、それに触れられたときの安堵、その実感の確かさがあるはずです。あちらこちらが異なること、忘れていたことを思い出すかもしれません。
2,200円

岡崎乾二郎 『抽象の力 近代芸術の解析』 (亜紀書房、2018)
人を描く、植物を描く、風景を描く、たとえば絵は何かを対象として描かれ、それを再現するものと考えられています。スケッチブックなどの画材を持って、ここだと思うところに腰を据え、目に映るものをじっと、あるいは、ぼんやりと眺めながら、線や色面で置き換えて、画面をつくりあげるように。そうして描かれた絵は、見たものを参照したにもかかわらず、絵それ自体でも強い印象を生むのではないでしょうか。図形や色が目立つから抽象というような、見た目の具象か抽象かよりも、絵を描き、見るという場に働く抽象に気づくとき、ひとつひとつの作品の、芸術の力を発見できるかもしれません。
4,180円

B・ルドフスキー 訳:渡辺武信 『建築家なしの建築』 (鹿島出版会、1984)
建築を設計するひとがいて、実際につくるひとたちがいて、その建築をつかうひとびとがいる、分業的な建築のつくられ方と使われ方があり、いまではそれが、すっかり当たり前になりました。かつて、あるいは、いまでもどこかでは、住み使うひとがみずから建築をつくっていたのです。わたしたちに、暮らす場所を整える力は、どれだけあるのでしょうか。Bernard Rudofskyさんは、「生活の技術などというものは道楽の一種だと考えているのだ」と言います。それほどまでに豊かになったのかもしれません。しかし、なぜか建築に、失われた質があるように感じられるのです。
2,200円

デイビッド・モントゴメリー 訳:片岡夏実 『土・牛・微生物 文明の衰退を食い止める土の話』 (築地書館、2018)
白茶けた土があって、そこにはもうずっと何も生えていません。渇いた地表からは、風が吹くたびに土埃が舞うだけです。ある作物だけが生産され、そのまわりは丁寧すぎるほどに土が裸にされている状況も、もしかしたら同じ景色に変わる手前なのかもしれません。ひとの手が及ばないところでは、植物たちがみっちりと繁茂していて、それでも土は豊かに生き続けています。動物の内蔵にはたくさんの菌がいるように、土では、植物が微生物を、微生物が植物を支えているのです。変わらない生産方法と既得権益から背を向け、土に向き合う必要があるのでしょう。
2,970円














