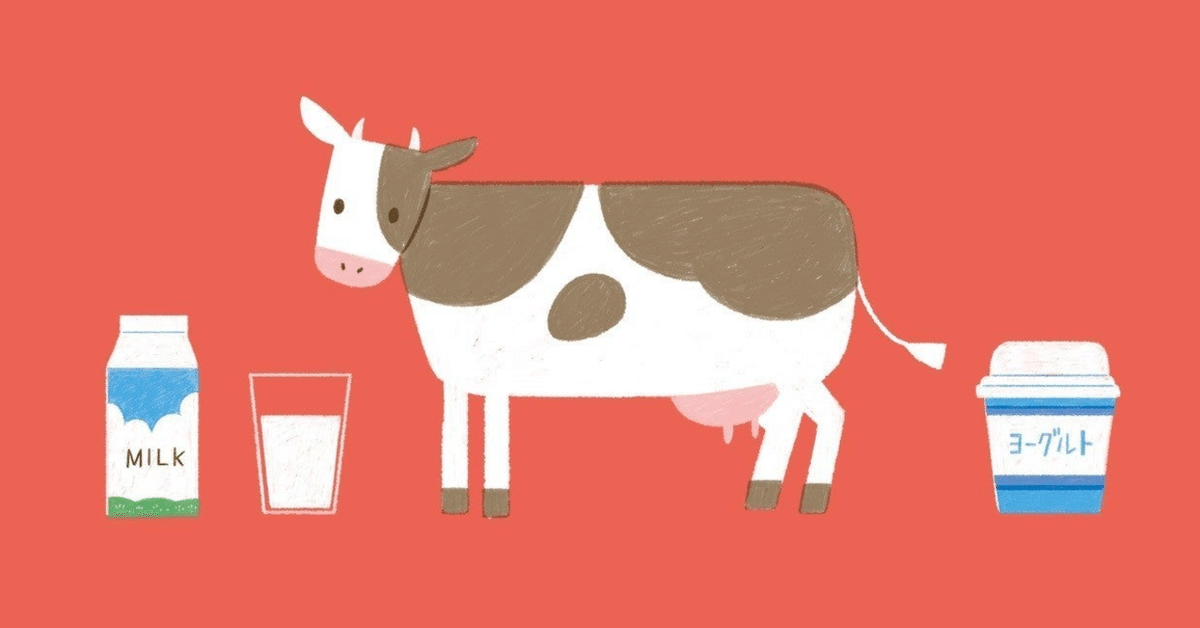
2022年02月選 部検 /評
部検 /評
死というものはありふれている。ただ人が人の死を悼むように、牛という経済動物の死を悼む人は、いないとは言わないが、多くない。この作品はその残酷を、グロテスクな表現を使うこともなく、残酷という言葉を使うこともなく、表現している。そこには生命活動の断絶という、ダイナミックな現象が描かれているが、ただ静謐なことばばかりが続いている。 本当に死というものは、本来はありふれた、生命の営みである。文中にもあるように、それは突然で、かつどうしようもないことだ。多くの人なら、「死」という言葉はいわばびっくりさせるため、インパクトを与えるために用いようとすることも多いが、この作品では、ただ日常として描かれている。この死への親しみこそがこの作品のキーになるのではないか、と感じた。しかしそこに悲しみが介在していないわけでは決してないのが、この語り手が、地に足がついた存在であることの表しになっている。 命が朽ちた、とあるが、朽ちたというのはぼろぼろになって、そうして斃れたということだ、言葉一つ一つへの繊細な選び方が、この詩文の空気を作っている。ただ事実だけが淡々と詩文としてつづられていく中に、牛の治療の描写が出てくる。そこには努力と苦痛とあるが、これは人間の側の努力と苦痛であり、牛にとってのそれである。そしてその苦しみ抜いて死んだであろう牛の臓腑を開く時の筆致には、淡々としながら、なおかつ自分の内臓に手を突っ込まれるような、それでいて牛、という存在と自分を他人でいさせてほしいと願うような切実さがある。そして牛の目は閉じられてさえいない。閉じられることさえなく、ただ剖検を待つばかりだ。 瞳の輝き、という言葉は生と死という狭間において、重要な役割を担っている。重要な役割の文言、というのは往々にしてリフレインのように使われることが多いが、この作品ではあえて瞳、という言葉は鈍い、と輝く、の二つしか使われていない。これが隠すことなく死の事実だけがつづられる本作において、象徴的な役割を果たしている。 死とは解放である。看病から、苦しみから、そして生きるためにかかるコストからの。そのことへの安心感が、“病を訴えることなく眠り続ける”という描写からにじみ出ているように思うし、そのことへのかすかなうしろめたさの種のようなものがその次の描写、“鈍い光の眼球が~”に現れている。 人にとって最も記憶と直結する五感とは、嗅覚であり、死より遠く見える存在のまず一つ目の死を確実と意識する感覚が、嗅覚であると、そして死は臭うものだと書かれている。つまりは作者の中で最も強烈な、死を感じる感覚は匂いであることを表している。そしてもう一つの象徴的に扱われている感覚が、克明に状況を記録し続ける視覚である。最後に瞳輝くと言っているように、視界は否が応にも生命というものを見なければならない。それがまたこの作品に隠された残酷のひとかけらであるように思う。そして死とはきれいなものでは決してないことをあえて使われた「汚い」という威力のある言葉が表しているように思うし、間に二回、挟まれる「合掌」という言葉が、もはや牛は人の理の中にないが、それでも家畜という歪んだ生命として生を全うさせられなかったということへの悔恨もあるように感じられた。 最後の餌やりだ、のシーンは、この死が珍しいことではない日常のワンシーンであることへの表しになっており、そしてこの描写があることでこの作品は円環、ループの構造を描く。これは繰り返され、かつ進む日常の円環の、一ページであるのだと。
