
清水幾太郎(社会学者、評論家、1907-1988) ブラジル版百人一語 岸和田仁 月刊ピンドラーマ2023年10月号

ブラジルには、ポルトガル人を中心とする白色人種、黄色人種のインディオ、アフリカから輸入されたニグロが混在し、それらの間の混血が進んで来ている。コントの『実証政治学体系』を読んでいくと、当時のヨーロッパの文献としては珍しいことだと思うが、白色、黄色、黒色の三人種を比較し、それぞれの長所を明らかにしている個所が幾つかある。彼の主張は簡単で、白色人種は知的な点で優れ、黄色人種は積極的活動という点で優れ、黒色人種は豊かな感情という点で優れている。従って、混血によって、二つ或いは三つの長所を兼ね備えた人間のタイプが生まれる。コントは混血を勧めている。また、彼は、北アメリカにおける人種的差別に見られるイギリス的プロテスタント的方法を非難し、南アメリカの混血の進行に見られるイベリア的カトリック的方法を賞讃している。コントの文字は、ブラジル人のために書いたわけではないが、ブラジルのエリートから見れば、自分たちのために書かれたものと思われたのであろう。私は、日本の近代化のイデオロギーとして天皇信仰は非常に優れたものと考えているが、コントの実証主義は、ブラジルの近代化のイデオロギーとして生まれたようなものである。

清水幾太郎という名前を聞いて、何がしかの感慨を覚えるのは、1960年代・70年代に日本で大学生活を経験した高齢者だろう。今や忘れられた思想家となった清水だが、1950年代から60年代初期までは、平和問題懇話会という戦後の反戦平和運動を構想した良心的インテリの集りをリードした“進歩的文化人”であり、60年安保闘争の時期には、雑誌『世界』に「いまこそ国会へ 請願のすすめ」を発表して安保条約反対運動の大衆化に“火をつけた”アジテーターでもあった。そんな実践的左翼人は、60年代になると政治運動から自ら離脱し、70年代以降は急速に右傾化、1980年には戦後民主主義を全面否定する論集『戦後を疑う』、『日本よ国家たれ 核の選択』を相次いで刊行し、いわば空想的右翼の核武装推進論を展開するに至る。左へ右へとジグザクに動き回る無節操にして無責任な思想家というよりも自画自賛型の「論壇の目立ちがり屋」でしかなかった、というべきかもしれない。
評論家としての活動歴を略記すれば上記の通りだが、彼の本業である大学教授・社会学者としての業績はどうだろうか。多作であった清水(講談社版清水幾太郎著作集は全19巻)の社会学や倫理学関連の著書や翻訳書にお世話になった人は少なくないはずだ。筆者が読んだことのあるものだけでも列記してみると、翻訳では、E・H・カー『歴史とは何か』、『新しい社会』(いずれも岩波新書)、マックス・ヴェーバー『社会学の根本概念』(岩波文庫)、一般書では、ロングセラー『論文の書き方』(岩波新書、1959年、累計販売部数160万部以上)が有名だが、筆者が学生時代に愛読したのは『本はどう読むか』(講談社現代新書、1972年)であった。
そんな清水も晩年の1975年から1976年にかけて初めての海外旅行に出かけている。二回の旅行でのべ3か月ほどかけて、米国、メキシコ、ペルー、チリ、アルゼンチン、ブラジル、スペイン、ポルトガルを訪問しているが、この紀行エッセイ集は『昨日の旅』(文藝春秋社、1977年)にまとめられた。ポルトガル訪問時はカーネーション革命の真只中で銃声も聞いてあわてて退散、メキシコではトロツキー旧居(彼が暗殺された所)を訪ね、1975年11月12日から19日までの7日間ブラジル(サンパウロ、リオ、ブラジリア)を訪ねている。その主な目的は、彼が卒論で取り上げて以来研究を重ねて来た実証主義哲学者オーギュスト・コント(1798-1857)の思想がブラジル共和制成立に影響を与えた経緯を実地体験し、コントを開祖とする「人類教」教会のリオ本部(実証主義教会)を訪問することであった。従って、清水のリオ体験は、ホテル~人類教教会~日本料理屋のみでしかなかった。コルコヴァードもイパネマも全く行かず、「アメリカでもラテンアメリカ諸国でも行く先々で、私は日本料理店へ案内された。短期間なのに日本で食べる2年分か3年分の刺身、天ぷら、寿司を食べる結果になった」と。
同書を久しぶりに読み返してみたが、シュラスコもフェイジョアーダも口にしておらず、あちこちに老人性「繰り言」が書かれており、折角の海外旅行なのに、現地食文化を試食する意欲もなく、なんとも、「知識だけは国際派だが頭でっかちで現地文化を楽しむ精神的余裕すらない老いぼれ旅行者」の文章が続く、無残な紀行文でしかない。そのなかでもコントの実証主義がブラジル近代化に貢献したと語る、冒頭の引用文は、読むに堪え得る部分といえるだろう。
岸和田仁(きしわだひとし)
東京外国語大学卒。
3回のブラジル駐在はのべ21年間。居住地はレシーフェ、ペトロリーナ、サンパロなど。
2014年帰国。
著書に『熱帯の多人種社会』(つげ書房新社)など。
日本ブラジル中央協会情報誌『ブラジル特報』編集人。
月刊ピンドラーマ2023年10月号表紙
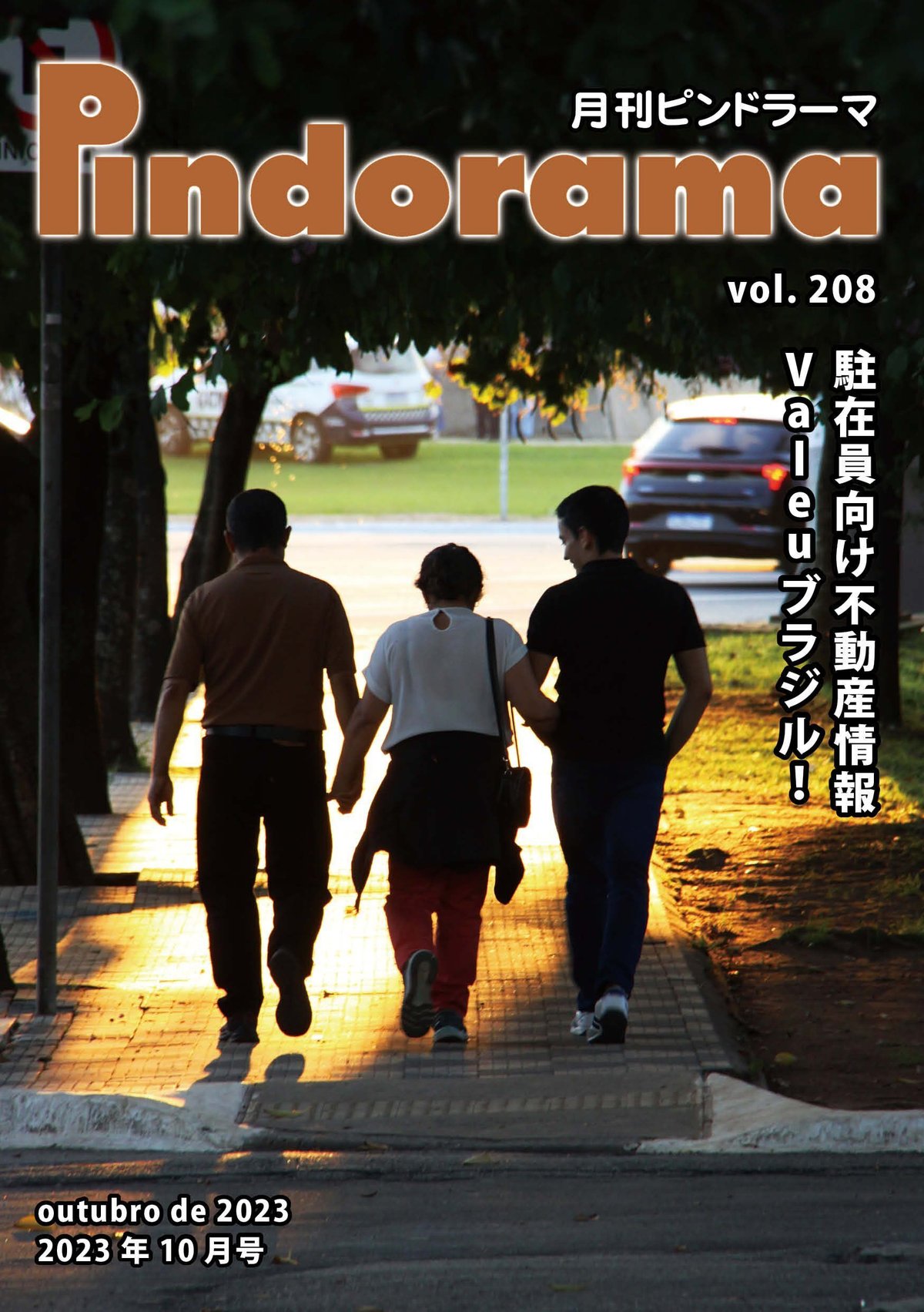
#哲学 #海外生活 #海外 #文学 #思想 #ブラジル #ポルトガル語
#サンパウロ #月刊ピンドラーマ #ピンドラーマ #岸和田仁
#ブラジル版百人一語
