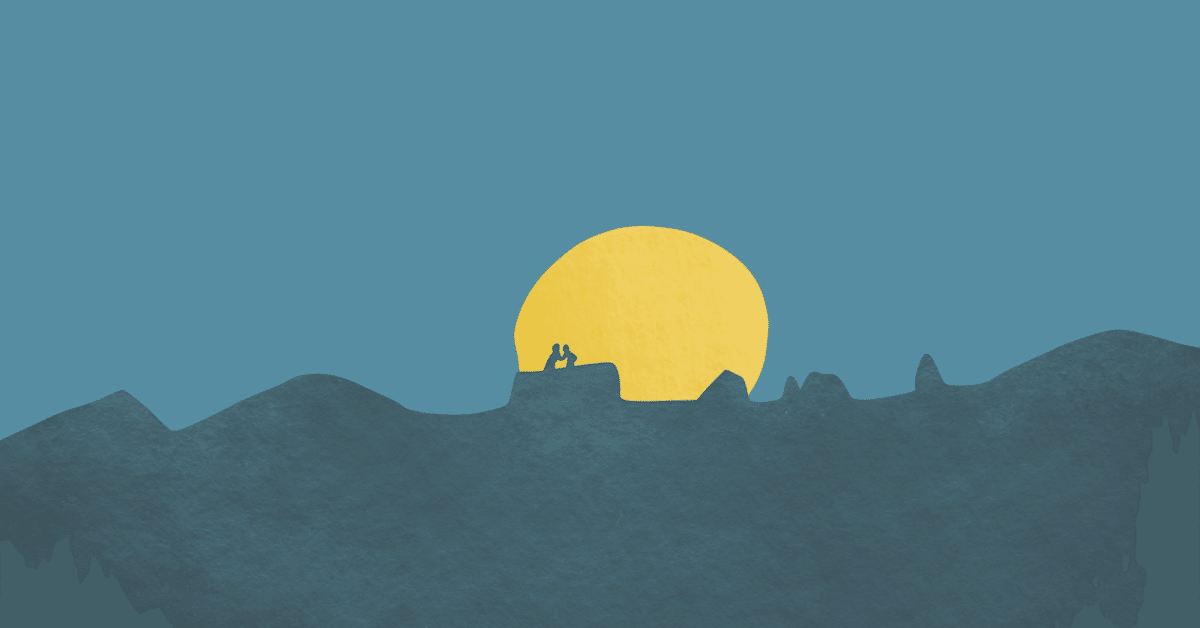
父よ、あなたは
わたしが高校に入りたてだった頃のある晩、祖母とわたしたち親子の4人の食卓で、ウィスキーの ショットグラスを傾ける手を止め、にこにこしながら父がわたしに、こう問うた。
「あんた、今ホントに自分がここにおるっちゅう自信、ある?」
こういう不可解な問いを、まるで学校での生活について質問するがごとき大らかな表情で、何の前触れもなく突然にペロンと訊いてくるのが、わたしの父である。いつもいつも、質問の意図や意味がイチドキには解りづらい。 今回のもそのタイプの、非常にエキセントリックな質問であった。
ハトぽっぽが豆鉄砲を食らったような顔をしていると、さらに質問に対する解説が続く。
「だからな。あんたは、今、お母さんとお父さんとばあちゃんと、おしゃべりしながら、夕ご飯食べよると 思うちょるやろ?これは果たして現実やろうか・・・と思うこと、ない?もしかして、自分がここにおると思うとるのは 自分だけで、ホントはここには3人だけかも知れん。自分は真っ暗闇のどこか違う次元の世界で独りでおるんかも知れん。 全ては自分の幻想かもしれん。そう思うたことないか・・・って言いよるのよ。」
こともあろうにおそらく人生でいちばん多感な年頃の娘にこんな複雑な質問の答えを探させるなよと、通常のヒトなら誰でも思うかもしれないが、こと我が父に限っては、こんなものは日常茶飯事である。相手が幼かろうが人格形成の途中であろうが、容赦はない。
そのうえ、ふつうの娘ならば、「いやだ、お父さん。そんな寂しいこと考えたこともないわ、わたし。」とでも、 やんわりとかわすところであろうが、この娘はちょっとばかり仕込みが違うのでややこしい。退かない。決して。 挑まれたら受けて立つ。
なにせわたしは、この父の膝で溺愛されて育った一人娘である。しかも、両親が共働きであったために、 この父を育てた張本人の祖母が赤子の頃から一時も離れることなく、しつけから作法から生活の知恵から、祖母オリジナルの数々の昔話に至る何から何まで、インプリンティング(刷り込み作業)を行い続けてきた娘である。 いわば生粋の「へそ曲がりの英才教育」を受けて育ったと言い放っても過言ではなかろう。
さらにご丁寧にこの娘には、「やんわりと事をかわす」とかいう生ぬるい処世術を覚えることは許されなかった。 これももうずっと以前、ある晩の晩酌の席でのことだが、父がわたしに何かの議論を吹っ掛けた。内容は覚えていないところをみると、これまた若輩者には不可解な、かなり捻りのある質問だったのだろう。内容を覚えていないのにもかかわらず 鮮烈にこれを記憶しているということはつまり、その時わたしがよほど悔しい思いをしたということだ。わたしは 必死で応戦したが、如何せん人生経験に31年もの隔たりがあると当然勝ち目はなく、ついには泣き出してしまったのだった。
そして忘れもしない。泣きじゃくる娘の背中をさすりながら、父はこう言ったのである。
「悔しいかえ?言いたいことがことばになって出てこんのやね?本をたくさん読みなさい。本にはことばが詰まっている。いろんな考え方の人間が、いろんなことを書いている。 本には、あんたが知りたいことの半分くらいは書いてある。たった半分。あとの半分は自分で探すこと。生きて人と出会って話して自分で探して見つけた答えは、きっと、あんたの財産になる。」と。
その時、わたしは若干9歳。まだ小学校3年生の時のことであった。父のことばの内容は、思えば深い示唆ではある。
が、どう譲っても、この年齢の娘っこにこの教育方法は、大人げなくはないだろうか。娘らしくやさしく 会話を交わす術を身につけるよりも、言葉を武器として身につけよと教えたのだ。けれども祖母によって勝ち気の素地は完成されていたと見えて、それ以来、わたしの目標は、「いつか、この父を言い負かす。」 というものになった。
さて、件の突拍子もない問いかけへの答えを準備しなければならなかった。
わたしの頭の中には、目を開いているのかどうかさえわからないような暗黒の世界が拡がり、そのまっただ中に独りで浮かんでいるような幻想が渦巻きはじめていた。瞬きをしたら父や母や祖母の姿は、霞のように消え散ってしまうのではないか・・・そんな不安がムズムズと動き出している。この渦に入り込んでしまったら、そこで、わたしの負けである。
こういう場合、余計な修飾辞のくっついた綺羅綺羅しい言葉は必要ない。相手の言葉の裏を読んで、簡潔に切り返すことが肝要だ。
「そんなこと、考える必要ないと思う。わたしは、今、ここにおる。それだけでいい。」
びし!と父の矛先をかわしたように思ったが、狸親父は一歩も引かなかった。
「ここにおるという保証はどこにもないんだぜ?お母さんもばあちゃんもお父さんも、ここにおると思うとるのは、 実はあんたの空想かもしれんのだもの。さ、どうする?」
混沌だ。出口のない、不安の輪舞の中に取り込まれそうだ。ムカムカする。胸の奥に音を立てて炎が生まれる。 なんで、家族の団らんの時間にわたしはこんなことを考えていなくてはならないのか。母と祖母は、 聞いているのかいないのか、何事もないかのようにおかずの味付けなど話題にしながら談笑していて助け船さえ出さない。もしかしたら、本当は2人の目の前にはわたしの姿がないからなのかもしれない。 不安が恐怖に変わりそうだった。
ばくっと頭の奥で何かが開いたような音がしたのと同時に、少々声を強くして、わたしは父に、ことばを 叩きつけていた。
「わたしは、ここにいる!お父さんもお母さんもおばあちゃんも、わたしの目の前にいる。自分の感じることや見ているもの以外に自分の存在を証明するものがないというなら、わたしがここにいて家族と過ごしているという、 わたしにとって今この瞬間の現実が全てだと思う。今、お父さんはわたしの横に座っていて、ウィスキーを飲みながらわたしと話している。この事実以外の現実は、どこにもないし必要ない!違うの??!!」
父は答えず、ただ黙って、にんまり…として頷き、ウィスキーのグラスを再び傾けた。父の投げた質問の意図は、とうとう解説されないままだった。
「やれやれ・・・。」
祖母が、このひと言で父とわたしの会話に終止符を打った。
「お父さん、飲み過ぎ。娘をからかうのもいい加減にせんと。」母がそれに念を押した。
2人はちゃんと、わたしと父の話の行方を聞いていたのだ。あまりに人が悪いじゃないか。これでわたしの人格がこれ以上歪んでしまったら、どうしてくれる。不覚にもこの時もまた、目の奥から湿っぽいものが滲み出してきそうだった。
どうして父が、こんな質問をしてきたのか。父自身から説明がないのなら、わたしが自分で答えを探さなければならなかったが、その頃のわたしは、まだまだ人生の「じ」の字も知らない(少しは知ったつもりでいるので、 なお質の悪い)お子様だったから、父親の心の中なんぞ覗いてみる気にもなれなかった。
自分なりに山谷乗り越えて 20余年の人生経験を積んでみてやっと気持ちが落ち着いてから、今頃になってゆっくりと、父の気持ちを考えてみた。
父は、退官するまでの間に通算13年間の単身赴任を経験した。家族第一の人なので、単身赴任中は金曜日の夜中に家族の元へと帰ってきて週末を過ごし、日曜日の夕方か月曜日の早朝、再び赴任地へと旅立つ・・・そんな行ったり来たりの落ち着かない生活を甘受していたのだった。大学時代を除けば故郷から離れたことのない父にとって、 そんな生活はどんなにか不安定で満たされない、味気ないものだっただろう。
あの問いかけが行われた頃は、最初の5年間の単身赴任生活から解放されて、3年間の地元勤務の辞令を受けたところだったと思う。
「もしかしたら、自分が今ここにいて家族と暖かな団らんの時を過ごしているというのは、 自分だけが見ている夢なのではないか。目を覚ましたら、殺風景な官舎の部屋で独りきりなのじゃないだろうか。」
そんな不安に囚われて、確たる答えを探していたのは、実は父の方だったのかもしれない。自分で自分に課した青臭い問いを持て余して、実は不安に苛まれていたのではなかろうか。わたしが父に叩きつけたあの答えが、もしかしたら、父自身のための存在確認になり得たのかもしれない。
あの時、そっと頷いてグラスに口を付けた父の微笑みを思い出して、わたしは、そんな答えを見つけたように思っている。
これは今から四半世紀も前に、当時34歳だったわたしが「父の存在確認」と題して書いたものです。句読点の位置やことばの使い方を少し直しました。
父はわたしにはとても甘く、強く叱ったりなどされた記憶はまったくありません。多感な年頃のわたしと、親になってさえまだ多感な少年のような思いを抱えた父。いいコンビだったと懐かしく愛しく思い出します。
2023年9月29日(金)
中秋の名月、前の月の日に。
もしも気に入っていただけたらサポートをお願いいたします。ご厚志で同居にゃんずのカリカリやおやつを買わせていただきます。
