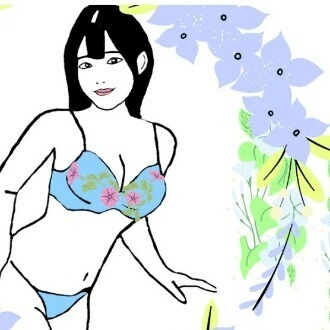短編小説 | ほくろ
(序)「ほくろ」の成り立ち
以前投稿した作品を再構成しました。
今のところ、私の代表作です😳💦。
この小説は(上)(中)(下)に分かれています。
最初に発表したとき、(上)の部分で完結した小説を書いたつもりでしたが、コメント💬欄で「続編は?」という書き込みが複数あり、(中)と(下)にあたる部分を書き足した短編小説です。
国木田独歩「運命論者」とソフォクレス「オイディプス王」をモチーフにしています。
(上)
ようやくこの席に座ることになった。ここまで辿り着くまでに、わたしは様々なものを犠牲にしてきた。
本当に愛する女性と結ばれることもできただろう。しかし、わたしは愛よりも野心を満たすことで、頭がいっぱいだったのだ。
わたしは出世のために、多少強引なことをしてきた。しかし、コストカッターとしての手腕を買われ、社長のひとり娘の令嬢と政略結婚をした。
妻には、ほとんど愛情を感じなかった。娘をひとりもうけたが、悲しい事件で、それも失ってしまった。愛なしで生きてきたが、後悔はしていない。ここまで、辿り着いたのだから...
「社長、例の件はどうしますか?」
部下がわたしに尋ねた。
「秘書などいらん」とわたしは答えた。
「しかし、秘書をおくと何かと便利ですよ。彼女はたいへん優秀です。一度、お試しになるといいでしょう。その後で、社長が必要ない、と判断なされたら、それで結構です。どうでしょうか?」
何度も断ってきたが、わたしの最も信頼する部下の言葉だ。わたしは、しぶしぶ秘書をおくことに合意した。
「わかった。とりあえず、3ヶ月の採用ということで、よろしく頼む」
わたしの元にやって来た秘書は、部下のいう通り、たいへん優秀だった。細かいところまで、実によく気が利く。今では、彼女なしで今までどう仕事をしてきたのだろうかと思うくらいだ。
彼女がきてから数ヶ月経ったある夜、わたしはよからぬ気持ちになった。彼女とわたし以外には、誰もいない薄暗いオフィス。
不意に彼女と目があった。彼女が瞳を閉じた。そのとき、わたしの中の野獣が目を覚ました。
彼女をソファーに押し倒した。彼女はただ一言こう言った。
「いいんですよ。私もそういう気持ちですから...」
その後、わたしも彼女も淫獣と化した。お互いの服を脱がせた。
「社長が横になってください」
彼女がわたしの上にのって、一心不乱に腰を振り始めた。しばらくして、わたしは飛び散った。
彼女との情事のあと、彼女はわたしの左乳首のほくろを見て笑った。
「社長、エッチぼくろがありますね。実は、私もここに、ほくろがあるんですよ」
わたしは彼女の、左側の乳輪を見た。確かに、そこに大きめのほくろがあった。
わたしは驚愕した。若かりし頃に誘拐された我が子にも、同じ場所に、大きなほくろがあったことを思い出したのだ。
(中)
「秘書」との情事のあと、わたしはしばらく茫然としながら、薄暗いオフィスのソファーで、彼女の左胸のほくろを見ていた。
「社長、じっと見ないでください。そんなに立派なおっぱいじゃありませんから」
彼女は照れくさそうに微笑んだ。
無邪気ににっこりと笑う彼女には、昔、生き別れた娘の面影が確かにあった。
「つかぬことを聞くが、君の初体験はいつだったんだい?」
わたしは場違いなことを口走った。彼女は少し照れながら、話し始めた。
「高校2年生のとき、先輩とでした。痛いだけだったんですけど、2番目の彼氏がとても上手だったので...」
「上手だったから?」
「それから、いろいろな男性と経験を重ねてきました。本気で誰かを愛したことはありません。でも、体が欲しがるんです。男の体を、肌を… …」
わたしはそっと彼女のブラを手に取り、ホックをとめた。もう彼女の乳房を見ることはないだろう、と思いながら...
服を着たあと、「お腹が空きましたね、どこかで食べていきませんか」と彼女が言った。
「この時間では...そうだ、洒落たところではないが、行き付けの居酒屋でもいいかい?」
「ぜひ、喜んで」
居酒屋に着くと、いつもの個室に案内された。秘書と再び二人になった。彼女が先に口を開いた。
「さっき、私の胸のほくろをじっとご覧になっていたでしょう?そんなに気になりましたか?」
「いや、そういうわけではないのだが」
「そうですか」と言ったあと、彼女は話し続けた。
「わたし、実は小さな頃、お寺の境内に捨てられていた子供なんです。いろいろあって、現在の両親に育てられたのですが...」
わたしは黙って彼女の話を聞いていた。
「さっき、社長に抱かれているとき、なんか不思議な気持ちになったんです。あの恍惚感の中で、私の本能のようなものが、社長が私の本当の父親なんじゃないかって。そんなことはあり得ないことなんですけど。社長の肌触りが、なんかとても懐かしくて」
わたしは、彼女の左胸を見つめた。
「そんなに見ないでください。冗談ですよ。それより、乾杯しましょう」と娘は無邪気に微笑んだ。愛おしい、と思った。罪悪感に苛まれながら...
(下)
あの日の情事以降も、「秘書」は、何事もなかったように、いつも通りの仕事をこなしていた。
彼女が来てから、そろそろ3ヶ月になろうとしていた。
「社長、申し訳ありませんが、最初の契約通り、3ヶ月で辞めようと思います」
「なぜだい?今、君に辞められると困るのだが...」
「今までも、契約期間の延長はほとんどしたことがないのです。少し、まとまった休みをとりたい気持ちもあります」
「秘書」はあっさり会社を辞めてしまった。わたしには、積極的に彼女を引き留めることが出来なかった。
彼女が辞めてから、早くも一年が過ぎた頃、彼女からわたしに電話がかかってきた。
「社長、お久しぶりです。私ですが、わかりますか?」
「ああ、君か、久し振りだね。今までどこで過ごしていたんだい?」
「いえ、ずっとこの街にいましたよ。わけがあって、住所はかわりましたが」
彼女は話し続けた。
「近いうちに、お会いすることは可能でしょうか?」
「ああ、来週の金曜日の夜なら空いているが」
「そうですか?よかったです。私の家までお越しください」
翌週の金曜日、わたしは彼女のもとを訪れた。
「お久しぶりです、さあ、どうぞどうぞ」
部屋に入っていった。赤ん坊が寝ていた。
「驚かせてすみません。女の子が生まれました。あのときの子供です」
「えっ!?」
「なぜ、わたしに知らせなかっんだ」
わたしは思わず大きな声を出してしまった。
「私がお腹の中に赤ちゃんがいると言ったら、社長は産むことを許してくださいましたか?」
わたしは何も言えなかった。
そのとき、赤子が急に泣き出した。彼女は、隠す様子もなく、わたしの目の前で授乳し始めた。
あのとき以来、再び彼女の乳房を見た。乳輪には、ほくろが見えた。
「社長、見てください。この子にも、ここにほくろがあるんですよ」
わたしは、孫であるのと同時に、自分の子どもでもある赤子の左胸を見た。わたしと彼女と同じ左胸の乳輪に、ほくろがあった。
「社長似かしら」彼女は無邪気ににっこりと微笑んだ。
了
#私の作品紹介
#国語がすき
#ほくろ
#小説
#短編小説
#国木田独歩
#運命論者
#ソフォクレス
#オイディプス王
#イラスト
いいなと思ったら応援しよう!