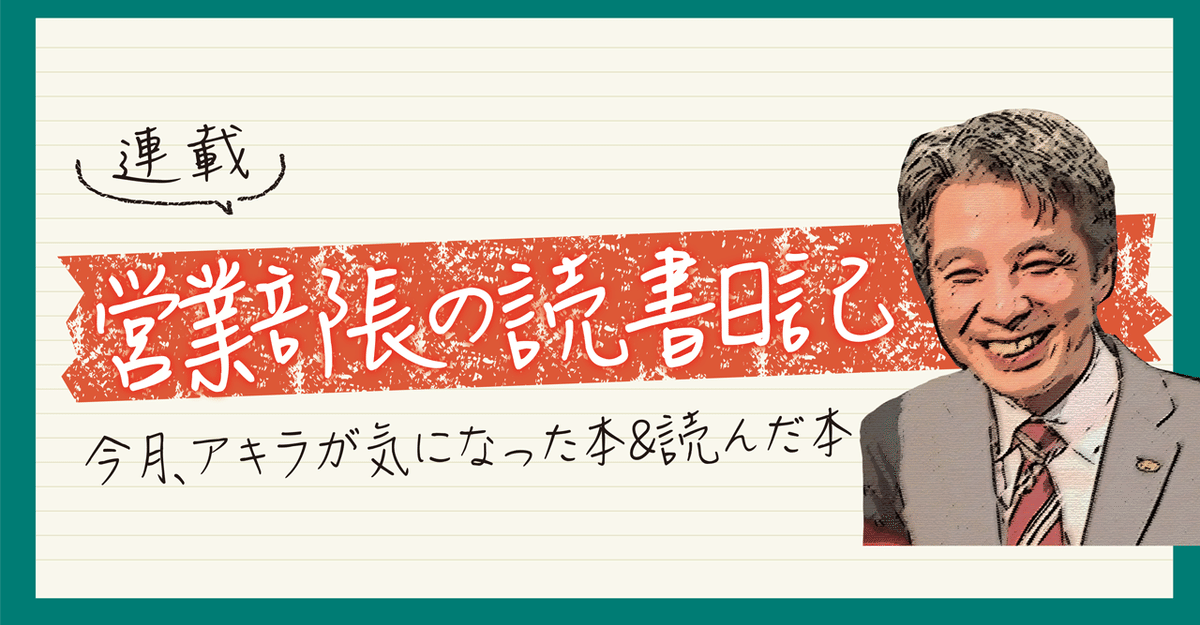
<第4回>オリンピック騒動で心乱れる日々のなかで
コロナウイルス感染が急拡大するなかで強硬開催(!?)された東京オリンピック。終わってみれば金27,銀14、銅17と、史上最高の58個のメダルを獲得する日本人選手の活躍もあって、直後の世論調査では「オリンピックを開催してよかったと思う」人が6割超と、国民の厳しい見方も和らいだようですが……。それにしても、マスコミもマスコミで、開催か中止か、有観客か無観客か、直前までのあの大騒ぎは、いったい何だったのでしょうか。今回のオリンピック騒動に心を搔き乱されたのは、たぶん私だけではないはずです。
さて、本題の読書日記に話を戻しますと、今月、新たに購入した本は以下の3冊です。
≪今月の購入リスト≫
①『Humankind 希望の歴史(上・下)』ルトガー・ブレグマン 文藝春秋 2021/7/27
②『スタンフォード大学の共感の授業』ジャミール・ザキ ダイヤモンド社 2021/7/7
③『心とからだの倫理学』佐藤岳詩 ちくまプリマー新書 2021/8/10
※上記①は丸善丸の内本店で、②③は8月6日にオープンした喜久屋書店府中店で、ともに上京した際に購入しました。
今年の春先に、「知の巨人」「戦後最大のジャーナリスト」と称された長崎出身の立花隆さんが亡くなられました。個人的な読書体験としては、『革マルVS中核(上・下)』(講談社文庫)が全共闘運動と内ゲバを理解する格好のテキストでしたが、昨年、『エーゲ 永遠回帰の海』(ちくま文庫)を読んで、キリスト教の聖母マリア信仰の本質が少しは理解できたかな、と思ったところだったので、とても残念です。
没後、「立花隆さんを偲んで」NHKスペシャルやETV特集のセレクションが初夏に放送されることになり、そのなかの1本、NHKスペシャル『臨死体験 立花隆 思索ドキュメント 死ぬとき心はどうなるのか』(2014年)の再放送を視聴しました。初っ端から読書日記ではありませんが、備忘録として感想を記します。
■2021年7月3日
【追悼】立花隆⇒不可知の臨死体験を求めて
とくに印象的だったのは、自身の20年前の臨死体験のテーマを追って、改めて世界の識者を訪ねる旅でなされた、ケンタッキー大学ケビン・ネルソン教授のインタビューでした。
ネルソン教授によると、死の間際に起こる神秘体験は脳の辺縁系で起こる現象だといいます。辺縁系は脳の奥深く、爬虫類にもあるという最も古い部分であり、長年の研究で睡眠や夢という現象の中心を担っていて、ここが死の間際に不思議な働きをするというのです。
それは人に眠りのスイッチを入れるとともに、覚醒を促すスイッチも入れ、それによってきわめて浅い眠りの状態を誘い、目覚めながら夢を見る、いわば白昼夢のような状態になるそう。さらに、辺縁系は神経物質を大量に放出して、人を幸福な気持ち、多幸感で満たします。こうして人は死の間際、幸福感に満たされて、それを現実だと信じるような強烈な体験をするというのです。これが臨死体験の真相だといいます。人が長い進化の過程で獲得した本能に近い現象ではないか、と考えられているそうです。
この神秘体験は、意識と現実とのあいだでつくり出される現象であり、神秘体験自体をどう受け止めるかは、必ずしも科学で証明する必要はないといいます。たとえば、死の淵で母親に会ったとき、それを母親の魂と受け止めるのか、母親についての記憶と受け止めるのか、それはその人にしか決められない心の問題であり、「信じるということ」の問題だからです。
そもそも科学というのは、どのような仕組みなのかを追究するもので、何故かという問いへの答えは、その人の信念に委ねるしかないといいます(小林秀雄の『感想』(新潮社)で有名な、水道橋のJRホームから酔って落下し、手にした一升瓶は割れて粉々に砕け散ったのに無傷で済んだのは、「おっかさんが助けてくれた」という逸話も、そうではないかと)。
立花隆さんは、どんな哲学やニューロ・サイエンスをもってしても、ほんとうのところはよくわからないという部分が、人間にとって永遠に残る、そういうあり方で人間が生き続けるというのが面白い、生きるってのは面白い、わからないから面白いと、番組の最後に繰り返します。人間という存在は面白くて、簡単にこうだとは言えない面白さがあるんだ、といいます。不可知論を楽しんでいるのです。
また、自身の癌を抱えながら死ぬことが、それほど怖いことじゃないとわかった、とも語ります。古代ギリシアの哲学者・エピクロスの「人生の目的というのは結局、アタラクシア(心の平安)を得ることだ」という言葉を引いて、いい夢をみたい、見ようという気持ちで人間は死んでいくことができる、と明言します。これも信念の問題ですが、果たして「知の巨人」がそれでいいのでしょうか……と、つい思ってしまいました。
■2021年7月10日
『落葉の声』⇒究極の利他主義は、結果を求めず
前回触れた、利己的遺伝子の利他的側面がもたらした悲劇が、どうにも気になっていました。利他主義が自己犠牲を伴わざるを得ないのは必然ですが、自己の生まで投げうつケースは、どう考えればいいのでしょうか。芋づる式「読書」が芋づる式「想起」になってしまいましたが、もう少しおつき合いください。
文学では、三浦綾子の『塩狩峠』(新潮文庫)を思い出します。悪いことも覚えはじめた、多感な思春期に読んで感動した作品です。暴走する列車を身を挺して停め、多くの生命を救ったという実話に基づく小説です。
同時期に読んでいた漫画に、梶原一騎原作・ながやす巧劇画『愛と誠』(講談社漫画文庫)があります。ここではギャグにもなっていた岩清水弘の有名な台詞「君のためなら死ねる」は、1970年に刊行された200万部(すべての版だと400万部?)ベストセラー、曽野綾子『誰のために愛するか』(祥伝社黄金文庫)の「愛とは、その人ために死ねるかということ」に呼応していたんだと、これも後年知ることになって感動しました。家族や恋人など、愛する人のためなら死ねると誰もが思うことでしょう。では、他人のために人は死ねるものでしょうか。
そして、改めて想起したのが「コルベ神父」の話でした。およそ90年前に日本に布教にやってきて長崎で出版活動を始めた神父さんです。私が最初にコルベ神父の名を知ったのは大学生のころ、たぶん遠藤周作さんの小説『女の一生<2部>サチ子の場合』(新潮文庫)だったと思います。ですが、ここで私が紹介したいのは、今回読み返してみた曽野綾子さんの『落葉の声』(聖母文庫)という小編です。数年前、四谷のサンパウロ書籍販売で購入した文庫本ですが、私にとっては戦慄(せんりつ)の自己犠牲の結果を問う小説です。
マキシミリアノ・コルベ神父は1936年7月30日、アウシュビッツ収容所において妻と子供をもつ軍曹の身代わりとして自ら志願し、餓死刑室(ガス室は未完成)に送られます。カトリック司祭で生涯家庭を持たない自分とは違う、妻子を持つ者のために、です。そこでコルベ神父は2週間も放置されて衰弱し、最後は薬物注射で死に追いやられます。曽野綾子さんは、コルベ神父に助けられたガイオニチェックという人物に会おうと、ポーランドの自宅に向かいます。そこで明かされるのが、衝撃の事実です。収容所から幸い生還することができたガイオニチェック氏に告げられたのは、息子二人がワルシャワにおいてロシアの爆弾により、すでに亡くなっていたという事実でした。コルベ神父が身を挺して守ろうとした家庭の幸福は、無残にも踏みにじられていたのです。
「神」は只、人間に使命を与えているだけのように見える。マクシミリアノ・コルベには、人間が人間に究極のところ何をなし得るか、という問いについて答えを出すことを。そしてこのガイオニチェックの一家には、そのコルベ神父の仕事に、生涯をかけて手を貸すことを。(『落葉の声』より)
収容所からの生還者であるヴィクトール・フランクル(代表作『夜と霧』/みすず書房)の、人間は「人生から問われている存在」だという言葉を思い出しました。人は何をなし得るか、です。上記に引用した直前の文章が、また強烈なのです。
うっとうしい、詐欺に等しい人生を私は感じていた。善きことをすれば、必ず報いてくれる「神」などというものは、この世の阿呆な人間の考え出した、ハリボテの神であった。(『落葉の声』より)
この作品の後日談が、『新潮45』2011年3月号に発表した「ポーランドの秋」(新潮文庫『立ち止まる才能』に所収)で明かされます。
著者は1982年、ヴァチカンでのヨハネ・パウロ2世の列聖式に参列したとき(マザー・テレサもいたそう)、式典ののち教皇がガイオニチェック氏に声をかけ、抱擁する光景を目にすることになります。それは生き延びたことによって人びとのそしりに遭っていたであろうガイオニチェック氏に、「お前の苦労は無駄ではない。それがために、コルベ神父が死を賭して守ろうとした愛の真髄を、人びとは見るようになったのだ。むしろ、この世で大きな義務を果たしたのだ」と説きます。
非情な世界に対する神の沈黙は、遠藤周作さんのテーマでした。
『沈黙』(新潮文庫)の「そしてあの人は沈黙していたのではなかった。たとえあの人は沈黙していたとしても、私の今日までの人生があの人について語っていた」。利他主義の到達点は、<あの人=神=愛>の顕現のための自己犠牲に尽きるのでしょうか。
曽野綾子さんは、同じコルベ神父を題材にしたノンフィクション『奇跡』(文春文庫)でも、
死んで無に帰すのなら、永遠の生命はどうなるのだ! とひとは言うだろう。しかし私も、別の形でなら永遠の生命を信じる。<中略>収容所に入って、もはや、現実の生命はほそって消えそうになり、人間としての外見上のあらゆる尊厳は失われてもなお、神父は敵にさえも深い感化を与えた。そのような或る精神の本質的な輝きを誰かに伝えることこそ、永遠の生命というものではないか。(『奇跡』より)
利己的遺伝子の利他行動から遠く離れてしまいましたが、改めて読書から受けた感銘ですので、備忘録として残しておきます。
それにしても、ながやす巧の漫画はいいですね。とくに『鉄道員/ラブ・レター』(浅田次郎作・ながやす巧画/講談社文庫)は名作で、ふと思い出しました。
■2021年7月17日
『進化思考』⇒人間の創造よりも、生物の進化は優れている
さて、私的な芋づる式読書は、「進化論」に引っかかったままです。もう少し時間をかけて格闘することにします。
先月購入した『進化思考』は、デザイナーである著者(太刀川英輔氏)ならではのビジネス書であり、未来を担う若い人に対する期待の込められた啓蒙書です。あらゆる進化の過程をトレースすることで創造をもたらす「進化思考」を提唱するもので、著者が重ねてきた貴重な体験と歳月の結晶です。普段の仕事で何がしらの発想に悩んだときには、これ以上ない、助けとなるテキストだと思います。
創造について、著者は「創造とは、言語によって発現した"擬似進化"の能力である」といいます。人間にとって言語の歴史は、ちょうど5万年、石器時代を乗り越えたところで、それ以降、人類は道具の発明によって急激なスピードで進化しています。ただし、生物の進化は38億年の自然選択によって磨き上げられており、人間の創造よりも優れているのは必然だといいます。その自然の進化から学ぼうというのが、本書の方法論です。
興味深い事例が満載で、大きくは「変異」(HOW)と「適応」(WHY)の探求です。
まず、「変異」については、変量(極端な量を創造してみよう)、擬態(ほしい状況を真似てみよう)、欠失(標準装備を減らしてみよう)、増殖(常識よりも増やしてみよう)、以下、転移、変換、分離、逆転、融合と九つのコンセプトを、豊富で説得力のある事例で説きます。
一方、「適応」については、解剖(内部の構造と意味を知ろう)、系統(過去の系譜を引き受けよう)、生態(外部に繋がる関係を観よう)、予測(未来予測を希望につなげよう)の四つコンセプトを展開しています。
本書はワークブックでもあり、勉強になります。ぜひ読んでみてください。これほど未来への道筋に希望を見出す、知的想像力をかき立てる本はありません。それも、著者の創造性教育にかける志が高いからでしょう。
ルネサンス期の創造性の爆発は、ペスト菌による感染症の蔓延がきっかけだそう。スペイン風邪が猛威を振るったときは、世界中で数千万人が亡くなったといいますが、その翌年に史上最高の創造性の学校といわれるバウハウス(Bauhaus:美術と建築に関する総合的な教育機関)がドイツで誕生しています。著者は、新型コロナウイルスで世界中が苦しむいまこそ、創造性を進化させるときではないかと訴えます。また、著者は2025年関西万博のメイン展示・日本館の基本構想クリエイターです。楽しみですね。
ちなみに本書は、島根県の北60㎞にある小さな離島の出版社が最初に発行したものだとのこと。世界は辺境から変わるそうです。オリンピック後、日本の重心は関西に移るのではないかと、ひそかに期待しています。4年後に備えましょう。
最期に、今回も読みながら考えた松下幸之助(PHP研究所創設者)の代表的なキーワードは、やはり「生成発展」「素直な心」でした。松下幸之助が日本の行く末を見通した書として、近未来小説『私の夢・日本の夢 21世紀の日本』(PHP文庫)があります。その後、世界を考える京都座会編『松下幸之助が描いた「21世紀の日本」』(PHP研究所)という書も出ていますので、ご参考までに。
