
食人とは一体何だろうか?
自分たちの目の前から、食料が無くなることはあるのだろうか?

地震や災害などによって都市の流通が止まってしまうことはある。人々は買占めを行い、店の棚から食料が消えてしまう。それでも、食べ物が無いのは今だけだろうとやり過ごす。だが、次第に空腹感が増してくる。このまま食べないでいられるだろうか。苛立ち始めた人々が店員に文句を言っている。

多くの人々が空腹で騒ぎだした。自分に食べものが回ってくるとは思えない。どこへ行けば食べ物が手に入るのか。田舎だろうか。電車は動いておらず、車が移動できる状況にもない。食べ物の値段はどんどん吊り上がっていく。このままのんびりしてはいられない。
どうすればいいのだろうか。もう、食べ物がないのだ。怒りをどこに向ければいいのか。体力が次第に消耗をしていく。空腹に呆れかえり、こんなはずではなかったとただ力なく横たわる・・・。
かつて冷害が起きると、娘売りが行われる地域があった。悲しい歴史のようにも思われるが、今でも世界のどこかで似たようなことが行われている。
作物が育たず、空腹な毎日が過ぎていく。ネズミや虫を食べ、草木を食べ、腐葉土や小石まで口にする。このままでは餓死をしてしまう。
もう口に入れるものが見当たらないのだ。生きていくために、人の肉まで考えなければならない。売れる娘があるだけ良かったのかもしれない。極度な空腹の先には、身内の誰を食うのかという話が出てきてしまうのだ。
人食いの行為自体は、恐ろしいものである。身の毛がよだつ話である。だが、人肉というのは極限状況で生をつなぐ食糧となり、富裕者たちには贅を凝らした料理にもなっていた。
中国は有史以来、食人の伝統や文化があった。中国近代文学の元祖である魯迅は、『狂人日記』(1918年)を書いている。周りの目つきが気になり、食われてしまうのではないかという被害妄想の手記である。
末尾では、「人を食ったことのない子供なら、もしかするとまだいるかもしれない。子供を救え」と叫んでいる。儒教を説きながら、その口で人肉を食っている日常を問うているのである。

西遊記はご存じであろう。三蔵法師が供を連れて天竺へ経典を求めに行く旅の話である。途中で待ち構える妖怪たちが、三蔵の肉を食って不老長寿をかなえようとする。三蔵は前世では釈迦の弟子(金蝉子)ということになっている。何度生まれ変わっても修行を続け、その身は元陽(精液)を漏らしたことがない。
出没する妖怪たちは庶民を捕まえて食ってはいるが、三蔵の肉が特別にありがたいことを知っている。動物の姿から人間に化けると、三蔵たちを巧みに騙しながらチャンスをうかがう。妖怪たちが食人であるがゆえにこの話は面白い。

食人というのは野蛮であり、未開人の行為だと思うかもしれない。だが、洋の東西を問わず、食人行為は行われてきた。
人が人を食べる理由は、エネルギー源や敵の征服、先祖の礼拝、治療効果、神との交流などいろいろ挙げられる。食人を行っていた民族たちは、文化的にも産業的にも進んでいたケースが多かったりする。
古代中国において、大飢饉があるたびに共食いが余儀なくされた。墓を掘り起こして屍肉まで食うほどであった。地面にいる虫たちに食わせるよりも、人間が食った方が合理的だったのだ。
そして、人の肉は犬や豚よりも安い。戦乱や天災による飢饉のたびに道に餓死者が溢れる。そのおびただしい数からして人肉は安いのだ。値打ちは米三升分しかなく、塩漬けや干し肉にして少しずつ食されていた。
『水滸伝』の話では旅人の肉を饅頭に入れて売られ、『韓非子』では主君のために我が子を蒸して献じている。また、父母の病気には子供が股肉を割いて食べさせる親孝行の話もある。戦乱時に人肉は貴重な兵糧となり、民衆や敵兵、戦友までもが食料となったりしていた。
西洋においても同じである。船が座礁して食料がないとなると残されるのは仲間の肉体だけになる。1875年のフェリシア号や1885年のブリタニア号の座礁や沈没で犠牲になったのは少年の水夫たちだった。身が小さくて肉が柔らかく、抵抗もできなかったのだ。

1884年には、後に有名になったミニョネット号事件が起こる。船は南大西洋で沈没し、乗組員たちは救命ボートで避難をした。船長、一等航海士、船員、給仕の4名で持ち物は缶詰だけである。
彼らは缶詰を食べ終えると、ウミガメを捕まえて食べた。だが、漂流18日目には完全に食べ物が尽きてしまった。船長は誰が犠牲になるかクジ引きをすすめたが、船員は気にいらないといって拒否をした。
少年の給仕だけ身寄りがいない。船長は海水を飲んで弱ったその給仕をペンナイフで殺害した。残った3人は少年の肉体と血液で生き延びることができた。その後、通りかかったドイツ船に3人は救助され、イギリスに帰国すると裁判になった。
マイケル・サンデルの授業でハーバード大生の多くは3人共有罪であり、道徳的に間違っているという考えを示した。他人の命を奪うことは許されない。とにかく食人は道徳的に正しくない。少年が死ぬまで待ってもダメだという。
生き残るためにはやむを得ず、道徳的にも許されるという主張も少数はあった。その他にもクジ引きなら平等に扱われるとか、同意を得られれば道徳的に正当化されるという意見もあった。
3人ではなく数千人と大勢の命がかかっている場合はどうかとサンデルは学生たちに質問を投げかける。1人の生徒は数の問題ではないと頑なな主張を繰り返す。この手の話は、ロースクールでもよく議論されているものだ。

航空機における事故でも同じである。1972年の航空機の墜落事故では、高度4000m近いアンデス山脈で死んだ仲間の肉を食べている(ウルグアイ空軍機571便遭難事故)。食べ物がない状況で、最終的に人の身だけが残される。その時にどうするかだ。
期待可能性がない、やむを得ないという理由で違法にしない法理論は存在する。だが、日本の裁判所は食人した者をなんらかの形で有罪にして、執行猶予をつけるのを落としどころとするに違いない。
実際に食料のない状態を迎えた時、我々はどのような判断をするのだろうか。今日、食べるものが無い。お腹がすく。明日も明後日もずっと無いかもしれない。喉も乾いている。仲間の血をすすれば生き延びられるかもしれない。誰が誰の血をすするのか。自分のか、他人のか。決断がせまられる。
そこに人権を気にしている余裕はないだろう。「食材にされない権利」が基本的人権として、どこまで機能するというのだろうか。裁判所が示せる正しさとは一体何だろうか。落としどころのある話を事務的にやっているだけではないのだろうか。
文明人として食人行為は人の道を外れており、野蛮だと忌み嫌うことはたやすい。だが、いつの時代においても、食料を喪失することはあり得る話である。その時どうするのか。確保したはずの食料が足りない。それすら他人に奪われないだろうか。自分や家族が襲われたりしないだろうか。
空腹に耐え続ける自分を想像し、餓死する自分を想像し、食材にされてしまう恐怖を想像し、仲間の首をかっ切る自分を想像してみる。
食べなければ死に、食べれば悪として扱われてしまう。社会とは残忍なものである。直面した人だけが味わう地獄である。食べずに死を選んだ人たちは本当に称賛に値するのだろうか。
一度、食料が無くなった時のことを真剣に想像してみてはどうだろうか。飽食である現在を大いに疑ってみてはどうだろうか。今一度、自分が普段口にしているものをよく噛みしめてみてはいかがだろうか。
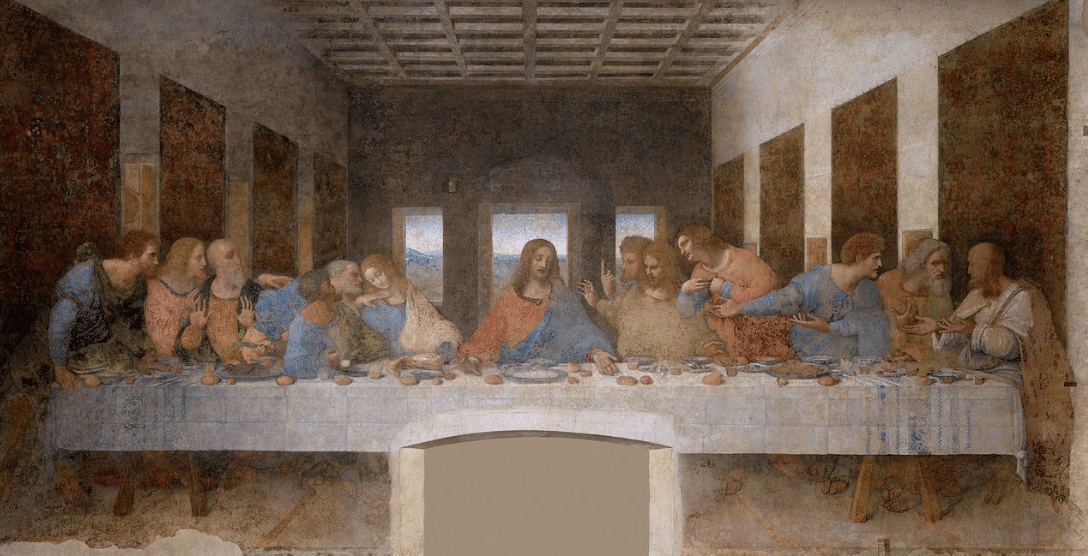
<参考>
『ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業〔上〕』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)2012年2月15日 発行 著.マイケル・サンデル
『なぜ食べ続けてきたのか!? 「食人文化」で読み解く中国人の正体』
ヒカルランド 著.黄文雄 第一刷 2013年6月30日
『図説 食人全書』 2001年3月22日 第1刷 株式会社 原書房
著.マルタン モネスティエ
『『西遊記』XYZ - このへんな小説の迷路をあるく』(講談社選書メチエ、2009年)著.中野美代子
『カニバリズム(人肉嗜食)論』(潮出版社 1975年)著.中野美代子
いいなと思ったら応援しよう!

