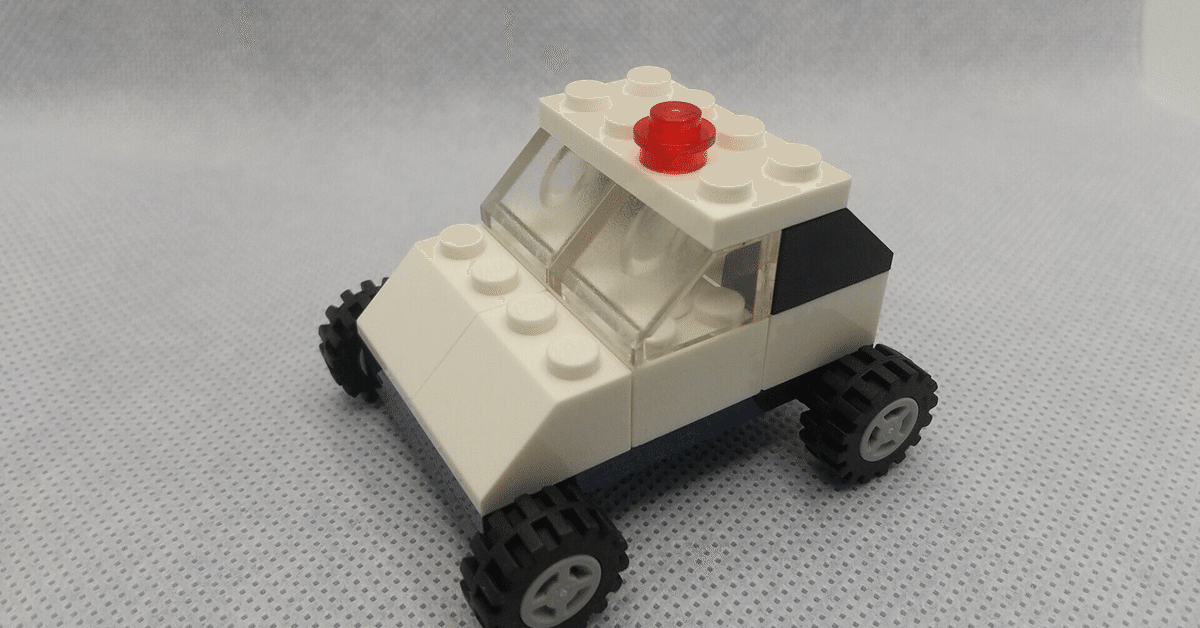
心のSOSを発信できる心を作る
ごきげんよう、おすみです。
このnoteでは一人の精神疾患当事者でB型作業所利用者であるおすみが実体験を元に障がい者福祉やメンタルヘルスに関する記事をほぼ毎日執筆しています。
今日は心のSOSを発信できる心を作り方を考えようと思います。
病気やケガは最悪119番通報すれば救急車が来て病院へ搬送してくれますし、事件や事故に遭遇した時も最悪110番通報すれば警察が駆けつけてくれますが、心のSOSはそうは行きません。
しかし、こんな経験はありませんか?
心のSOSを出す前にメンタルが崩壊してしまった。
SNSに心のSOSを発信したら通報されてしまった。
友人に心のSOSを発信したら関係が悪くなった。
今回は上の事案のおすみなりに考えた解決策をまとめようと思います。
メンタルが崩壊してしまう前に心のSOSを出す
ストレスやメンタリティーは一つのコップとそこに注がれる水によく例えられます。
そしてもう一つ良く言われるのが、精神疾患当事者はその水が溢れやすいという事です。
ちなみにストレスコップともいわれるこの例え。
ストレスで水が溢れやすい人は”器が小さい”と思われがちですが、実は器が小さいから溢れやすいという訳ではなく、みんな同じ大きさのコップを心の中に持っていることが前置きとしてあることを補足しておきます。
つまり、計り始めた時点でストレスと言う水がすでにまあまあ入っている状態か、性格上の個人差でストレスを溜めやすいという事です。
日ごろからこのストレスコップの考え方を頭の片隅に置いておくことでどのタイミングで心のSOSを出すべきかが徐々にわかってきます。
そのためにも、日ごろから自己理解や障害理解は自分の気が済むまで追求しておくと安心です。
SNS通報は誰かがSOSを受信した証
※この項目は内容的に重くなっていますので心苦しい方は遠慮なく飛ばしてください。
自殺や自傷行為(オーバードーズも含む)(そしていずれも未遂も含む)はやりたくなり気持ちも理解はします。
ただ、その行為をSNSで公開することはおすみは絶対におすすめしません。
なぜなら、その投稿が見ず知らずの人間の命にも係わる危険性があるからです。
SNSに投稿することはたとえ匿名投稿でも良くも悪くも影響を与えます。
投稿前に今一度踏みとどまってほしいと強く願います。
もしも投稿したことにその後自責の念を少しでも感じたときはすぐに投稿を削除してください。
そして見かけた人は迷わずに運営側に通報してほしいと願います。
『通報がありました』
と運営側から通知が来たときは余計な事をやられたと思わず、
『私の命を守りたいと思ってくれる人がいる』
と前向きに捉えてほしいと強く願います
なんでもかんでも家族や友人にSOSを発信すればよいわけではない
以前の記事でも書いた通りで、あなたの家族や友人はあなた自身の性格や特徴を知っているだけで、病気や法律や制度の知識はみんながみんな持ち合わせているという訳ではありません。
(以前の記事)
SOSは適材適所に出せるようにこれも日ごろから備えあれば患いなしです。
もしも日ごろ抱えている悩みの解決窓口がないと気がついたという事は、あなた自身のソーシャルサポート源が不足していることも意味しているので、少しでも充実できるように考え直すいい機会だと考えても問題ないかと思います。
今回は当事者が発信するという目線で記事を書いたので、次回はもしも相手から心のSOSを受信したときにはどのような対応をするのが当事者的にありがたいのかを考えてみようと思います。
