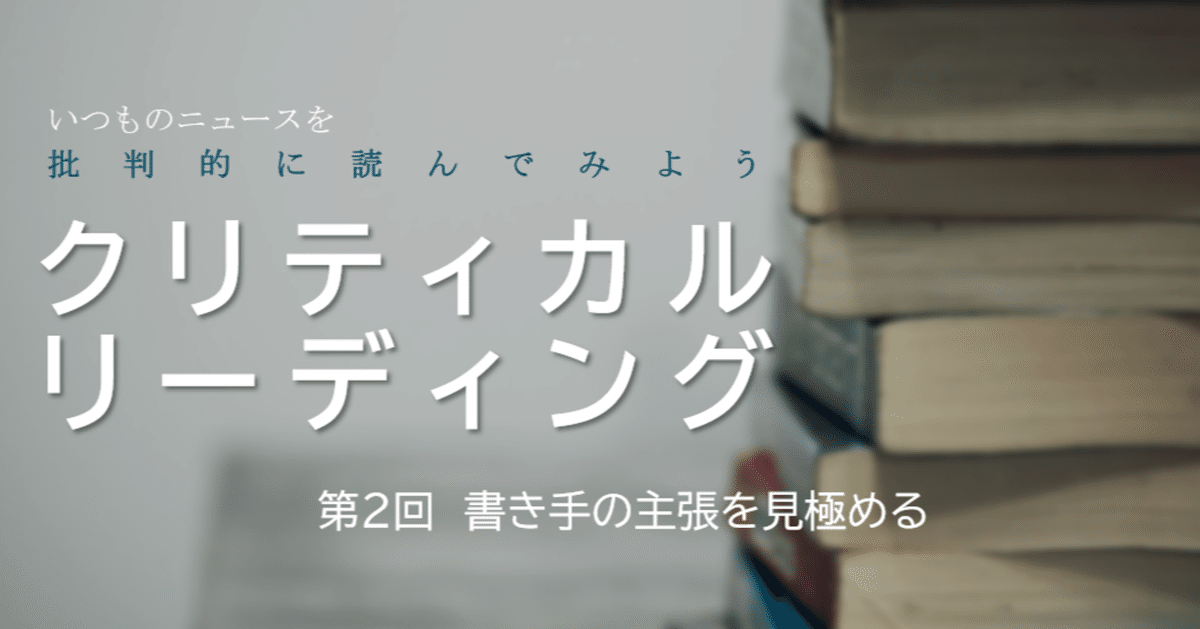
第2回「書き手の主張を見極める」

オシンテックのメルマガから飛んできてくれた方こんにちは。そうでない方もこんにちは。クリティカルリーダーのダイキです!今回のクリティカルリーディングのコツは、文章の要素で最も重要な「主張」についてみていきます。・・・と、その前にまずは前回のクリティカル・リーディングのおさらいから。
前回のおさらい
第一回の「情報の明確化」では、文章全体を構造的に捉えるための序章として、文章中の言葉の捉え方(書き手の定義)や記載されていない事柄への注目をしました。クリティカルリーディングは文章の主張やその根拠を構造的に捉え、多角的な視点で検証しながら読む手法なので、まずは文章の構造をしっかりと理解する必要があります。

今回のポイント「書き手の主張」に注目する
今回は新聞の社説を題材に、文章構成の軸となる書き手の主張に注目します。
その前に軽く文章の要素について説明しましょう。社説のような意見文は、主張とその裏付けとなる根拠が書かれています。根拠と主張を意識しながら、次の文章のどこが主張にあたるのか探してみてください。
※このシリーズに用いる引用は、著作権法第32条に認められる範囲内で行っております。
デジタル教科書 動画や音声の活用に限定せよ
デジタルには学習に効果的な面と、そうでない面がある。適否をしっかりと見極め、使い方を工夫することが重要だ。
デジタル化が進む社会での学校教育のあり方を検討する中央教育審議会・特別部会の初会合が7日開かれた。今後は端末を使った指導法や教材などについて議論を重ね、夏頃までに一定の結論を出すという。
全国の小中学生に1人1台の端末を配布する「GIGAスクール構想」は、新型コロナウイルスの流行による長期休校で計画が前倒しされ、すでに学校現場での使用が始まっている。
ただ、通信環境の整備や教員研修の拡充など、取り組むべき課題は多い。専門的な知見を生かし、十分に論議してもらいたい。
海外では、子供に端末を配ったところ、増えたのはゲームや動画を楽しむ時間ばかりで、十分な学習効果に結びついていないという報告がある。子供がすぐに答えを検索してしまい、自分で考えなくなるとも指摘されている。
すでに日本の小学校でも、休み時間にゲームに没入し、外で遊ばなくなった子供たちの問題が指摘され始めている。こうした課題にどう対処するかが大切だ。
東京都町田市で小学6年の女子児童がいじめを訴える遺書を残して自殺した問題は、深刻に捉える必要がある。端末のチャット機能がいじめを助長した恐れがあるからだ。原因を究明し、再発防止を徹底せねばならない。
特別部会は、文部科学省が2024年度の本格導入を目指すデジタル教科書について、作業部会を設けて検討することも決めた。
デジタルは、数学の立体図形や理科の実験、英語の発音などを、動画や音声を使って効果的に学べる利点がある。一方、デジタルは紙に比べて記憶に定着しにくいとする脳科学者らの研究成果も国内外で相次ぎ発表されている。
ページをめくり、マーカーで印をつけ、ノートに書く。こうした作業は記憶や深い理解に不可欠である。デジタル化によって学習を過度に効率化することは、逆効果になりかねないのではないか。
教科書は「紙」を基本とし、デジタルは動画や音声を活用できる特性を生かして、補助的な利用にとどめることが望ましい。
岸田首相は今国会の施政方針演説で、GIGAスクールを含むデジタル化の推進を掲げた。大事なのは機器を配ることではなく、子供たちのためになるかどうかだという点を忘れてはなるまい。
根拠も主張もたくさん盛り込まれた文章ですね。
そのため、まずはしっかりと根拠と主張を区別し、どこまでが”根拠”であり、どこからが”主張”なのかを区別する必要があります。

主張を抜き出してみる
まず、この社説のメインの主張、つまり筆者が一番伝えたいことはなんでしょう?
教科書は「紙」を基本とし、デジタルは動画や音声を活用できる特性を生かして、補助的な利用にとどめることが望ましい。
この部分ですね、そしてこの主張に至るまでに述べられている補助的な主張も以下のようにいくつかあります。
デジタルには学習に効果的な面と、そうでない面がある。適否をしっかりと見極め、使い方を工夫することが重要だ。
通信環境の整備や教員研修の拡充など、取り組むべき課題は多い。専門的な知見を生かし、十分に論議してもらいたい。
海外では、子供に端末を配ったところ、増えたのはゲームや動画を楽しむ時間ばかりで、十分な学習効果に結びついていない。外で遊ばなくなった子供たちの問題が指摘され始めている。こうした課題にどう対処するかが大切だ
東京都町田市で小学6年の女子児童がいじめを訴える遺書を残して自殺した問題は、深刻に捉える必要がある。(中略)原因を究明し、再発防止を徹底せねばならない
デジタル化によって学習を過度に効率化することは、逆効果になりかねない
大事なのは機器を配ることではなく、子供たちのためになるかどうかだという点を忘れてはなるまい
日本語の記述に一般的ですが、これらの主張には、それぞれ「誰に対して」の主張なのか明示されている部分はありません。
不足部分を補ってみる
それぞれが誰に対して書かれているのか、読み手としていったん補ってみましょう。

(以下の太字は筆者が補ってみた主張の相手方です)
・デジタルには学習に効果的な面と、そうでない面がある。「学校現場は/保護者は/教育産業は/学習者は」適否をしっかりと見極め、使い方を工夫することが重要だ。
→主張の相手方はかなり多岐に及びそうです。
・通信環境の整備や教員研修の拡充など、取り組むべき課題は多い。「中央教育審議会特別部会は」専門的な知見を生かし、十分に論議してもらいたい。
→文脈からここはパラグラフの先頭にある中央教育審が相手方になるのでしょう。
・海外では、子供に端末を配ったところ、増えたのはゲームや動画を楽しむ時間ばかりで、十分な学習効果に結びついていない。外で遊ばなくなった子供たちの問題が指摘され始めている。「教育行政は/保護者は/教育産業は」こうした課題にどう対処するかが大切だ
→これもまた、いろいろな相手方が入れられそうです。
・東京都町田市で小学6年の女子児童がいじめを訴える遺書を残して自殺した問題は、深刻に捉える必要がある。「学校現場は/国・自治体は/警察は」(中略)原因を究明し、再発防止を徹底せねばならない
→原因究明という言葉が入るので、これに対応する相手方というと警察まで範囲に入るかもしれません。
・「教育行政が/教育産業が/保護者が/学習者が」デジタル化によって学習を過度に効率化することは、逆効果になりかねない
→相手方は教育を与える者だけでなく、学習者自身を入れてみても文章の意味が通ります。とても幅広く感じられる主張ですね。それから、ここには「逆効果」という言葉が登場しますが、何に対する逆効果なのか。これを示す「本来求められる学習効果」について記載がないことも指摘できそうです。
・大事なのは機器を配ることではなく、子供たちのためになるかどうかだという点を「教育行政は/教育産業は/保護者は」忘れてはなるまい
→パラグラフの最初に岸田首相の名前が出ているので続けて読むなら岸田首相に対する主張になってしまいそうですが、「忘れてはなるまい」という結びと不整合ですね。
全体としては中央教育審議会特別部会に対しての主張だと取れますが読み手側にかなり委ねられた形になっています。もしこれが対話であったならば、その主張がどこに向けられたものか質問してみることもできるでしょう。
有効なコミュニケーションに使える
社説は一方的なのでこれ以上のやりとりをすることはできませんが、これが双方向のコミュニケーション、対談や討論、合意形成や交渉の場合、このように主張の不足情報に疑問を抱くというのはとても大切です。
読み方次第で対象が誰とでもとれてしまうような曖昧さは、お互いわかったつもりのミスコミュニケーションになることがあります。流し読みしただけでは違和感を感じない文章からも、足りていない情報や穴を見つけ出すことでそれを防ぐこともできます。
適切な質問をすることで、相手の主張を明確にすれば、よりよく情報を聞き届けることができ、交渉の場面などでは相手の矛盾している部分を指摘したりすることで事態を有利に動かすこともできるでしょう。
ではまた次回!
===== ===
オシンテックでは、情報を多角的に読み取り、ルール形成の国際動向に触れられるメールマガジンを配信しています!気になる方はこちらもチェック。
いいなと思ったら応援しよう!

