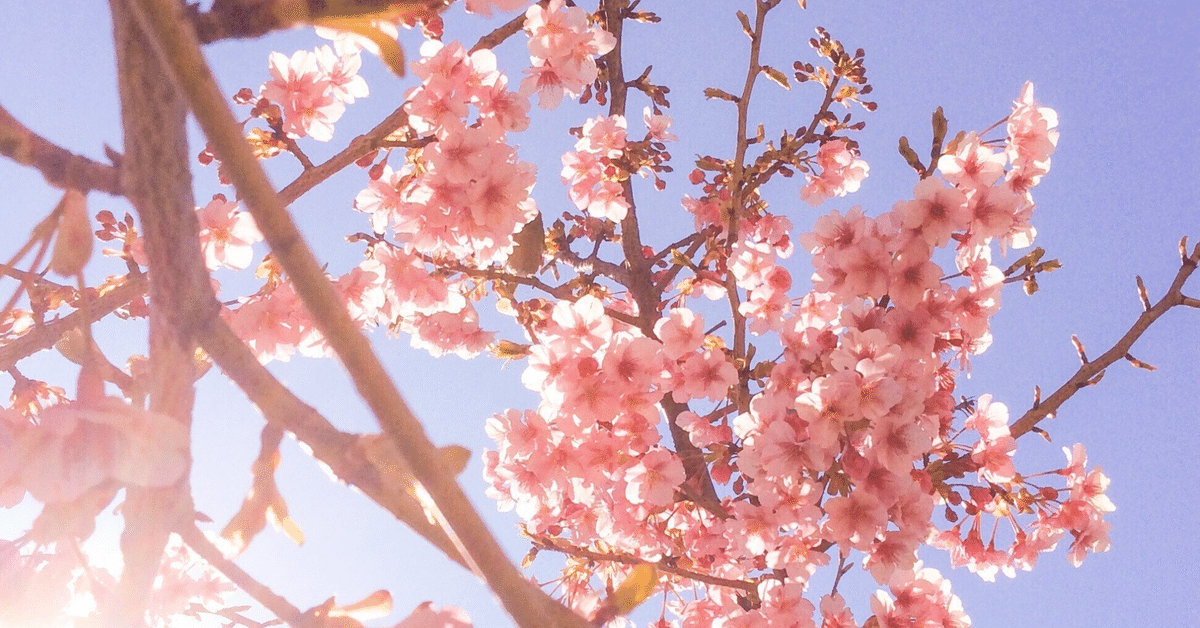
長編小説「紡がれた僕らに終わりの春を」最終章
最終章「桜の樹の下には」
骨壺を棚の上に置く。正しい置き場所なんてこの部屋にはなかった。
上着を脱ぎ、袖をまくって洗面台で水を捻りだす。手を洗い、そのまま手をコップ代わりにしてうがいをする。びたびたと垂れた水を、数日は洗濯していない汚いタオルで拭う。
洗面台の小さな鏡にうつる僕は、苛立たしそうに僕を睨みつけている。
風呂場のドアを開ける。洗っていない浴槽に栓をはめこみ、蛇口を捻る。水だったそれがお湯になり、少しずつ溜まっていく。床に座りこみ、浴槽の縁に手をついて、それをただ茫然と見下ろしていた。意識がぼやけて自分でもつかめない。
ポケットの中でスマホがラインの通知を呟いたけれど、ひとりごとになってむなしく浴室に反響しただけだった。
お湯を止める。
浴槽に上半身を突っこむ。シャツが張りつき、容赦なくお湯が喉に流れこんでくる。がぼ、と本能が吐き出そうとする。目を閉じる。からだにお湯が流れこんでくる気がする。息が時折止まりかける。お湯はにおう。なにか得体のしれない汚れを、その透明な中に確かに感じる。
入水したい。なにか僕を厭わないものに。入水して、沈められて、そのままなにもかもを鎮められて、呼吸が静まって死ねればいい。
頭だけ浮上したみたいに意識が遠のきだす。
――真央。
が、と変な音が喉の奥で破裂した。
浴槽から頭を上げる。ぐらり、重心が傾く。
目を見開いたら、浴室の照明が貫いた。ぐ、とお湯が逆流してくる。息がうまく吸えないまま、げえ、と吐き出す。
びしゃびしゃと、お湯だったものが僕の口から逆流する。唾液が糸を引き、もう一度、げえ、と汚い声が風呂場に反響した。唾液は生卵の白身によく似た粘度で、その瞬間にセージのアパートを思いだす。目尻に浮いた涙を、よれた袖で拭き取る。
ひどくむせる。喉がひりひりする。肺がきりきりと針で刺されたように痛い。病的だ。なにもかもおかしい。感情的な涙は出ないくせに、生理的な涙は滲む。
――ママが死んじゃったら。死んじゃったら、死んじゃったら、死んじゃったら、
……伯父さんの顔が思い出せない。僕を抱き上げているその腕にこもった力がおそろしかった。ママは死なないために一回真央と離れるんだよ。
死なないためってなんだよ。
死ぬつもりで産んだんじゃないのかよ。
胃が痛い。からだが痛い。だるい。座っても立ってもいられない。視界にラップかけてしまったみたいに、すべて透明であいまいになる。ぐるりと視界が半回転しては戻る。繰り返す。
赤カビの生えた椅子に手を伸ばしたら、空ぶってからだが滑る。浴室の乾いた床に転がる。頬に触れる床のその温度と感触が、いつかの母親の手と似ている。
手を伸ばす。伸ばして、その先に水垢まみれの鏡しかなくて、指先を見る。糸は一ミリも伸びていない。
なあ、なんかさ、嘘でもいいから伸びてくれよ。どうしてこんな大事なときに僕は泣けないんだろう。
*
母親の骨壺を部屋に置いたまま、ただやってくる春を迎えもせずに眠り続けた。部屋は冷たいままだった。腹が減ることだけ気味悪かった。規則正しく胃が空になり、縮んだ。家にあるものを食べた。スマホが騒ぐのはセージからの連絡だけだった。返せなかった。
生きている意味がわからない。
安っぽい小説や歌で使い回されたその言葉の意味をやっと知ることができた気がした。今までの僕は、それでもどうにか知らないふりでやってきたはずだったのに。
知りたくなかった。
布団にくるまって、浅い呼吸を聞いていた。これから考えなくちゃいけないことは、自分がやらなくちゃいけないことは、崩れ落ちるほどの山になって僕を待っていた。
泉さんとの連絡も、嫌になって返していない。
僕にとり憑くのはいつでも春だった。春になると死にたくなるのはどうしてだろう。いや、本当はずっと、毎日、死にたくて、それを強く感じさせるのがいつも春なんだきっと。夏はろくな思い出がない。季節は巡るたび、いつでも僕らに生きることのしんどさを強調する。
僕はなにもしなかった。ただ、狭いアパートで母親の抜け殻と眠った。
四月五日、僕の誕生日に電気が止まった。
何度ブレーカーを確認しても電気はつかない。電気代を払っていなかったことを思いだした。
しばらくどうでもいいかと寝転んでいたけれど、暗闇に慣れても不便だと知った。冷えた足でフローリングを踏み、デスクライトのしらじらしい明かりで払込書を探した。財布を掴んでアパートを出る。
四月になったばかりなのに、桜はすでに満開だった。駅前の道には両側に桜の樹が並び、看板や店の明かりに照らされて散り続けている。
久しぶりに歩くアスファルトのかたさに足裏が落ち着かない。一番近いコンビニを目指して、騒がしい往来に混ざっていく。
ドーナツショップの前を通ったら甘いにおいがした。ラーメン屋から濃いあぶらのにおいがした。腹はやっぱり規則正しく減っていた。
滞納していた電気代をコンビニで支払った。揚げ鳥を勧められたけれど首を振った。
背中を丸めて桜が巻き上がる道を歩いた。春風は強く、咲いたばかりの花弁を否応なしに引きはがし、汚い路上に放りだす。
信号を待てずに早足で横断する男。歩道を我が物顔で走り抜けるママチャリ。おしゃべりに夢中で広がったまま道を塞いで歩くカップル。俯いてヒールを地面に叩きつけながらどこかへ向かう女の、かったるく強すぎる香水のにおい。
なにもかもにうんざりだった。世界でひとりきりになってしまいたかった。ああ、こういうちょっとしたことで僕はひとと一緒にいることが嫌で仕方なくなった。でも消えたのは身近な人間だけだった。最もどうでもいい、そうして僕を最も無遠慮に汚す他人の群れは消えてくれなかった。
なんのために僕は今までひとりきりであろうとしたんだろう。
いつだって失うのはそういうものばかりだ。
信号を待ちながらぬるい風に叩かれていた。痛みはなく、乱れる髪に覆われる視界だけが不確かで、赤信号の光に眩暈を覚える。
ポケットに手を入れ、スマホを取り出した。
――城戸聖司。
デフォルトの登録名。ミズクラゲが泳ぐ丸いアイコン。未読メッセージ。
青信号になって何人も僕を追い抜かす。スーツ姿の男と肩がぶつかりあって、からだが前に出る。倒れないように力を入れる。
セージに会うわけにはいかない。
セージに会ったら僕は嘘をつけない。
うまく言葉にできない中身を全部ぶちまけて、セージになにかを訴えるかもしれない。僕はいつでもセージにわかってほしいと思ってしまうから。
セージが編みこんだ三つの小瓶の糸も。自分のことも。
上を見た。夜が深まりだした空は紺色をしていて、春のせいかすがすがしく晴れ渡り、星がいくつも点滅していた。都会でも星は見える。でも時間はわからない。縮み切った胃が何度目かの空腹を訴える。それは吐き気に近い不快な感覚に変わっていく。
セージ。
セージの、前髪で少しだけ隠れる賢そうな目つきや通った鼻筋、鬱々とした雰囲気、神経質そうな瞬きや呼吸や指の動き、ときどきそれらを嘘みたいにひっくり返す明るい笑い声や泣きそうに下がる目尻、上着の質感とそこに染みついたにおい、……セージを恋しいと思った。恋や愛やそういう馬鹿みたいな感情ではなくて、それは確かな執着だった。
どうしようもない執着だった。
ふらふらと帰路につき、薄暗い玄関で座りこんで未読メッセージを開く。
真央。
大丈夫ですか。
大丈夫ですか、って言うべきじゃないのはわかってんだけど、俺は今、それ以外の言葉をうまく考えることができなくて。
ごめん。
真央、落ち着いたら俺に連絡をください。
セージのトークルームで、僕は細い息を長く吐き出した。二週間ぶりに入ったその小さな部屋には、当たり前に僕とセージの言葉だけがあって、そのことに安堵した。
気づけば真夜中だった。セージは眠っているかもしれない。
僕も布団にくるまった。相変わらず浅い呼吸を聞いているうちに、自分の生を確かめているうちに、僕も眠りにつく。つこうと、する。
*
こころがどうにもならない状態にあるときほど、ちゃんと早くに目が覚める。
朝八時、着替えて顔を洗い、歯を磨く。リュックサックに必要最低限のものだけ入れて、骨壺を抱く。靴を履く。ほどけかけている靴紐を結ぶ。ドアを押し開ける。
四月ほどあいまいな季節はない。
春の鬱々とした死期を悟らせる空気の中に、生き生きとした他人の精力が混ざっていてうまく吸いこめない。酸素は、指先で押したら粉々に散ってしまいそうなくらいに固くて、薄い。
骨壺を抱えて歩き続けた。歩きなれたはずの駅前までの十五分間は、凝り固まってしまったなにかみたいだった。すべてが不確かだった。綺麗に晴れていた。
母親と並んで歩いたのが何年前だったかすら思い出せなかった。
通り道にあった区営住宅の小規模な遊び場で、小さな女の子が母親らしきまだ若い女とすべりだいで遊んでいた。古タイヤを吊るしただけの簡素なブランコに、女の子のたからものらしきねこのぬいぐるみが座らされている。アンバランスにタイヤの穴にはまった状態で、ねこは僕をじっと見つめていた。
俯いて、そうしたら投げすてられてここまで転がってきたコーヒーの空き缶にぶつかる。つまさきに少しの感触。蹴り飛ばさずにまたぐ。アスファルト、凹凸の隙間で震える桜の花びらがみじめでしかたなかった。
改札を通り、電車を待った。駅のホームにやけに人が多いから、そこでようやく曜日を確認する。スマホのカレンダー機能、赤い縁で今日の日付にカーソルが重なっていた。日曜日。
骨壺を抱えて電車を待つ男にたいして、ほとんどの人間が目を向けることはなかった。それでも数人が僕の手元を見て、すぐに目を逸らしたり、はんたいに凝視したりした。
桜の花弁がどこまででも憑いてくる。春は僕にとり憑き、離れてはくれない。ホームの屋根より少し向こう、線路にさす眩しい昼の光と、舞いこんでは線路の隙間に消えていく花弁。
風が吹き、そのにおいで胸が詰まる。俯く。顔を埋めるほど上着の首元はあまっていない。それからセージに上着を返していないことを思いだす。セージにはもう二週間会っていない。
電車は混んでいた。そのおかげか、僕の腕で覆い隠された母親がじろじろと見られることはなかった。あたたかい光が射しこむ電車内は静かで、光の水たまりの中でそれぞれ目を閉じたり、動画を見たり、本を読んだりしている。
規則的なようで不規則な揺れが足元をおぼつかなくさせるから、ぬるい吊革につかまる。骨壺を両手で支えられないから、必死に前かがみになる。腹のあたりに刺さる骨壺のかたい感触があまり好きじゃない。持ち直すために吊革を離したら、数歩よろけた。赤い優先席の端、大きく膨れ上がった腹に手を添えている若い女の薬指に嫌味な銀色が光る。
降りたのは知らない駅だった。あたたまった電車から一歩出てみると、四月でもまだほんの少し、風が冷たいことを知る。
泉さんが僕を待っていた。
改札を出ると、くぐもっていたようなこの町の春の正体があらわになって、さっきより眩しい陽の光の中で、泉さんが消えそうに突っ立っているのが見えた。母親が腹のあたりでまた滑る。
「……真央くん」泉さんはすぐに僕を見つけた。弱々しい声が僕の名前をなぞる。
「こんにちは」
僕の声はいつも通りだった。気持ち悪いくらいいつも通りだった。
泉さんの顔をちゃんと見ると、本当にどこにでもいそうな気の弱い男の顔立ちをしていた。着ている服もとってつけた感じで、でも金には困っていないんだろうな、そういうことがわかる身なりだった。僕らはしばらく黙っていた。
泉さんがなにか言おうと口を開いた。
「あの」泉さんを遮った。「……あなたのせいじゃない、って、わかってます。だからやめてください。そんなことしないでください」
頭を下げようとしていた泉さんが奇妙に固まって、それからゆっくりと俯く。
謝ってほしくなかった。これ以上。
泉さんを許しているからじゃない。
僕がみじめなことを再認識させられるから。
事故の詳細は聞いていた。スマホでゲームしながら運転していたトラックの男が一方的に突っ込んできた。それだけ。確かな事実。ちゃんとわかっていた。だって故意で死ぬほど、泉さんは社会的にみじめな人間には到底見えない。与えられた寿命分生きる気力のある人間だから。ありあまるほどの優しい善人だから。
ありあまるほどの善人だから、なおさらこの人に謝ってほしくなかった。純粋な善人は最悪だ。そういうひとを目の前にすると、どんどん自分の汚れが見えてくる。
母親を泉さんの胸元に突き出した。「母です」
骨壺を差し出した僕に、泉さんはしばらく言葉を探しているらしかった。切れ長の目が戸惑うように揺れ、僕を見て、母親を見て、地面を見て、また僕を見た。その瞬間、なんのつながりもないこのひとに、どうしようもない寂しさを感じてしまった。
「……僕はお金もないです。大学もたぶん、やめます。そもそも母の葬式すらやってあげられませんでした。焼かれた母を引き取ることしかできませんでした。僕の精一杯の生活の中で、母親をちゃんとした場所に眠らせてやることもできないんです。むしろすみませんでした。すみませんでした、僕のやるべきことに、あなたを巻きこんでるから、だから、」
どうして謝っているんだろう、とか。
どうしてこんな馬鹿みたいな話をしているんだろう、とか。
考えていたけれど、口を閉ざせなかった。
きょーおーは、やだ、かれー、やだ。
僕らを追い越していったママチャリで、小さい男の子が大きな声で叫んだ。ペダルを踏みこみながら、しょうがないでしょーお、と母親がなだめる。ぎゅっとひとつにまとめられた黒髪が揺れて消える。宙を彷徨う男の子の手も、消えていく。
「……あの、」
ぼろっとこぼした瞬間、頬に熱が駆けた。
顔を上げる。頬が濡れていた。泉さんが僕の顔を見て、泣きそうな顔になる。僕の手が離れたから、泉さんがあわてて母親を抱く。まぶたに触れたら、べしょりと濡れた。
僕は泣いていた。
視界が滲む。泉さんに大事に抱えられた母親の骨壺、その布が白いせいで確かな輪郭をなかなかつかめない。まばたきを繰り返すたび頬が濡れる。
「かえります」
声が震えた。呆然と頬に触れる。いつまでも乾かない。むしろどんどん熱を持って、湿っていく。息がしづらいから、無理にでも深呼吸をしようとする。べたべたと顔に触れるたびに濡れる。どうしたらいいのかわからなかった。どうしようもなかった。
「真央くん、」
改札に向かって一歩踏み出したら、泉さんが僕を呼んだ。
振り返る。
「ちゃんと、します。せめて僕の償いとしてきちんと――」
どん、と右半身に歩きスマホの女がぶつかってきた。よろけた僕を見てようやく顔を上げ、なんだこいつ、と言いたげな顔をして去っていく。母親に抱かれた赤ん坊がすれ違いざま僕に一瞬手を伸ばした。マタニティマークをつけたブランドバッグを腹の前に下げている若い女、ベビーカーを押しながら改札を通る女、それらを早足で抜けていくスーツ姿の女――。
償い。
償いってなんだよ。
改札の向こう、電車がくる。それに乗って僕はただ自分の部屋に帰るだけだ。帰る場所はもうあそこしかない。僕をつむいだひとはみんないなくなってしまった。それ以外のひとたちも、僕からどんどん糸を切っていった。これからどうしよう、僕にはなにもない、本当の本当になにもないから、だから当たり前の人生探してたどっていって、でも毎日なにかしらの、到底なんの役に立っているかもわからない茫然とした仕事について、それで最低限の生活を守るような、そういう人生、……なんの意味があるだろう。
こんなの、もう、無駄だ。
振り返ったら目の前にいたカップルを押し分けて泉さんのもとに向かう。彼氏が僕に驚き、彼女が苛立った声で僕を非難した。知らねえよ、口の中で呟く。
知らねえよ。
飛びこんできた僕を、泉さんは目を見張ったまま、よけることもできずにいた。
僕は茫然と突っ立った泉さんの腕に手をかけてバランスを大きく崩し、そのまま転ぶように地面に転がった。さらけだした足首にあたるアスファルトのかけらが痛い。鬱っぽい春のにおい。僕の汚い足取りで小規模に舞う桜の花弁。泉さんの腕はゴム製みたいでぬるくて跳ね返りも気持ち悪くて、こんな人間にすら僕はかてなかった。
「や、ッ、ぱり、かえして、ください」
どろり、鼻水が垂れる。すする。垂れる。俯くように崩れ落ちた僕に影を作るように、泉さんはそこに突っ立って、どうしようもない情けない顔で僕を見おろしていた。
「か、えして、ください……おねがいします。かえしてください」
「……あ、」
「かえしてください」僕は土下座同様、そのままアスファルトに潰れた。「かえしてください」
泉さんが戸惑って、その瞬間、わずかに母親が傾いたのを見た。
アスファルトに手のひらを叩きつけるようにして立ちあがる。泉さんのからだにぶつかったら、母親が弾けるように飛び上がった。数秒にも満たない時間で誰の手からも離れてしまった母親は、そのまま落下していく。べたべたべた、と強い僕の足音で、スニーカーの裏がアスファルトに激しくぶつかる。泉さんも手を伸ばす。
母親が僕の指先に触れた。
人差し指に一瞬走った布のかたい質感で、はっとする。がくり、と右足から力が抜けかけて、あわててからだを立て直す。骨壺はがつんとアスファルトに角をぶつけたものの、フィクションものみたいに中身をまき散らすことはなかった。拾い上げる。腹のあたりで抱えこむ。
泉さんから、今までのことから、自分の正直な感情から、なにもかもから、逃げた。
結局ひとりで逃げることはできなくて、母親を抱いて。
こんな調子はずれの奇妙なことが道の端で起きても、誰も気に留めなかった。
誰かの視線が僕らに突き刺さることはなかった。
無関心なままでいてほしいと思った。たとえ僕が死んでも、無関心で動かないままであってほしい。決まりきったことだけを守り続ける淡々とした世界であってほしい。
母親は僕の走るスピードで上下に揺れた。腹のあたりで何度も滑り、角を僕にあてた。痛い。骨壺は重さを増していく気がした。骨だけになった母親のからだはそれでも重かった。
今日の夕暮れは世界の終わりに似ていた。茜色にぶちまけた橙と少しの青、それから毒々しい紫色が世界の底に溜まっている。
ふいに吸いこめばむせてしまいそうな、薄いようでどこまでも追ってくる桜のにおいが、花弁が、その樹の抱える枝の重さが、すべてが煩わしい。
骨壺を腹に抱えたまま、往来を逆流して走った。世界はずっと無関心で、それはもうわかりきったことで、でもひとりくらい足を止めて、あいつおかしいんじゃねえのなんて言ってくれたとしたら、今この瞬間だけは、ほんの少しくらい救われるのかもしれないなんて思っていた。
逆らっていく。決まりきった無意識の流れを。
息が上がる。器官に入る風が冷たくて染みて、痛い。
呼吸をするだけで、痛い。
生きるための、たったそれだけの、そのための呼吸なのに、それすら痛い。
*
母親を抱いたまま、セージのアパートを目指していた。セージに会わなければ死ぬ気がした。僕は結局ひとりじゃどうにも人生背負いきれなくて、誰かに痛みをわかってもらわなければ壊れてしまう。そんな今更を今日になって知った。
自分のことは自分が理解している。
自分の痛みは自分だけのもの。
嘘をつけよと思う。違う。結局それらを土足で踏み入られても誰かに一緒になって持ってもらわないと、人間はうまく生きていけないようになってしまっている。
ひとりきりなんて無理だった。
いろいろを抱えるくらいならひとりでいたかった。
でもひとりになったら、生きることさえよけいに難しくなってしまって怖かった。
アパートの階段を踏みしめながら一段ずつ上がって、セージの部屋の前で足を止める。肺がひどく痛かった。うまく酸素を吸えなかった。足に力が入っていない気がする。
チャイムのボタンはかたかった。押しこむ。がらんとした空間に音が響いているのが、外からでもわかる。郵便受けには今朝突っ込まれたらしい、まだ折れていない地元のチラシが刺さっている。チャイムに腕を伸ばしているせいで母親が僕の腹を滑っていく。
セージはいない。
立っている感覚がはっきりしない。僕はなにもないそこで縋るようにしばらく突っ立っていた。それからそう仕向けられたみたいに思い出す。セージの指に絡まった聖書を。
キャンパスに植えられた無数の桜の樹は、駅前と同じように花を咲かせ、頼りない風に揺れていた。西東京町はずれ、山の少し上にある大学。ここには飽きるほど桜の樹が植えてあった。
春のにおいは形容しがたい。不確かに生ぬるい。それでもどこか懐かしいにおいがする。
そうしてそういうにおいに包まれて桜を見上げるとき、いつだって死にたくなる。
重いようで軽く、軽いようで重い母親を抱いて、僕は歩いている。羽織っている上着と骨壺を覆う布の相性はどっか悪くて、触るたびなにかが障る。
教会までの道はもう迷わずに済んだ。オルガンの音が今にも聞こえそうだった。
扉が開け放されているのが数メートル手前からでも見えた。早足になり、そこへ鬱っぽい春風がまとわりつく。誰かがいた。泳ぐように前へただ進んだ。確信があった。息が上がる。
セージは教会の前に立っていた。
風が吹き、セージの前髪をやわらかく揺らした。
その瞬間、どうしようもなく喉が詰まった。
「……セージ」
まお、とセージの唇がやわらかく、歪に動くのを見た。
「真央、」
「セージ、……いた、よかった、いた――」
セージに駆け寄る。
不安定な僕の足取りで、母親が腕の中で傾く。リュックサックの紐が片方ずれて、中身の重みも母親と同じように傾いて、僕も傾いて、僕の視界の中のセージも傾く。
踏みしめた草は乾いて足首にあたる。
聖歌が聞こえる。
世界の終わり、よく似た夕暮れ、その向こう側に空の忘れ物みたいに立つ十字架。セージの手に聖書はなかった。強い吐き気が襲って、口を押えて地面に膝をつく。母親が左腕の中でやけに重たい。ずるり、と背中を滑ったリュックサックが僕より先に地面に張りついた。
うえ、と声がかすかに漏れる。
目の前にセージの影が差す。
「せぇ、じ」嗚咽の隙間でセージを呼ぶ。「せー、じ」
口を覆った手のひらに、また白身に似た粘度の唾液が張りついている。
セージの手が頬に触れる。僕をまっすぐに見つめるその黒い瞳が、今日はやけに澄んでいる気がして、見つめ返す。ああそうだ、セージの目には、空がうつってるからだ、そう呟いて、僕はめまいに目を閉じる。開く。閉じる。開く。
「セージの、アパートに、行ったけど、鍵が、かかってて、それで、」
呼吸が難しい。視界いっぱいに湿った草と、骨壺の白い布。
「あー、なにやってんだろ、ッて、だって、セージ、朝は、礼拝に、いかなくちゃいけないじゃんって、それで、でも、なんか、あれ、なんか、セージに、会わなくちゃだめな気が、して」
かふ、と喉の奥で酸素が詰まる。
かふ、かふ、かふ。
マッチの空振り。穴のあいた空気入れ。壊れたピアノのペダル。そういうものに似た音が、僕の喉の奥で溜まっていく。かふ、かふ、かふ。吸えなくなる。酸素で息が詰まる。
「セージ」僕は母親に額をつけていた。「たすけてェ……」
ひッ、ひッ、ひッ、と酸素がどこにも行けなくなって騒ぎ出す。た、すけ、て、ェせーじ、せ、じ。せー、じ。僕の声も細切れになっていく。酸欠の呼吸の狭間で、言葉たちはどう分断されたらいいかもわからずに、ただただめちゃくちゃに切れていく。
セージの手のひらが背中に触れる。重いようで軽く、軽いようで重い。骨だけになった母親と、セージの手のひらの重さは、どこか似ていた。
涙が出たんだ。
かすれた声でセージに告げた。
教会の奥、少し盛り上がった、でも丘というには低すぎてなんにも届きやしない半端な場所。小さな桜の樹の下。僕らはそこに腰をおろし、冷たい幹に身を預けていた。
「泣いたんだ」
乾き始めた頬にあたる風は、毒々しい夕焼けに冷めたのか、優しくなかった。
「……泉さんに会いに行った」
「母親をどうにかしてもらうつもりだったんだ。そういう話になってた」
「僕にはなんもないから。金なんてもっとない――セージ、僕、大学もやめるよ。将来のためってみんな言うし、僕もそう思ってた。でも将来ってなんのことかわからなくなった」
「いっそセージと同じところに転部しようかな」
「神様を信じたこと一回もなかったな、それでも許してくれるのかな」
「セージ、僕どうしたらいいかな、もうあっけなく死にたくなる、なんでだろう、本当はずっと死にたかったのかな、ねえでも死にたいって口にするひといっぱいいるからさ、僕のは勘違いかな、母親死んじゃったらけっきょく……」
「真央」セージが口を開いた。
見つめあう。セージの目はいつでも真っ黒に、でもどっか澄んでいてどっか神経質で、この目を失うのが怖いと思う。抱えていた母親に頬をあてる。もうなにも言わない母親に。
「絆創膏みたいに使っていいよ、俺のこと。だから死ぬのは待ってよ」
「……うそだよ」僕の声はどんどん小さくなっていく。「死ねないよ――怖くて死ねないよ」
涙がまた、きりもなく頬を滑り落ちていく。
糸がもう出なくなったんだと知る。涙が出なかった五年間が嘘だったみたいに、僕の乾いた目からどんどん涙が滑りだす。セージは一度それらを拭おうとして僕に手を伸ばし、静かに腕をおろした。セージに手を伸ばした。
なにも言わずに、僕らはあの日みたいに、ただ指先同士をそっと繋げあった。桜の樹の下はどこか冷たい。草の感触は溶けきらなかったざらめみたいだ。沈殿したそこへ、僕たちは座りこんでいる。底の温度は冷たく、冬がまだどこかで生きのこっている可能性に気がつく。
僕の瞼に一ミリグラムずつ、誰かがおもりを乗せていく。目を開けようとすると、セージのうすくて冷たい指先が触れるから、目を開ける必要がないんだと知る。
今は――いや――今が――今がどうしようもなく苦しい。ただ深く眠って、すべてを夢だととらえてしまいたい。現実に囚われるのはもうたくさんだった――都合よく、この世界の呪いを受け流してしまいたい。生きていることは、バカみたいだ。一瞬一瞬をいちいち疑ってしまうから。すべてをまばたきのさりげない一瞬のうちに忘れてしまいたいのに、できない。
ひどく乾いた眼球が痛むのに、それでも僕はすべて見ようとしてしまう。
セージの肩に頭を預ける。母親は僕らのあいだで眠り続けている。言葉は見つからない。
言きれる。
いのちではないなにか大切なものが、生きているだけで、事きれていく。
桜は咲き誇って、それでも次の瞬間風にさらわれて死んでいく。ひどく、似ている。絡み合った指先で、共有する温度で、僕らはまだ生きていかなくてはいけないことを、今はただの眠りで、永久ではないことを思い知らされる。
いずれは目を開く。
ぼやけた視界に一番に飛びこんでくるのは、桜の花弁に違いない。
春の象徴は、実際、十日余りで散っていく。
了
