
◆読書日記.《藤本タツキ『さよなら絵梨』》
<2022年12月13日>
「止まない雨はない」より先に その傘をくれよ
藤本タツキの長編マンガ『さよなら絵梨』読みました!

『週刊少年ジャンプ』で連載されて大ヒットした『チェンソーマン』の作者・藤本タツキによる読み切り作品。
藤本タツキ作品を読むのはこれが初めてなのだが、著者のマンガが原作のアニメ『チェンソーマン』が最近とてもお気にいりで、ネット上でも「藤本タツキは天才である」と評価する人がちらほら見られるようになったので気になっていたのである。という事で「藤本タツキ入門」として、まずは本作を読んでみる気になったのだ。
少年ジャンプとしては珍しく「読み切り長編マンガ」のヒット作。本作の前に藤本タツキは『ルックバック』という長編読み切りマンガがネット上に無料公開されTwitter上でトレンド1位になったのは記憶に新しい。
最近、ネット上で連載時は全ページ無料で掲載されて一気に話題作となった作品が、単行本化されても売れるという現象がちらほら見られるようになった。『タコピーの原罪』しかり、『100日後に死ぬワニ』しかり。
これはマンガ業界の新しいトレンドになっている感がある。
「無料公開したマンガなんて売れるのか?」「売れたとして、どうやって資金を回収するんだ?」「作品の無料公開なんてやって商売になるのか?」……という懸念は以前の業界であれば当然あっただろう。だが、『タコピー』や『ワニ』が売れてしまった。
おそらく今後しばらくは、同形態の販売戦略によるヒット作がちらほら見られるようになる事だろう。
藤本タツキの『ルックバック』も、同じ手法の発表形態における大ヒット作となり、単行本でもベストセラーランキングに入るほどの売り上げを記録している。同作は『このマンガがすごい!2022』のオトコ編で1位を獲得するほどの評価も得ている。
その同じ発表形態による作品の第2弾が本作というわけである。
<あらすじ>
(家の中 中年夫婦がカメラに向かってⅤサインをして映っている)
優太「誕生日にスマホ買ってもらいました」「お父さんとお母さんで~~す」
(カメラ 中学生の男の子に向く 自撮りのように手元のカメラから煽る角度で顔のアップ)
優太「僕でーす こないだ中学生になりました」「いえーい じゃん」
(カメラ 誕生日ケーキに向く 手ブレ ケーキに「優太12さい」の文字が見える)
優太「誕生日ケーキです」「生クリームケーキ」
母親「優太 お母さんね優太に… 優太にひとつお願いがあるんだ」
(カメラ 母に向く)
母親「お母さん病気で死んじゃうかもしれないでしょ? その事…優太はどう思う?」
(沈黙)
(沈黙)
優太「…今する話じゃないなーと思う」
(カメラ 下を向いて手前のケーキが映る)
母親「あのね……優太あのね……」
母親「お母さんをね これからお母さんをね 優太に動画で撮ってほしいの」
(カメラ 母に向く 大きく手ブレ)
優太「え……」
母親「動画ならお母さんの声も動きも見返せるから…そうすればお母さんいなくなっても思いだせるでしょ? …撮ってくれる?」
(驚いたように母のほうを見る父が映る)
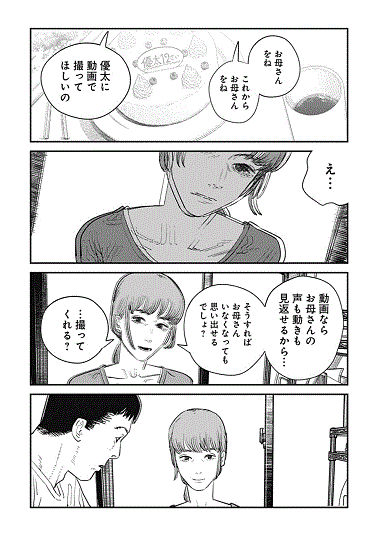
(沈黙)
優太「おっけー……」
(母のほうを見ていた父がちらりと優太のほうを見る)
母親「ありがと……」
<感想>
読後、最初に思ったのは、なるほど、この人は表現とかパーソナリティとかいう前に、とにかく物語作りとか演出とかといった「技巧」がまず巧い人なのだ、という事だった。
手法はある意味「実験的」と言えるかもしれない。この作品は各所でさんざん「メタフィクション」だと言及されているので、ここでメタフィクション作品である事をバラしてもネタバレとまでは言えないだろう。
この作者の巧い所は、このメタフィクションをネタにして物語を二転三転させ読者を飽きさせず翻弄していく手腕だろう。しかもそれだけコロコロと引っ繰り返していっても物語を破綻させずにちゃんとまとめ上げるだけの手腕を持っているのである。
200ページという分量の中で、話の構図が5~6回も変化しているのだから、時折リテラシーの低い人が「よく分からなかった」というレビューを上げているのも分からなくもないと思える。
著者は東北芸術工科大学に通って油絵を描いていたようである。確かに、美大系の作風である事は感じられる。
特に本作に濃厚なのは「"作品を作って表現をしている"という自意識」がはっきりと伺える所だろう。「商品」ではなく「表現」としての作品を描いている、という意識が見られる所が、いかにも美大出身らしい。
そして、そういう自意識があるからこそ、本作も著者なりの「創作論」として「フィクション論」としてのメタフィクションの手法が意識的に使われているというのが特徴になっている。
そして、そういうテーマだからこそ、ラストの流れから読者に対して「で、君の感想はどうだったの?」と問いかけて終わるような形式になっているのである(詳しくはネタバレになってしまうが…)。
ネット上を少し見て見れば、「考察」やら「ネタバレ」やら書かれたレビューが山ほど出てくる事からも、本作がこういう「問いかけ」を性格として持っている挑発的な作品である事は明白だろう(という挑発を自覚しながらあえてそれに乗ってしまうぼくというのもどうかと思うが)。
本作の重要なモチーフは「映画作り」だ。
本作の主人公は平凡な人生を歩んでいくが、この人物が唯一、人とは違う特徴を持っていると言えるのは「映画を撮っている」という所だろう。何もない平凡な人生の中で唯一「映画を撮っている」という事が、この主人公の人生に小さなアクセントを加えている。
病におかされた母から「これからお母さんをね 優太に動画で撮ってほしいの」と言われた時から、優太はそれが「呪い」となって、一生自らの人生に動画が関わってくる。
メタフィクションの手法を使って二転三転する技巧的な物語の中に埋もれて見えにくくしている部分もあるが、この「呪い」を優太がどう浄化するのか……というのが本作の「ドラマ」的に重要な部分の一つにもなっている。
それが著者の「創作論」として、「フィクション論」として、メタフィクションの手法が使われる理由ともなっているのだ。こういう所が、やはり巧いなぁと思わせられる部分でもある。
テーマ論だけでなく技術論的に言っても、本作は実験的であり、著者のマンガ表現技法の巧さが光っていると思える。
本書は半ばドキュメンタリー・タッチで描かれたフィクション……いわゆる「モキュメンタリー」で作られたマンガだという所もユニークだ(少年ジャンプの連載作品では、まず使う事ができない手法である)。
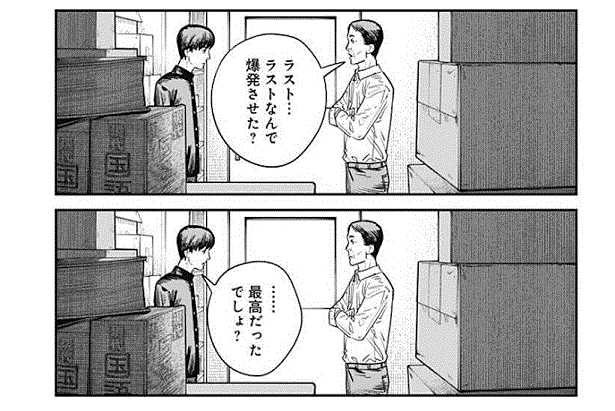
基本的にこの作品のコマは全て「スマホで撮られた動画」という体裁で描かれているので、普通のマンガのコマ割りの形態をしていない。
マンガ表現の大きな「武器」の一つは、この「コマ割り」なのである。
ストーリーの流れによってコマの大きさが大きくなったり小さくなったりする事である種のリズムが生まれるし、シーンごとの「時間経過の流れ」を早くしたり遅くしたり調整する事もできる。
マンガという表現は、コマ割りによって時間の流れが表現できるのである。
しかし、本作は「スマホで撮られた動画」という体裁で描かれているために、コマは全てスマホ動画の画面に合わせた横長の画面で構成される事となる。コマの大きさは全て均一だ。
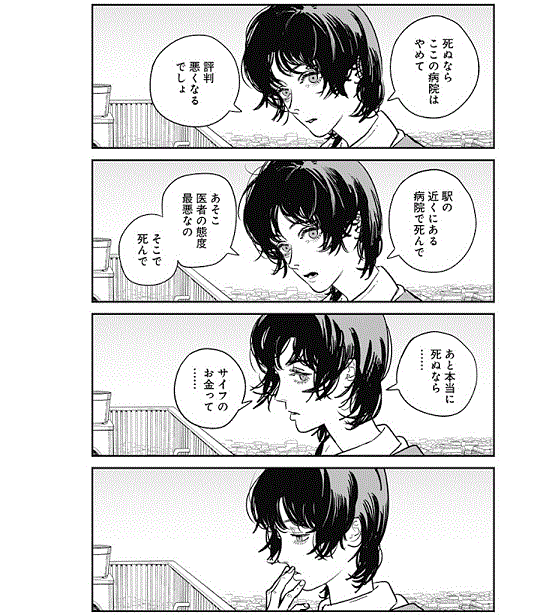
全てのコマが《同じ形・同じ大きさ》をしていると、全てのコマは全て同じ価値を持つようになる。全てのコマの中に流れる時間も均一になる。
コマによって「ここが重要ポイントだ!」といったようにクローズアップされるコマもなくなり、マンガの流れは非常に単調になる。淡々とした読み口になり、マンガ特有の外連味を出す方法が使えないのだ。

マンガというよりかは、絵コンテに近い体裁になると言えば分かり易いだろうか。
こういう体裁を採りながらも、本作では巧く物語時間の緩急をつける事に成功している。
同じ構図で同じポーズをしたキャラクターを何コマも描く事で時間をゆっくりと描きながら、物語が動くシーンになると激しく構図を動かし手ブレが発生しカメラを持っている人がせわしなく動いている様を表現したり、あるいは実写映画のようにクローズ・アップやカット・バックといった映画の編集技法が使われたりもする。時折(反則ではあるが)見開きの大ゴマを使ったりもする。
やはりマンガ手法的、演出的に言っても、この著者はとても「技巧的」なのである。
それで、著者はこういった技巧を動員してメタフィクションの手法を使う事で、何を表現したかったのだろうか。
「映画作り」をモチーフとし、それをメタフィクションの手法を使って表現し、幾重にも「フィクション」を意識した作品作りの本作は、何を主張しているのだろう。
ぼく個人は、本作は基本的に「虚構がリアルを救済する物語」なのだと受け取った。これは「人が虚構によって救われる物語」なのだと思うのである。
◆◆◆
【注!】以下、本作の内容の重要部分に触れるレビューになります。本作をお読みでない方はその旨ご了承の上、以下をお読み頂ければと思います。
◆◆◆
本作がいわゆる「モキュメンタリー」の手法を使っているのは、「作中作」ー「それを見ている人」という構図を幾重にもマトリョーシカ的に重ねるためにあると言って良いだろう。
こういう幾重にも作中作が重なっているスタイルというのは、ポストモダン文学の例をあげずともさほど珍しい手法ではない。
重要なのは「どうしてそういうスタイルを使うのか」という点にある。
注目したいのは、この「作中作」が「作中作」であると分かるシーン――その「作中作」を見ている観客が描かれて「今までのページは全て上映されている映画だったのだ」と分かるシーン――の前には必ず決定的な「死」が描かれるという点にある。
母親が死んだ。
その決定的な瞬間、優太は病院から逃げ、母の死という決定的な瞬間から逃げ、「病院の大爆破」という明らかに映画的なフィクションを思わせるシーンで、母の死をフィクションにしてしまった。
その「フィクションとなった母の死」は、大勢の観客が見る事で余計に「フィクション」であるという事が強調される。
絵梨が死んだ。
絵梨が死ぬのは「リアル」だ。だが、優太は彼女に小さな「フィクション」の要素を付与する。
彼女は吸血鬼だ……と主張するのである。何故、彼女の「リアルな死」を撮るためにドキュメンタリー・タッチの体裁が採られていたはずなのに、彼女の存在にそんな「虚構」を張り付けるのか?
「吸血鬼設定」のままの絵梨が死に、それが大勢の前で上映される事によって、彼女の死にはどこか「リアル」と「虚構」がない交ぜになった、あやふやなものになってしまった。
因みに優太は「母親の時には撮れなかった死を撮れて(P.165)」、他人の「死」に向き合い、決着をつける事ができた……のかと思いきや、今度は絵梨の死に憑りつかれる事となる。
母からの「呪い」から解放されたかと思えば、今度は絵梨に決定的に呪われるのである。
「それからも僕は誰に見せるでもない絵梨の映画を何度も何度も編集した」
妻と娘と父が死んだ。
優太は、交通事故で一気に家族を亡くしてしまった。もう一人ぼっちだ。こんな現実は耐えきれない。優太は自殺を決意する。
彼が自殺をしようとした所に、今度は「決定的にフィクショナルな存在となった絵梨」が現れるのである。
彼女は優太が昔撮っていた映画を見ながら「ファンタジーがひとつまみ足りないんじゃない?」と感想を述べる。
続けて彼女は「映画に救われた」という事を優太に告白する。
「前の絵梨はきっと絶望していたと思う… でも大丈夫」「私にはこの映画があるから」「見る度に貴方に会える…私が何度貴方を忘れても 何でもまた思いだす」「それって素敵な事じゃない?」
この言葉によって絵梨からの「呪い」から解放された優太は「さよなら」と言って絵梨の元から去っていく。そして――絵梨のいた建物は大爆破されるのである。
「病院の大爆破」によって母の死を「フィクション」の中に封じ込めてしまった優太は、ここでも絵梨のいた建物から離れ、そこを爆破して「フィクション」化してしまう。
――このラストシーンで、この「フィクション」を見ている「観客」は、本書を読んでいる読者自身なのだと誰もが気づくという仕掛けになっているのである(優太が自分の作品を見せた観客には必ず感想を求めていた事を思いだそう。ぼくが、本作が『「問いかけ」を性格として持っている』と言った理由がそれだ)。
優太は「妻と娘と父が死んだ」という決定的な不幸さえも、このようにしてフィクションの中に閉じ込めてしまった。
優太は、耐えがたい不幸を何度も「フィクション化」する事によって誤魔化してきたのだ。
「思えばずっとそうだった」「僕は目の前の問題を客観的に見てしまう癖がある」「母親の死も絵梨の死もカメラ越しだったし」「高校生の時にこうして自殺を考えていた時もそう」「カメラの前でしか現実を見る事ができなかった」
「その結果今 僕にはもう誰かの死に耐えられるほどの魂が残っていない事がわかった」「死ぬのは思い出の場所にする」「おわり」
優太が「カメラの前でしか現実を見る事ができなかった」のは、その不幸を「直接おのれの身に降りかかっている事実」だとして見る事が耐えられないからだ。
だから、それをフィクションとして、その痛みを和らげるしかなかった。
優太の「母親の死から逃げて、母の入院している病院が爆発して終わる映画」を見て絵梨が言った「どこまでが真実か創作かわからない所も私には良い混乱だった(P.53)」という感想は、半ば優太の感覚を鋭く言い当てていたのだろう。

現実で起こった不幸をフィクション化する事で痛みを和らげるのは、彼の繊細な心を守る防御手段であった。
自分を虐待していた、愛憎半ばする母。その母が死ぬ時、自分はその現実に真正面から向き合って問題解決をするような強いヒーローにはなれなかった。
だから、母の死に背を向けて無様に逃げていき、コメディ・タッチの「爆破オチ」で滑稽な自分を笑い飛ばしてしまう。どうですか、滑稽でしょう? あはは。こいつの情けない顔ったら。最高だったでしょう?

優太は逃げた。自分を傷つける"あまりにリアルすぎる"現実界に背を向けて、想像界の虚構に逃げ込んだ。
過去の辛い思い出を「何度も何度も編集」する事によって、母は息子に愛情を注ぐ普通の親に、絵梨はメガネをかけていない優太の恋人の美少女に――編集された。
優太にとってそれは「どこまでが真実か創作かわからない所も私には良い混乱だった」。
これは「虚構がリアルを救うお話」だ。
それがいい悪いはまた別として、これは「人が虚構に救われる物語」なのだ。それが、この世代のある種の心性を言い当てている風にも、ぼくには思えるのだ。
臆病者と言われようと、現実と向き合えと言われようと、そんなのは誤魔化しだと言われようと、傷つきたくないのだ。痛みには耐えられない。そんなのは御免被るのだ。
辛い現実でもそれにしっかり向き合わなければ、現実の問題はいつまで経っても解決しないぞ?虚構に逃げ込んで誤魔化したって、いつまで経っても問題はそのままあり続けるんだぞ?
いいよ。別に。圧かけてくんなよ。
そんなデカすぎる問題に、もうつきあってられないんだよ。ムリだよ。
そんなの、お前が解決してくれよ。俺はゴメンだ。
もう"今"現実に耐えられないんだよ。
痛くて、耐えられないんだよ。
「止まない雨はない」より先に その傘をくれよ――もう寒くて、これ以上ガマンしてらんねぇんだよ(因みに米津玄師と藤本タツキは1歳違いのほぼ同年代である)。
「この世は死で満ちている メメントモリ 以上優太でした さようなら」
