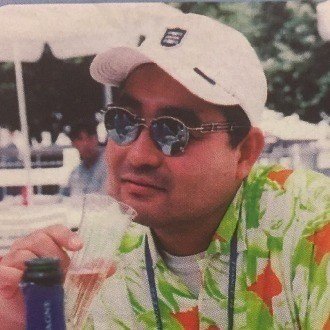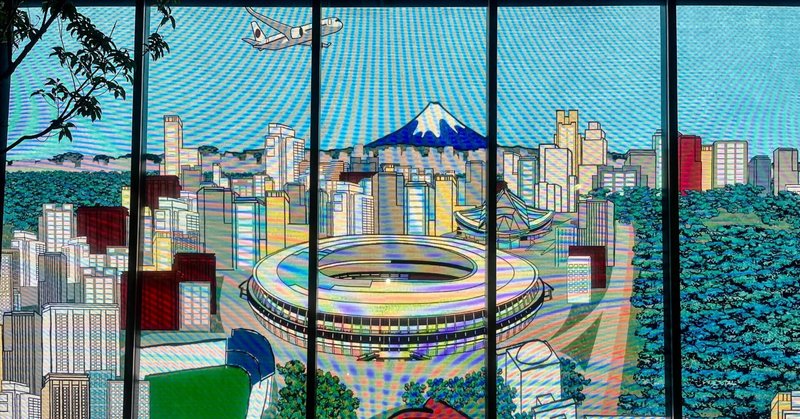#サッカー
パリオリンピック。スペイン優勝でいっそう露わになった日本サッカーの方向性なき強化策
0-3の敗戦といってもいろいろある。0-2に近いものもあれば0-4に近いものもある。0-1に近いものもあれば0-5に近いものもある。サッカーの結果、スコアには幅がある。内容とスコアを照らし合わせながら実際の差はどれほどなのか、探る必要がある。
結果がすべてという価値観に支配されるスポーツの世界において、サッカーは異端に属する。だが得点が最も入りにくいという競技の特性を忘れ、つい他の競技と同じ
森保、池田、鬼木……日本人指導者が取り憑かれる5バックなら守り切れるという幻想
「前からプレスを掛けに行けば後ろにスペースは生まれるわけですから……」。「理に適った現実的な作戦だと思います」と、テレビ解説者は、5バックで守りを固める戦法を否定するどころかむしろ肯定する。森保一監督の表現を借りれば「臨機応変」、「賢く、したたかな戦い方」となるが、日本人の指導者の間ではどうやらこの森保的な思考法がスタンダードとして浸透しているようである。
たとえば、つい2〜3シーズン前まで1
絶対に負けそうもない“無風区”を戦う日本代表と森保監督に求められる姿勢
2026年W杯までたっぷり2年半あるというのに、日本代表は半ば完成された状態にある。1トップを任すことができる選手が現れれば、いつでもW杯本大会に臨める状態にある。
選手はザクザクいる。日本サッカー史上、選手層は最も厚い。一方で来年1月に開催されるアジアカップは、ベンチ入りのメンバーがコロナ禍以前の23人に戻るので、選考は難航しそうである。
最悪でもベスト4は行けるとされる中、どんなメン
サッカーのデータに決定的に不足する2つの要素。半世紀も前から研究されている事象はなぜ表に出ないのか
サッカーは主観のスポーツである。選手の善し悪しを示す確かな個人データは得点数ぐらいだ。監督が変われば確実にスタメンは変わる。その産物として他の競技より選手の移籍、監督交代が多く発生する。
とはいえデータの総量は増えている。ボール支配率、選手の走行距離、図入りで示される布陣などは2002年日韓共催W杯前後から徐々に浸透。パスの数とその成功率、ロングボールの頻度やクロスの数、実際のフォーメーショ
感覚的なスポーツであるサッカーと難解な日本語の親和性
日本語は難しさにおいて、世界でも指折りの言語として知られる。音読みと訓読みがあることの厄介さに加え、語彙の多さも習得が難しい要因だとされる。一方、サッカーはデータの類が決定的に少ない感覚的なスポーツだ。指導者に問われているのは伝える力で、高い表現力が不可欠になる。言葉はおのずと重要なウエイトを占めることになる。
サッカーと難解な日本語と相性がいいと考えるのが自然だ。外国人の指導者より日本の指