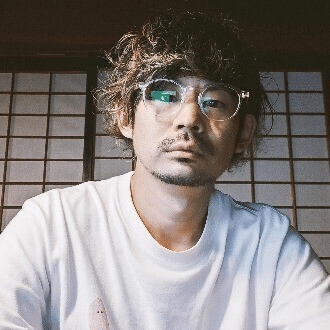黄泉がえり、からの蘇り
昨晩の日記を書き終えたあと、アマプラビデオで『黄泉がえり』を観た。「死」に引き摺られちゃったみたい。
最近は「昔観たけど、今観たらどう感じるんだろう」シリーズを開催しており、中~大学生のときの鑑賞記録を上書きするべく、2周目の作品をあれこれ手を出すようにしている。
『黄泉がえり』もまさにその枠の作品で、調べたてみたら2002年公開だった。高2の頃、帰り道に浦添(沖縄)のとあるTSUTAYAに頻繁に立ち寄っていたが、そこで借りたんだはず。
草なぎ剛と竹内結子が出てて、なぜか人が蘇る現象が起こって、柴咲コウが歌手としてめっちゃ売れた作品。ざっくり覚えてるのはこれだけで、その記憶を頼りに、再生ボタンをタッチした。
観終わると、点と点がつながるように断片的な記憶が結びついた。寺門ジモンとか、思っていた以上に芸人が出てたんだなぁ。それに若かりし市川隼人や長澤まさみもいて、今は亡き田中邦衛もいて、昔は俳優に疎かったときに観たのだと実感。なぜ熊本阿蘇なのかなど、土地の意味も考えたり、そもそもの作品の味わい方も違っていた。
抱きしめようとして抱きしめられないシーンがあるんだけど、ものすごく感動的で象徴的なものとして記憶していたが、そんなことはなく、思ってた以上に草なぎ剛のひょろさと内股が気になってしまった。そんなこと気づかなくていいのに。
お盆のような霊が帰ってくる期間に加え、それが"肉体と共に"蘇ってきたことで家族や恋人は困惑しながらも喜び、また悲しむという一つのフレームワークがあった気もする。
突然死からの蘇りが多かった印象だけど、だからこそ、最後に交わすことのできなかった会話の続きが描かれていたのだろう。また死んだはずの人が戻ってきたせいで築いてきたものが壊されそうになる、ってのがリアルな感じがした。ここは藤子・F・不二雄のブラック多めな短編集『ミノタウロスの皿』に収まる作品ともリンクするなぁと。
現実で、竹内結子本人があのような亡くなり方をしてしまったこそ、この作品には新たな意味が付与されてる気もした。また気づいたが、「いないはずなのに、いる」という役割を演じるのは、この作品の流れだったのか。
他にもいろいろ感ずるところはあるけど、竹内結子の作品を観たくなったから、次は『いま、会いにゆきます』を観よう。たしか初めての彼女と初めて映画館で観たやつだったような。
黄泉がえりという一本の映画から揺り起こされ、連鎖しながら、あらゆる記憶が蘇ってきた。次は何を思い出せるのか、次の作品へとつながってくのか。こういうひとり時間は堪らないね、こりゃあ。
ちなみに、よく通ってたTSUTAYA伊祖店、Googleマップでみたら閉店となっていた。あげちゃびよ。
いいなと思ったら応援しよう!