
おいしい流域 第2回 -あゆ:奥多摩 あゆが減ってふたたび増えたわけ- 【開催レポート】
山から海までのつながりを食を通じて体験する「おいしい流域」イベントの第2回目を、東京都奥多摩にて8月6日(火)に開催しました。
おいしい流域プロジェクトとは?
おいしい流域プロジェクトは、食を切り口に山から川、そして海までの繋がりについて、子どもたちと共に学ぶプロジェクトです。今年は多摩川流域を題材として全6回のイベントを開催し、山の湧水から始まり、川上から海に至るまでの各回を重ねるごとに下っていくことで、水とともに人々が形成してきた流域における食文化と自然環境、土地の歴史や文化について知り実際に食べて触れて体験していきます。

本プロジェクトは、現代の都市生活において、海と川、そして山までの繋がりへの理解が薄いことが、地球環境問題への興味関心をはじめ食文化の理解継承等の取り組みがうまくいかないことに繋がっているのではないかという私たちの仮説及び課題意識をもとに企画しました。次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる"日本財団「海と日本PROJECT」"の一環として開催しています。
第1回目では、東京都唯一の村”檜原村”で水の循環システムの仕組みや、山が水に与える影響、秋川および多摩川水系について学びました。
それを経て、第2回目のテーマは、「あゆ:あゆが減ってふたたび増えたわけ」。
舞台は、奥多摩にある大丹波国際虹ます釣り場。
実際に川魚を自分で釣り、その場で焼いて食べながら、川魚の生態系や木の山に対する影響について学ぶことが講義の趣旨です。
この記事では、そんな「おいしい流域」第2回目の様子をレポートでお届けします!
この講義のキュレーター
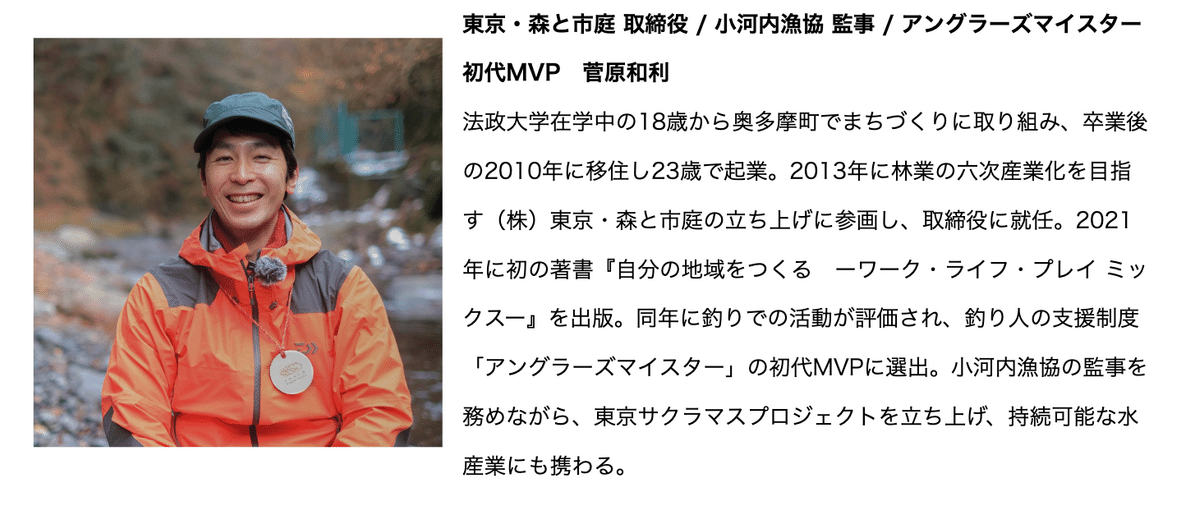
大丹波国際虹ます釣り場に集合

集合場所は、武蔵五日市駅から車で5分ほど行ったところにある「大丹波国際虹ます釣り場」。大丹波川の中流に位置しており、渓流の流れに沿って釣場が設けられています。到着した子どもたちは、川で泳いでいる魚を見て、早く釣りがしたいとウズウズ。待ちきれなくてフライングして釣りを始めた子もいました。

さて。みんなが揃ったら、講師である菅原さんの初めのオリエンテーションからスタートです。まず運営と講師の菅原さんより本日の主旨の説明がありました。
あゆがテーマだったのに、今回釣るのはニジマス?!なんでだろう・・・


実は、「あゆ」をテーマとしている「おいしい流域」第二回の本講義。でも、実際に当日釣るのは「ニジマス」です。
その事実を伝えられても、大人も子どもたちもあまりピンときていない様子。
”なぜあゆではなく、ニジマスを釣るのか。”
その答え合わせは、実際に釣りを体験し、ニジマスを食べ終えた後に行う講義にて知ってもらうとして、まずは自分の感覚をつかってニジマスを釣ってみることに!

大人も子どもも、ニジマス釣りに夢中!気がついたら2時間も



どんどん気にしなくなってきて、黙々と餌をつけています。
「餌だけ食べられて逃げられちゃったー!」「餌はイクラより幼虫の方が釣れるよ。」「この流れの下だと釣りやすいね。」
などなど、大人も子ども関係なく、気づけば2時間もニジマス釣りに夢中になっていました。
初めは「釣れない〜」と言っていた子も、一回釣れるとその感覚にやみつきになったようで、何度も自分で餌をつけては川に釣竿を垂らして、待つ。
だんだんコツを掴んできたのか、みんな何匹も釣って大盛り上がりでした。


釣ったニジマスは、その場で焼いていただきました


釣れた魚はどんどん内臓処理をして、30分から1時間程度じっくりと中まで火を通し、その場でスタッフが焼いていきます。モクモクと煙がたち、香ばしい香りも・・・。変化していく魚の色を見ながら、早く食べたいな〜と待っている子もいれば、ひたすら釣りを楽しんでいる子もいて、みんな思い思いに過ごしました。そして、いい具合に焼けたら、みんなで一斉にいただきます!
自分で釣った魚を、まるごと頬張って美味しくいただきました。


あゆではなくニジマスを釣った理由とは・・・。菅原さんの講義で明らかに
お腹いっぱいになった後は、講義スペースに移動して、菅原さんから川魚の生態系や木の山に対する影響についてお話していただきました。



まずは水槽に入っているあゆを見て触って、ニジマスとの大きさの違いや匂いを体感してもらいました。苔という主食や川の匂いが影響してか、菅原さん曰くスイカの匂いがするとのこと。子供たちは半信半疑で匂いを嗅いでみると、本当にスイカのような甘くて爽やかな匂いがしました。さらに、あゆを釣るときはニジマスと同じように釣れるかな?と質問がありましたが、答えはNOです。あゆは苔を主食にするため、ニジマスやヤマメのようにエサで釣ることができず、「おとりあゆ」や専用のルアーを使って縄張り争いで体当たりしてくるところを針にかけて釣るそうです。
川と海を行ったりきたりする”あゆ”の存在、特徴とは

こうして、様々な角度から、あゆとニジマスの違いを理解した後に、あゆという存在についてもお話ししてもらいました。
縄文時代から生息しているあゆは、川で生まれて海に向かい、またそこから自分達の川の匂いをもとに登ってきます。広い海に降りて大きくなり、おいしい苔を食べに夏頃に遡上をし、産卵をして一生を終える「年魚(ねんぎょ)」という生態になっているのです。
あゆが川に戻ってこれなくなった理由は、人間の影響だった

”あゆは川と海を行ったりきたりする・・・”そこから、海と山のつながりが見えてきました。ここ奥多摩から海までは138キロ。果たして、あゆは戻ってこれているのでしょうか?答えはNOです。
あゆは自分が生まれ育った川を目指してのぼろうとするけど、多摩川では人が水を飲むために必要な8カ所の取水堰があり、あゆの遡上を堰き止めています。坂道でものぼれるように工夫された魚道はあれど全ての魚が登れるわけではありません。ここに、人間が生態系に影響を与えた経緯がありました。また、放流のために外来種として持ち込まれたニジマスも、あゆや本来多摩川にいるはずのヤマメを主食にしているため、結果的にあゆの数が減ってしまったとも考えられています。
このような理由で、いま多摩川上流部にいるあゆは、遡上してきたわけではなく養殖して放流されたものが多く、あゆを釣るのではなくニジマス釣りになったというわけです。

最後に。私たちは何ができるだろうか

「私たちは何ができるだろうか」と問いかけながら、菅原さん自身の経験談を伝えてくれました。今の活動や想いの理由は、”ずっと魚が好きなこと”。3歳からおじいちゃんに連れられて行っていた釣りで、はじめて釣れてとても嬉しく感動したことが原体験であること。その感動体験が続いていって、魚釣りも魚もずっと好きでいられて、大人になって魚を保護するための活動をするようになったのだと、笑顔で話してくれました。
「初めてのこと、やってみることを大事にしてほしい。自分達の代では変えられないかもしれないけれど、好きでい続けられたら関わり続けていられるし、大人になってからできることもあるかもしれない。」と、優しく、でも力強く、子どもたちに向けて想いを語ってくれました。

解散後、数人の子どもたちに、講義の中で菅原さんが話してくださったことをいくつか質問してみました。そしたらなんと、全問正解!
複雑さも含む、海山川のつながりの話。
全てを伝えてもらったり理解しきることは難しいかと思っていたけれど、子どもたちはちゃんと理解してくれていました。
釣れて嬉しかった!思っていたようにいかず難しかった・・・。という感情。触った感触。たった今泳いでいた魚をその場で食べるという感覚。自分で釣った魚の味。
それらの五感を通して感じた記憶と菅原さんの話が、リンクして子どもたちに少しでも残っているといいなぁと感じました。
次回のテーマは、「のりと、経済の、密接な関係」@大森 海苔のふるさと館。
第二回「あゆ」のイベントを終えて、次回のテーマは「のりと、経済の、密接な関係」@大森 海苔のふるさと館。
のりが成長するためには、太陽の光と、山から川を伝って流れてくるミネラルなどの養分が必要です。今回の舞台である東京都大田区の大森エリアは、かつてのりの名産地でした。しかし戦後、流域の宅地化や工業化によってのりの養殖がむずかしくなってしまいました。江戸料理研究家のうすいはなこさんをナビゲートに、のり養殖が今や風前の灯火になってしまった背景にフォーカスを当てながら、海にとっての山の恵みの大切さを体験してみましょう。
詳細はこちらからご覧ください。
最後までお読みくださりありがとうございます。
