
#30 強み探しの旅へ
(この記事は約3分半で読めます)
前月号に続き、今月も「強み探しの旅」について考えてみましょう。
前回ではドラッカー氏の考える「本質的な強み」と「出来ること」は、実は似て非なることを中心に話しました。
自分の本質的な強みを知るうえで分かりやすい問いが、
「ほかの人には難しいらしいけど、自分には簡単にやれてしまうことは何か?」
身近な例で言えば、「誰とでもすぐに仲良くなってしまう友人」や「いつも机の上が綺麗な同僚」っていますよね。
人見知りな人や整理整頓が苦手な人にとって、そのような人たちの能力は驚くばかりです。

一方、当の本人たちにとって、「人と仲良くなる」「整理整頓」は至って当たり前のこと。
とても簡単なことをやっているだけなのに、なぜ「凄い!」と驚かれることに驚いています。
実はこれが、「自分の強みは何か?」に気付きにくい落とし穴。
つまり、自分には余りにも”当たり前”過ぎて、それがまさか他の人には難しいとは思いもよらないことが多々あります。
この落とし穴を埋める最も簡単な方法は、家族や友人、同僚に尋ねること。
周囲には当たり前のように見えていて、自分自身だけ見えていない「本質的な強み」。
周囲に尋ねるだけで、自分自身には意外な発見が多々あるかもしれません。
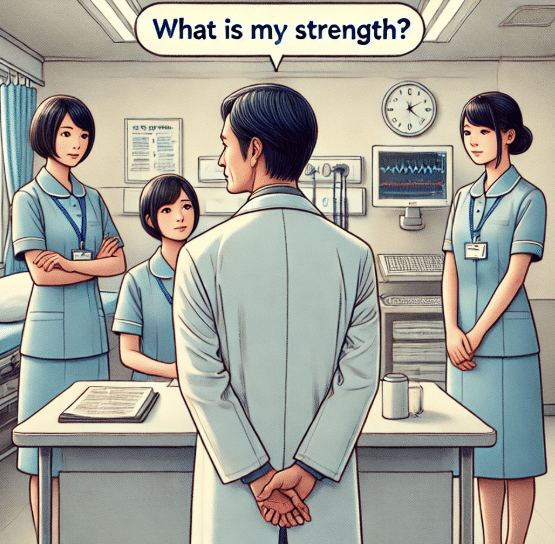
では個々の強みを、組織やチームで如何に活かしたらよいのでしょうか?
「インクルーシブ教育」「ダイバーシティ経営」「ソーシャル・インクルージョン」などなど。
いずれの言葉も、今後は「多様性」を尊重し、受け入れ、「個の違い」を活かす社会にならなければならないという、ある意味社会道義的な呼びかけ用語。
5年前には聞いたこともなかった横文字ですが、最近は社会の色々な場面で耳にするようになりました。
「解決すべき問題」や「欲しいモノ」が次から次へと出てきた20世紀後半。
戦後日本の「単一民族国家」「画一的教育制度」が時代の流れに上手くマッチし、その時代の日本は奇跡的な発展を遂げました。
しかし、世の中が「問題解決型」から「課題発見型社会」へ急速に移行している現代。
みなが同質的、全ての科目で平均点以上を良しとする日本の教育や社会構造は、厳しい時代を迎えています。
そして私たちのような小さな企業が生き残るには、「過去に捉われない、多様な発想力や組織力」が強く求められています。

多様性とは一般的に性別、年齢、国籍、人種、宗教、性的指向、価値観などを指します。
それらの多様性も大切ですが、組織に最も必要となる多様性は「個々の強みの多様性」だと、私自身は考えています。
”組織とは、強みを成果に結びつけつつ、弱みを中和し無害化するための道具である”
この言葉の意味を裏付ける具体的な事例として、税務会計の専門家としては一流だけど対人関係が極端に苦手な税理士の話を、ドラッカー氏は上述引用の章で述べています。
もしその税理士が個人事業主として開業したら、営業から顧客対応に至る、様々な対人業務が求められます。
しかしそのような人も組織の税務専門家として働けば、組織における貴重な存在として持続的な高い成果を出し続けることが可能になります。
組織の中なら、その税理士の「対人能力の低さ」は中和され、無害化されます。
そして、組織にとって大切なのは「強みの多様性」。
ヒトは多種多様。
Aさんは、好奇心旺盛でアイデアは次から次へと出るけど、持続力がなく、仕事の質にムラがあるのが弱いところ。
Bさんは、モノゴトを俯瞰し、論理的に考えるのは得意だけど、ヒトの気持ちを察するのが苦手なので、同僚とは時々もめ事に。。。
Cさんは定型的な仕事を真面目にコツコツと喜んでやってくれるけど、新しい取り組みには拒絶反応を示すタイプ。
もし先生の治療院で働いている人が全員Aさんのような方だったら、どんな組織になるでしょう?
面白い取り組みに挑戦し、楽しそうな組織ですが、間違いなくカオスですよね。。。
逆に全員Cさんタイプだったらどうでしょう?
役所のような決まった仕事に対する安定性は抜群でしょうが、その組織からのイノベーションは絶望的ですよね。

私たちマネジメントの最も重要な役割は「仕事を通じて働く人たちを生かすこと」だと、ドラッカー氏は名著「マネジメント」の冒頭で明確に述べています。
「マネジメント」を精読すると、働く人たちにとって最も重要な働き甲斐は「仕事自体に組み込まれた”責任”を通じ、持続的な”成果”を出し続けること」であることが読み取れます。
そして、持続的な成果を出し続けるための一丁目一番地が、「課された”責任”が、自分の強みに立脚していること」。
強みに立脚しているから、具体的な成果を生み出しやすくなります。
持続的な成果を出せるから、働き甲斐を感じながら仕事に取り組めます。
”組織の目的は、凡人をして非凡を行わせることにある”
実にインパクトのある言葉ですね。
組織における「非凡」なヒトの定義は、IQ130でも、東大卒でもありません。
組織が社会に対して出すべき成果に対し、持続的に高い貢献力を発揮し続けているヒトが、組織における「非凡」な社員。
治療院で言えば、誰が非凡な社員でしょうか?
以前は先生が診療後3時間かけてまとめていたレセプトを、手際よく1時間で処理する管理業務が得意な社員。
無口で愛想は無いけど、診察力と技術は一流で、患者さんから絶大なる信頼を得ている柔整師社員。
いずれの社員さんも、その組織においては大いに非凡な能力を発揮していますよね!
ポイントは、
1.誰にでも強みと弱みがある。
2.その強みを高い生産性に転換する責任を与えられ、モチベーションを維持する機会が整えば、誰もが非凡な社員になり得る
3.社員が凡人社員になるか非凡になるかは、その組織のマネジメント力にかかっている

米国の鉄鋼王アンドリュー・カーネギーは、自らの墓碑銘に以下の言葉を刻ませたことで有名です。
”おのれより優れた者に働いてもらう方法を知る男、ここに眠る”
2回に渡って一緒に考えてみた「強み探しの旅」、如何でしたか?
そもそも論ですが、先生の強みは何ですか?

