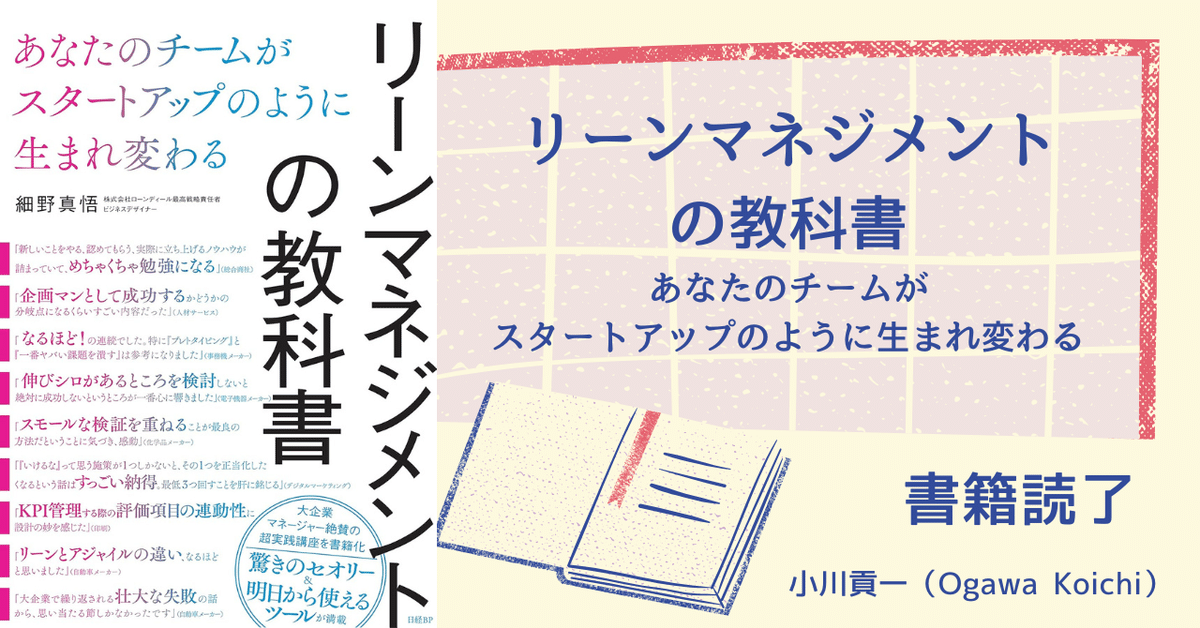
書籍【リーンマネジメントの教科書~あなたのチームがスタートアップのように生まれ変わる】読了

https://booklog.jp/users/ogawakoichi/archives/1/B09XN5QMY9
◎タイトル:リーンマネジメントの教科書~あなたのチームがスタートアップのように生まれ変わる
◎著者: 細野 真悟
◎出版社:日経BP
新規ビジネスを成功させるためのノウハウ本は数多く出ているが、どれもなかなか難しいと感じてしまう。
私自身、いわゆる一般的な日本企業に勤めている。
官僚的な組織をどうやって崩し、横の連携を進めていくかは、本当に課題だと思っている。
横ともっと繋がってブレストしたり、お互いの得意分野で協力したりできれば、新しいビジネスが生まれやすくなると思うのだ。
しかしながら、なかなかそれが進まない。
現状の目の前のビジネスを愚直に行う方が、結局「損が無い」状態だからだ。
人は大きなプラス要素よりも、ほんの少しのマイナス要素があるだけで、心に大きな痛手を負ってしまうものだ。
会社全体では「新しいビジネスを始めよう」と掛け声を出しても、結局既存の仕事を疎かにしたら、それだけでマイナス点が付く訳だから、尻込みするのも当たり前だ。
さらに言えば、その状態で新規ビジネスに精を出し、その新規がコケた場合は、さらに大きな痛手を負ってしまう。
そもそも社内の既存部門の中身がこういう仕組みになっているのに、社員個人が意識を変えて、自ら「損するかもしれないが、やってみよう」と思わせるのには相当に無理がある。
評価の仕組みを変えるとか、そもそも新規ビジネスを行う部署は完全に別の場所として組織化するなどの案はあるが、人々の意識や感情はそんな単純な話ではない。
根本的に、新規ビジネスやチャレンジに向いている人、いない人が存在する。
全員にこの意識を持たせることは現実的に無理だろうと思う。
それが悪いという話ではない。
会社の中は様々な事情を抱えた人がいるし、必ずしもチャレンジ精神溢れた人がいないと成り立たないということでもない。
現実的にオペレーショナルな仕事は多い訳だし、コツコツと地道に作業することも、会社にとってはすごく大切なことだ。
そんな状況の中で、現実的にどうやって新規ビジネスを進めていくのか。
本書のリーンマネジメントの考え方は、確かに一つの解決策かもしれない。
様々な書籍でも、「小さく始めてみよう」は叫ばれているが、本書ではより具体的に方法論が記されている。
確かに、何でもかんでも闇雲に小さく始めてみても、成功確率は高くないだろう。
「早く始める」も、他の理論では推奨されているが、本書では、事業が成り立つかどうかをスタート時に見極める点が、他の理論と異なる部分だ。
もちろん、アジャイルにスタートすることは重要だろうと思う。
それを否定する訳ではないが、「まずはきちんと考える」ということか。
極めて当たり前のことだが、案外できないものである。
何よりも、新規ビジネスは形がない。
他人に説明しようにも、形がないものをどうやってイメージさせるのか。
相手側もビジネス感度が高く、足りない部分を想像力で補ってくれるならば、会話も成立するものだが、いずれにしても相手に期待するのは無理がある。
結局、上司を説得する、役員を説得するということは、そういうことなのだ。
それであれば、自分の決裁の範囲内で小さく始めてみて、結果を数字で示した方が、相手には伝わりやすい。
見えないものを想像させるよりも、小さな規模でも「こんな結果が出ました」という形を示した方が分かりやすいのは確かだからだ。
本書を読むと、確かに理屈は分かるが、このやり方でもハードルが高いことが想像できる。
「自分の決裁範囲内で小さく始める」ことが、意外と日本企業の中では明確化されていない場合が多いと予想されるからだ。
著者自身がリクルートエージェントの事業モデル変革で、1年間で100億円の収益改善をしたのはすごいと思う。
いわゆる一般的な日本企業で、リーンマネジメントの手法を取り入れたとしても、これらが達成できるかは未知数だ。
私の会社でも、自分の決裁範囲が分かるようで分かりにくいのも確か。
例えば、何かを調べものしたり、挑戦するために、外部に依頼してみるとする。
これらのことであっても、金額にもよるのだが、今までに行っていないことを始めてみるのは、意外と心理的ハードルが高いものだ。
「否定されたらどうしよう」などの感情が出てしまうのは当然のことだろう。
テクニカルな部分よりも、これら心理的ハードルをどうやって超えていくのかが、新規事業の本質のように感じてしまう。
そういう意味では、今ではアプリのツールをプロトタイプとして作ったり、データについても分析ツールを使ったりなど、自分自身で小さく始められるアイテムが数多くある。
お金をかけずに、自ら小さな実験を重ねていくのは、確かに一つの手段だろう。
さらに言えば、そういう人たちが数多く増えていけば、それらを組み合わせることで、新しいイノベーションが生まれるかもしれない。
このような文化作りが大切なのだろう。
今までの延長線上で当たり前のことを当たり前に行っていても、新しい発見は得られない。
これから社会が劇的に変化していく中で、既存事業を守っていくだけでは、行き詰まることは目に目に見えている。
不安はあるかもしれないが、一歩踏み出すことが重要だ。
それは小さな一歩でいい。
これでもハードルはあるかもしれないが、小さなものだ。
まずは自分自身で飛び越えてみたいと思っている。
(2024/10/31木)
